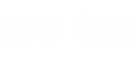研究業績
学術研究論文
| 年月 | 題目名 | 掲載誌 | ページ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年(令和7年)3月 | 「日本語母語話者の意見表明に発話に見られる「と思っていて」「と思っているので」」 | 『東京外国語大学国際日本学研究』第5号 | pp.109-130 | |
| 2024年(令和6年)8月 | 「 生成AIに日本語教育に資する例文作成は可能か−ChatGPT(GPT-3.5, GPT-4.0)と「Jreibun」プロジェクトによる作成例文およびその英訳を比較する−」(共著:鈴木智美・中村彰) | 『東京外国語大学論集』第108号 | pp.47-60 | |
| 2024年(令和6年)3月 | 「日本語例文バンク(Jreibun)プロジェクト中間報告−作成された全例文を使用語彙・文パターンの観点から見る−」(共著:鈴木智美・清水由貴子・渋谷博子・伊達宏子) | 『東京外国語大学国際日本学研究』第4号 | pp.156-180 | |
| 2024年(令和6年)3月 | 「「V1V2型複合名詞」に対応する動詞と「V1V2+する」サ変動詞の分布・ふるまいの違いを探る−「書き込む」と「書き込みする」はどう違うのか−」 | 『認知言語学会論集』第24巻 | pp.24-35 | |
| 2023年(令和5年)5月 | 「学習者の語・表現の習熟に焦点を当てた日本語教育」 | 日本語習熟論学会 『日本語習熟論研究』第1号 |
pp.34-48 | |
| 2023年(令和5年)3月 | 「日本語例文バンク(Jreibun)における例文の質の向上と英訳の工夫」(共著:鈴木智美・中村彰) | 『東京外国語大学国際日本学研究』第3号 | pp.122-139 | |
| 2022年(令和4年)3月 | 「日本語例文バンク科研(Jreibun)第1回公開研究会報告−日本語学習ツールに使用可能な良質な例文をオープンデータで公開する−」(共著:鈴木智美・清水由貴子・中村彰・加藤恵梨) | 『東京外国語大学国際日本学研究』第2号 | pp.191-208 | |
| 2021年(令和3年)3月 | 「2020年度COVID-19状況下における国費学部留学生予備教育コースー既習者対象文章表現遠隔教育の報告」 | 『東京外国語大学国際日本学研究』第1号 | pp.133-142 | |
| 2020年(令和2年)12月 | 「世界の上級日本語話者はどのようにその学習を継続させてきたのか—2020年COVID-19の影響も含めたインタビュー調査に基づいて—」 | 『東京外国語大学論集』第101号 | pp.131-146 | |
| 2020年(令和2年)3月 | 「海外の大学における日本語学習者のツール使用状況の解明—ICT時代における教師の教育設計リテラシーの向上を目指して—」(共著:鈴木智美・清水由貴子・中村彰・渋谷博子) | 東京外国語大学国際日本研究センター『日本語・日本学研究』第10号 | pp.23-48 | |
| 2020年(令和2年)3月 | 「日本語学習者の学習ツール使用の変遷をその学習歴から探る—初級から超級までの6名の留学生へのインタビュー調査に基づいて—」(共著:中村彰・鈴木智美・渋谷博子) | 『東京外国語大学国際日本学研究』プレ創刊号 | pp.186-196 | |
| 2020年(令和2年)3月 | 「抽象概念を表す表現の導入例を考える—『うがった』見方/解釈とは—」 | 『東京外国語大学国際日本学研究』プレ創刊号 | pp.179-185 | |
| 2019年(平成31年)3月 | 「日本語教育における『文型』再考」 | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第45号 | pp.123-131 | |
| 2019年(平成31年)3月 | 「東京外国語大学全学日本語プログラムで学ぶ留学生の学習ツール使用状況―2016~2017年度実施のアンケート調査の結果と分析」(共著:鈴木智美・清水由貴子・渋谷博子・中村彰・藤村知子) | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第45号 | pp.221-238 | |
| 2019年(平成31年)3月 | 「ICT時代の日本語学習者はどのような学習ツールを使っているか―日本語教師を対象としたワークショップ実施報告」(共著:鈴木智美・中村彰・清水由貴子・渋谷博子) | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第45号 | pp.239-255 | |
| 2018年(平成30年)3月 | 「サ変動詞を形成するV1+V2型複合名詞-対応する複合動詞の有無に基づく違いの観点から-」 | 東京外国語大学国際日本研究センター『日本語・日本学研究』第8号 | pp.37-49 | |
| 2018年(平成30年)3月 | 「予備教育課程の国費学部留学生の学習ツール使用状況-2016~2017年度実施のアンケート調査の結果から見えるスマートフォンアプリの使用目的の多様化と学習スタイルの変化-」(共著:鈴木智美他全5名) | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第44号 | pp.195-217 | |
| 2017年(平成29年)7月 | 「辞書ツールは文法的正確さの産出につながるか-ICT時代の日本語学習者の効果的な辞書使用を考えるために-」 | 『日本語教育と日本研究におけるイノベーション及び社会的インパクト』(第11回国際日本語教育・日本研究シンポジウム 大会論文集)香港日本語教育研究会 | pp.129-147 | 要旨 |
| 2017年(平成29年)3月 | 「2016年度夏学期『辞書を使おう』ワークショップ実践報告-初中級~中級レベルの日本語学習者の辞書ツール使用を考えるために-」 | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第43号 | pp.177-190 | |
| 2016年(平成28年)3月 | 「日本語学習者は辞書からどのように言葉を探すのか-中級・中上級日本語学習者7名の辞書使用についての調査報告事例から-」 | 東京外国語大学国際日本研究センター『日本語・日本学研究』第6号 | pp.1-23 | |
| 2016年(平成28年)3月 | 「抽象概念語彙を説明するための適切な導入例を考える-現場教師の授業準備に役立つための試案作成に向けて」 | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第42号 | pp.97-110 | |
| 2015年(平成27年)3月 | 「中上級日本語学習者の辞書使用-作文時の辞書使用の詳細調査と文章表現のための辞書使用スキルアップを目指すワークショップ実践報告-」(共著:鈴木智美・高野愛子) | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第41号 | pp.137-156 | |
| 2015年(平成27年)3月 | 「意見表明に用いられる『かなと思う』-対立・摩擦を避け内に向かう言葉-」 | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第41号 | pp.61-78 | |
| 2014年(平成26年)3月 | 「現代日本語における対応する動詞形のないV1+V2 型複合名詞-辞書に基づくリスト化- 」 | 東京外国語大学国際日本研究センター『日本語・日本学研究』第4号 | pp.95-109 | 要旨 |
| 2014年(平成26年)3月 | 「中上級日本語学習者の作文過程における辞書使用-辞書使用の詳細を可視化するデータベース作成に向けて-」 | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第40号 | pp.15-33 | 要旨 |
| 2013年(平成25 年)7月 | 「日本語学習者のための辞書使用のスキル養成のポイント―留学生の辞書使用に関するアンケート調査自由記述欄のSCATによる質的分析を通して― 」 | 『東京外国語大学論集』第86号 | pp.131-158 | 要旨 |
| 2013年(平成25年)3月 | 「大学教育における日本語コースのCan-do設定-日本語の技能を言語知識や態度と結びつけた記述の試み-」(共著:鈴木美加他全7名) | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第39号 | pp.65-82 | |
| 2013年(平成25年)3月 | 「対応する動詞形のないV1+V2 型複合名詞について-辞書からのリストアップの試み-」 | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第39号 | pp.83-91 | 要旨 |
| 2012年(平成24年)11月 | 「辞書使用をめぐって留学生はどう考えるか-アンケート調査自由記述欄の回答内容からの考察-」 | 『日本語教育論集』第8号(中日国交正常化40周年記念国際シンポジウム篇)中国赴日本国留学生予備学校日本語教育研究会 | pp.45-59 | |
| 2012年(平成24 年)7月 | 「ニュース報道およびブログ等に見られる『~です』文の意味・機能―『~を徹底取材です』『~に期待です』『~をよろしくです』―」 | 『東京外国語大学論集』第84号 東京外国語大学 | pp.341-357 | 要旨 |
| 2012年(平成24年)3月 | 「留学生の辞書使用についての実態調査―東京外国語大学で学ぶ留学生へのアンケート調査の結果と分析―」 | 『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』第38号 | pp.1-16 | 要旨 |
| 2011年(平成23年)3月 | 「全学日本語プログラムの取組と課題―アカデミック・ジャパニーズ能力向上の観点から―」(共著:藤森弘子他全7名)(4-2節「入門100レベル」担当執筆) | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』 第37号 | pp.119-134 | |
| 2011年(平成23年)3月 | 「ブログ等に見られる『{動名詞(VN)/感動詞相当句}+です』文について―『~に感謝です』『~をよろしくです』の意味・機能―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第37号 | pp.15-28 | 要旨 |
| 2010年(平成22年)7月 | 「辞書の使用が引き起こす学習者の不自然な表現―『JLPTUFS作文コーパス』の作文から見えてくること―」 | 『2010世界日語教育大会論文集』(DVD版)1436-0-1436-9 | ||
| 2010年(平成22年)3月 | 「JLPTUFS作文コーパスの構築について―全学日本語プログラムで学ぶ日本語学習者の作文データベース化―」(共著:鈴木智美・中村 彰・韓 金柱) | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第36号 | pp.123-133 | 要旨 |
| 2010年(平成22年)3月 | 「ニュース報道における『{動名詞(VN)/名詞(N)}+です』文について―『現地を緊急取材です』『老舗料亭に問題発覚です』―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第36号 | pp.57-70 | 要旨 |
| 2009年(平成21年)3月 | 「比較表現『AはBより~』再考―参照点(reference point)の観点から考える―」 | 『日本語教育学研究への展望―柏崎雅世教授退職記念論集』(シリーズ言語学と言語教育 第19巻)藤森弘子・花薗悟・楠本徹也・宮城徹・鈴木智美編 ひつじ書房 | pp.201-220 | 要旨 |
| 2009年(平成21年)3月 | 「『呼ぶ』と『招く』の意味分析―その多義的意味とコロケーションについて―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第35号 | pp.1-15 | 要旨 |
| 2008年(平成20年)3月 | 「事態に対する話者の期待と感情・評価的意味―理想化認知モデルの観点からの考察―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第34号 | pp.27-42 | 要旨 |
| 2007年(平成19年)12月 | 「現代日本語における接辞『めく』の意味・用法」 | 東京外国語大学『東京外国語大学論集』第75号 | pp.271-282 | 要旨 |
| 2007年(平成19年)3月 | 「日本語・日本文化研修留学生プログラム―東京外国語大学におけるプログラムの現状と展望―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第33号 | pp.149-167 | 要旨 |
| 2006年(平成18年)3月 | 「『そんなX…』文に見られる感情・評価的意味―話者がとらえる事態の価値・意味と非予測性―」 | 日本語文法学会『日本語文法』6巻1号くろしお出版 | pp.88-105 | 要旨 |
| 2006年(平成18年)3月 | 「『~として』再考」東京外国語大学留学生日本語教育センター | 『留学生日本語教育センター論集』第32号 | pp.1-17 | 要旨 |
| 2005年(平成17年)3月 | 「指示詞『そんな』に見られる感情・評価的意味―その意味の実態を探る―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第31号 | pp.61-75 | 要旨 |
| 2004年(平成16年)4月 | 「『~だの~だの』の意味」 | 日本語教育学会『日本語教育』121号 | pp.66-75 | 要旨 |
| 2004年(平成16年)3月 | 「日本語合同授業の報告(漢字・聴解ほか)」(共著:鈴木智美・金子比呂子) | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第30号 | pp.249-254 | 要旨 |
| 2004年(平成16年)3月 | 「接辞『~めく』の意味と用例」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第30号 | pp.1-15 | 要旨 |
| 2003年(平成15年)3月 | 「『NだのNだの』の意味」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第29号 | pp.1-12 | 要旨 |
| 2003年(平成15年)1月 | 「多義語の意味のネットワーク構造における心理的なプロトタイプ度の高さの位置付け―多義語『ツク』(付・着・就・即・憑・点)のネットワーク構造を通して―」 | 日本語教育学会『日本語教育』116号 | pp.59-68 | 要旨 |
| 2002年(平成14年)3月 | 「2000年度中級作文に見られる語彙・意味に関わる誤用―初中級レベルにおける語彙・意味教育の充実を目指して―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第28号 | pp.27-42 | 要旨 |
| 2001年(平成13年)3月 | 「多義語の意味のネットワーク構造におけるプロトタイプ」 | 名古屋明徳短期大学『名古屋明徳短期大学紀要』第16号 | pp.165-178 | |
| 2001年(平成13年)3月 | 「多義語『ツク』(付・着・就・即・憑・点)の意味分析―そのスキーマ的意味の抽出と関係付け―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター『留学生日本語教育センター論集』第27号 | pp.79-92 | 要旨 |
| 2000年(平成12年)12月 | 「言葉の『慣習性』と『固定性』―『記号性』と『非記号性』の概念をめぐって―」 | 名古屋大学言語文化部言語文化研究会『ことばの科学』第13号 | pp.5-23 | |
| 2000年(平成12年)9月 | 「現代日本語研究における『モダリティ』の定義―『主観性』をキーワードとすることの適切性について―」 | 名古屋大学留学生センター『名古屋大学 日本語・日本文化論集』第8号 | pp.29-42 | 要旨 |
| 2000年(平成12年)3月 | 「人と言葉との関わりの探究に向けて― "言葉で言い表せない" 体験をめぐる現代日本語研究と力動記号学の観点からの考察―」 | 名古屋大学大学院文学研究科博士学位論文 | ||
| 2000年(平成12年)3月 | 「言葉を取りまく言葉―連想を手がかりとして言葉のイメージの多重性を探る―」 | 名古屋大学大学院文学研究科『名古屋大学人文科学研究』第29号 | pp.125-146 | |
| 2000年(平成12年)3月 | 「言葉の "意味可能性" を探る―言葉のイメージの多重性の観点から―」 | 名古屋大学国際言語文化研究科日本言語文化専攻『言葉と文化』創刊号 | pp.75-91 | |
| 1999年(平成11年)12月 | 「言葉の記号性と非記号性―話者の内的体験と言葉との関わりを考えるための視点として―」 | 名古屋大学言語文化部言語文化研究会『ことばの科学』第12号 | pp.145-170 | |
| 1999年(平成11年)3月 | 「初級日本語学習者の個人指導の報告―教室と生活場面との媒介として―」 | 名古屋大学大学院文学研究科『名古屋大学人文科学研究』第28号 | pp.159-170 | 要旨 |
| 1998年(平成10年)12月 | 「日本語研究における『モダリティ』論の問題点―モダリティは『主観的』な意味要素か―」 | 名古屋大学言語文化部言語文化研究会『ことばの科学』第11号 | pp.243-256 | 要旨 |
| 1998年(平成10年)7月 | 「『~てしまう』の意味」 | 日本語教育学会『日本語教育』97号 | pp.48-59 | 要旨 |
| 1998年(平成10年)3月 | 「オーストラリア中等教育レベルの日本語教育における日本語ネイティブスピーカーの新しい役割」 | 名古屋大学大学院文学研究科『名古屋大学人文科学研究』第27号 | pp.109-118 | 要旨 |
| 1997年(平成9年)3月 | 「多義語『ツク』(突・衝・撞・搗・吐)の意味分析」 | 名古屋大学大学院文学研究科『名古屋大学人文科学研究』第26号 | pp.165-191 | 要旨 |
著書等
| 年月 | 書名 | 編著者 | 出版機関名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年(平成7年)5月 | 『理想の辞書を求めて―学習者にほんとうに役立つ辞書とは』 | 石黒圭(編著)他全16名分担執筆 | 明治書院 | 第3章「日本語学習者が文章を産出する際に役立つ辞書―質の良い例文を参照できる辞書を目指して―」執筆 |
| 2023年(平成5年)8月 | 『日本語複合動詞活用辞典』 | 姫野昌子(監修)/柏崎雅世・田山のり子(編集代表) | 研究社 | 編集委員、「対応する動詞形のない「V1+V2」型複合名詞のリスト」提供 |
| 2012年(平成24年)11月 | 『日本語コロケーション辞典』 | 姫野昌子(監修)/柏崎雅世・藤村知子・鈴木智美(編集委員) | 研究社 | |
| 2011年(平成23年)12月 | 『これからの語彙論』 | 斎藤倫明・石井正彦編(他全13名分担執筆) | ひつじ書房 | 第12章「日本語教育と語彙」執筆 |
| 2007年(平成19年)5月 | 『複合助詞がこれでわかる』 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター グループKANAME編著 代表 鈴木智美 (他全12名共同執筆) | ひつじ書房 | 編著代表、担当執筆項目:「として」「に基づいて」 |
| 2004年(平成16年)6月 | 『日本語表現活用辞典』 | 姫野昌子(監修・執筆)他全7名共同執筆 | 研究社 | 担当項目:動詞「ひ」「ふ」(ふえる、ふかまる、ふかめるを除く)、「ほ」(ほれるを除く)、「ま~も」 計200語 |
教材等
| 年月 | 教材名 | 編著者 | 出版機関名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年(平成29年)9月2日公開版 | 「対応する動詞形のない『V1+V2』型複合名詞のリスト」(PDF) | |||
| 2017年(平成29年)3月、7月 | 『大学の日本語 初級 ともだち』Vol.1, Vol.2 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター(編著) | 東京外国語大学出版会 | 共著 |
| 2016年(平成28年)3月 | 『日本をたどりなおす29の方法 国際日本研究入門』 | 東京外国語大学国際日本学研究院日本研究センター(編) | 東京外国語大学出版会 | 第5章1-4、第4章5 日本語編集担当 |
| 2011年(平成23年)3月 | 『「JLPTUFS作文コーパス」の構築』 | 鈴木智美・中村 彰(編) | 東京外国語大学留学生日本語教育センター | 東京外国語大学留学生日本語教育センター教育研究開発プロジェクト「JLPTUFS作文コーパス」報告書・CD・ご使用にあたって(平成20(2008)年度~平成22(2010)年度) |
| 2010年(平成22年)3月 | 『大学生の日本語』(Elementary Japanese for Academic Purposes)Vol.1, Vol.2(試用版・2010年)(試用版・2012年) | 初級総合教材開発グループ | 東京外国語大学留学生日本語教育センター | |
| 2008年(平成20年)7月 | 『ことばの説明・文例集 この言葉、外国人にどう説明する?』 | 全5名共編著 | アスク出版 | 担当講評項目:「おしゃれ」「きっかけ」「しかたがない」「すごす」「そろう」「もったいない」「やばい」「だらしない・みっともない」「ふざける・からかう」「やさしい・親切」 |
| 2005年(平成17年)10月 | 『新版日本語教育事典』 | 日本語教育学会編 | 大修館書店 | 担当項目:「語の意味―単義・多義・同音異義」「語の意味―多義の構造」 pp.270-273 |
| 1996年(平成8年)3月 | 「中級日本語会話インターネット教材」 | 大曽美恵子他10名 |
報告等
| 年月 | 題目名 | 掲載誌等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年(令和2年)3月 | 『日本語学習者の学習ツール使用状況の解明と教師の教育支援リテラシーを結ぶ総合的研究』 | 平成29年度(2017年度)~平成31年度(2019年度)日本学術振興会学術研究助成金 基盤研究(C) 研究成果報告書(課題番号:17K02842、研究代表者:鈴木智美) | 東京外国語大学国際日本学研究院 鈴木智美(編) |
| 2012年(平成24年)3月 | 『留学生の文章産出時における辞書使用の実態調査―言いたい日本語はどう見つけるか―』 | 平成22年度(2010年度)~平成23年度(2011年度)科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 研究成果報告書(課題番号:22652047、研究代表者:鈴木智美) | 東京外国語大学留学生日本語教育センター 鈴木智美(編著) |
| 2000年(平成12年)3月 | 「大学院日本語教育実習におけるティーチングアシスタントの役割―日本言語文化専攻春季実習を例として―」 | 『1999年度 日本語教育実習報告』 | http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/ ̄mohso/jisshu99/ |
| 1999年(平成11年)2月 | 「意味的な誤用に見られる主な傾向―慣習的に定着した表現および類似の表現に関わる誤り―」 | 平成8年度~平成10年度科学研究費補助金(基盤研究 (A)(1) ) 研究成果報告書(研究課題番号 08558020) 研究代表者:大曽美恵子(名古屋大学大学院国際言語文化研究科教授) |
『日本語学習者の作文コーパス:電子化による共有資源化』 pp.131-145(研究協力者)要旨 |
| 1997年(平成9年)3月 | 「オーストラリア中等教育レベルの日本語教育において貢献することのできる日本語ネイティブスピーカーの資質と役割」 | 名古屋大学大学院文学研究科日本言語文化専攻『1996年度 日本語教育実習報告』 | pp.163-174 |
| 1997年(平成9年)3月 | 「オーストラリア エリザベス・カレッジ」 | 名古屋大学大学院文学研究科日本言語文化専攻『1996年度 日本語教育実習報告』 | pp.105-130 |
| 1994年(平成6年)1月 | "The Japan Foundation Teaching Assistant Program Report, 1992-1993." | 国際交流基金日本語課およびオーストラリア・タスマニア州教育省保管「海外派遣青年日本語教師プログラム」総合報告書 |
口頭発表
| 日時 | 題目名 | 学会・研究会等 | 開催場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年(令和6年)11月9日 | 「日本語教育に資する良質な例文作成に求められるもの―『ねっこ日日学習辞書』および「「Jreibun」プロジェクト」を通した考察―」(鈴木智美・砂川有里子) | 東アジア日本研究者協議会 第8回国際学術大会 | 淡江大学(台湾) | |
| 2023年(令和5年)11月5日 | 「日本語教育における「文型」再考−慣習的に定着した文パターンをとらえる一つのあり方として−」 | 東アジア日本研究者協議会 第7回国際学術大会(パネル発表) | 東京外国語大学 | |
| 2023年(令和5年)9月2日 | 「「V1V2型複合名詞」に対応する動詞と「V1V2+する」サ変動詞の分布・ふるまいの違いを探る―「書き込む」と「書き込みする」はどう違うのか―」 | 日本認知言語学会 第24回全国大会(招聘発表) | 桜美林大学(ハイブリッド) | 予稿集 pp.78-81 |
| 2023年(令和5年)3月4日 | 「例文作成の工夫と中間報告」 | 日本語例文バンクJreibun 第2回公開研究会 主催:日本学術振興会学術研究助成金 令和3(2021)年度〜令和6(2024)年度 基盤研究(B)「辞書サイト・アプリ開発に資する質の高い日本語例文バンクの構築とその応用研究」 (課題番号:21H00535 研究代表者:鈴木智美) |
東京外国語大学(オンライン形式) | |
| 2022年(令和4年)7月30日 | 「学習者の語・表現の産出に焦点を当てた日本語教育研究―日本語教育における『語彙の教育と習熟』について―」 | 日本語習熟論学会 第1回研究大会 | オンライン形式 | 予稿集 |
| 2022年(令和4年)3月25日 | 「日本語例文バンク(Jreibun)プロジェクトの目指すもの:日本語学習ツール開発に利用可能な良質な例文をオープンデータで公開する」(鈴木智美・中村彰)
What the "Jreibun" (the Bank of Japanese Example Sentences) Project Aims for: Making Public High-Quality Example Sentences Usable for Japanese Language Study Tools as Open Data |
ポズナン&クラクフ日本学専攻科設立35周年記念学会 Practicing Japan-35 years of Japanese Studies in Poznań and Kraków |
アダム・ミツキェヴィチ大学/ヤギェロン大学 Adam Mickiewicz University, Poznań/Jagiellonian University in Kraków (オンライン形式) |
|
| 2021年(令和3年)7月18日 | 「『例文バンク』プロジェクトの目指すもの:教科書・辞書作成の実体験をふまえて」 | 日本語例文バンク科研 第1回公開研究会 主催:日本学術振興会学術研究助成金 令和3(2021)年度〜令和6(2024)年度 基盤研究(B)「辞書サイト・アプリ開発に資する質の高い日本語例文バンクの構築とその応用研究」 (課題番号:21H00535 研究代表者:鈴木智美) |
東京外国語大学(オンライン形式) | |
| 2021年(令和3年)7月18日 | 「世界の日本語学習者のツール使用状況」 | 日本語例文バンク科研 第1回公開研究会 主催:日本学術振興会学術研究助成金 令和3(2021)年度〜令和6(2024)年度 基盤研究(B)「辞書サイト・アプリ開発に資する質の高い日本語例文バンクの構築とその応用研究」 (課題番号:21H00535 研究代表者:鈴木智美) |
東京外国語大学(オンライン形式) | |
| 2019年(令和元年)8月2日 | 「抽象概念を表す表現の導入例を考える―『うがった』見方/解釈とは―」 | 第17回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | 予稿集 pp.18-21 |
| 2019年(平成31年)2月21日 | 「今、日本語学習者はどんな学習ツールを使っているのか―教師の教育支援リテラシーの向上と学習支援について考える」(鈴木智美・清水由貴子) | 東京学芸大学許夏玲研究室研究会 | 東京学芸大学 | |
| 2018年(平成30年)12月8日 | 「世界の日本語学習者は今どのような学習ツールを使っているか―ICT時代の日本語教育の鍵をツール使用状況から考える―」(鈴木智美・清水由貴子・渋谷博子・中村彰) | 第12回 国際日本語教育・日本研究シンポジウム | 香港理工大学 | |
| 2018年(平成30年)8月9日 | 「日本語教育における『文型』とは何か―『文型』批判の誤解を解く―」 | 第16回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | 予稿集 pp.18-21 |
| 2018年(平成30年)7月31日 | 「日本語学習者はどのような学習ツールを使っているのか―留学生を対象にしたアンケート調査の結果から見えるもの―」 | 国際シンポジウム「コミュニケーションのための日本語学習辞書を求めて―学習者調査から新しい辞書の構想と開発へ―」 主催:北京日本学研究センター 共同プロジェクト「新しい日本語教育文法辞典構築のための基礎研究」、国際交流基金 共催:国立国語研究所 共同研究プロジェクト「日本語学習者のためのコミュニケーションの多角的解明」、東京外国語大学国際日本研究センター国際日本語教育部門 |
国際交流基金日本語国際センターホール | |
| 2018年(平成30年)3月9日 | 「ICT時代の日本語学習者はどのような学習ツールを使っているか」(鈴木智美・中村彰・清水由貴子・渋谷博子) | 東京外国語大学 平成29年度 日本語教育・教材開発・実践教育研修共同利用拠点事業 第7回ワークショップ (共催:日本学術振興会学術研究助成金 平成29年度~31年度 基盤研究(C)「日本語学習者の学習ツール使用状況の解明と教師の教育支援リテラシーを結ぶ総合的研究」) (課題番号:17K02842 研究代表者:鈴木智美) |
東京外国語大学留学生日本語教育センター | |
| 2017年(平成29年)8月9日 | 「サ変動詞を形成するV1+V2型複合名詞―対応する複合動詞の有無に基づく違いを探る―」 | 第15回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.18-21) |
| 2016年(平成28年)11月30日 | 「日本語学習者の辞書ツールの使用について考える 」 | 東京学芸大学許夏玲研究室研究会 | ||
| 2016年(平成28年)11月20日 | 「辞書ツールは文法的正確さの産出につながるか―日本語学習者が日本語を書くための効果的な辞書使用を考えるために―」 | 第11回 国際日本語教育・日本研究シンポジウム | 香港公開大学 | 予稿集 |
| 2016年(平成28年)8月9日 | 「『のだ』の拡張的使用―自己防衛の柔らかな言語表現化「のかなと思います」―」 | 第14 回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.18-21) |
| 2015年(平成27年)8月6日 | 「抽象概念語彙を説明するための適切な導入例を考える―現場教師の授業準備に役立つための試案作成に向けて―」 | 第13 回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.18-21) |
| 2014年(平成26年)8月4日 | 「対立・コンフリクトを避け内に向かう言葉-『かなと思う』の意味と使用-」 | 第12 回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.38-41) |
| 2014年(平成26年)7月12日 | 「現代日本語における対応する動詞形を持たない『V1+V2 型複合名詞』の辞書に基づくリスト化-『*立ち読む』の形を持たない『立ち読み』などの複合名詞はいくつあるのか-」 | 2014年日本語教育国際研究大会(SYDNEY-ICJLE2014) | シドニー工科大学 | 要旨 |
| 2013年(平成25年)8月5日 | 「日本語学習者の辞書使用に関するCan-do記述の試み-アンケート調査自由記述欄の質的分析をもとに-」 | 第11 回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.34-37) |
| 2013年(平成25年)6月8日 | 「対応する動詞形のないV1+V2型複合名詞-辞書からのリストアップの試み-」 | TGU日本語研究発表会 | 東京学芸大学 | |
| 2013年(平成25年)3月18日 | 「学習者辞書の開発とその活用に向けて―調査・研究事例から見える文章作成時の学習者の辞書の使い方 ―」 | 「汎用的日本語学習者辞書開発データベース構築とその基盤形成のための研究」日本語学習辞書科研 第4回全体研究集会 | つくば国際会議場 | 資料 |
| 2012年(平成24年)8月19日 | 「留学生は言いたい日本語をどう見つけるのか―留学生の文章産出時における辞書使用の実態調査―」 | 2012年日本語教育国際研究大会 | 名古屋大学 | 予稿集【第2分冊】p.164 |
| 2012年(平成24年)7月8日 | 「辞書使用をめぐって留学生はどう考えるか―アンケート調査自由記述欄の回答内容からの考察」 | 中日国交正常化40周年記念日本語教育国際シンポジウム | 東北師範大学 | |
| 2012年(平成24年)3月3日 | 「ニュース報道およびブログ等に見られる『~です』文の意味・機能―『~を徹底取材です』『~をよろしくです』『~に感謝です』―」 | 東京外国語大学国際日本研究センター対照日本語部門 第6回研究会 | 東京外国語大学語学研究所 | |
| 2012年(平成24年)3月2日 | 「JLPTUFS作文コーパスの構築と今後の展望―日本語教育アーカイブ化構想への足がかりとして―」 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター統合20周年記念国際シンポジウム『これからの教材開発・教育リソース研究を考える』分科会1「日本語教育研究リソースとしてのデータベースの構築と利用」 | 予稿集 pp.38-39 | |
| 2012年(平成24年)2月17日 | 「留学生の辞書使用についての実態調査―東京外国語大学で学ぶ留学生へのアンケートおよびインタビュー調査の結果と分析―」 | 鹿児島日本語教育研究会 平成23年度第2回例会 | 鹿児島大学留学生センター | |
| 2011年(平成23年)8月21日 | 「留学生の辞書使用についての実態調査―東京外国語大学で学ぶ留学生へのアンケート調査の結果と分析 ―」(Investigating Dictionary Use by Foreign Students:Analysis and Results of the Survey of JLPTUFS Foreign Students ) | ICJLE2011世界日本語教育研究大会 | 天津外国語大学 | 予稿集『異文化コミュニケーションのための日本語教育』Vol.2 pp.328-329 |
| 2011年(平成23年)8月8日 | 「 留学生の辞書使用についての実態調査―東京外国語大学で学ぶ留学生へのアンケート調査結果」 | 第9回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.10-13) |
| 2010年(平成22年)8月9日 | 「留学生の文章産出時における辞書使用―その実態調査の実施に向けて―」 | 第8回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.52-55) |
| 2010年(平成22年)7月31日 | 「辞書の使用が引き起こす学習者の不自然な表現―「JLPTUFS作文コーパス」の作文から見えてくること―」 | ICJLE 2010世界日本語教育大会 | 台湾国立政治大学 | ハンドアウト(予稿集PDFは論文No.30) |
| 2009年(平成21年)8月3日 | 「比較表現『AはBより~』再考―日本語教育における的確な導入例を考える―」 | 第7回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.38-41) |
| 2008年(平成20年)8月4日 | 「事態に対する話者の期待と感情・評価的意味―理想化認知モデルの観点からの考察―」 | 第6回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.14-17) |
| 2007年(平成19年)8月6日 | 「日本語・日本文化研修留学生プログラム―東京外国語大学における現状と展望―」 | 第5回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.30-33) |
| 2007年(平成19年)3月22日・23日 | 「日本語教育と語彙」 | ベトナム・ハノイ国家大学外国語大学 東洋言語文化学部 日本語科 日本語教師養成課程 教員研究会 | ハノイ国家大学外国語大学 | |
| 2007年(平成19年)3月5日 | 「『日本語表現活用辞典』について」 | 平成18年度国立国語研究所言語教育データベース研究会(第7回) | 国立国語研究所 | 姫野昌子他 4名 |
| 2006年(平成18年)8月7日 | 「複合助詞『として』の意味・用法再考―日本語研究と日本語教育研究からの包括的記述の試みの一事例として―」 | 第4回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.2-5) |
| 2005年(平成17年)8月8日 | 「『そんなX』に見られる感情・評価的意味―話者がとらえる事態の価値・意味と非予測性―」 | 第3回日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.2-5) |
| 2005年(平成17年)7月2日 | 「指示詞『そんな』に見られる感情・評価的意味―話者がとらえる事態の価値・意味と非予測性―」 | 現代日本語学研究会(名古屋地区現代日本語研究会)第98回研究会 | 名古屋大学 | |
| 2004年(平成16年)8月9日 | 「接辞『~めく』の意味」 | 第2回名古屋大学日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.10-13) |
| 2003年(平成15年)10月14日 | 「2003年度1学期日本語合同授業の報告(漢字・聴解ほか)」 | 第6回日本語科研究会 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター | 共同発表 |
| 2003年(平成15年)8月1日 | 「『~だの~だの』の意味」 | 第1回名古屋大学日本語教育研究集会 | 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 | PDF(予稿集 pp.10-13) |
| 2001年(平成13年)6月24日 | 「多義語の意味に関わる二つのネットワーク構造―"心理的プロトタイプ" 度の高さを位置付ける―」 | 日本言語学会第122回大会 | 一橋大学 | 予稿集 pp.59-64 |
| 2000年(平成12年)5月21日 | 「言葉の『慣習性』と『固定性』について―『記号性』と『非記号性』の観点から―」 | 日本記号学会第20回大会 | 静岡県立大学 | |
| 2000年(平成12年)2月26日 | 「人と言葉との関わりの探究に向けて―"言葉で言い表せない体験" をめぐる現代日本語研究と力動記号学の観点からの考察」 | 現代日本語学研究会(名古屋地区現代日本語研究会)第66回研究会 | 名古屋大学 | |
| 1999年(平成11年)9月18日 | 「言葉を取りまく言葉―言葉のイメージの多重性を探る―」 | 第2回認知言語学フォーラム | 京都大学大学院人間環境学研究科 | |
| 1999年(平成11年)5月16日 | 「現代日本語研究におけるモダリティ論から丸山圭三郎のランガージュ論へ―話者の内面と言葉との関係を探るための視点の転換―」 | 日本記号学会札幌大会(第19回大会) | 札幌大学 | |
| 1998年(平成10年)12月19日 | 「日本語研究における『主観的』モダリティ論の問題点」 | 現代日本語学研究会(名古屋地区現代日本語研究会)第53回研究会 | 名古屋大学 | |
| 1997年(平成9年)5月25日 | 「『~てしまう』の意味」 | 国語学会平成9年度春季大会 | 大阪市立大学杉本学舎 | 予稿集 pp.132-139 |
| 1997年(平成9年)1月25日 | 「『~てしまう』の意味」 | 名古屋・ことばのつどい(中部地区国語学研究会)第182回例会 | 名古屋大学 | |
| 1996年(平成8年)9月28日 | 「『~てしまう』の意味」 | 現代日本語学研究会(名古屋地区現代日本語研究会)第28回研究会 | 名古屋大学 | |
| 1996年(平成8年)1月27日 | 「多義語『ツク』(突・衝・撞・搗・吐)の意味分析」 | 現代日本語学研究会(名古屋地区現代日本語研究会)第21回研究会 | 名古屋大学 | |
| 1993年(平成5年)9月25日 | "Activities for Learning Kanji and Counters", and "How to Find the Group of Verbs." | Japanese Workshop in State Conference of M. L. T. A. T. (Modern Language Teachers Association of Tasmania) | The Westside Hotel, Hobart |
その他
| 日時 | 題目名 | セミナー・ワークショップ等 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 2025年(令和7年)5月26日 | 「日本語学習者が文章を産出する際の辞書使用をめぐって」 | 台湾国立政治大学日本語文学系 オンライン研究会 プロジェクト「網路外語學習」(ネットによる日本語学習)王淑琴先生 |
オンライン |
| 2025年(令和7年)1月23日 | 「教育とICTとの可能性を考える―教育に生かすためにAIを教育する―」 | 講演者:王棟氏(早稲田大学) 主催:東京外国語大学国際日本研究センター国際日本語教育部門 共催:日本学術振興会学術研究助成金 令和3(2021)年度〜令和7(2025)年度 基盤研究(B) 「辞書サイト・アプリ開発に資する質の高い日本語例文バンクの構築とその応用研究」 (課題番号:21H00535(2021-2023年度), 23K20470(2024-2025年度) 研究代表者:鈴木智美) |
東京外国語大学 |
| 2023年(令和5年)7月30日 | 現代日本語のおもしろさ−日本語教育の観点からの再発見− | 東京外国語大学2023年度オープンキャンパス 模擬授業 | 東京外国語大学 |
| 2023年(令和5年)3月4日 | 日本語例文バンクJreibun 第2回公開研究会「日本語例文バンクJreibunプロジェクト中間報告」 | 鈴木智美・中村彰・望月源・アールストロム,キム 主催:日本学術振興会学術研究助成金 令和3(2021)年度〜令和6(2024)年度 基盤研究(B)「辞書サイト・アプリ開発に資する質の高い日本語例文バンクの構築とその応用研究」 (課題番号:21H00535 研究代表者:鈴木智美) |
東京外国語大学(オンライン形式) |
| 2021年(令和3年)12月18日 | 「世界の日本語教育の現場から—今求められる教育・教師—」 | 話題提供者:平川俊助氏・アフメット ギュルメズ氏・古川嘉子氏 指定討論者(鈴木智美・荒川洋平) 進行(石澤徹) 東京外国語大学大学院国際日本学研究院 公開研究会 (企画・運営および指定討論者) |
東京外国語大学(オンライン形式) |
| 2021年(令和3年)7月18日 | 日本語例文バンク科研 第1回公開研究会「『例文バンク』プロジェクトの目指すもの—良質な例文をオープンデータで」 | 鈴木智美・中村彰・清水由貴子・加藤恵梨 主催:日本学術振興会学術研究助成金 令和3(2021)年度〜令和6(2024)年度 基盤研究(B)「辞書サイト・アプリ開発に資する質の高い日本語例文バンクの構築とその応用研究」 (課題番号:21H00535 研究代表者:鈴木智美) |
東京外国語大学(オンライン形式) |
| 2019年(令和元年)7月18日 | 「多様化する日本語教育」第3回研究会 | 講師:浦 由実氏(アン・ランゲージ・スクール成増校) 「ICT時代における教師の授業設計を考える—日本語教育の現場の実践から」 主催:東京外国語大学国際日本研究センター国際日本語教育部門 共催:日本学術振興会学術研究助成金 平成29年度~31年度 基盤研究(C)「日本語学習者の学習ツール使用状況の解明と教師の教育支援リテラシーを結ぶ総合的研究」 課題番号:17K02842, 研究代表者:鈴木智美 |
東京外国語大学留学生日本語教育センター |
| 2018年(平成30年)8月8日 | ワークショップ「デジタル時代の教師の学習支援のあり方」 | 日本語教育振興協会主催:平成30年度 日本語学校教育研究大会 分科会Ⅴ(渋谷博子・清水由貴子・鈴木智美) | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
| 2018年(平成30年)7月11日 | 「ICT時代の日本語学習者における効果的な辞書ツールの使用を考える」 | 東京外国語大学国際日本研究センター 夏季セミナー&サマースクール2018 講義 | 東京外国語大学 |
| 2018年(平成30年)6月5日 | ワークショップ「日本語学習者のための人気の辞書サイト『jisho』の作成者に聞こう!」 | 講師: Kim Ahlström氏 主催:日本学術振興会学術研究助成金 平成29年度~31年度 基盤研究(C)「日本語学習者の学習ツール使用状況の解明と教師の教育支援リテラシーを結ぶ総合的研究」 課題番号:17K02842, 研究代表者:鈴木智美 |
東京外国語大学留学生日本語教育センター |
| 2016年(平成28年)7月19日~7月20日 | 「『辞書を使おう』ワークショップ」 | 東京外国語大学全学日本語プログラム夏学期自律型学習コース | 東京外国語大学留学生日本語教育センター |
| 2014年(平成26年)3月17日 | 「日本語の文章表現における辞書使用を考える:調査研究事例に基づいて」 | ヘルシンキ大学文学部世界文化学科アジア研究専攻日本コースワークショップ | ヘルシンキ大学文学部世界文化学科 |
| 2012 年(平成24年)8月23日 | 「教材開発に向けた基盤研究:調査・研究事例から見える問題点およびより良い用法解説書作成への視点」 | 第4回トゥルク諸国日本語教育セミナーワークショップ(カザフ国立大学・カザフスタン日本語教師会主催) | カザフスタン日本人材開発センター |
| 2011年(平成23年)12月9日 | 「日本語っておもしろい―語と意味の観点から考えてみよう―」 | 平成23年度 ちょうふ市内・近隣大学等公開講座 東京外国語大学「日本語再発見!」第2回 | 調布市文化会館たづくり |
| 2011年(平成23年)2月28日 | 「辞書の使用が引き起こす学習者の不自然な表現―「JLPTUFS作文コーパス」の作文から見えてくること―」 | テヘラン大学 外国語学部日本語日本文学科 ワークショップ(2) | テヘラン大学 |
| 2011年(平成23年)2月27日 | 「日本語のおもしろさ―文法・語彙」 | テヘラン大学 外国語学部日本語日本文学科 ワークショップ(1) | テヘラン大学 |
| 2009年(平成21年)5月29日 | 「ことばについて考えるのは私の最大の楽しみ―だから、そして、日本語教育へ―」 | 平成21年度 進路別研究会 | 修猷館高等学校 |
| 2007年(平成19年)9月13日 | 「現代日本語のおもしろさ―日本語教育の観点からの再発見―」 | 第541回二木会(東京修猷会) | 学士会館 |
| 1994年(平成6年)8月 | 「海外派遣青年日本語教師体験談」 | アルク地球人ムック『海外就職 '95―日本語を教える―』p.143 |