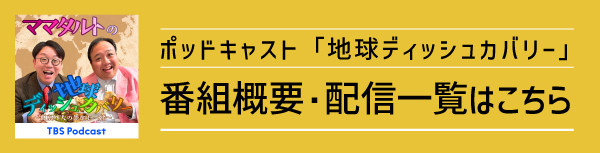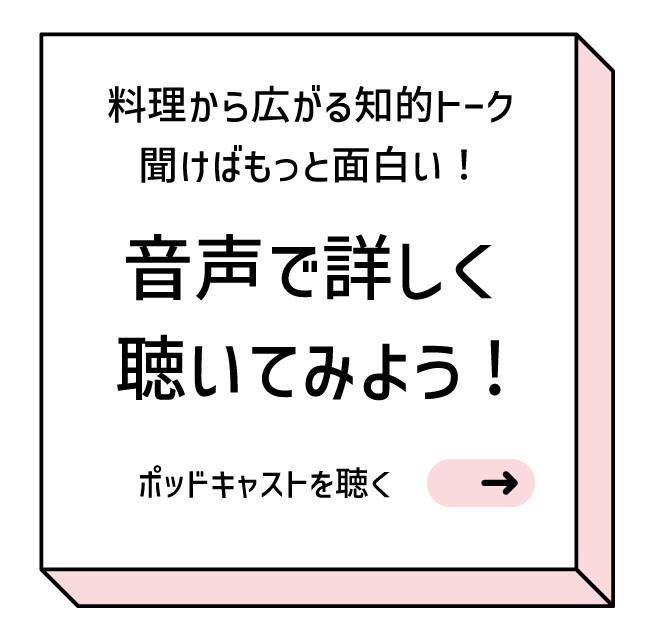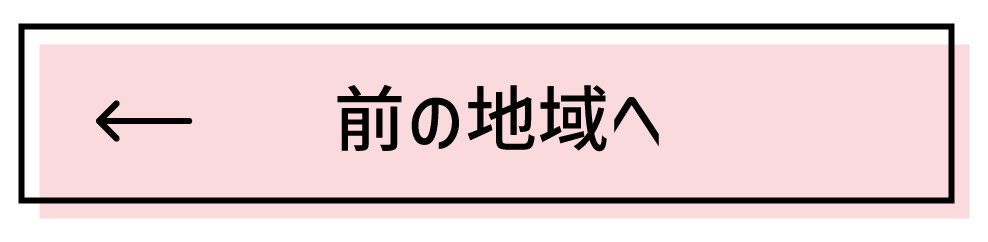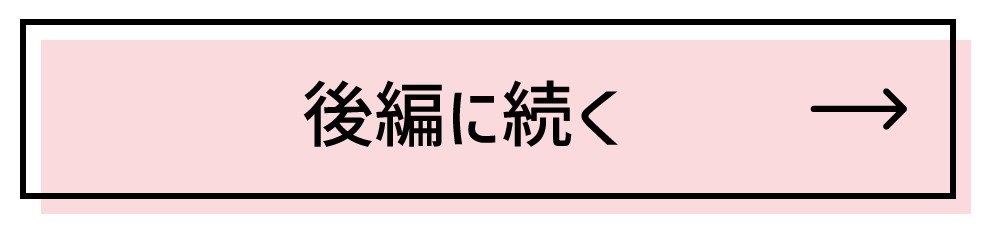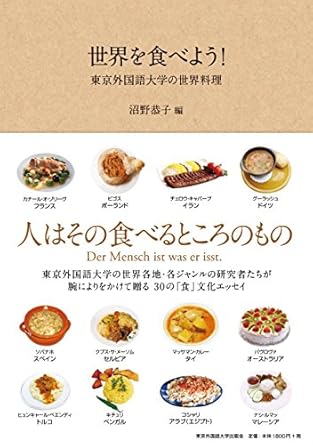地球ディッシュカバリー【第2回・前編】私たちの知らない中東シリア ゲスト:青山弘之 教授
研究室を訪ねてみよう!

お笑いコンビ・ママタルトさんをパーソナリティに迎え、世界の食文化を入り口に、地域の社会や文化を掘り下げるポッドキャスト「ママタルトの地球ディッシュカバリー 〜東京外大の先生と一緒〜」が始まりました。教員の専門領域を、料理や言語といった身近なテーマを通してひもときながら、地域の魅力や国際的なつながりを多角的に紹介していきます。
今回は大学院総合国際学研究院の青山弘之教授をゲストに迎え、日本人にとってあまり馴染みのない中東シリアについて深く掘り下げます。情勢が不安定とされる現在のシリアですが、実は豊かな農業国であり、温かい人々が暮らす魅力的な国でもあります。アラビア料理を味わいながら、シリアの文化、国民性、そして現在の状況について、東アラブ地域の政治学が専門の青山教授に詳しく伺いました。
ゲスト: 青山弘之 教授
東京外国語大学大学院総合国際学研究院 教授。1991年に東京外国語大学外国語学部アラビア語学科を卒業。一橋大学大学院にて博士号取得。ジェトロアジア経済研究所研究員などを経て、2008年に東京外国語大学に着任。東アラブ地域の政治学を専門とし、ニュースメディアなどにも数多く寄稿している。シリアでの滞在経験も豊富で、現地の言語・文化に精通している。近年は日本とシリアの交流促進のためにNPO「シリアの友ネットワーク」を立ち上げ、2023年のシリア地震後の支援活動や日本語教室の開設など、両国の架け橋として活動している。研究者情報
パーソナリティ: ママタルト 檜原洋平さん、大鶴肥満さん
-
緑の砂漠と農業の国、シリア
──今回、ぼくらが青山先生に中東シリアについて教えていただく学びの食卓は、こちら、港区六本木にあるアラビア料理レストラン『アル・アイン』さんです。青山先生はこちらのお店にはよくいらっしゃるのでしょうか。
こちらのお店は、もともと横浜にありましたが、最近六本木へ移転してきました。移転後はまだ訪れていなかったので、今回が初めての来店になります。


──青山先生がアラビア語を学ぼうと思ったきっかけは。
きっかけには「公式な理由」と「非公式な理由」があります。非公式な理由としては、食べ物が好きだったことですね(笑)。
中学生や高校生の頃、中東を舞台にした映画をよく観ていて、外国に触れてみたいという思いがありました。英語は多くの人が話せるので、もっと珍しい言語を学びたいと思い、東京外国語大学でアラビア語を専攻しました。先生方との交流や現地での体験を通して、食べ物も人も含めて本当に好きになりました。大学卒業後も中東とのつながりを持ち続けたいと思い、研究の道に進みました。

──まずはシリアの基本情報を教えていただけますか。
シリアはアジア大陸の西側、地中海に面した国です。北にトルコ、南にヨルダン、サウジアラビアとエジプト、東にイラク、イランが位置しています。国土の広さは日本のおよそ半分ほどで、地理的には「中東」に分類されます。
中東というと砂漠のイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、シリアの緯度は東京とほぼ同じです。冬は寒く、夏は日本と同じくらい暑くなるなど、四季の変化も感じられる気候です。
言語はアラビア語が話されており、これはヨーロッパと同じくらい広い地域で使われている言語です。現在、20数カ国が標準語・国語としてアラビア語を採用しています。その中でも、アラビア語教育のレベルが高いとされているのがシリアとエジプトです。教育面でも非常に注目されている国なんですよ。

──シリアの主な産業について教えてください。
中東の国と聞くと、どうしても石油のイメージが強いですよね。でも、シリアは隣国のレバノンと同様に、実は「農業国」なんです。もちろん石油も採掘されていて、外貨獲得のために輸出されていますが、産業の中心はあくまで農業です。たとえば、今日の料理に使われているような野菜もシリア国内で採れるものですし、地中海に面しているため、柑橘類やオリーブ、麦なども豊富に収穫できます。
また、チグリス川とユーフラテス川が流れているので、灌漑が可能で、農業にとって非常に恵まれた環境なんです。さらに、シリアとレバノンの間には高い山脈があり、そこから湧き出る水を利用してオアシスが形成され、そこでも農業が営まれています。こうした自然の恩恵もあって、シリアの食料自給率はなんと100%を誇っています。
──シリアは砂漠のイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。
確かに「中東=砂漠」という印象を持つ方は多いと思います。でも、シリアの砂漠は一味違うんです。春になるとザーッと雨が降り、すると一面に緑がバーッと広がるんですよ。その草を羊たちが食み、結果として美味しいお肉が育ちます。
シリアの砂漠は「バーディア」と呼ばれていて、そこにはベドウィン(遊牧民)が暮らしています。砂漠というと、何もない不毛の地というネガティブなイメージがあるかもしれませんが、バーディアでは肉がとれ、草も生えていて、ちゃんと生活ができる環境なんです。もちろん、シリア全土が砂漠というわけではありません。緑の多い砂漠も存在していて、自然の多様性を感じられる場所なんですよ。
手で味わうアラブの食文化
──一品目が届きました。これはどのような料理ですか。
まず前菜として出ているのは「メッゼ」と呼ばれるものです。ナスを焼いてすり潰し、ごまペーストを加えた「ムタッバル」、ひよこ豆のペースト「フンムス」、そしてヨーグルトのペーストなどがあります。これらはパン(フブズ)につけて食べるのが基本です。アラブ世界全体で食べられている料理で、日本でいう納豆のように、毎日食卓に並ぶような基本的な存在なんですよ。

──この料理の食べ方を教えていただけますか。
パンをちぎって、ペーストにつけて食べます。オリーブオイルがかかっているので、それも混ぜながら食べると美味しいですよ。アラブ料理は基本的に手で食べることが多くて、サラダも葉っぱで巻いて食べたりします。

──いただきます!・・・・・美味しい!アラビア語で「美味しい」はどう言うのですか。
アラビア語は単語の数が他の言語に比べて何倍も多いと言われています。「美味しい」という表現もいろいろあって、一番普通なのは「ラズィーズ」です。でも、食べたときに心の底から声が出るような感動がある場合は「タイイブ」と言います。また、高貴な方が「美味」と表現する場合は「シャヒー」という言葉もあります。気持ちに合わせて使い分けていただければ大丈夫です。

──こちらは何か葉っぱに巻かれていますがなんでしょう。
これは「ワラカト・イナブ」というブドウの葉で包んだ料理ですね。中にはお米が詰められていて、酸味のある味付けがされています。中東地域ではよく見られる一品で、特に夏に食べると暑さを和らげる効果があると言われています。
隣にあるサラダも特徴的ですね。小麦の粒が使われていて、ドレッシングはイタリアンドレッシングに近い風味です。食べるときは基本的に手掴みなので、大きな葉っぱなどで巻くようにして食べたりします。

──食べるときによく飲まれる飲み物はあるんですか。
基本的に食事中はあまり飲まず、水だけです。食後にコーヒーやお茶を飲みます。朝や夜は紅茶と一緒に軽いものを食べることが多いですね。
食文化から見えるシリアの日常
──シリアの人々の食事の時間や習慣はどのようなものですか。
シリアでは昼食が一番重要な食事です。朝早くから働き始めて、2時頃まで仕事をして、3時頃に帰宅してしっかり食べます。その後はお昼寝をして、夜になると気温が下がるので外に出て遊んだり買い物をしたりします。夜は軽く食べる程度です。夜は2時3時まで活動して、朝6時頃に起きるというリズムですね。公務員や学校の先生などは朝8時から働き始めて、2時には仕事が終わるという6時間労働が一般的です。
──シリアの交通事情はどのようになっていますか?
シリアでは乗り合いタクシー、いわゆるハイエースのような10人ぐらい乗りの車が走っています。相席・相乗りが一般的で、希望する場所で降ろしてくれます。電車については、長距離の電車はあるものの、制裁や内戦の影響でほとんど走っていない状況です。
──そのような状況で人々はどのように移動していますか?
基本的に人々は遠出をせず、自分の町だけで済ませることが多いです。それぞれの町に必要なものが全て揃っているので、あまり他の町に行く必要がないのです。それぞれの町が全然違う特徴を持っていて、とても面白いです。町ごとに独自の文化があり、ボードゲームのように点在しているイメージです。内戦の影響で町と町の間の移動が危険になってしまったという背景もあります。日本の戦国時代のような状況に似ているかもしれません。それぞれの町に独自の文化が生まれ、良い面も悪い面もありますが、良い面がどんどん出てきてほしいと思います。

食事の流れにも文化がある
──続いてこちらのお料理は何ですか?ドラクエのふしぎの木の実のような見た目ですね。
コロッケのような感じで、中に挽肉が入っています。「クッベ」と呼ばれるもので、ドーム型の形をしています。普通は中が見えないように出されますが、今回は中身がわかるように切ってあります。ヨーグルトソースをつけて食べますが、ソースなしでも全然美味しいです。スパイシーで少し酸っぱい味がするのはザクロの風味です。日本でいうとカレーパンのような感じで、サクサクした衣に包まれています。とても美味しいです。これはまだ前菜の段階なんですよ。

──他のお料理はなんでしょうか。
そら豆のコロッケのようなものや、羊やヤギのチーズなどですね。このチーズは日本の居酒屋でも出てくるようなものに似ていますが、羊やヤギのチーズならではの風味があります。これらも全部前菜ですね。
日本では最初にすべての料理がぱっと出てくることが多いですが、シリアやレバノンでは最初に前菜だけが出て、その後に主菜が出てきます。量自体は結構多いです。夜までにお腹いっぱいになるように食べる習慣があるようです。


シリアで暮らして見えた、人の温かさと個性
──シリアで暮らしてみて感じたことや、シリアの人々の国民性について教えてください。
シリアに行くと、文化や習慣の違いをいろいろと感じますが、一番驚いたのは「人の良さ」です。日本人はあまり見かけないので、警戒されるかと思いきや、むしろ好奇心を持って温かく接してくれるんです。
シリアは古くから東西交易の要所で、旅人をもてなす文化が根付いています。日本人として訪れると「お客さん」として歓待されることが多く、街を歩いていると「おいでおいで」と声をかけられてお茶をごちそうしてくれたり、家に招いてくれたりすることもあります。バスで知り合った人が「泊まっていきなよ」と言ってくれることもあるほどです。
治安も良く、例えば私が胸ポケットに札束を入れて歩いていると、それが見えていることを親切に教えてくれる人がいるくらいです。日本人が海外で遭遇しがちな犯罪に巻き込まれることは、シリアではほとんどありません。

-
学びを広げるリンク集
訪れたお店の紹介
アラビア料理レストラン
アル・アイン (AL AIN)
東京都港区六本木3丁目1−25 六本木グランドプラザ 1F(六本木一丁目駅すぐ)
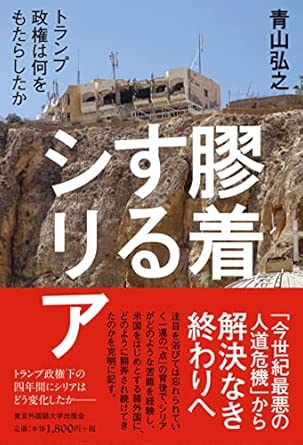
『膠着するシリア トランプ政権は何をもたらしたか』
第一次トランプ政権下の四年間にシリアがどのような苦難を経験し、米国をはじめとする諸外国にどのように翻弄され続けてきたかを、克明に記す書籍です。
『膠着するシリア トランプ政権は何をもたらしたか』青山弘之【著】
ジャンル:国際情勢・中東・地域研究
版・頁:四六判・並製・274頁
ISBN:978-4-904575-91-8 C0031
出版年月:2021年10月28日発売
本体価格:1800円(税抜)
https://wp.tufs.ac.jp/tufspress/books/book69/
世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―
食を通じて文化を知る――そんな体験をもっと広げたい方には、東京外国語大学出版会の『世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―』がぴったりです。料理から見える世界の多様性を、ぜひ味わってみてください。
世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理― 沼野恭子【編】
ジャンル:食文化・料理・地域研究
版・貢:A5判・並製・224頁
ISBN:978-4-904575-49-9 C0095
出版年月:2015年10月30日発売
本体価格:1800円(税抜)
東京外国語大学オープンアカデミー
「もっとアラビア語を知りたい!」と思った方には、東京外国語大学オープンアカデミーのアラビア語講座がおすすめです。言葉を学びながら、シリアやアラブ地域の文化や人々の魅力に触れてみませんか?年に2回の募集期間を設けているため、自分のペースで学び始めることが可能です。さらに、オンラインでの開講により、全国や全世界どこからでも気軽に参加できるのも大きな魅力です。新しい言語を学び、異文化交流の扉を開く絶好のチャンスです。アラビア語を学びながら、未知の世界への一歩を踏み出してみませんか?
詳細・お申込みはこちらからご覧ください:
本記事に関するお問い合わせ先
東京外国語大学 広報・社会連携課
koho[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)