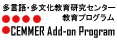1月16日 塩原良和先生の授業終了
コーディネータの青山です。冬休み明け最初の今週の授業は、本学の塩原良和先生に、多言語・多文化社会を考える背景について講義をしていただきました。なお、本日は配付資料はありません。
来週は、多文化共生センターの田村太郎さんの再登場です。
以下は、青山による今週の講義のまとめです。
今日の授業は、多言語・多文化社会を考える背景について考えてみます。定住外国人について、最近、とくに議論されるようになったのは、深刻化する少子高齢化が根本的な理由です。
【ここで、ビデオの上映。ビデオは、ヨーロッパでも、少子高齢化にともない、労働力として移民を受け入れるようになったと説明。】
この問題はヨーロッパだけの問題ではありません。日本につても、社会の生産力を維持するためには、毎年647000人の移民受け入れが必要という国連人口部の移民レポートの推計結果があります。
また、2050年には、日本の総人口1億4000万人のうち4000万人が移民とその子孫となるという推計結果もあります(三和総研の推計結果)。
つまり、これから相当な日本社会の変化が来ることが予想されます。
そこで、未来学者になったつもりで、グループディスカッションをしてもらいます。議論するテーマは、移民(外国人)の導入以外に、少子・高齢化と労働力人口の減少という問題を解決する方法はあるのだろうか?というものです。ヒントとして、1)子どもを増やす?2)労働力を増やす?3)労働力が少なくともやっていける社会にする?という選択肢をあげておきます。
【グループ・ディスカッションの時間のあと、グループごとに学生の回答を出してもらう。】
学生の皆さんの回答をふまえて、いくつかの選択肢について検討してみます。
1. 子どもを増やすという選択肢:
・少子化対策に熱心な他の先進諸国も、合計特殊出生率を十分に上げることができていない。
・未婚化・晩婚化:実際には「結婚したくてもできない」女性が多数派。
・子育てのコストの増大と家計の経済的不安定。
2. 労働力を増やすという選択肢:
・出稼ぎは、地方の過疎化・荒廃を招く。
・女性の社会進出と男女共同参画→女性の労働力率はすでにかなり上がっている。
・男性の終身雇用の崩れにより、夫婦共稼ぎが家計安定のための合理的選択になっているという現実。
→男女共同参画の推進は一定の対策となりうるが、限界もある。
・ニート対策:35歳未満のニートの数は約130万人(2003年)→労働力不足の抜本的解消にはほど遠い。
・高齢者の再雇用と言っても、彼らには3Kの職場はきつい。
3. 労働力が少なくともやっていける社会にするという選択肢。
・しかし、どうやってそのような社会を築くのか?
・自給自足?
・脱工業化の進展:産業構造の高度化(製造業→サービス業)、高度消費社会(モノつくり→ソフトつくり)
→しかし、その場合でも、専門職種、消費社会を下支えする大量の非熟練サービス労働者や建設労働者が必要
→彼・彼女らはますます低賃金・非正規雇用化。
・避けられない課題としての、外国人受け入れ→だからこそ、日本社会にはすでに200万人の外国人住民がいる。
・日本社会はどのように変化していくのか、どのような社会が望ましいのかを、広い視野に立って構想してみる必要がある。
授業のあと、いくつか質問がありました。
1)フランスの人口6000万人、1904(明治37)年の日本の人口が4,613万人であったことを考えてみれば、人口が1億人を越える現在の日本にとって、少子高齢化による労働人口の不足と言っても、いったいどれくらいが適性なのか?
2)非熟練労働者による消費社会の下支えとして外国人労働者の受け入れが不可避であるとする考え方は、国際間の南北格差を助長・維持・拡大につながるのではないか?
これらについてのより深い議論は、最終回の総合討論に持ち越されました。
- by AOYAMA Toru
- at 2007年01月18日