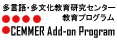12月5日 伊藤マヌエルさんの講義終了
コーディネーターの青山です。本日は伊藤マヌエルさんから、在住外国人としてのご自分の経験をかたっていただきました。個人的な経験にも触れて、静かな口調でしたが心の内面に迫るお話でした。なお、本日は、配布資料はありません。
来週は、多言語・多文化教育研究センターのプログラム・コーディネータの杉澤経子さんに、前の勤務先である武蔵野市国際交流協会での経験もふまえて、外国人とかかわる地域に根ざしたコミュニティー・ネットワークのあり方について語っていただきます。
今週の講義は、初めに40分ほどのお話をしていただき、そのあと20分ほど青山と伊藤さんのあいだで質疑応答をおこない、残りの時間で学生からの直接の質問を受け付けました。学生からの質問がもう少し積極的にあればよかったように感じました。グループ・ワークをいったんした方が質問が積極的にでるようです。ただし、いつでもグループ・ワークでの議論の材料が出てくる講義テーマとは限らないので、グループ・ワークをするかどうかはいつも思案のしどころです。
以下、今週の講義のまとめです。個人的なお話が多かったので、概略のみとさせていただきます。
アルゼンチン生まれの伊藤さんは、両親が日本に住むことを決断したことから、中学1年生のときに家族と共に日本に住み始めました。自分としてはアルゼンチンに住みつづけることを希望していました。
スペイン語を母語とする伊藤さんは、はじめ中学校では、教科によって教室を移動することがわからないなど、日本語が不自由であるゆえの苦労を経験しました。しかし、部活などを通じて日本語の表現を吸収しました。高校に進学の受験では、大学生の学習支援ボランティア団体である
高校・社会人になってからは、CCSでスペイン語圏の子どもの支援をしたり、ラテンダンスを披露したりする余裕もあり、自信がつきました。
高校を出た後は、現在の会社に就職することができました。会社では、学校時代とは違う敬語の問題など言語の壁があったが、他の社員と同じように研修や社内教育を受けることができ、仕事にもやりがいを感じています。
自分の回りに壁にぶつかっている在住外国人がいるのを見て、自分たち自身で何かをやろうと思って、仲間といっしょにHome for Voiceという組織をつくりました。これは、自分たちの居場所とそこから声を発信していく為のホームという意味です。高校生から30代の人までの十数か国の人々が参加しています。エンパワー・キャンプなどを企画しています。
今年、15年ぶりにアルゼンチンに戻る機会がありましたが、今、大人の目でアルゼンチンを見ると、自分の生活の基盤が日本にあるということを強く感じさせてくれた旅行となりました。
お話は以上で、このあと質疑応答に入りました。
アイデンティティの話では、アルゼンチン人としてのアイデンティティと日本人としてのアイデンティティを共有しているという話が興味深かったでした。
Home for Voiceについては、在住外国人に居場所を提供するためのものだが、将来的には日本人も含めた企画も考えてみたいとのことでした。また、Home for Voiceとして現在は、日本社会への提言のようなことは考えていないが、難民の強制送還問題に関連して署名運動をしたことがあるとのことでした。
最後に、高校のなかには入学に際して外国人枠を設けていることがあるが、その是非はどう思うかという学生の質問に対しては、楽に入れてもあとで苦労することもあるから、外国人枠で入学するかどうかについては本人が慎重に決める必要があるし、又、両親又は学校の先生、支援してくれている団体等選択するに当たってはメリットとデメリット等の説明・アドバイスも必要であるのではと思います。
- by AOYAMA Toru
- at 2006年12月05日