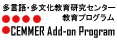12月12日 杉澤経子さんの講義終了
コーディネーターの青山です。今日は、多言語・多文化教育研究センターのプログラム・コーディネータの杉澤経子さんに、前の勤務先である武蔵野市国際交流協会(MIA)での経験もふまえて、外国人とかかわる地域に根ざしたコミュニティ・ネットワークのあり方について語っていただきました。講義にはパワーポイントが使われました。
配付資料はありませんが、講義でも触れられた「都内リレー専門家相談会」を紹介する文章と、桑山紀彦著『多文化の処方箋』を紹介する文章(いずれも杉澤さんの書いたもの)が参考資料として配付されました。必要な方はセンターまで取りに来てください。
今週の講義は、講義の前後に青山がこの講義の位置づけの説明と次回の案内をした以外は、すべて杉澤さんにお任せしました。杉澤さんの講義はグループ・ワークを取り込んだ形で進められ、最後に残った15分間で学生からの質問を受け付けました。グループ・ワークの進行はパワーポイントの説明があったのでわかりやすかったと思います。グループ・ワークの結果はコメント・シートの裏に書き込み、授業の後で提出してもらいました。学生からの質問がいずれも的確で、しかもしっかりとした内容(講義の関連部分に言及、疑問のポイントを説明、なぜ疑問に思ったのかの説明)だったことに感心しました。
今日は今年最後の授業です。冬休みの間に、NPOの企画作りを進めてください。次回は1月16日、センター教員の塩原良和さんの講義です。
以下は、青山のまとめです。なお、詳細はパワーポイントを参照してください。
------------------------------------------------------------------------------
若い頃、大学を卒業してすぐにタイのバンコクに駐在していました。そこでタイ人の少女を連れてホテルにやってくる日本人の男性たちをよく見かけました。彼女たちに話を聞くと、タイの貧しい地方から連れてこられたこと、彼女たちの仕送りで一家が支えられていること、日本人の客は他の外国人よりもやさしいから好ましい、ということでした。もし仮に、このような日本人男性の行動が禁止されたとしても(現在では不法行為)、今度は彼女たちの生活が行き詰まることを知り、ジレンマを感じました。
バンコクにあるクロントイというスラムを訪問し、貧困にあえぐ多くの子どもたちを見ました。このスラムで長年教育ボランティア活動をしてこられたプラティープさんという女性がいます。彼女の活動を見て素晴らしいと感じつつも、自分にはとてもできないというジレンマを感じました。
【プラティープさんには夫の秦辰也さんとの共著『体験するアジア―ボランティア夫婦の日本・タイ共生論』があります。】
帰国後、途上国からの研究生たちと話す機会がありましたが、彼らから、自分たちは日本語もできるし、何年も日本に住んでいるのに、日本人はだれも家に招いてくれないという不満を聞き、なぜなのだろうという疑問をいただきました。
その後、1989年に武蔵野市国際交流協会に就職し、行政の立場から国際交流、在住外国人の支援に関わってきました。しかし、あるとき、両親がオーバーステイの3歳のフィリピン人の子どもが重い病気で苦しんでいるのに、行政の立場からは何の手助けもできないという経験をしました。行政は人の幸福のためにあるのになぜ無力なのかというジレンマを感じました。
このような若い日々に感じたジレンマが今の私の活動の原動力になっています。
【ここでグループワークにはいりました。このグループワークは、人から人へ情報を伝えることの意味、それをネットワークとして共有することの意味を考えることを目的としています。もっと深く考えてみたい人には金子郁容著『ボランティア―もうひとつの情報社会』が参考になります。】
武蔵野市国際交流協会の活動として、外国人のための日本語学習支援をおこなっていくうちに、外国人が抱えているさまざまな問題が掘り起こされてきました。このような問題を解決するためには、1)言語と文化の専門性をもった人々が必要、2)日本の制度を説明できる専門家が必要、3)日本人側の意識を変えることが必要、といった壁があります。そこで組織されたのが、東京外国人支援ネットワークで、問題解決のための具体的活動が「都内リレー専門家相談会」です。【パワーポイントおよび参考資料を参照】
これは、都内の国際交流協会が中心となって、行政、専門団体、NPOなどで構成されるネットワーク組織です。在住外国人の間では情報はそれぞれの使用言語のチャンネルで流れますから、行政地区単位では対応できません。
「都内リレー専門家相談」で重視しているのは、毎回相談会のあとで開く、専門家、通訳を交えてのフィードバック・ミーティングです。ここで出される情報を吟味し、徹底的に共有することがネットワークの構築にとって大変に重要です。
コミュニティ・ネットワークでは、必要としている人に必要とされる情報を伝えることが肝要ですが、このことが実は大変に難しいことです。
NPOは、多文化化する日本社会の問題を解決していくための(唯一ではありませんが)一つの方法です。
------------------------------------------------------------------------------
このあと、学生との質疑応答がありました。2点、取り上げます。
都内リレー専門家相談で得られた情報を、より広く社会にフィードバックすることはされているのか、という質問がありました。それについては、個人のプライバシーに関わることなので、ここで得られた情報はまず専門家の手を経た上で、社会に還元されるようになるとの回答がありました。多言語・多文化教育研究センターには研究部門があり、ここが現場で得られた情報を社会へ還元する役割を果たしていくことが期待されます。
次に、学生が都内リレー専門家相談にボランティアとして参加することはできるのか、という質問がありました。相談会では離婚や家庭内暴力(DV)など重い事例が多いので、学生では対応できないが、会場への道案内や会場設営などを手伝うことによって、すこしずつ現場の雰囲気を知ってもらうことは可能だとの回答がありました。多言語・多文化教育研究センターのAdd-on Programでは、2008年度から実習部門としてボランティア活動やインターンシップを取り入れた授業を開講する予定です。この中に、提案された活動などが取り込めないか検討していきたいと思います。
【追記】
杉澤さんの講義用パワーポイント資料はご本人の要請で削除いたしました(2010-04-12)。
- by AOYAMA Toru
- at 2006年12月13日