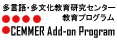11月7日 中西智恵美さんの講義終了
コーディネーターの青山です。本日は法廷通訳人の中西智恵美さんに、法廷通訳のお仕事について語っていただきました。外国人の被告にも公平な裁判を受けてもらうことが大事であり、法廷通訳はそれを支える大切な仕事だということがよくわかるお話でした。
来週は、矢崎満夫さんから公立小中学校での国際学級についてのお話をうかがう予定です。
以下、青山による今日の講義のまとめです【12月13日に修正しました。中西さん、ご指摘ありがとうございました。】。なお、本日はA4版1枚の配付資料があります。必要な人はセンター(319)でもらってください。
***************************************************************************
法廷通訳をおこなう人を法廷通訳人と言う。16年間法廷通訳をしてきたが、最近は外国人の数が増加すると共に、国籍も増加し、犯罪の種類も多様化してきたように感じる。かつてはオーバーステイのほかに売春、麻薬くらいだったが、今は日本人による犯罪と変わらない。
レジュメの表からわかるように、2006年に外国語で裁判(第1審)を受けている者のうち、中国語による者がもっとも多く(43.6%)、増加中である。10年ほど前にはペルシア語が2番目に多かったが、現在は上位10番にもはいらず、「その他」の項目に含まれている。逆にベンガル語が増えて9番目にはいっている。
現在、全国で52言語、3772人の外国語通訳人が裁判の名簿に登載されている。通訳人の数が多い言語もあるが、ベトナム語やルーマニア語のように数が少なく、所在地にかたよりがある言語がある。スペイン語は1997年の時点で200人ほどおり、多い方である。
私の場合は個人的なつてでこの仕事にはいった。今は公報で通訳人を募集している。試験はないが、面接とセミナーを受けて、法廷通訳の仕事につく。法廷での通訳が主であるが、事前に弁護人が接見するときにも通訳が必要である。被告人、通訳人の双方にメリットがあるので、事前の接見通訳にも同じ通訳人がつくことが多い。
他に手紙、起訴状など書類の翻訳もある。また、外国人が証人、被害者である場合にも通訳になる。1回で終わることもあるし、数回になることもある。
通訳は、同時通訳ではなく、逐次通訳である。書類の場合は、起訴状、判決文以外は、同時に読み上げあげる。起訴状、判決文は被告人にしっかりと聞いてもらう必要があるので、聞き終わってから通訳をする。
他の通訳と比べて、極端なまでに正確な訳が必要であり、一語一句もらさず、訳す。落とすな、変えるな、まとめるな、という心構えだ。たとえば、3回「ごめんなさい」と言ったら、3回訳す。ながながした話や、言い間違いも、そのまま通訳する。裁判官は通訳された言葉にもとづいてしか判断できないからだ。
単語を機械的に訳していると問題になることがある。証人がコロンビア人だった麻薬関連の事件で、証人が「ポルボを片づけよう」と言った。ポルボには、粉の意味とほこりの意味がある。掃除をするときにこの言葉を発している。訳し方で解釈がかわる例だったので、あえて「ポルボ」というスペイン語のまま訳した。これをどう解釈するかは裁判官、検察官、弁護士にまかせる。
別の例では、スペイン語の「上」を意味する語は、何かの表面上を意味することも、上方の空間を意味することもある。被害者の「上」にのって鞄を掴んだのか、ずっと上の方から鞄を掴もうとしたのかでは、印象が異なる。こういう場合は、より細かく聞き直してもらう。
日本語がある程度できる外国人の場合、話の途中で日本語になったり、外国語になったりする。また、日本語であっても外国人のあいだでだけ通用する日本語がある。たとえば、スペイン語圏の人たちにとって「お店」は、水商売の店、風俗店を指すことが多い。定冠詞をつけて「エル・オミセ」と言ったりする。「マニージャ」という言葉は「マネージャー」から来ていて、売春婦の管理者のことだ。
文化面にも考慮する必要がある。スペイン語圏では、父と母の名字が違うことも多い。しかし、裁判官は父と母の名字が違うと、籍に入っていない家庭の子どもと見て、心証を悪くすることがある。この場合には、通訳を中断して、裁判官に文化的違いを説明する。
また、親しい間柄でも、個人名で呼び合っていて、名字を知らないケースも多い。名字を知らないから、親しい仲ではないといった誤解をまねくこともあるので、注意を要する。
法律用語の知識をもっている必要もある。辞書に載っている訳語のとおりにいっても通じないことがあるから、自分でも用語の意味をよく理解している必要がある。たとえば、「執行猶予」などといった用語も、システムが違うと意味が通じない。
外国人の場合、日本人なら裁判にならないようなケースでも裁判にもちこまれることがある。たとえば、歯ブラシ3本盗んだとか、パン1個を持ち逃げしたとかいったケースだ。
法廷通訳人の質も問題になる。スペイン語の場合は選ぶことができるが、少数言語の場合は、法廷通訳人がいるだけで満足しなければならない。また、少数言語の場合は、事件の数も少ないので、能力を伸ばす機会もすくない。
裁判の手続きの流れがわかっていないと、トラブルがおこることがある。また、国によっては、被告人が訴えを取り下げたら裁判が終了する国もあり、被告人が苦情を言うことがある。
一度、裁判が始まると、とくにビザがない場合など、長期の拘束になる傾向がある。迅速に裁判をすることが必要だ。今後、裁判員制度が始まると変わってくるだろうが、通訳がはいるとどうしても時間がかかる。広島のヤギ事件の場合には、特例で、大阪から呼んだ通訳人を2人いれて、集中的におこなった。
何かの拍子に犯罪をおこしたケースがかつては多かったが、最近は、初めから犯罪をしようと来日するケースも増えているし、凶悪な事件や、集団による大がかりな事件も増えているように思う。少年犯罪の場合は、本人は日本語が流ちょうな場合が多いが、親の日本語能力が不十分なために、法廷通訳を必要とすることがある。親子のコミュニケーションの不足が犯罪の要因と感じる。
外国人の犯罪であっても、日本人と同じように裁判を受けられるようにすることが大切だ。一つの取り組みとして、裁判の流れの説明を各国語版のビデオで作成し、あらかじめ見せて、裁判の流れを理解させるようにしている。
法廷通訳のためには、特殊な用語の手引きとなるハンドブックを作っている。新人の法廷通訳希望者には、模擬法廷によってトレーニングをおこなったり、セミナーをうけてもらったりして、適切な人選ができるように努力している。現在は、資格試験はないが、将来的にはできると思われる。
家族や知人、友人で傍聴に来る人が最近は増えてきた。傍聴者が多いと裁判官への心証もよく、きっちりとした判決が期待できる。横浜では市民グループが活動していて、外国人の裁判を傍聴して、正しく行われているかをチェックしている。東京には残念ながらまだない。
ヤギ事件以来、入官審査が厳しくなった。日系ペルー人の集住地域では、個別訪問もあったと聞く。しかし、肝心なことは、来日し在住する外国人に対しては、犯罪を起こさせないようにすること、そのために、正しい法律を知ってもらうこと、それでも犯罪を起こした場合には、公正な裁判を受けてもらえるようにすることである。
***************************************************************************
【講義の進め方】紹介などで5分。50分の講義のあと、「もし自分が法廷通訳人だったらどのような心構えをもつか」というテーマで15分間のグループ・ディスカッションをおこない、続いて、グループごとに発表してもらった。これを受けて中西さんに応答とコメントをしてもらった。これに20分ほど使った。法廷通訳人は被告人に対して住所、名前を明かさないといった話もうかがえた。最後に、法廷通訳が国の制度としてきちんと確立しておらず、職業として生計をたてていくうえでも問題があることが指摘された。法廷通訳人と被告人とのコミュニケーションという側面と、法廷通訳という制度の側面のうち、後者について議論を深める時間がなかったのは残念だった。
【2006年11月7日掲載、12月13日に修正版を掲載しました。】
- by AOYAMA Toru
- at 2006年11月07日