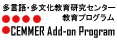11月29日 名越康文さんの講義終了
コーディネーターの青山です。本日は精神科医の名越康文さん在日外国人のメンタル・ケアについてのお話をうかがいました。医療現場の生々しい話をたくさんうかがうことができました。
精神科医療について学生側に予備知識があまりないであろうと予想されたので、今回は授業進行のやり方を少し変えてみました。最初の50分は名越さんの話をうかがい、そのあと15分ほど青山が名越さんと一対一で質疑応答をしました。残りの時間を使って、学生から個別に質問を受け付けました。グループワークはおこないませんでしたが、青山との質疑応答の中に、疑問に対する答えが見つかれば幸いです。
来週は伊藤マヌエルさんから定住外国人の視点からのお話をうかがう予定です。なお、来週は授業時間のうち10分ほど使って授業評価アンケートをおこないます。ご協力をお願いします。
以下、今日の講義のまとめです。塩原先生に作っていただいた文案に青山が少し手を加えました。なお、本日は配付資料はありません。
------------------------------------------------------------------------------
そもそも精神科医は何をやっているのかから話したい。
先日、恵比寿にある職業訓練校で講義をした。そこはネイルアートやヘアデザインの学校だが、ドロップアウトする女の子がすごく多い。年間10%以上も脱落してしまう。何が原因かというと、ほとんどは恋愛が理由だ。すごく優秀な生徒が、突然辞める。「彼が、働いてほしくないというから」というのが理由だ。ドロップアウトの多さを危惧した学校が統計をとったら、その学校の生徒の20数%が、精神科の通院歴があった。実は、僕は、そのくらいの専門学校の生徒だったら、そのくらいはあるだろうと予測はしていた。精神医療は身近な問題になっていると確信した。
精神科の外来は、昔は分裂病が主流だった。現在は、この分裂病は軽症化の傾向がある。普段はほとんど僕たちと変わらない人もいるということもあり、現在は統合失調症という呼び方に変わっている。統合失調症の患者は、外国人住民のあいだにもみられる。統合失調症の患者は、90%の時期はすごくおとなしい。自分の声が他者の声のように聞こえてくる幻聴のように、むしろ、言われるままになってしまうことがある。
しかし、統合失調症はこの10年間のあいだに激減し、精神科医の外来の患者の様相は激変した。現在は、うつ病を多く診ている。うつ病に付随して、神経障害、不安障害、適応障害などの患者もある。
かつては、あらゆる神経科の病気は人口の100分の1以下であるというのが常識であったが、それはこの10年間のあいだにもろくも崩れ去った。軽症も含めれば、国民の20人にひとりはうつ病であると考えられている。小中高の教員の20%がうつ病という報道もある(注1)。私のクリニックでは思春期の人を対象にしているが、患者さんも60%がうつ病である。ほかには、対人関係で悩んでいる人が20%、それ以外の病気が20%である。
この傾向はおそらく、在日外国人でも一緒である。以前、大阪で開業していたが、東成区や生野区の人口の多くが在日韓国・朝鮮人である。その人たちやニューカマーの外国人をみていても、そうだといえる。
昔、外国人を見ていた頃は、ほとんどは救急患者だった。日本人でもそうだが、外国人の場合はなおさら、病気を発見するような試みはなされない。「怠け者」「酒飲み」「ダメなやつ」といった解釈をされてすまされていた。こういうケースは、ちゃんとした検査をしないと掘り起こせない。90年代に、ようやく日本でも精神科に救急をつくらなければならないということになり、千葉や東京で精神科に緊急救急センターがつくられた。大阪でもつくられ、そこに、かなりたくさんの外国人の患者さんが入院した。
当時は、「ジャパゆきさん」という言葉がはやった。フィリピン人女性の飲食、風俗産業従事者などのことで、悪徳業者やヤクザが絡んでいるケースも多い。僕が最初に見たフィリピン人女性は21歳で、彼女を日本に連れてきたヤクザの男と肉体関係にあった。厳格なカトリック信者だったので、肉体関係をもった男性とは絶対に結婚しなければならないということですごい混乱状態に陥って病棟に運ばれてきた。急性期の統合失調症の様子だった。鎮静剤を打っても3日間くらい起きたまま、興奮状態にあった。服を着せてもすぐ脱いでしまい、自分の排泄物を壁になすりつけることが続いた。
別のケースでは、20代半ばのタイ人の男性が大阪の飲食街で混乱状態に陥って大暴れした。取り押さえるときに警官から殴打をうけ、ボコボコにされて入ってきた。鎮静剤を打っても、落ち着いて話ができるまで5日間くらいを要した。
こうした患者さんと相対するときに困る問題が3つある。まず第1は、コミュニケーションである。混乱状態になれば、母語しか使えない。母語をネイティブの速度で話すからまったくわからない。それに、ボランティア通訳をお願いしても、すぐには来てくれるものではない。ただし、フィリピン人の場合にはカトリック教会のネットワークがあり、助けをもとめられる。タイ人の場合はそういうツールがまったくない。そう言う場合でも、コミュニケーションの糸口になるただひとつのツールは「数字」である。1、2、3という数字はほぼ世界共通。本人が何がいいたいときに、数字をつうじてコミュニケーションを試みているうちにラポール(信頼関係)ができることがある。
第2に、もっと大変なのが「お金」の問題である。医者がもっと診たいと思っても、「健康保険がない」というのは大きなネックになる。日本の健康保険では本人の負担は3割である。そのうえで、いろいろな規定によって負担を軽減するシステムがあるが、そのためには、まず健康保険に入っているということが基本である。しかし、外国人は健康保険に加入していないが多い。その場合、どこがお金を出せばいいのかという問題がおこる。
ソーシャルワーカーがお金を集めてくることもあるが、それでも無理な場合は母国に連絡をとって家族に払ってもらう場合がある。しかし貨幣価値が違うので、家族にとっては大変な負担になる。このように、診療の難しさの根本は、お金にある。たとえばフィリピンの女性で、妊娠しており、重度のうつ病の場合、家族の誰に言えばいいのか?金銭的問題に直面すると、患者を掘り起こしても、治療はそこで止まってしまう。
3番目に大変な問題は「通訳」である。血液検査やレントゲン検査ができる身体疾患とちがって、精神科の場合は、最後まで問診なので通訳が必要。しかし通訳の実力次第で、患者の心の内部が伝わるかどうかが変わってくる。相手のニュアンスをうまく汲み取って通訳してくれる人もいれば、それだけの力がない人もいる。それはキャリアの差で、だいたい10回ほど経験を積むと、初心者と雲泥の差が現れる。
精神科の患者のあいだにも国民性の違いがある。イギリス人には理性的な人が多い。イタリア人にはマッチョが多く、芸術に対する造詣が深い人が多い。感情の表出の仕方も全然違う。また、日本人は世界で一番時間にうるさいが、外国人の場合は、時間どおりに外来に来てくれる患者さんは20%くらい。それから、家族のなかでの距離感も本当に違う。
僕が病院で診察した外国人患者さんはラッキーな部類に入る人たちだった。あるとき、入管センターに収容されている患者さんを見に行ったことがある。大阪の茨木市にある入管センターは収容者が多くてパンク状態で、小さい部屋に6人入っている。殺伐とした環境であるうえに、母国に帰ると厳しい処罰が待っている可能性がある国の出身者もいる。そういう状況で長期間拘留されると、拘禁反応が起こり、錯乱状態になる人もいる。本当に怪我して病院に運ばれる人もいるが、わざと病院に運ばれるために自ら怪我をする人もいる。そこで診断する際には、専門家としては厳しい判断を迫られる。
(青山教員との対談)
青山:うつ病患者の急増には、診断の敷居が低くなったということもあるのではないか?
名越:それはあると思う。日本全体が、自分が弱者でいたほうが楽なのだという流れにあると考える研究者もいる。うつ病には確定診断はないので、どれだけの人がうつ病になるかは、ファジーな領域ではある。しかし、実際にうつ病と診断された場合、世間では「治る病気」と宣伝しているが、うつ病の中核群は世間でみられているほど軽くはなく、激しい病気であるとは確か。
青山:薬で治すということは意味があり、また、完治するのか?
名越:うつ病は、カウンセリングで治しているのはごく一部である。一つの理由は、薬なら診療で保険がきくので数千円だが、カウンセリングだと1回1万円以上かかる。たしかに薬は効果があるが、いつ薬を絶ったらいいのかということがひとつの問題としてある。また、患者自信に自分は服薬しているという後ろめたさが生じる。どの病気でも最低半年から1年は飲む。薬をやめた後も、半数が再び薬をのみはじめている。
青山:ストレスの影響は?
名越:適度なストレスは必要だ。しかし、過剰なストレスは負担になる。多くは、ストレスがかかったときに出口・代替案が見えるかどうかが大きい。いつまでがまんすればいいのか、どこに出たら解放されるのかということがわかれば良いストレスになるし、袋小路感があると、悪いストレスになっていく。刑務所を訪問したときに、死刑と終身刑は全然ちがうと言われたことがある。死刑囚は出口がない。しかし、終身刑なら、模範囚ならば20年くらいで出所できるかもしれない。両者はまったく違う。
青山:外国人のうつ病患者も増えているというが、いわゆる日本人の国民性だけでは説明がつかないということか。
名越:日本で働いている中国人なども、うつ病になると、日本人の患者さんと本当に変わらない表情になる。その文化の枠内というものがある。うまく日本に適応している人こそ、過剰適応の餌食になり、家に帰ると疲弊してしまうということが起こるような気がする。ペルー人でもブラジル人でも、うつ病になるときには日本人的なうつ病になることが多い。ある意味で日本文化に適応したが、そこで自文化との断絶が生じている。
青山:定住の在日外国人は、「日本人として」うつになってしまう。一方、ニューカマーの外国人は、日本人に適応していく過程でうつになっているということか。
名越:そうだと思う。在日2世・3世の例だが、両親の世代が自分たちだけでがんばるという人たちで、本人が日本企業に勤めてうつになった場合、親が非常に強い人で「負けたらアカン」と言って、治療の許可をもらうことが、非常に困難という経験をしたことがある。
青山:NPOなどで学生たちができることは何か?
名越:自分はすべての面でNPOにお世話になっていると思う。人的資源という意味ではすごく助かっている。しかしいっぽうでは、精神科というのはすべて行政に関わっているものなので、せっかく来ていただいても医療システムがわかっていないので機能しないというケースがあったことも事実である。医療システムのなかでどのようにNPOが関われるのかがひとつの課題である。もうひとつ、NPOの長所として、自由な議論ができるということがある。医者やそれ以外の分野の人々がNPOに集まって議論すれば、先進的な議論ができ、それをもう一度医療現場に持ち込むこともできる。
(学生などからの質問)
高橋教員:うつ病が増えて統合失調症が少なくなったのは社会的な要因があるのか?
名越:統合失調症が軽症化したのは、よい治療薬が発明されたということも大きかった。副作用が非常に少ない。また、うがった見方であるが、社会心理学的にみると「オタク文化」が日本文化になったことも大きいと思う。そのため、濃厚なコミュニケーションが不要になった。こういう薄いコミュニケーションは分裂気質にはすごく親和性がある。それとは別に、分裂気質の人は生身の温かさを求めるので、明るく振舞うと、家に帰ると疲れてしまう、というジレンマがあるということができる。それから、環境問題からも説明がつく。躁鬱気質とは、これまで世界を汚してきた人々。分裂気質の人々は世界を汚さない。分裂気質の人が増えたほうが環境は守られる!という人もいる。
学生A:外国人が診療に来る状況で、働くために来た人と、留学生とでは症状に違いはあるのか?
名越:発病の背景には、日本文化との違いが大きかった人もいたいっぽうで、複雑な家庭環境の人もいた。たとえば、関西の大学の中国人留学生だった患者の主訴は、とにかく勉強ができないということだった。うつ病の人だと極端に集中力が衰えてしまって新聞も読めなくなってしまったりする。この患者は、感情の起伏が激しくてなかなか本音をいえなかった。2年くらいたつと、突然、衝撃的な家庭の過去を話し出した。自分の母親が父親に毒殺されたと訴えたのだ。それが事実かどうかはともかく、母親が重度の人格障害であったなかで本人がそのことを確信するにいたったのは確認できた。
学生B:外国人の患者だと、治療の途中で帰ってしまう人もいるのではないか?
名越:精神科における「心を開く」というのには、二つの意味がある。「コンプライアンス」、すなわち治療のベースにはなっているという心の開き方のことと、より深く心を開いてもらうことである。より深く心を開いてもらうレベルでは、外国人患者の場合は言語コミュニケーションの不足が大きく、日本人よりも時間がかかることがある。しかし治療ができないというわけではなく、薬による治療は可能だ。上記の中国人留学生でも、カウンセリングで深い話ができるほど日本語の語彙数がなかった。
青山教員:精神科医の側も、言語のコミュニケーション能力を高めることが重要か?
名越:重要だと思う。多忙な日本の医療現場における外国人への診療という問題点がある。
(文責:塩原による記録に青山が修正・加筆)
注1:asahi.comの記事によると、小中高学校の男性教師の抑うつ感は他職種の1.8倍とのこと。
- by AOYAMA Toru
- at 2006年11月29日