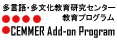11月14日 矢崎満夫さんの講義終了
コーディネーターの青山です。本日は矢崎満夫さん(静岡大学教育学部、元東京都小学校教員、日本語国際学級担任)に「日本語を母語としない子どもたちへの支援―ここまでの自分、そしてこれから―」というタイトルで公立小中学校での日本語国際学級についてのお話をうかがいました。児童生徒を対象にした実践の報告であるためか、授業が終わってからも学生たちの質問が絶えませんでした。
来週は外語祭のため休講、再来週11月28日に精神科医の名越康文さんに外国人のメンタルケアについて語ってもらいます。
以下、青山による今日の講義のまとめです。なお、本日は配付資料があります。必要な人はセンター(319)でもらってください。
はじめに、矢崎さんが、自分の夢を追いかけて実現されてきたこれまでを振り返って、日本語国際学級担任になるまでの経歴を語られました。
--------------------------------------------------------------------------
小学校教員を辞めて青年海外協力隊員として中国へ行き、吉林省長春大学で日本語教師となりました。その後、いったん帰国したのち国際交流基金日本語教師としてオーストラリアに赴任し、クイーンズランド州立高校で日本語を教えました。帰国後、教員採用試験を受け、渋谷区立小学校に着任し日本語クラス担当になり、通級制日本語クラスの立ち上げに参加しました。学校の統廃合のため、別の小学校に異動し、その後、再び、オーストラリアに渡り、国際交流基金日本語教育専門家としてニューサウスウェールズ州教育省において日本語教育アドバイザーを勤めました。帰国後は、目黒区に異動し、区内小学校の国際学級担任になり、2006年4月に静岡大学教育学部に着任しました。
経歴の紹介のあと、目黒区での日本語国際学級集会の様子についてのビデオが上映されました。ここで、矢崎さんから質問がありました。1)ビデオの中に全部で何人の児童が登場しますか。2)その子どもたちはどんな背景をもった子どもたちですか?3)その子どもたちは、この後、どんな活動をするでしょうか?
ビデオには、ドイツ語、英語、ラオス語、フィリピノ語、ヒンディー語、ウズベク語、中国語、ロシア語、キルギス語をしゃべる23人の子どもたちが登場しました。彼らは、両親が外国人の子どもたち、帰国子女、国際結婚の子どもたちといった背景をもちます。さらに、23人中14人は通級制の児童です。それぞれの言語で挨拶を言ったあと、観客を含めて全員で英語、フィリピン、中国語を使ったじゃんけんをしました。600人を前にして自分の母語で大声で言う勇気を持ったと言えます。
続いて、日本語国際学級での取り組みの変遷について説明がありました。オーストラリアでゲームやタスクを通じて日本語を教えた経験から、日本語授業は「楽しく!」を基本にしました。しかし、異動先の学校で、日本語をしゃべることはできるが、教科の勉強に追いつけない子どもたちがいることに気付かされました。たとえば、「二等辺三角形」を理解するためには、漢字、読み方、概念の3要素を結びつけなければならないといったポイントがあります。また、日本人の友人とかかわれない子どもたちが目立つことにきづきました。この点については、大学院でならなったソーシャルスキルが応用できるとひらめき、朝のあいさつやありがとうについて、文化的に言わない地域もあるので、その言い方や質問の仕方を教えるようにしました。
これらの問題を突き詰めると、在籍学級の問題があることに気付かされます。そこで、担任教師がどのように取り組んでいるのか、インタビューをおこなってみました(配布の資料参照)。A先生は問題のあるクラスを担任していましたが、外国人児童を受け入れることで、クラスがまとまりだし、教師自身のクラスの再評価につながりました。C先生のクラスでは、幼稚園の頃から日本にいるので日本語がわかる外国人児童がいました。日本人の児童が、その児童に悪口で「金髪」といったので、それでは黒い髪の方が偉いのか?と問いかけることによって、日本人児童の考え方を変えることができた、という事例が紹介されました。
最後に、現在の職場である大学での学生ボランティアの可能性について触れ、学のゼミでおこなっている、学生ボランティアによる地域支援について語られました。ゼミの学生を派遣することによって、学生たちができることが何であるかに気付くようになりました。学生ボランティアの運営は学生に任せていますが、そのポイントは次の三つです。
1)その子に寄り添う。2)クラスの子どもたちと共に遊び、学ぶ。低学年の子どもなので、慕ってくる。3)子ども間のつなぎ役となり、双方の成長を願う。
--------------------------------------------------------------------------
矢崎先生の講義のあと、矢崎先生の講義の中で欠けている部分は何か、もっと掘り下げて欲しい部分は何かというテーマで、20分間のグループ・ディスカッションをし、グループごとに1つか2つのポイントを発表してもらい、最後に矢崎先生にまとめて回答してもらいました。
学校教育という、受講生にとってもイメージしやすい現場の話であったためか、受講生からも具体的な質問がたくさん出ました。授業時間内にはすべてに答えていただけなかったので、残った質問については、メールで回答していただき、このブログに掲載する予定です。
- by AOYAMA Toru
- at 2006年11月15日