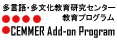10月31日 山口元一さんの講義終了
コーディネーターの青山です。本日は弁護法人あるとの弁護士山口元一さんに、外国人をめぐる法律問題について語っていただきました。具体的な事例にもとづきながらも、法的側面からみた日本の外国人に対する意識を鋭くつく問題提起に富んだお話でした。山口さん個人のブログもありますので、ごらんください。
弁護法人あるとでは、みなさんの先輩である東京外国語大学卒業生が6人もそれぞれの語学力を活かして活躍しているそうです。山口さんも、受講生たちの将来に期待されていました。来週は、法廷通訳の中西智恵美さんのお話をうかがう予定です。
以下、青山による今日の講義のまとめです。なお、本日は配付資料はありません。
今日の講義では、まず初めに、在外公館(外務省)が発行する推薦状である査証と上陸審査時に入国管理局長(法務省)が付与する在留資格の違いを説明され、いわゆるビザ(visa)というのは査証のことであるが、日常的には在留資格についてもビザと呼ぶことが多いとの説明がありました。
さて、年間300件もの事件を取り扱っておられるという弁護法人あるとですが、今回はその中でも、ペルー出身の日系3世男性の例を取り上げて、法律の運用に見られる問題点を指摘されました。この男性は2000年に日系人として来日在留し、2003年には在留期間を更新し、南米出身の女性と結婚して家族とともに生活していましたが、2002年に交通事故を起こして罰金刑を受けたことがあったという理由で、2006年になって在留資格の更新が認められなかったというものです。
これは、2006年4月の法務大臣告示によって、日系人のみが、在留資格更新のときに無犯罪証明書を提出することが義務づけられたことによります。このため、道路交通法違反以外の罰金刑以上の刑罰を受けた日系人は在留資格の更新が認められなくなりました。
この告示が出された背景には、2005年に発生した日系ペルー人による広島での殺人事件があるとされています。しかし、一人の日系人が引き起こした殺人事件を理由としてすべての日系人に対して、他の外国人とは異なる形での法の適用をおこなうことは、おかしいと言えます(明らかに法の下での平等という原則に反している、と感じました[青山記])。
さらにさかのぼると、この告示は、そもそも外国人の滞在はその人の権利ではなく、滞在の許可は国の広い裁量である、という考え方に基づいていることに注意する必要があります。これは、ベトナム反戦デモに参加した外国人の在留期間の更新不許可を認めた1978(昭和53)年10月4日の最高裁判決で示された見解で、以来、現在までこの見解が維持されており、日本に定住している外国人の立場をきわめて不安定なものにしています。
この例では日系人の例でしたが、私たちの日常生活の中でも「外国人犯罪に気を付けましょう」といった、一部の外国人の事例を取り上げて、外国人全体を犯罪者であるかのように表現することが多く見られます。これは、個々の外国人を一人の人として見ていない意識の現れです。日本に行って働きたいという外国人の気持ちはよくわかるし、彼らの来日を拒絶することはできませんが、今述べたような意識とそれに基づく制度がある限り、外国人を積極的に労働力として呼び込もうといった政策をとる準備は日本にはまだできていないと言えるでしょう。
最後に、学生たちから出た質問の一つ、私たちは何をなすべきか、に対して、仮にもし外国人を積極的に受け入れていくというのであれば、1990年の入管法改定以来、外国人に対して何がなされてきたのかについて検証をおこなう必要がある、との答えで講義は締めくくられました。
【講義の進め方と反省】45分の講義、20分のグループ・ディスカッション、25分の質疑応答という構成で進めました。質疑応答の中でグループからの質問を全部だしてもらうまでに時間がかかり、山口さんに答えていただく時間がすこし不足しました。次回はグループ・ディスカッションの時間を少し短めにしてもよいと感じました。TAには、いつものように、グループ・ディスカッションではA3判の紙とポストイットの配布、質疑応答ではパソコンとプロジェクタで教室前のスクリーンに質疑応答の表示をしてもらいました。
【補足】最初のエントリーには、私の聞き間違いなどによる誤りがありました。山口さんから訂正の提案があり、修正しました。
- by AOYAMA Toru
- at 2006年10月31日