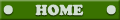1998年 大阪市立大学 インターネット講座
文学部 山口裕之
メディア・情報・身体
メディア論の射程
(2001/01/21内容更新)

(2005/07/15以降
この日まで約24,000件)
- はじめに
- 第1回 メディア論とは
- はじめに
- 「メディア論」をめぐる状況
- この講座の目標
- 「メディア論」のいくつかの論点
- 他の学問領域との関係
- 第2回 マクルーハン(1)
- medium/mediaのさまざまな意味
- 「形式」としてのメディア
- マクルーハン理論
- 「メディアはメッセージ」
- メディアの展開の図式
- 口述文化から文字文化へ
- 文字文化への批判
- 活版印刷
- 第3回 マクルーハン(2)
- 電子文化――口述文化への回帰
- 電子メディアの特性
- ホットとクール
- その他の論点
- 第4回 マクルーハン的視点の継承
- これまでの論点
- 口述文化と文字文化(ハロルド・イニス、ウォルター・J. オング)
- それぞれのメディアの特性
- メディアの展開の図式(吉見俊哉)
- 情報様式(マーク・ポスター)
- 第5回 チューリングの銀河系(1)
- グーテンベルク銀河系の終焉(ノルベルト・ボルツ)
- 「技術メディア」におけるアナログ技術とデジタル技術(フリードリヒ・キットラー)
- A.M.チューリング
- J.フォン・ノイマン
- チューリング・マン(J.D.ボルター)
- 第6回 チューリングの銀河系(2)
- デジタル・メディアの特質――離散的か、感覚的か
- チューリングの銀河系(V.グラスムック)
- 抽象ゲーム (V.フルッサー)
- 第7回 メディアと身体(1)――感覚変容
- メディアと人間の接続――身体論
- 電話・テレビ・コンピュータにおける感覚の変容
- 道具を媒介とした身体空間の感覚変容
- 感覚変容の二つのありかた
- 第8回 メディアと身体(2)――文字における「イマジネーション」
- 音声言語と身体性
- 文字と身体性
- 文字というインターフェースにおける「読む」「書く」という行為
- コード化・デコードの能力としてのイマジネーション
- 文字による感覚変容
- 第9回 メディアと身体(3)――ユーザー・インターフェースの「感覚性」?
- 技術メディア・身体性・インターフェース
- テレビ・ラジオ・電話の「感覚性」?
- 音声言語の段階と技術メディアの段階での感覚性の違い
- 第10回 デジタル技術時代のテクスト(1)――人文的価値観と技術
- テーマの方向付け――デジタル技術文化と文字文化
- 文字文化としての人文的思考
- 文字文化の牙城としての大学
- 「内容」のあり方・枠組みに作用を及ぼすものとしてのコンピュータ――再び「メディアはメッセージ」
- 新しいメディアへの抵抗感
- メディア内メディア――文化内文化
- 第11回 デジタル技術時代のテクスト(2) ――テクストの臨界点と「テクノ画像」
- フルッサーのテクノコードの理論
- 最初のコード:「画像」
- 「画像」から「テクスト」へ
- テクストにおける「歴史/物語」
- 「画像」における時間
- テクストの臨界点としての言語危機
- ホーフマンスタール
- カフカ
- テクノ画像
- 再び、技術メディアにおける感覚性と論理性の両極
- 第12回 デジタル技術時代のテクスト(3)――ハイパーテクストとテクスト
- 一種のテクストとしてのハイパーテクストの位置づけは?
- ハイパーテクスト小史
- ヴァネヴァー・ブッシュの「メメックス」とテッド・ネルソンの「ザナドゥ」
- ハイパーカード
- World Wide WebとHTML
- ハイパーテクストとテクスト
- ネルソンの「ザナドゥ」とインターネット上のハイパーテクスト・システム
- ハイパーテクストの特質
- ハイパーテクストとポスト構造主義のテクスト理論
- 間テクスト性とハイパーテクスト性
- テクストvsハイパーテクスト? ――ハイパーテクスト批判の素描