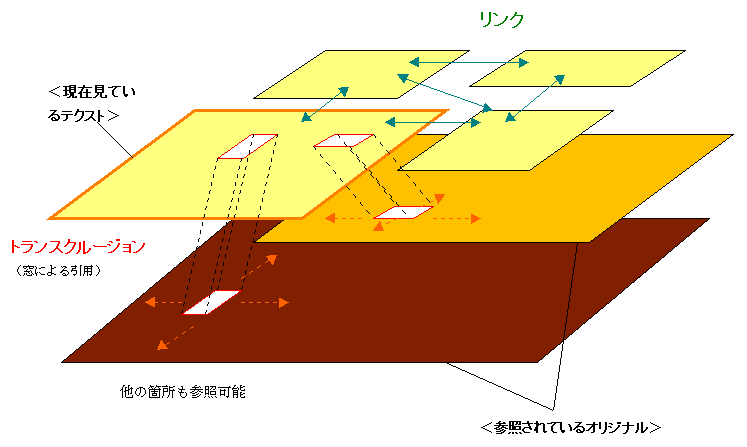
1998年度 インターネット講座
(99/03/11 更新)
デジタル的な技術メディアの文化と文字メディアの文化との関係をとりあげてきたこの三回の講義の最後として――そして、このインターネット講座の最終回として――、今回はハイパーテクストをテーマとします。ハイパーテクストは、主に文字を用いているという点で、それ自体確かに一種のテクストのようではありながら、基本的に使われている形態としては技術メディアに基づくものです。[註0a]コンピュータの世界に視点を置いて考える人からすれば、見たところ、それはコンピュータという技術メディアの中に生き残っている、古いメディアとしての「テクスト」のようでもあります。あるいは反対に、「テクスト」の文化の思考様式に根ざした視点からすれば、前々回にもふれたように(→参照)中身としてのテクスト自体が重要なのであって、それが書物の上にあろうが、コンピュータの画面の上に見るものであろうが、基本的にはかわりはないという考え方も、幅広く見られるものであるように思われます。
前回の講義ではとりわけ、技術メディアとしての「テクノ画像」と、メディア論的な展開の図式においてその前の段階に位置づけられる「テクスト」との関係に焦点を当ててきました。しかし、今回取り上げるハイパーテクストは、結論からいえば、確かに一種のテクストではあっても、文字通りテクストを「超え」(hyper-)て、新たな段階にあるものとして位置づけることのできるものといえるでしょう。
自明なものであるかのようにハイパーテクストという言葉を使ってきましたが、その簡単な歴史とともに、ハイパーテクストとは何か、ということをまずひととおり概観しておきたいと思います。
厳密な規定や歴史はともかくとして、インターネットを使ってこの講座をご覧になっている人にとって、「ハイパーテクスト」がとりあえずどのようなものかということはそれほど説明を要しないものではないかと思います。要するに、みなさんがふつうにインターネット上で見ている World Wide Web 上のさまざまなテクストの連鎖、例えばクリックして次のページのテクストに移るような仕方で見ることのできるようなテクストの網の目によって成り立っているものがハイパーテクストです。この講義を見ている多くの方は、HTMLをご存じではないかと思いますが、そういった言語を必ずしも用いなくとも、要するにさまざまなテクストが網の目状にお互いに結びつけられて存在していれば、それはハイパーテクストであるということができるでしょう。
* * *
「ハイパーテクスト」という語を最初に用いたのは、シオドーア・ホルム・ネルソン(一般には、テッド・ネルソン)とされています。彼の有名な著書『リテラリー・マシン』[註1]によれば、(これまでのところ私自身、文献として直接名前を出されているのを見たことはありませんが)1965年に発表された彼の論文『複雑で、変化を続ける、非定型な情報のためのファイル構造』 の中でこの言葉が初めて用いられたようです。「ハイパーテクスト」とともに現在広く用いられている「ハイパーメディア」という言葉も、もともとはネルソンによるもので、この同じ65年の論文の中で使われているということです。
1965年にすでにハイパーテクストの構想をもち、さらにその実現に向けて「ザナドゥ」と名づけられたプロジェクト(Project Xanadu) [註2]をすすめていたということは、現在インターネットという形で、これほどまでにハイパーテクストが一般的なものとなり、社会・文化のあり方に対してますます力を及ぼすほどになっていることを考えるならば、驚嘆すべき先見性であるように思われます。しかし、そのテッド・ネルソンの構想に対して、その原型となるような影響を与えているアイディアはさらに1945年にまで遡ることになります。
ハイパーテクストの歴史をたどる上で最初に言及されるその人は、その当時アメリカの戦争技術開発の学術面での最高責任者であったヴァネヴァー・ブッシュです。[註3] 1945年に『アトランティック・マンスリー』誌上で発表した「われわれが考えるように」(As we may think) と題された短い文章の中で、ブッシュは、人間の脳が連想によってさまざまな思考の要素を結びつけていくのと同じような機能をもった、ある仮説上の機械を提唱し、それを「メメックス」memexと名づけています。メメックスの基本的な構想は、相互に連結され、閲覧することが可能なマイクロフィルムによるものであり、資料の閲覧に際してはレバーによる機械的な操作を行うというものですが、それらの資料をデジタル化し、相互の結合と閲覧の操作をコンピュータ上で行うとすれば、それは基本的に現在われわれがコンピュータ上に見ているハイパーテクストであるといってよいでしょう。
ブッシュのアイディアがどれほどネルソンに対して影響を与えるものであったかは、ハイパーテクストが自分自身のアイディアによるものであることをあれほど強調しているネルソンが、『リテラリー・マシン』の中でブッシュの「われわれが考えるように」全文を(もともと発表された『アトランティック・マンスリー』の許可を得て)掲載していることからも推察できます。[註4]ちなみに、彼のホームページでも、ダグラス・エンゲルバートとともにヴァネヴァー・ブッシュについてのページが作られています。(「ハイパーテクスト関連リンク」参照)
ネルソンの構想したハイパーテクストのシステム「ザナドゥ」は、一時期は企業ベースにものって開発が進められ、β版までできたということですが、いまだに実現されていないシステムです。(「ザナドゥ」の基本的構想の見取り図とともに、こういった経緯も『リテラリー・マシン』に紹介されています。) しかしそれでも、ネルソン自身の言葉によれば、直接・間接にザナドゥの影響を受けた重要なプログラムやシステムがいくつもあるようです。ネルソン自身による「プロジェクト・ザナドゥ・ホームページ」に含まれるあるページで、ネルソンは、制作者自身がザナドゥの構想から影響を受けたデザインをもつシステムであることを認めているものとして、
をあげています。
また、制作者自身がそう認めているわけではないにせよ、ネルソンが自分のザナドゥからの影響を直接に受けていると考えているものとして、以下のものをあげています。
* * *
これらのうち、ハイパーテクストの展開を考える上で、とりわけ、マッキントッシュ上のプログラムであるHyperCardはきわめて重要な位置を占めているようです。実は、私は基本的にマック・ユーザーではないので、あまりHyperCardについて知らないのですが、それはただ単に、アプリケーションの使い方を知っているかどうかの問題ではなく、昔からのマック・ユーザーにとって、HyperCardが(とりわけハイパーテクストのシステムとして)どのように受け止められてきたかという、体験を持っていないということが大きいのです。
そういうわけで、ここでは、人文系のハイパーテクスト構築に初期の頃から関わってきたランドウの言葉を引き合いに出してみたいと思います。
ほとんどの人々、とりわけ人文系の研究者は、アップル・コンピュータのハイパーカードという形で、ハイパーテクストが全体としてどのようなものかということが捉えられるようになったわけだから、この話を始めるもっとも良い方法には、この特別なシステムにいくつかコメントを加えることも入ってくるだろう。
ハイパーカードの最初のバージョン(これは多くのマッキントッシュ・コンピュータに無料でインストールされていた)は、他のいかなるプログラムよりも多くの人々にハイパーテクストの使い道を示してくれるものであったが、それが提示するものはほんとうのハイパーテクストではない。そして、それゆえに、このパワーを秘めたテクノロジーがどのようなものであるか、あるいはどのようなものとなりうるかということについて、残念なことに、あまりにも限定された観念を広める結果となってしまった。機能的に優れ、きわめてコンパクトなデータベース・マネージャーであるハイパーカード1.0は、そのネーミングに現れているように、「カード」というメタファーに基づいている。このように「カード」に基づいているということは、確かに電子アドレスブックや他の多くの重要なアプリケーションにふさわしいものではあっても、それぞれのレクシのテクストは、一枚のカードという狭い視野に収まるもるでなければならないということを意味していた。すなわち、その一枚のカードは、たいていのワープロ・プログラムとは異なり、スクロールするフィールドをもっていなかったのだ。さらには、ハイパーテクスト・システムを作り出す、他の初期の試みと同様に、ハイパーカード1.0は一度に一枚のカードしかディスプレー上に見ることができなかった。しかしそれによって、著者や読者が、どんどん入手が容易になっていった、より大きなスクリーンを使おうとすることを妨げる結果となり、ハイパーテクストの可能性を大幅に制限することになった。ハイパーカード1.0はまた、単一のカード同士の一方向のリンクに基づいており、その意味で原始的なナビゲーション的支援の機能を提供するに過ぎないものであった。また、他にも、このメディアの完全な能力をテストするための制限がいろいろあった。とりわけ、これにはネットワークで作動するための備えがなかった。[註5b]
こういった引用を行ったのは、初期のハイパーカードがいかにハイパーテクストのシステムとして貧弱であったかを強調するためではなく、逆に、ハイパーテクストの歴史において重要な地歩を占めていたことを確認するためです。というのも、現在日本で出ているハイパーカードについてのいくつかのマニュアル本をみると、狭い意味での「ハイパーテクスト」ではなく、むすろマルチメディアの可能性をユーザーに提供するものとして、とりわけ画像、そして音声に重点が置かれているように思われるからです。「ハイパーテクスト」は広い意味では「ハイパーメディア」と同義に考えることができますから、その意味では、画像や音声が用いられることはまったくおかしなことではないのですが、テクストのリンクのために用いるというニュアンスは、一般には弱いのではないかという気がします。
ハイパーカードのマッキントッシュ・コンピュータへのバンドルは、当初の完全な製品版のから、Lite版をへて、新たにスタックを作ることが基本的にできないプレーヤ版へと、いわばどんどん衰退していきました。MacOS8からは、一応プレーヤ版がついてはいますが、自分で特にインストールしなければ、もともとは入れられていない状態になっています。いろいろな理由があるのでしょうが、一つの大きな点として、やはりWWWの普及ということがあるようです。
ちなみに、上に言及した同じWeb上のページ[註5]でネルソンは、「もともとのウェブ・プロトコルのデザイナーであるティム・バーナーズ=リーが、1990年頃に着手したとき、われわれの仕事のことを知らなかったというのはほんとうのことである。明らかに彼はHyperCardをそれ以前に目にしており、彼が創作したものは本質的にいってインターネット上のHyperCard(R)だったのである」と述べています。ネルソンのいうとおり、HyperCardがザナドゥから直接の影響を受けているとすれば、結局いまのインターネット上でのWWWも、間接的にザナドゥから影響を受けていることになります。
* * *
World Wide Webについては、それがどのようなものかいまさら説明するまでもないでしょう。そこで見ることができる「ホームページ」を記述するための言語がHTML、すなわちHyper Text Markup Languageです。自分でホームページを作る人にとっては周知のことですが、HTMLを記述するファイルは単なるテクストファイルであり、< >によって囲まれるタグが視覚的にテクストなどがどのように配置されるか、他のどのファイルとリンクされるかといった、いわばテクスト外の情報を指定します。HTMLはインターネットを構想する際に、WWW上でのファイルをみるソフトウェア(つまりブラウザ)の開発者が集まって作り上げられ、現在も次々と新たな機能が加えられつつあります。現在もっともよく使われているInternet ExplorerやNetscape Navigatorなどのブラウザは、テクストファイルとして書かれたHTMLを解釈し、デザインされたように表示するものですが、結局は、ユーザ・インターフェースとしてのブラウザが、ハイパーテクストをわれわれに(多くの場合無意識のうちに)浸透させる働きを、今後も続けていくことでしょう。現在のわれわれにとって、ハイパーテクストとは何か、ということがわからなくても、インターネット上でブラウジングを行うことは簡単ですから、このようにして「ハイパーテクスト」的な感覚を広めていく標準的な形式ととりあえずはなるでしょう。
そのほかにも、個々のアプリケーションの文書形式で使われるHTMLではないハイパーテクストがあり得ます。私自身、最近好んでそうしているのですが、Wordや関連のアプリケーションのファイルを相互にリンクして、研究の資料として活用しています。
その際HTMLをもちいない理由はいくつかあります。たとえば、ワープロの機能の方がはるかに豊富であり、融通が利くということ、書くときにいちいちテクスト外部のこと(つまりタグ)を考えていたのでは、内容に集中できないということ(もちろん、ワープロ的に使えるソフトもありますが)、また特に私のようにドイツ語などと日本語を混在させた文章を書くことは、単一のコード(Shift JISなどの)ではできないということ、等です。それはともかくとして、こういった手段などによって、現在、一般のアプリケーションにおいても、ますますハイパーテクスト化が進んでいるということを指摘することができるでしょう。
以上、ハイパーテクストの展開を考える上でおそらく欠かすことができないであろういくつかの事項について、大まかに見渡してきました。そのためにとりあえず、ハイパーテクストとはわれわれがインターネット上で見ることのできるような、相互に網の目のようにリンクされたテクストのシステムである、と暫定的な説明を与えてきたのですが、ハイパーテクストとはいったいどのようなものなのか、ここでもう少しくわしく見ていくことにしましょう。
ネルソンが構想していた「ザナドゥ」というハイパーテクストのシステムは、実は、現在WWW上でふつうに用いられているハイパーテクストのシステムとは、かなり異なったものといえますが(この両者がどのような関係にあるかについては、後で取り上げます)、もっとも根本的なハイパーテクストの規定としては、テッド・ネルソンの次の言葉は、現在用いられているようなハイパーテクストのシステムに関しても当てはまるものと言えるでしょう。
私の言う「ハイパーテクスト」とは、順序通りに書かなくてもよい文章、つまり一つの文章がいくつかに分かれていて、対話的な画面上で読者が読みたいところを自由に選択できるようなものである。一般に理解されているように、ハイパーテクストとは、いくつかのちがった道筋を読者に提供するために「リンク」された文章が並んだものなのである。[註6]
とりあえずこの言葉から理解する限り、ハイパーテクストを成り立たせている最低限の要件として、
という3点をあげることができるでしょうか。
では、最初の点に関して、ここでの「複数のテクスト」とは何を指しているのでしょうか。何を指しているかといったって、テクストといえばふつうの文章から成り立っているテクストに決まっているじゃないか、と思われるかもしれませんが、実は、この問自体が、私が次に述べようと思っていることを先取りしています。もちろん、現在のインターネット上のハイパーテクストにおいて、相互にリンクされているものは狭い意味でのテクストに限られず、音声や画像でもありうるということは、みなさんよくご存じの通りです。その意味では、「ハイパーテクスト」ではなく、しばしば「ハイパーメディア」という言葉がもちいられているということもよくご承知のことでしょう。(ちなみに、はじめにもふれたように、「ハイパーメディア」という言葉もテッド・ネルソンが最初に用いたそうですが。)現在では、音声や画像が含まれるからといってことさらにハイパーメディアという言葉を使わなくても、ハイパーテクストという言葉が拡張されて一般に用いられてるのではないかと思います。その場合、相互にリンクされている「テクスト」とは、単に文章だけではなく、画像や音声をも含むものとなっています。
しかし、さきに私が、ここでの「複数のテクスト」とは何を指しているのか、といったときに、そういった意味で、「テクスト」のことを問うたわけではないのです。私が考えているのは、狭い意味でのテクスト、つまりふつうの文章から成り立つようなテクストのことなのです(ハイパーメディアの話はひとまず置いておきましょう)。少し先取りすることになりますが、現在、人文的なハイパーテクストの理論において、「ハイパーテクスト」は、これまでわれわれが用いてきたような「テクスト」とは全く異なるパラダイムをもつシステムとして、「テクスト」に対置されるものとされています。そのように考えた場合、リンクされている個々の「テクスト」も、われわれがいまふつうに考えているような「テクスト」と全く同じものと考えてよいかどうか、ということには少し注意を払わなければならないのです。
とはいえ、ブッシュやネルソンが、ハイパーテクスト的なシステムの構想を提示したときには、彼らの考えていた相互にリンクされる個々のテクストとは、従来のふつうのテクストであったといってよいでしょう。少なくとも、ブッシュに関しては、完全にそうであると言えます。
メメックスで閲覧する資料の大半は、マイクロフィルムの状態になって、すぐに機械に入れられるものを購入する。あらゆる分野の書籍、絵画、最新の定期刊行物、新聞はマイクロフィルムで購入し、所定の位置に収める。ビジネスのための通信も同じようにして出し入れされる。直接書き込んで保存する方法もある。メメックスの上部には透明なプラテンがある。そこに手書きのノート、写真、メモ、その他あらゆる種類のものを置いてレバーを押し下げると、メメックス用フィルムの次のプランクの場所に写真として記録する。もちろん、乾式写真が使われる。
当然、通常の索引によっても記録を検索できるようになっている。ユーザーがある書籍を読みたいと恩えば、キーボードから書籍コードを入力すると即座に表紙が目の前に映し出される。
(ブッシュ「われわれが考えるように」、ネルソン『リテラリーマシン』ジャストシステム、pp.125-126からの重引)
参照される「テクスト」として考えられているものは、絵画や写真も含められており、その意味で現在のマルチメディアにつながるものですが、通常の文章からなる「テクスト」とされているのは、書籍・定期刊行物・新聞といった既存のメディアそのものに他なりません。
テッド・ネルソンの場合には、(これは上にあげた、ハイパーテクストを成立させる三つの要件のうち、2番目の項目に関わってきますが)決められた順番をもたない読みということを特に強調しているため、もう少し事情は複雑になってきますが、それでも彼が出発点としていたのは、やはり既存のテクスト・「文献」(あるいは、そのアイディア・カード)の整理・保存とそれらへの効率的なアクセスです。[註7]その意味で、相互にリンクされる複数のテクスト自体は、当初から特別のものとして考えられていたわけではなく、むしろ旧来のテクストそのものであったかもしれません。つまり、出発点においては、旧来の「文献」[註8] を有効に生かすために、どのようなアプローチがよりふさわしいものであるかが試みられている、という立場がとられていたと思われます。
しかし、現在、人文系のハイパーテクストの理論において、ハイパーテクストの構成要素である個々のテクストの単位は、旧来のテクストのあり方を解体したものとして捉えられているといってよいでしょう。このことは、とりわけ先に挙げたハイパーテクストを成立させている3つの要件の二番目、「読まれる際に固定された順番をもはやもたない」という特性にわっています。このことは技術的には、三番目の要件、「テクストが相互にリンクされている」ということにももちろん関係しています。これらの特性は、旧来のテクストの保存とそれへのアクセスという視点から出発したネルソン自身が、強調しているものでもありました。
私は単純に、順序のない著述をハイパーテクストと呼んでいる。連続するテクストやイラストの挿入、囲み罫が入った雑誌のレイアウトは、まさにハイパーテクストだ。新聞の第一面、ドラッグストアの本棚で見かける種種のプログラムされた本(ページの最後である選択をすると、次にどのページへ進むべきかを指示されるようになっている本)もハイパーテクストである。(『リテラシーマシン』p.80)
リンク機能は、単に文書の断片や枝葉をくっつけ合わせているわけではない。逐次的でない著作物、すなわちハイパーテクストが可能になるのだ。
ジャンプリンクという単純な機能から、学問、教育、小説、ハイパーポエムなどの分野における新しいテクスト形式すべてが容易に導き出せる。このやり方で、自由に拾い読みをして思わぬ発見をする、そんなことが可能になる。(『リテラリーマシン』p.160)
この、特定の順序がないという特性、読む際に任意の順序を選択できるという特性が、なぜ旧来のテクストを越えたものとなりうるのか、なぜ旧来のテクストのあり方を解体する可能性をもつものとなるのか、ということは、旧来のテクストのあり方を考えるときに、より明瞭なものとなります。旧来のテクスト、そしてそれが書かれている通常の形態である「書物」は、(辞典類はのぞいて)一般に<始まり>と<終わり>をもち、読者は書物の<始まり>から読み始め、<終わり>へといたります。本を読むという文化に生きる人にとっては、こういったことは自明のことであり、ことさらにそのことに対して何らの不自由も感じないかもしれません。
しかし、こういった読み方は、実は、テクストが依拠している「文字言語」の根本的な特性である線状性liniarityに基づいたものであり、自明のものと感じていることも、「文字言語」というメディアの特性によっていわば強制された一種の習慣であると考えるならば、われわれのこれまでの読み方の前提は根底からくつがえされかねないものとなります。
それでは、そのように線状的に(つまり、<始まり>から中間部を経て<終わり>へといたるように)読むという、従来の思考法をなぜことさらに否定し、ハイパーテクストの非順序的な読み方をそれに代わるものとして掲げる必要があるのでしょうか。ネルソンは例えば、「ひとつながりの表現は、すべての読者に一つの順序を強要するが、それが結局どの読者にとっても適切なものではない可能性がある」(『リテラリーマシン』p.76)と指摘しています。また、ブッシュは、人間の脳の思考のプロセスは連想のつながりであることを強調しています。ハイパーテクストの原型である「メメックス」はまさにそういった非順序的な脳のプロセスをモデルにしたものなのですが、その意味でも、ハイパーテクストは、メディアの展開においていわば中間的に挿入された(とはいえ、われわれの現在の文化のあり方を根底から規定している)「文字言語」の優位性を相対化し、順序的ではない読みの可能性を提起するものとなっているのです。
ネルソンがハイパーテクストの意義を強調する仕方は、従来のテクストに対してハイパーテクストが人間にとってどれだけすぐれたものであるかといった、単なる効用性にアクセントをおいたものであるかのようにも見えます。しかし、現在の人文系のハイパーテクスト理論において問題となっているのは、そういった、より有用であるというような尺度ではなく、「テクスト」の線状性というメディアの特性のうちに無意識にとらわれた人間の思考法を解体するということにあるように思われます。このことに関しては、あとで取り上げることにしましょう。
従来の「テクスト」のあり方と「ハイパーテクスト」のあり方とを、より対照的に浮き上がらせるための一つの手だてとして、少し回り道になるかもしれませんが、テッド・ネルソンが提唱する「ザナドゥ」と、現在一般的に用いられているハイパーテクストのシステムとを少し比較してみたいと思います。すでに述べたように、「ザナドゥ」はいまだ実現にいたっていないシステムであり、それに関してことさらに取り上げる必要はないように思われるかもしれません。(実際、ジョージ・P・ランドウやJ. D.ボルターのハイパーテクストに関する重要な著作においても、「ハイパーテクスト」の命名者としてのネルソンに言及されるにせよ、彼の「ザナドゥ」自体が考察の対象となっているわけではありません。)
しかし、「ザナドゥ」は、ハイパーテクストのシステムでありながら、従来の「文献」の理想的な管理システムとしての構想という側面も強くもっているため、「テクスト」と「ハイパーテクスト」を対比的に考える上で、非常に貴重な視点を与えてくれるものとなるように思われます。
すでに述べたように、テッド・ネルソンは「ハイパーテクスト」という語を最初に用いた人として知られていますが、彼は現在のハイパーテクストが広く用いられている形態である World Wide Web について、次のように述べています。
われわれは、ほとんど誰もハイパーテクストなど想像だにできなかった60年代においてさえ、ワールド・ワイド・ハイパーテクストをはっきりと明確に予見していた。他の誰もこのことを予見していなかった。何百万人もの人々がコンピュータ・ネットワーク上でハイパーテクストを出版しようとするということが、われわれには分かっていた。そして、誰もが出版できるというこの自由を約束することは、つねに「ザナドゥ」のビジョンの一つであったのだ。このことを実現させることは、われわれの自由への責務だった。
しかし、伝説とは裏腹に、プロジェクト・ザナドゥはワールド・ワイド・ウェブを作り出そうとするものではなかった。ワールド・ワイド・ウェブは、まさにわれわれが阻止しようと考えていたことに他ならない。われわれははるか昔から、一方通行のリンクの抱えるさまざまな問題、つまり、中断する(長期間の出版が保証されない)リンクの問題、コメントを出版できないということ、バージョン管理ができないこと、出版の権利が管理できないということといった諸問題を予見していた。これらすべては、「ザナドゥ」の構想のうちに組み入れられていたのである。[註9]
テッド・ネルソンのこの言葉が、実現しなかった構想の、実現したシステムに対する単なる対抗心によるだけのものでないことは、『リテラリーマシン』のうちに示されている「ザナドゥ」の構想のうちに見て取ることができます。
「ザナドゥ」のアイディアとしてネルソンが述べているものをいくつかあげてみましょう。[註10]
これらのうち、リンク機能、電子出版、ネットワークによる分散されたシステム管理については、現在のハイパーテクストのシステムと基本的には共通するものといえるでしょう。しかし、それ以外のアイディアは、現在のシステムのうちに見ることのできないものです。
* * *
最初にあげた<代替バージョン>機能と<時間的な追跡>機能は、この言葉だけではわかりにくいのですが、基本的には同じ事柄に関わっています。現在使われているような、文書をすべて保存するという形式においては、HTMLにせよ、他のさまざまなワープロの保存形式を用いるにせよ、もとの文書に何か一部分の変更を加えても、もとと同一の部分も含めて、すべてが新たな文書として保存されます。これは、考えようによっては、確かに非常に大きな無駄、同じものの繰り返しという「冗長性」を生み出すものといえます。もっとも効率的な記憶方式を考えるならば、同じ部分はそのまま利用して、異なる部分だけを差し挟むという形式であるべきです。しかも、変更される前のバージョンもそのままに残されたまま、変更される部分の最初と最後に、挿入の記号を入れておけば、どのような変更が加えられていったかをすべてたどることができます。これは<代替バージョン>を管理するシステムであると同時に、どのような変更が加えられていったかという<時間的な追跡>を可能にもするシステムとなります。
実際問題として、すべての場合においてそのように過去のバージョンをたどる必要があるか、という疑問も当然呈されることになるかもしれませんが、そういった必要がある場合には、このシステムはきわめて有用なものとなり得ます。少なくとも、そういった可能性をある文書管理システムがもっているということは、ものを書く人間にとってはきわめて重要な機能となり得ます。このことは、ネルソンにとって、電子出版のシステムや所有権の問題とも絡んでくるのですが、とりあえず、プライベートな執筆の場においても効力を発揮するでしょう。
* * *
「トランスクルージョン」という聞き慣れない言葉は、テッド・ネルソンの造語です。もともと同じような事柄を言い表すのに「インクルージョン」というふつうの言葉を用いていたのですが、とりわけ最近の著作『情報の未来』The Future of Information では、彼のコンセプトによりふさわしい「トランスクルージョン」が使われています。[註11] これは簡単にいうと他の文書を参照するための機能ですが、そのように説明すると、すぐに「リンク」を考えてしまうかもしれません。しかし、「トランスクルージョン」は、リンクとは根本的に異なり、他の文書へと移動するものではなく、いま見ている文書の中にある「窓」を通して、言及されている文書のある箇所をいわばのぞいて参照するというものです。紙媒体の文書であれば、それは「引用」にあたるものですから、ネルソンはこれを<引用窓>とか<引用リンク>と呼んでいます。紙媒体と同じように、単に引用箇所だけ参照するにとどまらず、望めば、引用されている文書の全体(あるいは引用箇所の前後)を見ることももちろん可能です。
このシステムによって他の文書を参照するときには、もとの文書からもう一つの文書へと移動するのではなく、もとの文書のうちにある「窓」を通じて、参照する文書の一部を「含む」includeかのように見るのですから、ネルソンは当初「インクルージョン」という言葉を用いたのではないかと思われますが、この行為は厳密に「含む」というよりは、そこに「通過」「移動」(=trans-) の要素が加わっていますから、その意味で、「トランスクルージョン」という語は、よりコンセプトにふさわしいものかもしれません。
この「トランスクルージョン」という発想は、ネルソンのハイパーテクストのアイディアの中でもとりわけ独自なものであり、貴重なものであるように思われます。そのためもあってか、現在のハイパーテクストのシステムでもっぱら用いられている「リンク」に対して、ネルソンは彼のホームページ内でも、「リンクvsトランスクルージョン」という項目を掲げて、トランスクルージョンの独自性を強調しています。[註12]
* * *
「所有権」あるいは「著作権」の問題は、現在のインターネット上のシステムにおいてもきわめて大きな争点の一つとなっていることはいうまでもありません。ネルソンのアイディアは、「オリジナル」を保持した上で、誰でもそれに対して、自分自身の変更やコメントの「出版」が可能となり、それがまたそれ自体の新たな「所有権」をもち、それが電子的に管理されるというものです。その管理は、所有者と利用者とのあいだの金銭的な授受も、当然重要な要素として含んでいます。
「所有権」のネット上での電子的な管理という考え方は、一見、非常に進んだ形態を可能にするものであるようにも見えます。しかし、後でふれるように、実は「所有権」「著作権」という考え方自体が、テクストという旧来のメディアの特性に結びつくものであり、ハイパーテクストはその本質上、「著作権」という自明とも思われる概念を根底から揺るがしかねないものなのです。(実際、それがネット上のいたるところで現象として露見しているわけですが。)
* * *
さて、ネルソンが「ザナドゥ」のシステムとして構想しているいくつかの独自なアイディアを取り上げてきましたが、これらは現在用いられているハイパーテクストのシステムと比べて、非常に優れた点をもっていると思います。個人的には、「インクルージョン」による引用と参照のシステムは、きわめて優れたものであるように思われ、なぜ現在のハイパーテクストのシステムにこういった機能がないのか、とさえ感じます。
しかし、そのように感じるのは、私自身が旧来のテクスト的な思考にどっぷりとつかっているためかもしれません。というのも、ネルソンの「ザナドゥ」は、いってみれば、旧来の文献が文字通り「理想郷」(ザナドゥ)にあるかのごとく管理されているシステムであると思われるからです。先にもふれたように、ネルソンが出発点としているのは、既存の文献をいかに効率的に、理想的に管理するか、ということです。そういった視点からすれば、文章を書くことに携わる人、そして、厳密に文献に当たる人にとって、ネルソンの提起するようなシステムは、まさに理想的なものです。そういった人たちにとって、ネルソンのシステムによれば、次々と稿を改める際に、古いバージョンを参照することは、何の苦もなく行うことができますし、他の文献を参照したり、註をつけたりするというテクストのもつ機能は、物理的な障害を大幅に取り払われて、頭の中(書き手)や物理的に他の文献を参照するという手段(読み手)によってこれまで行ってきた、テクスト間の相互指示・相互連関を、ほとんど労力を用いないで進めることができるのですから。あるいは、「著作権」も、これまで以上に自動化されて、金銭的により厳密に保証されることにもなるでしょう。これは、技術的な手段を用いることによって達成しようとした、「テクスト」のユートピア、ザナドゥであるといってよいでしょう。
「ザナドゥ」がいまだ実現しないのは、まさにその名前の通りの事態を反映しているといえるかもしれません。というのも、「理想」は実現してしまえば、もはや「理想」ではなくなるからです。「ザナドゥ」という構想された理想的なシステムは、いつまでも「理想」として、しかも(ハイパーテクストというよりは)「テクスト」の理想としてとどまることになるかもしれません。
* * *
比較のために、ネルソンが「ザナドゥ」で構想していたようなハイパーテクストと、現在われわれがふつうに使っているようなハイパーテクストをそれぞれ図示してみましょう。
「ザナドゥ」のハイパーテクスト(図1)
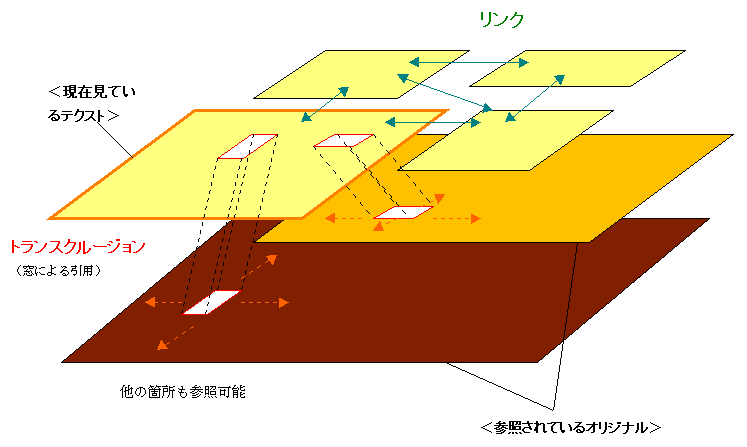
「ザナドゥ」においてもごくふつうのリンクはもちろん存在するのですが、非常に特徴的であるのは、すでにふれたように、参照するあるオリジナルのテクストを「窓」を通して引用する「トランスクルージョン」という機能です。それによって、リンクされたテクスト同士がいわば横並びの関係となっているのに対して、それにさらに重層的に連なるテクスト群が考えられることになります。
このように、テクストとテクストの結びつきや「引用」が、コンピュータの内部で技術的に行われているのですが、これは要するに、実際に、人間が本を読んでさまざまな別のテクストを参照したり、連想したりする作業と基本的に同じことなのです。例えば、論文の「註」、そして「引用」やその全体を指し示す「参考文献」は、あきらかにテクスト間のリンクを提供していますし、文学作品や報告にしても、そのテクストの中で他のテクストを指し示すことは、ごくふつうに見られます。ハイパーテクストの最初の構想者であるネルソンは(あるいはブッシュにしても)とりわけ文献を扱う研究者としてこういった構想にいたったようですが [註13]、研究者にとって、相互にリンクし合う膨大な文献を、コンピュータ上で簡単に次々とたどることができるとすれば、それはまさしく「理想郷」(ザナドゥ)であるといえるでしょう。
ネルソンの構想したハイパーテクストに対して、現在ふつうに用いられているハイパーテクスト、WWWでふつうに見ることのできるハイパーテクストがどのようなものかは、ほとんど図示する必要もないかもしれませんが、例えば、下に示されるようなものと考えられます。
ふつうのハイパーテクスト(図2)
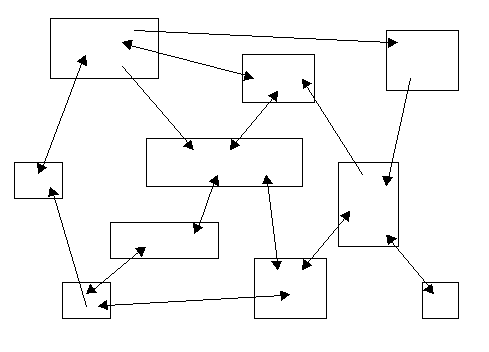
「ザナドゥ」のハイパーテクストとの対比でいえば、要するに「トランスクルージョン」に相当するものがなく、全部横並びのテクストのリンクだけで成り立っているシステムといえます。では、「トランスクルージョン」による「引用」にあたるものはどうするかといえば、ふつうは、従来の「テクスト」と同様に、文書の中に「 」などを用いて引用するか、必要があれば、他のリンクされたテクストと同様に、別のハイパーテクストの要素とすることもできるでしょう。
この二つのタイプのシステムのうち、ネルソンの構想の方がより優れているようにも見えます。確かに文献の参照や、これまで紙と筆記用具で行ってきた記述など、従来の「書く」「読む」という考え方からすれば、「ザナドゥ」の方が優れているといえるでしょう。というよりも、「ザナドゥ」とはこれまでの文献管理のための「理想郷」として構想されたものなのですから、優れているのは当然だともいえるでしょう。
しかし、現在用いられているようなハイパーテクストのシステムは、おそらくそれをデザインした人も予見していなかったであろうような、テクストのあり方の根本的な変革をもたらしつつあると思われます。ハイパーテクストは、単に旧来の「テクスト」を効率よく管理・閲覧するための便利な道具に過ぎないものではなく、リンクされている個々のテクスト、それらのテクスト群を「読む」ことによって形成される像、そして「読む」「書く」という行為そのものを変えていく力を、現在ますます発揮しつつあります。その意味で、(当初、そういった意図によって命名されたわけではないでしょうが)まさに「テクスト」を「超」(hyper-)え、旧来の「テクスト」の概念を解体するものとさえなり得ることが、現在、人文的なハイパーテクストの理論において指摘されつつあります。
その意味では、「ザナドゥ」のハイパーテクストも、その行き着く先としては、同じような可能性をもっていたはずでしょう。ただ、「ザナドゥ」が旧来の「テクスト」の理想的な管理を目指していることによって、それだけ「テクスト」の概念を越え出る立場に至りにくいのではないかとも思えますし、何よりも、それぞれの構想の基本的な形が、(同じ「ハイパーテクスト」でありながらも)「テクスト」と「ハイパーテクスト」の違いを明確に示していると思われたので、この両者を対比したのです。その違いはまず、重層的なテクスト間の関係と平面的・モザイク的なテクスト間の関係という対比として言い表すことができそうです。
上に示した図であれば、確かに現在用いられている「ふつうのハイパーテクスト」において、テクスト相互の関係は「平面的」、つまり同一階層での横並びの関係であるように見えます。しかし、ハイパーテクストを構築する人間は(私もそうですが)、リンク先を後からすべて修正するのは大変な作業となるため、収納されるべきファイル群がどのようなものとなるかあらかじめ分類し、さらにそれを細分して階層化しておきます。コンピュータを使い始めた人がまず必ず慣れなければならないのが、ディレクトリ構造としてあらわれるファイルの分類と階層化ですが、ハイパーテクストの要素である個々のファイルも要するに全く同じようなツリー上の構造の中に収められているわけです。ということは、ファイル間の関係は平面的などではなく(そうだとすれば、すべてのファイルは同一ディレクトリ上に入っていることになります)、むしろ立体的・重層的ではないかといわれそうです。
しかし、こういったディレクトリ構造は、個々のハイパーテクストをブラウザによって次々と見ていく人にとっては、通常ほとんど見えないものとなっています。もちろん、「アドレス」をきちんと確認しながら、いま自分が見ているものがどういった構造のどの部分に収納されているものであるかを意識して、ブラウジングすることも可能ではあります。しかし、通常は、たぶんそういったことをほとんど意識しないで、見ているページの内容だけに注意を向けているのではないでしょうか。誰のサイトかぐらいは意識するにしても、そのページを作った人が、その人のサイト内でどのようなディレクトリ構造を構築しているか、そしてその構造の中のどこに自分が今いるかまではふつう意識しないでしょう。結局、ある構造のどこに収納されていようが、ブラウザ上に見えている画面としては基本的に同じものであり、前に見た画面と今見ている画面、そして次に見る画面は、見る人にとっては同じ平面上にあるものの連鎖として感じられることになるのです。
それと関連して、さらに「テクスト」と「ハイパーテクスト」の違いを考えてみることにしましょう。「ザナドゥ」の構想とWWWのハイパーテクストを比較する際に、「ザナドゥ」をとりあえず、ハイパーテクストでありながらテクスト的な性質をも多分に含んだものとして位置づけてきたのですが、それは相互にリンク・引用される文書そのものとして、旧来の文献そのもの(あるいはそういった性格をもつもの)がまず考えられていることにも現れています。もちろん、WWWで用いられているようなハイパーテクストでも、旧来の文献同士をリンクさせることはできます。もちろん、著作権の問題などが絡んできますから、そう簡単にはいきませんが、現在、ますます多くの文献が電子テクスト化され、すでにオンライン上でアクセスできるものもかなり多数に上ります。
しかし、もともと「書物」として書かれていたもの(要するに旧来の「テクスト」とここで呼んでいるもの)を電子テクスト化したものではなく、そもそもハイパーテクストとして書かれたものは、次第に、これまでのテクストにおけるとは異なった書き方によって書かれ始めているように思われます。インターネットが普及し始めたのは94年から95年くらいですから、ハイパーテクストが一般に用いられるようになってからまだほんの数年しか経っていません。その意味でも、ハイパーテクストを書くとはどういうことか、あまり意識的に考えられていないかもしれませんし、そもそもハイパーテクストがこの先どうなるかということさえ十分に予見することはできないかもしれません。それでもいくつかの基本的な傾向を見て取ることができます。
その一つは、個々のテクストが比較的小さなもの、さらにいえば、断片的なものとなっているということです。もちろん、長大な書物一冊をそのまま一つのファイルとして他のテクストからリンクさせることも可能ではありますが、どちらかといえばそんなことはあまりやらないで、章などの要素ごとに分割してリンクさせることをまず考えるのではないでしょうか。そうするのは、とりわけWWW上では巨大なファイルだと読み込むのに時間がかかるという単純に技術的な問題もありますが、それだけでなく、長大なテクストを最初から最後までまとめて一つのファイルとするのはハイパーテクスト的ではないという感覚が働いているように思われます。
最初の方の話に少し戻りますが、ハイパーテクストを成り立たせている最低限の要件として、
という3点をとりあえずあげておきました。その際、最初にあげた「複数のテクスト」とは何を指しているのでしょうか、という問いを掲げたのは、まさしく今問題としていることに関わっているのです。つまり、ハイパーテクストにおいては、旧来の「テクスト」をリンクさせることももちろん可能ではあるけれども、その構成要素は一般的にいって、もっと小さな単位が用いられます。その意味では、そのリンクされている「複数のテクスト」と呼んでいるものも、旧来の意味で「テクスト」と呼べるものかという疑問さえ起こり得ます。もちろん、長いテクストもあれば短いテクストもあるわけですが、単に長さの問題ではありません。著者があることを語ろうとしたとき、語りはじめからそれなりの長さをもつ中間部を経て集結へと至る全体(これを、広い意味で「物語」と呼ぶことにしましょう)は、ある統一的な構成と内容をもつひとつのまとまりであり、一般的にいって、著者が書いた順序で(そして、著者が意図したように解釈されて)「読む」ことが要請されています。長大なテクストを最初から最後までまとめて一つのファイルとするのはハイパーテクスト的ではない、と感じられるもう一つの決定的な理由は、ここまでくれば明らかなように、ハイパーテクストにおいては、各要素を読む順序が固定されていない(「非順序性」)という特質に関わっています。「はじめ」から「終わり」へといたるひとつの「物語」の統一的な全体を「テクスト」と呼ぶとすれば、非順序的に読まれうる、「テクスト」の個々の断片は、(それらをつなぎ合わせれば確かにもとの「テクスト」と同じ情報になるとはいえ)素朴に「複数のテクスト」と呼んでよいものなのでしょうか。(すでに私自身の文章で、そういった曖昧な表現を何度も使ってきましたが。)
個々のハイパーテクストを任意の順序で読むにせよ、それらを全部読めば、とりあえず著者の書こうとした全体像が見えてくるだろう、といった譲歩も可能かもしれません。ところが、ウェブ上のさまざまな文章を読んでいる人にとっては周知のように、ある人が述べようとしている内容に関連するその人のすべてのページを読む必要などなく、全部を読む前に、リンクをたどって他のサイトに移ることはごく自然なことです。伝統的な「書物」であっても、つまみ食い的に読むことはもちろん可能ですが、一続きのものとして全体の統一的な構成と内容をもっている場合には、そういったことは本来ふさわしいことではないと承知した上でやっていることです。しかし、ハイパーテクストにおいては、そもそも個々のページの全部を読むこと自体が要請されていないといってよいでしょう。その意味においても、ハイパーテクストは「断片的」なのです。ハイパーテクストは、著者の意図する順序、著者の意図する全体性という考え方自体、いや、そもそも「著者」とか「意図」という概念そのものを解体する可能性をもっているのです。
すでに述べたように、従来の「書物」・「テクスト」も相互に指示し合い、その意味でやはりリンクし合っています。それらの「リンク」を視覚的なイメージで表現するとすれば、「はじまり」から「終わり」へと至る完結した統一的な「物語」同士が、明示的・暗示的に言及するという形で、重層的な関係を持ちながら結びついているとでもいえるでしょうか。伝統的な文書・テクストのリンクとは、「物語」としての統一的な全体性と線状性をもつもの同士のあいだに成立する、いわば「大きなリンク」とでも呼べるようなものであり、「テクスト」を「読む」ことは、著者の意図によって間隙なく満たされた、ある統一的な空間のうちに沈潜し、テクスト内の著者の意図へと求心的に志向する性格を強くもっています。
それに対して、ハイパーテクストによってある人が述べようとした思考の個々の断片(WWWでは、それぞれが一つのHTMLファイルとなります)が相互にリンクされた全体を、伝統的な書物の「テクスト」にあたるものととりあえず見なすとすれば、そこでのリンクは、伝統的なテクスト同士のそれに対して「微細なリンク」とでも呼べるかもしれません。そして、それらのハイパーテクストのいくつかは、他の人が作ったハイパーテクスト群へもリンクしていきます。
図3
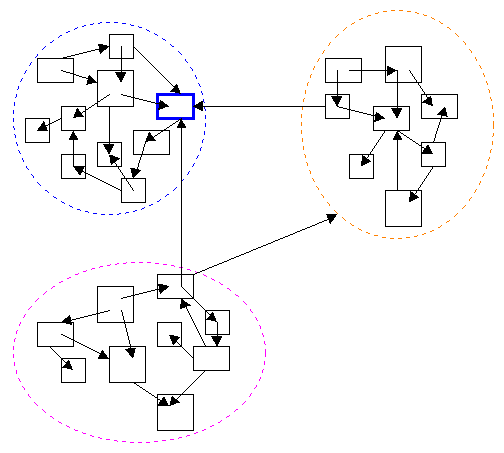
この図では、他の人のハイパーテクスト群へのリンクは、上に述べた、旧来のテクスト同士のあいだの「大きなリンク」に対応するものとも見えます。しかし、実際には、これらのハイパーテクスト群をすべて読むとは限らず、それぞれのグループの中から自分にとって関心のある一部だけをたどっていくことになります。つまり、上の図のように書いた人ごとのテクスト群という意識は弱まり、下の図のように、ある関心によって取り出されたハイパーテクストの断片的な要素群が、そのときの思考像を作り上げることになるでしょう。
図4
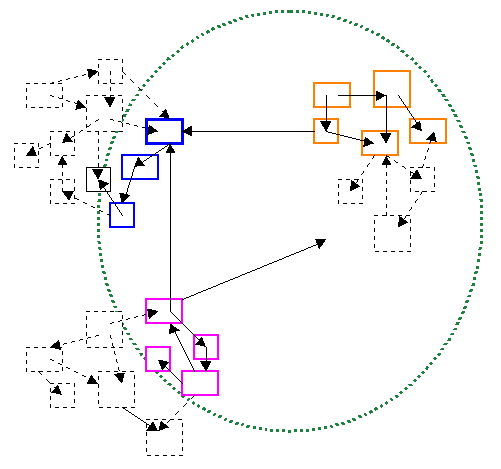
このように、ハイパーテクストの個々の断片が非順序的に読まれることによって得られる像においては、もともとある同じ人が書いたテクスト群全体としてある意図が存在するとしても、その「意図」へと向かうべき要素が力を結集する前に要素が断片として切り取られることによって、「意図」は解体されてしまいます。また、その「意図」を統合的なテクストによって構成する「著者」もほとんど消し去られてしまいます。つまり、伝統的な書物においてみられる「著者」と「著者」のあいだの「大きなリンク」と呼んだものは、ハイパーテクストにおいては実質上ほとんどないに等しくなり、すべてが「微細なリンク」と呼んだような断片化された思考砕片相互の結合となるのです。それらの砕片によって得られる像とは、一種のモザイク像といってもよいかもしれません。
こういったハイパーテクストの捉え方は、いわゆるポスト構造主義のテクスト理論ときわめて顕著な親近性を示しています。というよりも逆に、これまで述べてきたようなハイパーテクスト理解は、ポスト構造主義的な視点によって示されたものだともいえそうに見えます。しかし、もともと異なるところから発した二つの出来事が、本質的に同じ方向を共有することとなったという側面もやはり見逃すわけにはいきません。現在、人文的なハイパーテクストの理論において非常に重要な位置を占めているジョージ・P・ランドウの著書『ハイパーテクスト』は、そのオリジナルの副題が示すように、「現代批評理論とテクノロジーの収束」、つまり、ロラン・バルト、ジャック・デリダ、ミシェル・フーコー等、ポスト構造主義のテクスト理論と、ヴァネヴァー・ブッシュ、テッド・ネルソンに端を発するハイパーテクストの構想が、同じ方向へと集結していることを指摘しています。[註14] この『ハイパーテクスト』の2年後にランドウが編集者となって発行されたハイパーテクストの理論に関する小論集『ハイパー/テクスト/理論』の巻頭論文で、こういったことをより簡潔にまとめている箇所があるので、そこをひとまず引き合いに出してみましょう。
ハイパーテクスト、すなわちテクストの個々のブロックないしはレクシ、およびそれらを結合する電子的なリンクからなる情報テクノロジーは、近年の文学理論・批評理論と多くの共通点を有している。例えば、ロラン・バルトやジャック・デリダといったポスト構造主義者の近年の著作がそうであるように、ハイパーテクストは、著者や読者、および彼らが書いたり読んだりするテクストに関して長い間抱かれていた因習的な見解を受け取り直している。ハイパーテクストの決定的な特性の一つとなっている電子的リンクはまた、ジュリア・クリステヴァの間テクスト性の概念、ミハイル・バフチンの多声性の強調、ミシェル・フーコーの権力ネットワークの概念、そしてジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリのリゾーム状態のアイディアや「遊牧的思考」を具現している。ハイパーテクスト性というまさにその考え方が、ポスト構造主義がおこったのとほぼ時を同じくして形を取ってきたように見えるが、この両者の収束点は、単なる偶然性によるものというよりは、もっと親近的な関係を持つものである。というのも、この両者とも、印刷された書物や階層的思考といった、相互に関連する現象に対する不満から育ってきているからだ。[註15]
「ポスト構造主義」とは、「主に1960年代の後半にフランスで台頭し、構造主義を批判的に継承したとされる一群の思想を指す用語」(岩波『哲学・思想辞典』)と、とりあえずは位置づけることができますが、誰が(その多くはもともと「構造主義者」とされているのですが)どの時代から「ポスト構造主義」に属するものとなったかということも、確定的なことでは決してありませんし、例えば、ポスト構造主義者とされるフーコーが「ポストモダンの思想家あるいはポスト構造主義の思想家と呼ばれている人々にとって、いったいどのような種類の問題が共通の問題であるのか、私にはさっぱり分かりません」[註16]と発言している状況も、ことさら彼に限ったことではありません。そもそも、「ポスト構造主義」という呼称自体、それに属するとされているクリステヴァ、R. バルト、ラカン、デリダ、フーコーらの人々が自ら用いているものではなく、外部から与えられたものに過ぎないという側面もあります。さらに、上に引用したフーコーの言葉にも見られるのですが、「ポスト構造主義」と「ポストモダン」とがしばしば同一視されるということも、こういった錯綜状況をさらに加速させているようです。
本来は、言葉通りに取れば、「ポスト構造主義」は構造主義の批判的継承として、とりわけ批評理論の分野において展開されてきたものであり、「ポストモダン」は啓蒙的な理性に依拠した「近代」の思想の枠組みそのものを問題視する、より広い視野に立つものともいえます。しかし、この両者がしばしば「混同」されるのも、あながち理由のないことではないとも思えます。というのも、「ポスト構造主義」における新たなテクスト概念の提起が、これまで引き継がれてきた「近代」のテクストに関わる思考を批判的に解体する姿勢に基づいているからです。例えば、おそらく「ポスト構造主義者」の筆頭として一般に理解されているであろうデリダに依拠しつつ、「神」「自己」「歴史」「本」という四つの概念、とりわけ「西欧近代」の刻印を受けたこれら四つの概念の終焉・消滅・解体を「神学解体」として描き出したマーク・テイラーの『さまよう ポストモダンの非/神学』などには、そういった方向が顕著に示されていると思われます。 次のようなM. テイラーの言葉は、ランドウがそのまま引き合いに出しそうなものかもしれません。
どこからきて、どこへゆくのか、人々は誰もみな、おぼつかなげな様子に見える。自分たちがどこにいるのか、人々にはそれがいっこうにはっきりしない。しかもまた、先行する数々の世代の人間を、これまでずっと、方向づけ根拠づけてきたあの「テクスト」そのものが、このモダン世界・ポストモダン世界では、往々にして、読みとり不能、の様相を呈している。それというのも、人間の生そのものが、単一の物語、ないしは、一貫する筋の展開、という表現を取る代わりに、今では、それが、多種多様な、それもしばしば相互に矛盾し合うようなテクスト群に記載される、という傾向を取り始めたからである。[註17]
ランドウは、「現代批評理論とテクノロジーの収束」がどのような点において起こっているかををとりあえず提示するために、批評理論において「網目(ネットワーク)」や「結節点(ノード)」について言及された箇所や、「間テクスト性」「多声性」「脱中心性」といったハイパーテクストのアイディアにもつながる概念にふれた後、両者の「収束点」として、さらに「テクストの再編」「作者の再編」「物語の再編」「文学教育の再編」といった論点を集中的に取り上げていきます。これらはすべて、「近代」の遺産としてポストモダンの論議において解体の中心的な対象となるものであり、「現代批評理論」としての「ポスト構造主義」をめぐるものとされながらも、実際には「ポストモダン」のスタンスが問題となっているといった方が、最終的にはより近いものとなるかもしれません。(ランドウ自身、ポスト構造主義とポストモダンの区別を、全体としては曖昧に扱っているように思われます。)ただ、ランドウの語り口には、技術がもたらす新しい未来に対する楽観的な希望があふれているように感じられ、その点はポストモダンの姿勢とは著しく異なるものですが。
ハイパーテクストの理論に関心をもつ人には、ランドウの『ハイパーテクスト』はぜひ自分で読んでもらいたいと思いますが、彼が取り上げている重要な論点のうちいくつかについて、少しふれてみたいと思います。ハイパーテクストとポスト構造主義の文学理論との親近性を指摘する文脈でしばしば引き合いに出されるのが、ロラン・バルトの『S/Z』の冒頭付近にある次の箇所です。
一つのテキストを解釈するということは、それに一つの意味(多かれ少なかれ根拠のある、多かれ少なかれ大胆な)を与えることではなく、反対に、それがいかなる複数から成り立っているかを評価することである。まず、いかなる再現の(模倣)束縛も貧しくすることのない輝かしい複数のイメージを思い浮かべよう。この理想的なテキストにおいては、網目が多様で、いかなる網も他の網の上に立つことがなく、互いの間でたわむれる。このようなテキストは、記号表現の銀河であって、記号内容の構造ではない。それは始まりをもたず、可逆的である。いくつもの入り口からそれに近づくことができ、どの入り口がぜったいに主要な入り口であると断定することはできない。それが動員するコードは見渡すかぎり横に並び、そのうちのどれと決定することはできない。[註18]
ここに見られる表現は、まさにハイパーテクストのあり方を言い表しているようでもあり、ハイパーテクストの理論家がこの箇所に引きつけられるのも頷けます。このロラン・バルトの著書は、1968-69年にパリの高等研究院で行われた彼のセミナーの成果ですが、デリダとの関連と並んで(1967年は、『エクリチュールと差異』と並んで、とりわけ『グラマトロジーについて』が出版された決定的な年でした)、65年以来バルトのセミナーに加わっていたクリステヴァからの強い影響も受けています。上のバルトからの引用も、とりわけ、生産性としてのテクスト、間テクスト性という彼女の基本的な思考と切り離して考えることはできないでしょう。(「間テクスト性」とハイパーテクスト的思考との「収束点」を指摘するランドウが、『ハイパーテクスト』でクリステヴァに全く言及していないのは意外です。94年の『ハイパー/テクスト/理論』ではすでに引用したように、一応名前を出していますが。) 『テクストとしての小説』(1970, 執筆は1966-67)や『セメイオチケ』(1969)で提起された「間テクスト性」inter-textualitee(あるいは「相互テクスト性」「テクスト間相互関連性」などとも訳される)という概念は、現在では広く使われるようになっていますが、その意味するところの説明を、最近出たクリステヴァの解説書から借用させてもらうことにしましょう。(クリステヴァが実際にこの言葉をどのように用いているかは、資料「クリステヴァの<間テクスト性>についての引用」を参照して下さい。)
間テクスト性 クリステヴァがミハイル・バフチンから継承した考え方。あらゆるテクストは、様々な引用のモザイクとして作られており、すべてのテクストは他のテクストの吸収であり、変形であるという考え方のことである。一つのテクストは、孤立して存在するのではなく、今まで書かれたテクスト、これから書かれるテクストと関係し合っており、テクストは社会と文化環境と歴史という外部へと開かれたものとして捉えられる。テクスト空間は独語(モノローグ)つまり単一論理が支配する空間ではなく、対話(ディアローグ)する複数の論理の構造として捉え直される。テクスト上で読み手は書き手と、一つの社会・歴史は別の社会・歴史と、フェノ=テクスト[現象としてのテクスト]はジェノ=テクスト[起源/生成としてのテクスト]と、対話し、あらたなテクストを生み出し、テクストを多声化する。[註19]
ランドウは『ハイパーテクスト』の中で、「間テクスト性」という概念をことさらに規定して用いてはいませんが、おそらく一つのテクストが他の複数のテクスト群と顕示的・暗示的に参照しあうことによって結びつき、そのようにして開かれたテクストとなっていること、また、他のテクスト群と参照しあう際の離散性(「線状性」に対する)・引用可能性・分割可能性によってあらたなコンテクストを生産する可能性、を意図しているようです。ランドウは「間テクスト性」について、とりわけデリダに関連づけて述べていますが、彼がこの言葉によって意図するところはたとえば次のような箇所に見て取ることができるでしょう。
バルトやフーコーやバフチンのように、デリダは連鎖(link)、蜘蛛の巣(web)、網の目(network)、綯い交ぜ(interwoven)といったハイパーテクストを思わせるような術語を一貫して使ってきた。バルトは読みうるテクストとその非直線性を強調したが、彼と対照的にデリダはテクストが開かれているということ、間テクスト性、ある特定のテクストの内側/外側の区分の不適切さを強調する。(p.18)
新しく、より自由で豊かなテクストの形態――われわれの潜在的体験により忠実で、認識していないとしてもわれわれが実際に行っている体験により忠実なテクストの形態――が離散的な読みのユニットに依存しているということを、デリダは正しく(前もって、と言ってもいいだろう)知っていた。(p.19)
「(...) すべての記号は、言語的なものであれ非言語的なものであれ、言表されたものであれ書かれたものであれ、... 引用され、引用符に括られうる」(Ulmer)。この引用可能性と分割可能性は、ハイパーテクストにとって決定的な次井の事実に現れる。それはデリダの付言によれば、「このようにしてこの可能性が所与のコンテクストとの関係を断ち切れるようになり、絶対的に制限できない方法で無数の新しいコンテクストを生み出している」(Derrida) という事実である。
バルトと同じように、デリダもテクストを離散的な読みのユニットから構成されるものだと捉えている。デリダのテクスト観は、哲学の境界を超越する彼の「解体の方法論」と関連している。(p.19)
ハイパーテクストは基本的に間テクスト性をもつシステムであり、書籍という形の製本されたテクストでは不可能な方法で間テクスト性を強調できる。われわれがすでに見たように、学術論文と学術書は電子形態での明示的なハイパーテクスト性のあからさまな一例を提供してくれる。逆に、文学作品は(...) 非電子形態での暗示的なハイパーテクスト性の一例を提供してくれる。(p.21-22)
「間テクスト性は文学史の発展史観モデルを記号体系としての文学の構造的ないし共時的モデルに置き換える。この戦略の変化のもっとも突出した効果は、文学テクストを心理学的、社会学的、歴史的決定論から解放し、関係性の明白に無限な戯れへとテクストを開くことである」(Morgan)。モーガンはハイパーテクスト(ハイパーメディア)の間テクスト性が主に含意しているものをうまく記述している。このように開くこと、このように相互のつながりを自由に想像し認知させること――これは実際に起こっている。(pp.22-23)
さて、このようにたどっていくとき、間テクスト性とハイパーテクスト性とのあいだに、指摘されるような親近性を確かに見て取ることができますが[註20]、同時に、(厳密な概念規定上の差異以前の)ある重大な相違点があるのではないか、ということに気づかされます。それは、相互に関わり合う複数のテクスト群とというときの個々のテクストとはどのような単位かということです。たとえばクリステヴァの場合(また、上に引用した意味においてはランドウもそうなのですが)、その単位とは、ひとつの書物(ないしは、ひとつの書物の中のある完結したまとまり)であり、それが関わる他の「テクスト」もやはり同じようなまとまり(あるいは文化的・社会的・歴史的テクストの場合もありますが)であると考えられます。ハイパーテクストはそういった単位同士のリンクによって成り立つことももちろん可能ですが、しかし、その本来のあり方によりふさわしいのは、「書物」がより細分化された単位同士の結合であるといえるでしょう。こういった言い方だと、書物とハイパーテクストとの違いは、ただ単に、構成単位をどのように捉えるかということだけであり、ハイパーテクストにおけるより小さな構成単位を寄せ集めればテクスト(書物)になるというように聞こえますが、問題は単に構成単位の大きさだけではありません。
単にもともと「書物」(つまり線状的なテクスト)であるものを細分化して、それらの要素をハイパーテクスト的に相互にリンクしたもの(いわば「テクスト」から「ハイパーテクスト」への翻訳)であれば、もともとの読みの順序と各要素の結合関係がほぼ保たれるであろうため、それほどハイパーテクストとしての顕著な特質を示さないかもしれませんが、はじめから「ハイパーテクスト」としてデザインされたものは、トータルとして同じような記述を含むものであっても、各要素の自由な結合と非順序的な読みの可能性によって、「書物」とは全く異なったものとなるでしょう。そして、「書物」ではその全体を読むことが前提となっているのに対して、すでに図4でも示したように、ハイパーテクストにおいては、より細かな構成要素の任意のものだけ読み、他のハイパーテクスト群のひとかたまりのうち、やはり任意の構成要素へとつながることが可能であり、実用上も、そのように読まれることがごく普通となっていると考えられます。
ランドウは、たとえば学術論文・学術書あるいは文学作品を「間テクスト性」に関わるものとして引き合いに出していますが、もちろん彼自身、ハイパーテクストにおける各構成要素間のリンクとして、本来はより小さな単位におけるものを考えているはずです。確かに、他の構成要素/テクストとの結合という機能とそれによるテクスト空間の広がりということに関しては、間テクスト性とハイパーテクスト性との間の親近性を認めることができるかもしれません。しかし、ハイパーテクストにおいて一般に見られるような、はるかに微細化された要素間のリンクと、さらにそれらの要素が(全体としてではなく)任意のものだけ選ばれて他のハイパーテクスト群のやはり任意の要素とリンクされるといったあり方は、少なくとも、一般に「間テクスト性」として理解されているものとは決定的に異なると思われます。
「間テクスト性」の要約的な説明として上に引用した箇所の中に、「あらゆるテクストは、様々な引用のモザイクとして作られており」という記述がありますが、「間テクスト性」の個々の単位は、「モザイク」というには少し大きいものかもしれません。それに対して、ハイパーテクストにおける個々の構成要素は、単にそれがより小さなものであるというためばかりでなく、他のハイパーテクスト群の要素と自由に結びつけられるという性格をもつために、より「モザイク」的であるということができるように思われます。たとえば、ある図柄と色彩をもつ薄い陶器を砕いて、それをまったく別の図柄や色彩のいくつかの陶器の破片とともに、ある大きな平面へと張り付けて新しい図柄を描き出すことを考えてみて下さい。その新しい図柄を作り出すために、もともとあったすべての破片を用いることはありませんし、どこにどのように配置するかも全く自由なのです。しかし、それによってそれぞれ異なったモザイク像が生み出されることになります。
このことをハイパーテクストに当てはめて考えれば次のようなことになります。ある人(ないしは団体)が構築したハイパーテクスト群(たとえば私の「ホームページ」という一つのかたまりにおける、個々のページの集まり)は、個々の要素から成り立ちながらも、多くの場合、全体としていわばひとつの「意味」をもたらそうと意図されています。(たとえば、わたしはこういった人間です、といったアピール。)しかし、そういったハイパーテクスト群の中から、それを見る(インターネットでは「ブラウズ」する)人間が任意の要素だけ抜き出し、他のハイパーテクスト群の任意の要素と結びつけるとき、その人の頭の中では、もともとその人が参照したあるテクスト群における「意味」は解体され(このことが「作者」の解体につながっていくわけですが)、その人の頭の中であらたに再構成された像(モザイク像)となってあらたな意味を形成することになるのです。
こういった間テクスト性とハイパーテクスト性との違いを図示するとすれば、ちょうどネルソンの「ザナドゥ」の模式図(図1)とハイパーテクストのモザイク性の図(図4)の違いと言い表すことができるかもしれません。もちろん、「ザナドゥ」もハイパーテクストのシステムですから、そこでの各構成単位は必ずしも「書物」にあたるものとは限らないのですが、すでに述べたように、旧来のテクストの「理想郷」としての性格を強くもっているために、かなり間テクスト性に近いものとも感じられます。
さて、最終的には「間テクスト性」と「ハイパーテクスト性」との違いを強調することに終わってしまうかのような印象を与えることになったかもしれませんが、それにもかかわらず、やはり「ポスト構造主義」あるいは「ポストモダン」的な思考とハイパーテクスト性との間には、きわめて重要な親近性が存在していると私も考えています。私が「間テクスト性」と「ハイパーテクスト性」とを対比したやり方は、ことさらに「間テクスト性」が旧来のテクストそのものを単位としているかのような提示の仕方だったのですが、そこでの単位とした「テクスト」も、線状性から解体されたものをむしろ志向するものでもあり得るでしょう。
私の本来の意図としては、「ハイパーテクスト」が「テクスト」より優れているということを主張するつもりは全くありません。なぜならば、これらは別のメディアのあり方であって、後者が前者によって変容を被ることがあるにせよ、両者ともにそれぞれの意義をもって存続していくものと考えるからです。しかし、それに対して、そもそも「ハイパーテクスト」と「テクスト」という対置的な関係そのものに対して疑問を呈する立場もあり得ます。ユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』の中で(第5編)ノートル=ダム寺院の司教補佐クロード・フロロが口にする「これがあれを滅ぼすだろう」という言葉、すなわち印刷された「書物」が、ノートル=ダム寺院という石でできた「建築物」を滅ぼすだろうという言葉は、メディア論の文脈で好んで引き合いに出されるものですが、それは次のユゴー自身の説明を読めば納得のいくものとなるでしょう。
つまり、人間の思想はその形態が変わるにつれて表現様式も変わってゆくのだ、新しい時代の代表的思想はいつまでも古い時代と同じ材料や方法では記録されない、さすがにじょうぶで持ちのよい石の書物も、さらにいっそうじょうぶで持ちのよい紙の書物に取って代わられることになるのだ、という予感なのである。(...) つまり一つの技術がもう一つの技術を追い払おうとしている、という意味があったのだ。言い替えれば、印刷述は建築を滅ぼすであろう、ということなのである。(ヴィクトル・ユゴー『ノートル=ダム・ド・パリ』辻昶・松下和則訳、講談社、1975、p.188)
ここで問題となっているのは、「書物」が「図像」を滅ぼしてしまう、というメディアの転換ですが、同じことが「コンピュータ」と「書物」とのあいだについてもいえるか、ということを、ウンベルト・エーコがそういった問題設定そのものに対して批判的な立場から問いかけています。[註21] ここでのエーコの批判は、意外なほど些末なことに向けられたものがありますが、これはよく耳にする批判でもあります。たとえばエーコは、「しかし、書物には、コンピュータに対する利点もあるのです。耐用年数たった七十年の酸性紙に印刷されたとしても、磁性的な媒体より永続的であることです。しかも、電力不足や停電の影響を受けることなく、衝撃に対してもより強い」とか「無人島に難破したとき、コンピュータは無用の長物と化しても、書物は役に立つのです。電子テクストには読む場所と機械が必要です」といった効用性に関わることを主に、本を支持するための論拠にあげています。確かにその通りかもしれません。しかし、そうであったとしても、電子的なテクストに関わるほんとうの問題はそこではないのです。問題なのは、書物の物質的なありようではなくて、「書物」という形でわれわれがこれまで築き上げてきた文化の総体に関わるものが、ハイパーテクストと呼ばれているものによって変わるのか否か、ということであると思われます。エーコは、ジェイムス・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』などによって、すでにテクストという形でハイパーテクスト的なものが過去に存在しているのであるから[註22]、「ハイパーテクスト」なるものはことさらにコンピュータによって特徴づけられるものではない、と述べていますが、だからといって、現在これほどまで圧倒的に波及したハイパーテクストがコンピュータによるものであることを無視することはできないはずです。自分のたどっているものが「ハイパーテクスト」であると意識しないままに、インターネット上でさまざまなページを「ブラウズ」する人がますます増え、その人にとってはかなり重要な道具となりつつあるという現実があります。そこで用いられている「ハイパーテクスト」というシステムは、これまでの「テクスト」とほんとうに対置されるようなものなのでしょうか――まさにこのことを、今回、取り上げてきたわけです。
たまたま、上にあげたエーコの文章が掲載されている『本とコンピュータ』の同じ号の中に、ハイパーテクスト論における「読む」行為の楽観性に対する批判が提起されていました。[註23] 一言でいえば、いかに電子化されたテクストへのアクセスが技術的に便利なものとされようとも、結局は、「読む」という行為自体は同じであり、ハイパーテクストを称揚する論議においてはそこがおろそかにされている、と要約できるでしょう。こういった考え方は、かなりのコンピュータ・ユーザであっても、とりわけ人文系の研究者において広く見られるものであると思われます。たとえば、『現代文学理論 テクスト・読み・世界』というタイトルどおりの概観を行っている本の最後に、「コンピュータと文学研究 人類究極の道具(ツール)は既存の文学研究を根底からくつがえすか?」という章があてられています。そこでは、人文系の研究者にとってコンピュータがいかに有用な研究の道具となりうるかがさまざまなトピックを掲げながら提示されていきますが、最後には次のような結論に至ります。
しかしながら、デジタル処理をコンピュータにやらせ、その結果を読みとり、意味を与え、解釈するのは、昔ながらのアナログ志向を駆使する研究者に他ならない。そこにあるのは、昔ながらの、テクストからの世界の想像と構築なのである。コンピュータを利用する検索や統計分析は、一見して無味乾燥な様相を呈し、しばしば批判の対象となりがちである。しかしながら、その陰に隠れている研究者の発想と解釈は、明らかに熱い血が通ったアナログ的思考なのだ。コンピュータによる文学研究とは、紛れもなく、生身の人間のアナログ的思考と、コンピュータのデジタル能力との、共同作業に他ならない。[註24]
私もやはりだいたい同じように考えていました。どんなに電子テクストで検索するのが容易になろうと、文献へのアクセスが容易になろうと、リンクによって文献をつなげようと、結局はそのテクストを読まなければ話にならない。その通りです。少なくとも、人文研究者が従来の研究を続けようとする限りにおいて、その点は基本的に変わることはないでしょう。
しかし、ここには落とし穴があります。上に引用したような立場は、これまで行ってきた人文的な研究が絶対的なものであるという前提に立って、コンピュータを単にそのために従属させるべき「道具」(まさにそういっていますが)として用いるという姿勢に基づいています。「道具」とは目的に至るための手段に過ぎないということです。確かにコンピュータは、「人文研究」という目的に仕える、使いようによってはきわめて有用な手段となっています。しかし、これは私がとりわけ身体性に関わる論議で強調してきたことですが、道具はそれを使うものに対して変容をもたらし、それにともなって、目的として考えられていたこと自体も変化を被ることがあります。コンピュータをかなり集中的に使う人は、「読む」こと、「書く」ことに対する微妙な感覚の変化、あるいは実際上の変化にすでに気づいているでしょう。それはコンピュータというメディアによってもたらされたものです。ここでも「メディアがメッセージである」というテーゼが決定的に成り立ちます。
「テクスト」を「読む」ということ、これが人文的な立場において決定的に重要なものであることは強調するまでもありません。ところが、とりわけ「ハイパーテクスト」という、同じ「文字」を使うがゆえに気づかれにくいのですが、これまでの「テクスト」とは根本的に異なる思考様式をもたらすシステムのうちにそれとは知らずとも身を置くことによって、「テクスト」的な思考は、少しずつではありますが揺らいでいくことになるでしょう。本を読むのも、ハイパーテクストを読むのも、書かれている中味自体が対応していれば、同じことだ、大切なのは、それを「読む」ことだ、という主張は、ハイパーテクストにおいては当てはまらなくなっていきます。そこでの「読む」とは、テクストの線状的な特質を前提としたものだからです。これまでの「書物」であったものを単にハイパーテクストへと電子化したものであれば、「読む」ことの経験は、とりあえずそれほど変わらないかもしれません。
しかし、これから「ハイパーテクスト」としてはじめからデザインされたものがますます広がっていくとき、「読む」とは、もはや従来のテクストを読むという行為ではなく、ハイパーテクストを非順序的にたどっていくことによって得られるようなモザイク的な像の構成を指すものとなるかもしれません。そんなものは人文的な研究とは無縁だ、という主張も確かにある意味で正しいといえるでしょう。というのも、これまでの人文的な研究は圧倒的にテクスト的な思考に依拠したものであるからです。
しかしながら、これからもし、ハイパーテクスト的な読み方が社会・文化において圧倒的な力をもつものとなるとすれば(ちょうど、技術メディアによる映像的・音響的な文化がそうであるように)、そういった読みのあり方、さらにはそれによってもたらされる文化のあり方を無視することはできなくなるはずです。こういった事態がとりわけ顕在化するならば、それまで絶対的な準拠枠と思われていたテクスト的な思考、テクスト的な文化のあり方に対して、疑問が生じることにさえなるでしょう。ハイパーテクストとポストモダンの「収束点」は、まさにこの根本的な点にあると考えます。コンピュータは人文研究のための有用な道具となりうるという側面を持ちながら、同時に、人文的な思考のあり方そのものを解体する可能性をももっています。自分の手の中にあると思っていたものが、その特性にしたがって、知らないうちに自分の立っている基盤そのものを掘り崩すことにもなりうるのです。
ハイパーテクストがインターネット上で広く使われるようになってからほんの数年しか経たない現在、テクストとハイパーテクストがこれからどのような経過をたどっていくか、見通すことはできません。しかし、おそらく、インターネットはさらに社会的・文化的にますます浸透していくでしょう。そして、「書物」が消えることがないとしても、ハイパーテクストを「読む」経験・「書く」経験がさらに規模・程度を増していくことはまちがいないでしょう。こういった事態を認めることは、従来の人文研究の立場からすれば、我が身が脅かされるべき憂うべきものとうつるか、あるいはそもそも、「ハイパーテクスト」にそのような(人文にとっての)脅威があると考えること自体ナンセンスなこととして排除されるだけかもしれません。しかし、もし、文化の総体的な趨勢において、テクスト的な思考が没落する運命にあったとしても、大きな視点から見れば、それはただメディアの転換の一場面であり、それが悪いこと・憂慮すべきことであるとか、逆に新たな文化の出現を楽観的に称揚するといった態度とは、それ自体としては無関係に進行していくことでしょう。