| <世界> | <画像> | |
|---|---|---|
|
|

|

|
1998年度 インターネット講座
(99/01/02 更新)
前回は、メディアと身体の接続に際してどのようなことが起こっているか、論議となる点を全般的に概観してみました。これから、それぞれのメディアの段階ごとにもう少し詳しく見ていきたいと思います。ここでメディアの段階と呼んでいるものは、これまでもそれにしたがって話を進めてきたような「音声言語」を中心とする感覚的直接性の段階、「文字言語」の段階、そして電気/デジタルメディアの段階です。
最初の「音声言語」を中心とする段階は、これまでも述べてきたように、単に音声言語だけが問題となるのではなく、五感によって世界を統合的に感じ取る状態にあると考えてきました。その性格として「直接的」という言葉を何度も用いてきましたが、この言葉自体は、本来は何の媒介・媒体も存在しないということを意味するはずのものです。そういった状態において身体と接続している「媒体」などそもそも存在するのでしょうか? ここで私が考えている媒体とは、身体的な感覚器官(目・耳・舌・鼻・皮膚)に対して、対象としての世界が刺激を運んでくるもの、つまり光、音、あるいは臭い・味(感覚としての臭い・味ではなく、臭い・味の物質そのもの)、あるいは熱などのことです。これらを媒体と呼ぶのは少し奇異な感じを受けるかも知れませんが、それはこれらがわれわれの日常的な感覚にとって、対象と直接に(つまり無媒介に)結びついているように感じられるからです。しかし、光、音などを通じて(つまりそれを媒介として)対象がわれわれに知覚され認識されるわけですから、その意味で光、音などは理屈として媒体と呼ぶことができるでしょう。
このことは、ここではじめて言及されるのではなく、実はすでにマクルーハンについて述べたところでも問題となっていたことです。「メディアはメッセージである」という有名なテーゼを説明するために、マクルーハンは電気の光を引き合いに出しています。電気の光自体は(たとえばそれがネオンサインとして用いられ、それによって何らかの言述が見えてこない限り)もともと何の内容ももっていませんが、そもそもそれ自体がメディアであるということが気づかれないという機能自体がある文化的段階を指し示すという意味で、その文化段階のメッセージとなっているのです。[註1] マクルーハンがこのように、光や音といったレベルのメディアと、書物、新聞、ラジオ、テレビといったレベルのメディアを同じように扱っていることは、彼の理論の混乱ぶりを示すものとして批判の対象となっていますが、この文脈で彼が述べている「どんなメディアでもその「内容」はつねに別のメディアである」(『メディア論』P.8)というもうひとつの重要なテーゼは、これからも何度か言及することになるでしょう。この場合であれば、光や音といったレベルのメディア――これはさきほど述べたように、「音声言語」の段階での身体的な感覚性に「直接」に接続しているように感じられるメディアですが――は、たとえばテレビというメディア――これはもちろん電気メディアの段階です――の内容となっています。
少し先取りして述べることになってしまいました。話を元に戻しますと、光や音といったメディアがそもそもメディア(媒体)として日常的には感じられないのは、それが身体と接続して知覚・認識を生じさせる際に、間接性・媒介性がほとんどないように思われるからでしょう。だからこそ、こういった刺激による感覚が人間にとって「直接的」と呼ばれても違和感がないのです。本当は、光や音が媒体であるかぎり、「直接的」ではありえないのですが。光や音などの対象からの刺激がそのように「直接的」と感じられるのは、何よりも目や耳といった人間の感覚器官、すなわち外界との間のインターフェースがきわめて精巧にできているからであるとともに、そのインターフェースにわれわれは長い時間をかけて極めて高いレベルで習熟しているからです。
音声言語の段階の身体的な感覚がどれほど「直接的」と感じられるか(それはあくまでも「感じられる」だけで、上に述べたような考え方をすれば、本来は「直接的」ではないのですが)は、次の文字というメディアの根本的に間接的な性格と比較するとき、はじめてはっきりしたものとして捉えられることになるでしょう。マクルーハンは、「音声言語」の段階では人間の感覚のうち聴覚が中心となっているのに対して、「文字言語」の段階では文字をたどる視覚が中心的役割を果たしていると述べています。しかし、われわれが本を読むとき、その視覚が捉えているものは何でしょうか? 本の形状やページの白い背景が本来もっている物質性を無視するとしても、その白い背景の上に浮かんでいるものは、それ自体としては単にインクがつけた二次元的な黒い模様にすぎません。もちろん、その黒い模様によって表されている記号としての文字、そしてその文字によって表されている言語に習熟している人にとって、それを「読む」ことが問題となります。文字言語の段階の中心に位置するのは、間違いなく「書物」でしょうが、この「書物」というメディアに接続するときの身体性として問題となるのは、一般的には、その最初のインターフェースとしての視覚自体ではありません。ひとつ例を出してみましょう。
彼は硝子戸をがたごといわせて、土間にはいった。乾魚の臭いがしていた。彼は「ただ今、」と言った。
「寒かったろうに。早くおこたにおはいり、」とおばあさんが言った。
叔父さんはもうそこにはいなかった。一郎と二郎とがこたつの中で餅を食っていた。叔母さんはお勝手でことことやっていた。おばあさんがこたつの側に七輪を置いて餅を焼いていた。一郎が早口に喋っていたが、彼には方言が多すぎてよく意味が掴めなかった。彼は餅を口に入れ、ぬるいお茶を飲んだ。一郎は汚れたジャンパーを着て、腕まくりをしていた。しかし部屋の中は寒かった。(福永武彦「夜の寂しい顔」から)
短編小説の中のごく些細な描写ですが、これを「読む」人には、ここでの情景がかなりありありと思い浮かべられるでしょう。ここには視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚にかかわる情報が記述されています。これらの感覚は、もちろん実際に感じられているわけではないのですが、この小説をはじめからずっと読んできている人にとって、その小説の中の世界としてあたかもそこで描写されていることを実際に見たり、聞いたり、味わったり、臭ったり、触りごこちや温度を感じたりしているかのように感じることでしょう。そういった身体的感覚に対して刺激を与えているのは、紙の上のインクの模様による視覚的情報(あるいは視覚障害者の場合は、紙の上の凹凸という触覚的情報)そのものではなく、その人があらかじめ習得している「文字」のコードと、実際の世界の経験を通じての「想像・イマジネーション」に他なりません。本を読むためには、人間の身体と外部の世界とを接続する第一次的なインターフェース(視覚・聴覚あるいは触覚)をまず必要としますが、文字を「読む」「書く」という行為そのものがもっとも本質的なインターフェースとなっているといえるでしょう。
上の小説の引用にあげたような「文字言語」を「読む」ことによって与えられる身体的な感覚性が、実際にそれらのものを体験するときの身体的感覚性と異なる点は、それが実際のものか、仮想的なものかということだけにあるのではなく、たとえば視覚的刺激がそのまま対象の知覚・認識となっているかどうかということにあります。文字言語の場合、インクの模様としての文字という視覚的情報そのものが(その文字によって指し示されている)対象の知覚・認識につながるのではなく、視覚によって捉えられた「文字」というメディアを介して、ようやく対象に至ることになります。つまり、媒体となるものがもう一段余分に存在することになるわけですが、しかもこの文字を「読む」「書く」というインターフェースは、たとえば実際に何かを「見る」ことと比べて、外部世界と接続するにはきわめて間接度の高い、決して能率がよいとはいえない代物です。にもかかわらず、この使い勝手の悪いインターフェースが文化の中心に位置することになったのは、その媒体(文字)の保存可能性、それにともなう時間的・空間的な伝達可能性、そして複製可能性、そしてその線状的な特質に伴われる論理性などの機能的な長所のためです。ちょっと先取りすることになりますが、コンピュータの進歩においては、それを使う人間の身体性に対してできるだけ間接性の度合いが少なくなるような仕方でインターフェースが進化していくことがもっとも重要な要件となっているように思われます。それによってコンピュータというメディアをより自然に用いることに近づきつつあるといえるでしょうが、そういった長い目で見るのではなく、ある特定の段階だけを見る場合には、ユーザーがより「自然」に用いることができるようになるためには、結局その現状のインターフェースにユーザーが慣れるより他ありません。文字を「読む」「書く」という、本来きわめて使い勝手の悪いインターフェースについても同じことがいえます。小さな子供のうちから文字メディアを介しての入力と出力(つまり「書く」ことと「読む」こと)の仕方を練習し、その入出力に際してできるだけノイズや誤変換がないように、つまり「文字」メディアと像とのあいだに正しく効率のよい変換ができるように訓練しています。上に引用された小説の文字メディアを「読む」ことによって再現される像には、もちろん人によってかなりの差が生じますが、それはその人のもっている経験的なデータの蓄積の差によるところが大きいとともに、読み書きを行う場としての文字というインターフェース(媒体であるとともに、インターフェースでもある)に、どれだけ習熟し、どれだけ効率よく正確度の高い変換を行うことができるか、ということにかかっています。「本を読みなさい」という親や教師の言葉は、ひとつには、文化の中心を占めている文字というインターフェースを介しての像変換の効率性・正確性を上げさせること、つまりこのインターフェースに習熟させることを結果としてもたらします。そして、文字が文化の中で中心的なはたらきをしている以上、このインターフェースに習熟しているかどうかということは、社会の中で力を手にするために決定的な意味を持つことになります。
このインターフェースにまったく習熟していない場合、たとえば、知らない文字言語を読もうとする場合、像はまったく再現されません。あるいは、まだ慣れていない外国語の場合、再現される像はかなり多くのノイズを含むものとなり、また変換の効率もきわめて悪いものでしょう。反対に、非常にたくさん本を読む人(つまり文字というインターフェースに非常に習熟している人)が自分の母国語で読む場合には、そこでの像はかなり再現性の高いものとなり(つまりノイズが少ない)、しかも変換のスピードも一般的に言ってかなり速いものとなるでしょう。本の世界の中に没入し、夢中になって読むという経験を、たぶん多くの人がもったことがあると思います。そこで再現されるものとは、自分の外部にある世界の経験に関わるものですが、そこでは感覚器官という外界とのあいだのインターフェースによって再現される像(われわれが「現実」に経験していると考えている像)が、文字というインターフェースを介して仮想的に再現されているのです。その仮想的な再現に必要なのは、それまでの経験とともに、なによりも「想像力」です。逆に言えば、実際にわれわれが何かを見たり、聞いたりする場合には、想像力を必要としません。その感覚をそのまま受けとめているだけです。文字とはつまり、「想像力」という、一方ではきわめて効率性・正確性の劣悪な、しかし他方ではきわめて多産で創造性豊かな可能性も持つ中間段階をへることを余儀なくされている、きわめて間接度の高いメディアです。その効率性・正確さの低い、そして間接性の高いインターフェースに習熟している人のみが、文字を「読む」というインターフェースを介して本の中の世界に没入する、つまり仮想的な感覚性をありありと再現させることができるのです。
そのインターフェースから仮想的な感覚を導き出している「想像力・イマジネーション」とは、たとえば芸術的な生産にかかわるものとか、あるいはもっと日常的に、空想的なものといった意味でいわれているのではなく、ここではもっと即物的な機能を指しています。「イマジネーション」を説明するために、ドイツのメディア論の文脈で大きな影響力を持っているヴィレム・フルッサーの言葉を引き合いに出してみたいと思います。
「イマジネーションとは、ここでは、四次元的な時空関係を二次元的な関係へと縮減する(画像を作る)ばかりでなく、その二次元的縮減から、念頭におかれた四次元性を逆推論する(画像を解釈する)能力をも意味する。二つの能力は、むろん表裏一体をなす。イマジネーションとは、画像によってコード化するとともに解読(デコード)する能力である。」(フルッサー『テクノコードの誕生』p.140)
フルッサーの論議には後でまた触れることになりますが、ここでいわれている「画像」とは、私のこれまでの説明でいえば、「音声言語」の段階の身体的な感覚性に基づいた<世界>の表現だととりあえず理解してください。「画像」という言葉自体はもちろん、視覚的に表現されたもののみにかかわっているのですが、ここでは少しそれを拡張して捉えて音声などの感覚性なども含むものと考えたいと思います。それに対して、「四次元的な時空関係」といわれているものは、<世界>そのもの、現実そのものを指します。<世界>を二次元的に表現したものとしての「画像」がきわめてリアルである(「現実」そのものではないにせよ、「現実」にきわめて近い感覚性を喚起する)場合、先にも述べたように「イマジネーション」はほとんど必要ないでしょうが、それがもう少し抽象度の高いシンボリックな表現となった場合、その二次元的画像を四次元的な時空関係をとらえる身体的感覚性へと「解読(デコード)」することが必要となります。その「解読(デコード)」の能力が「イマジネーション」とここでいっているものです。と同時に、イマジネーションはその反対に、四次元的<世界>を捉える身体的感覚性を、二次元的な「画像」へと「コード化」する能力でもあります。
イマジネーション
| <世界> | <画像> | |
|---|---|---|
|
|

|

|
ここでいわれているのは四次元的な時空関係と二次元的な「画像」とのあいだの「コード化」と「解読(デコード)」ですが、これを四次元的な時空関係と一次元的・線状的な「テクスト」とのあいだの「コード化」と「解読(デコード)」に置き換えても同じことがいえるでしょう。その場合、四次元的な時空関係(<世界>)を感覚器官のみを介して捉える身体的な感覚性の、一次元的な「テクスト」への「コード化」とは、つまり「書く」ことであり、反対に、「テクスト」を四次元的時空関係へと「解読(デコード)」することが「読む」ことを意味するというのは、いうまでもないでしょう。つまり、「イマジネーション」とは、「読む」「書く」という行為の際の、「解読(デコード)」と「コード化」の能力そのものです。フルッサーは先の引用に、次のように続けています。
「この[イマジネーションの] 定義は、ふつうの定義と共通するところがほとんどないように思えるかも知れないが、実は、普通の定義を確認するものだ。なぜなら、これは、イマジネーションとは意味にかかわる(つまり記号とコードにかかわる)能力だとするものだから。」
イマジネーション
| <世界> | <テクスト> | |
|---|---|---|
|
|
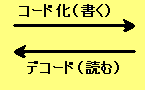
|
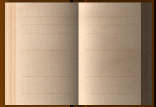
|
文字というインターフェースに習熟する問題に話を戻しましょう。<世界>を単に感覚器官を通じた「見る」「聞く」という行為と比べると、文字というインターフェースを通じて<世界>を感じ取る感覚性を再現させる(=「読む」)ことには、一次元的「テクスト」を四次元的時空関係へと「デコード」するための圧倒的なイマジネーションの能力が必要となります。あるいは逆に、四次元的時空関係に際しての感覚性を一次元的テクストに「コード化」する(=「書く」)ためには、おそらく「デコード」以上のイマジネーションの能力を必要とするでしょう。
<世界>を感覚器官によって「見る」「聞く」こと、またその感覚性を「画像」(イメージ・表象、あるいは「作品」など物理的な対象物)へと定着させることとは、目・耳・舌・鼻・肌などのインターフェースを通じて、四次元的時空関係と「画像」(イメージ・表象)とのあいだを「コード化」「デコード」することですが、その能力をわれわれは生まれるとすぐに少しずつ身につけてゆき、このインターフェースを介しての「コード化」「デコード」には、ほとんど「イマジネーション」が働いていることさえ意識されません。
それに対して、文字というインターフェースを用いるためには、はるかに多くの、「コード化」「デコード」の能力としての「イマジネーション」を必要とします。たとえば、そのインターフェースを習得しはじめるのがより遅い時期である(とりわけ外国語の場合)という比較的小さな理由もありますが、なによりも身体的な感覚性とのあいだの距離がきわめて大きい(間接度が高い)ということ、そして、一次元的・線状的コードとしての「テクスト」は、二次元的「画像」と比べても情報量が必然的に縮減しているために、その「テクスト」を四次元的時空関係へと「デコード」するには、情報を補ってやる必要がある、ということが「イマジネーション」を圧倒的に必要とする重要な理由といえるでしょう。このデコードする際に情報を補う能力が、一般的にいわれている意味でのイマジネーションといってよいかも知れません。また、情報を補う際に、あやまった(あるいは不必要な)情報(ノイズ)が加わって、再現された四次元的時空関係における感覚性が曖昧なものとなることも、きわめてしばしば起こります。
文字というインターフェースに習熟する――すなわち、文字というメディアによって構成される「テクスト」をすらすらと読み、身体的感覚性をより正確に・効率よく再現させること、また反対に、身体的感覚性を「テクスト」という一次元的・線状的コードへと縮減していくこと――とは、つまり「文字」というきわめて間接的(つまり身体性から遠く離れた)で、能率・正確度の低い媒体・手段によって身体性を再現させる能力、またその逆の機能を持つ能力(「イマジネーション」)を高めていくということを意味しています。それは、確かに身体的感覚性を再現させるひとつの手段ではありますが、「見る」「聞く」という手段と比べれば、それが<世界>の経験にとって本来どれほど間接的なものであるかということは、否定できません。
イマジネーションをコード化とデコードという機能から捉えるならば、「画像」と「テクスト」の違いは、上に述べたように、必要とされるイマジネーションの程度が圧倒的に異なるとはいえ、単に変換する/されるコードの違いにすぎないようにも見えます。しかし、たとえば機械が、プログラムさえされていれば異なった種類のコード化/デコードを行い、その機械自体に何ら変化がないのとは異なり、人間の場合、これまで繰り返し強調してきたように、「テクスト」と<世界>の身体的経験とのあいだのコード化/デコードの能率・正確性を高めていくように文字というインターフェースに習熟していくのであって、そのことはつまり、コード化/デコードを行う主体自体が変化していくということを意味します。そして、その変化は、単に「テクスト」のコード化/デコードの能率・正確性だけにかかわるのではなく、その同じ主体が行う「画像」におけるコード化/デコードにもかかわります。つまり、ひとたび「テクスト」を「読む」「書く」ということを覚えれば、それまで行ってきた「画像」のレベルでの<世界>の把握も変わってくるということです。こういった事態は、フルッサーの視点から部分的にひろっていくと、次のように言い表されることになるでしょう。
「状況を特徴づけるのは、アルファベット(エリート層のコード)と画像のコード(<民衆>のコード)との戦い、つまり計算する(<歴史的な> [「歴史」・「物語」の線形性にかかわる特性])意識とイメージ化する(<呪術的な>)意識との戦いである。計算対祭儀、概念対表象、字母対画像、これがソクラテス前の哲学からスコラ学を経て人文主義に至るこの時代の主題であった。それは、<歴史の核心>であった。/この時期の最初のうちは、アルファベット化されたエリートたちも、アルファベットに潜む可能性を完全に意識していたわけではない。彼らは、まだ<書ける>ようになっていなかった。時間をかけてようやく、書記や物書き、<作家や学者>が登場し、商品目録だけでなく出来事や思想や願望を書き留めること、アルファベットで情景を記述するばかりでなく歴史を物語ることができるようになったのである。行に並べられた字母が<明晰判明>であること、すなわち、行そのものの逐次的progressiveな線形性も、時間をかけてようやく意識されるようになり、意識をプログラミングするようになった。」(フルッサー『テクノコードの誕生』p.111)
「まず市民、それから労働者をアルファベットの意識レベルに取り込むことによってはじめて、アルファベットに潜んでいた可能性が実際に展開されることになる。アルファベットの構造によってプログラミングされている社会は、今はじめて、アルファベットのコードの最終的帰結、つまり厳密な化学とそれに基づく技術を展開できるようになった。」(同書、p.113)
フルッサーはことさらにマクルーハンに言及するということはしていませんが、上に述べられていることは、とりわけ西欧文化がアルファベットという表音文字を用いることによって、文字以前の文化の統合的な感覚性が、文字のもつ線状的論理性へと移し変えられ、知覚・認識・思考様式のあり方、またそれにともなってさまざまな社会装置がまったく変わってしまったというマクルーハンの指摘(第2回講義 資料2 資料3 参照)と基本的に対応しています。(ただし、「画像」というコードについて、これまで私が述べてきたことは、フルッサーの文脈を意図的にマクルーハンよりに多少読み替えたものなのですが。)しかし、マクルーハンの場合顕著に見られる、文字以前の文化における統合的な感覚性のきわめてオプティミスティックな称揚、その意味での一方的な文字文化批判、また文字文化を「視覚」中心主義に単純に還元している点などに対して、批判的な距離をたもつことにしましょう。とすれば、ここでマクルーハンをわざわざ持ち出すまでもないかも知れません。彼自身『グーテンベルクの銀河系』の冒頭で述べているように、口述文化から文字文化(とりわけ印刷文化)への転換によって、人間の知覚・認識様式およびそれにともなう社会組織が根本的に転換したという彼の基本的テーゼは、ミルマン・パリーやアルバート・B・ロードの口承文学研究における主題を引き継いだものであり、またすでに取り上げたように、たとえばW.J.オング(第4回講義参照)においても、口述文化・筆記文化・活字文化といった展開とそれにともなう知覚・認識様式の転換は指摘されているからです。[註2]
それはともかくとして、『グーテンベルクの銀河系』であげられている、次のようないくつかの見出しは、文字文化における知覚・認識・思考様式の転換をきわめて明確に示すものとしてもう一度言及しておいてもよいでしょう。「表音文字技術が精神構造として内化されたとき、人間は聴覚中心の呪術的世界から、中立的な視覚世界へと移った」
「<文字>のようなメディアの精神内部への内化は、われわれの五感の比率を変化させ、心理作用を変えるであろうか」
等々。
テクストを読み、その中の仮想的な世界の中に没入するとき、ちょうどコンピュータゲームで仮想的な世界の役になりきるような感覚を得るように、読者がそのとき実際に得ている身体的経験とは異なる身体感覚をもっています。たとえば、本を読んでいるときの実際の身体的知覚は、とりあえずはインクの模様によって得た視覚的刺激によるものですが、テクストを「読む」ときには普通はその文字自体を「見る」ということを意識しておらず、まったく別の仮想的な感覚を得ています。そこでは外界との接続の界面、インターフェースとしての「目」とつながる「光」という媒体は、「テクスト」という媒体の中にいわば吸収されています。(つまり、前に言及したように、「どんなメディアでもその「内容」はつねに別のメディアである」)本を読むときの仮想的な感覚も、ある意味では一時的な感覚変容によるものといえるでしょうが、問題となるのはやはり、その前に述べてきたようなより根本的で持続的な知覚・認識・思考様式の転換です。では、こういった根本的な感覚変容が、文字言語というメディアから、現代のわれわれの生活においてますます大きなウェイトを占めつつある電気的・電子的(デジタル的)技術メディアへと転換する際に、どのようにわれわれのうちに起こっているか、そしてその際、われわれのこれまでの文化の中心を占めていた(そして技術メディアの加速度的な浸透にもかかわらず、やはり中心を占めているといえる)文字言語・テクストに対するわれわれの関係はどうなるのか(これについては、特に最後の三回の講義でとりあげます)――このことが、私が「メディア論」としてもっともテーマとしたかったことです。