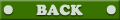1998年度 インターネット講座
メディア・情報・身体 ―― メディア論の射程
第2回・第3回講義
マクルーハンのテーゼの論点
資料03
文字文化の新たな段階としての「印刷術」
- 『グーテンベルクの銀河系』p.116<活版印刷文化は文字使用の歴史のごくごく一部を占めるにすぎない>
- 「寸分違わぬ複写反復の技術は、ギリシャ人たちがすでにはじめていた現実の視覚による分析をローマ人たちがさらに強化することで手に入れたものであった。それは連続的で画一的な線の上に事象が存在するという線形思考の強調であり、話し言葉社会の特色であった多元的な要素の組織化が持つ価値を無視することでもあった。」『グーテンベルクの銀河系』p.124
- 「印刷文化の人間と写本文化の人間の違いは、非文字が他文化の人間と文字型文化の人間との違いに優るとも劣らぬほどである。」『グーテンベルクの銀河系』p.142
- 「古代のものであろうと、中世のものであろうと、われわれは写本文化のもつ口語的性格のいろいろな面について、やや長々と検討を加えつつあるわけだが、(…)それは広大の印刷文化の所産である文字型文化に属するような諸性質を、写本文化の中に求めなくなる、という利点である。/それのみか口語文化の特色を減水させていった印刷技術からなにが期待できるかということもわかりはじめる。さらには、巡りめぐって電子時代に突入した今日、逆に印刷文化のもつ諸特徴がどんどん薄れつつあり、言葉を用いて経験を組織化する場合にも、文字よりも口語的、聴覚的な価値が復活しつつある理由も納得できるのである。」『グーテンベルクの銀河系』p.167-168
- 「字義もしくは解釈されるべき「文字」はのちにテキストを<通して>くる光というよりも、テキストの<上を>テラス光として考えられるようになった。それにつれて「視点」つまり、読者が「自分が座っている場所」という<固定された>位置からの展望が強調されるようになった。こうした視覚の強調は、印刷術が完全な同一性と反復可能性を達成することで書かれた頁の視覚生をますます高めていったときにはじめて可能となったものであった。この印刷の本質である同一性と反復可能性は写本文化とは全く縁のないものであり、[視覚的に]統一された空間、もしくは絵画的空間、さらには「透視画法的視点」が生まれる前提条件であった。」『グーテンベルクの銀河系』p.173
- 「その後到来したグーテンベルクの技術とともに発生する視覚の離陸を理解するために知るべきことがある。それはこのような離陸は写本時代には不可能であったろうという点だ。というのは、写本文化は、全ての感覚経験を、均質的で連続的な絵画空間の中へ翻訳し移し変えてゆく印刷文化の抽象的視覚性とは両立不可能なほど、人間の感覚の中にある聴覚・触覚的様式を留めているからだ。」『グーテンベルクの銀河系』p.174
- 「ダンテのような経験に彫刻的な輪郭を与える普遍主義は、その先に控えていたグーテンベルクの星座を宿す、均質的な絵画的空間とは全く相容れないものであった。なぜならば「機械的筆記mechanical
writingという様式、つまり活字の技術は、共感覚もしくは「韻文の彫塑」には不適当であったからである。
- 「要するに印刷が発明されたのちも、その後数世紀にわたって散文も視覚的と言うよりは聴覚的であり続けたのだ。印刷面と黙読がもたらす均質性の変わりに、変化に富んだ語調と姿勢の混在があり、作者はいつでも詩のように文の途中からでも調子を変えることができた。(…)印刷が広まってしばらくときが経過して初めて、作者や読者は「視点」を発見したのだった。(…)視覚的に構成された世界は、統一され、均質化された空間の世界である。そしてこのような世界は話し言葉がもつ複数の要素が共鳴しあう世界とは無縁のものなのだ。というわけで言語芸術はグーテンベルクの技術の視覚性の論理を一番最後に受け入れた芸術であり、また電気時代を迎えて真っ先に元に戻った芸術でもあった。」『グーテンベルクの銀河系』p.208,209
- 「印刷は、まず第一に人間を非部族化し、非集団化するアルファベット文化の最終段階である。印刷はアルファベットのもつ視覚的特性をその最高の鮮明度にまで上げる。そのために印刷面は表音文字がもつ個別化の力を、写本よりもはるかに強烈に持つことになる。印刷とは個人主義の技術なのだ。」『グーテンベルクの銀河系』p.242
- 「すでに幾度となく述べたように、印刷はあらゆる言語表現期式、および社会形態に対して画一化の機能を果たした。たとえば<who-whom>のように印刷体ではいまだに語形変化がそのまま残っている部分では、いわゆる「正しい文法」という「間抜け落とし」が顔をのぞかせているのである。つまり、視覚的様式と口語的様式とのあいだに深淵が口をあけているのだ。」『グーテンベルクの銀河系』p.363
- 「性格かつ反復可能な形式で絵画的な陳述を行う技術は、西欧では長いこと当然の技術と考えられてきた。けれども、印刷や青写真がなかったら、また地図や幾何学がなかったら、現代の科学と技術の世界もほとんど存在しなかったであろう。このことが通例忘れられている。(...)
世界中のすべての語をもってしても、バケツといったような対象を描写することができない。もっとも、どうすればバケツを作ることができるかということなら、数語あればできる。ことばは対象について視覚情報を伝えるのに不適切である。(...)
ここで、われわれはメディアの基本的な機能、すなわち情報を蓄え、それを伝えるという機能に直面することになる。簡単に言えば、蓄えることは伝えることである。蓄えられているものは、これから集められなければならないものより容易に近づきうるものでもあるからだ。草木や花々にかんする視覚的情報がことばで蓄えることができないという事実は、また、長い間西欧世界の科学が視覚的要因に依存してきたということを指し示してもいる。このことも、また、アルファベット技術が話し言葉さえも視覚的な方にしてしまうものである以上、その上に成り立っている文字文化においては、驚くにあたらないことである。」(『メディア論』「印刷」p.161)
- 「たぶん、印刷のもつ最高の性格は気づかれていないであろう。あまりにもありふれて、明々白々の存在となっているからだ。ただ、その性格が、性格かつ無限に反復可能な視覚的な陳述である、ということである。(...)
反復可能性というのは、とりわけグーテンベルクの技術以来、われわれの世界を支配してきた機械の原理の核心である。印刷および活字の伝えるメッセージは、第一に、その反復可能性というメッセージである。活字印刷とともに、その原理が一つの統合的行動を分節し細分するという過程によってどんな手仕事も機械化していく手段をもたらした。アルファベットは話されることばに含まれる多様な身振り、視覚、聴覚などを分離するものとして出発したけれども、それが新しい段階に到達したのであった。まず木版印刷として、ついで活版印刷として、アルファベットはことばの中で視覚要素を最高のものとして残し、それ以外の話されることばの持つ感覚事実を視覚形態に還元してしまった。このことは、なぜ木版が、さらには写真すらもが、文字文化の世界でかくも熱烈に歓迎されたかを説明するのに役立つ。木版とか写真とかの形態は、書かれたことばで不可避的に省かれてしまう包括的な身振りとか劇的な姿勢とかの世界を提供してくれるものなのである。」(『メディア論』「印刷」p.162)
- 「心理的に見れば、印刷本は視覚機能の拡張したものであるから、遠近法と固定した視点を強化することになった。視点と消失点とを強調すると、そこに遠近法の幻覚ができあがる。これに結びついて、空間が視覚的、画一的、連続的なものであるという、もう一つの幻覚が生ずる。活字が線状をなして正確に画一的に配列された姿は、ルネッサンス期に経験された偉大な文化の形態および革新と切り離せないものである。印刷の最初の一世紀に、視覚と個人の視点とが初めて強調されたのは、活字印刷という形をとった人間の拡張によって自己表現の手段が可能となったからであった。」(『メディア論』「印刷されたことば」p.175)
- 「たぶん、活字印刷が人間に与えた贈り物である能力の中でもっとも意義のあるものが、非密着性(detachment)
と非関与生(noninvolvement)
――すなわち、反応することなしに行動する力――であろう。ルネッサンス期以来、科学はこの能力を高めてきたが、電気の時代となると、これが困惑の種となってしまった。この時代には、すべての人がいつも他のすべての人と関与しあっているからである。」(『メディア論』「印刷されたことば」p.176)
- 「印刷のもつ画一性と反復性が、時間と空間が連続的で測定可能な量であるとする考え方を携えて、ルネッサンス期に浸透した。この考え方に直接の影響を受けて、自然の世界と権力の世界の両方が非神聖化されることとなった。物理的な過程を分節したり細分したりすることによって統御する新しい技法のせいで、人間と自然、あるいは人間と人間が分離されただけでなく、神と自然もまた分離されることになった。」(『メディア論』「印刷されたことば」p.179)
- 「いったん新しい技術が社会的環境に入ってくると、あらゆる制度がそれで飽和するまで、その環境に浸透することを止めない。活字印刷も、過去五〇〇年のあいだ、芸術と科学のあらゆる局面に浸透してきた。連続性、画一性、反復性の原理が工業生産、娯楽、科学ばかりか、計算やマーケッティングの基礎にもなっている。その過程を実証することは容易であろう。印刷本の上に、画一の定価を付けられた商品という奇妙に新鮮な正確を付与したのが反復性であり、その結果、価格システムへの道を開いた。このことを指摘するだけで十分であろう。加えて、印刷された書物には、形態の便利さ、入手のしやすさという正確があった。それは、手書きの写本にはないものであった。」(『メディア論』「印刷されたことば」p.181)
- 「写真は外界を鏡のように自動的に映すものであって、正確な反復が可能な視覚的映像を生み出す。この画一性と反復可能性というきわめて重要な特質こそ、中世とルネッサンスのあいだにグーテンベルクのくさびを打ちこんだものであった。写真は、機械産業一辺倒の時代と電子工学的人間の画像的時代とのあいだに裂け目を生じさせたわけだが、その際に写真が果たした役割は、かつてのグーテンベルクの場合に決して劣るものではない。写真の発明によって、「活版印刷的人間」の時代から「画像的人間」の時代へ向かって、一歩が踏み出されることになった。」(『メディア論』「写真」p.195)
- 「非言語的経験形態としての映画は、統語法をもたない陳述形態である写真と似たところがある。ところが実際は、映画は印刷や写真と同じように、その利用者に高度の式辞能力があることを前提としているため、緋文字分化的な人間を当惑させてしまう。われわれも自分か的な人間は、カメラの目が人物を追ったり、それを視野から消したりする動きを難なく受け入れるが、それは映画を観ているアフリカ人には受け入れがたいことである。もし、だれかが画面の端から姿を消せば、アフリカ人はその人物のみに何が起こったかを知りたがる。しかし、文字文化型の観客なら、線状性の論理を疑うことなく、印刷された象を一行一行追っていくことに慣れているので、フィルムの連続性を何の抵抗もなく受け入れるであろう。」(『メディア論』「映画」p.294-295)
- 「このように、われわれ西欧人が映画という形態を受け入れるにあたって、映画のリールの世界と、印刷されたことばの詩的な幻想体験との密接な関係は不可欠のものであった。映画業界そのものも、彼らの最大の傑作は小説を原作とするものであると認めているが、これ張りの当然といえる。映画は、フィルムの形であれ、シナリオやスクリプトの形であれ、完全に本の文化と結びついている。」(『メディア論』「映画」p.295)
- 「この新しい活字印刷によって問題を精細に画一的に分節化していけば、いかなることでも達成できるように思われた。実は、この方法によって、後に映画が作られることになるのである。形態としての映画は、活字印刷による断片化がもつ偉大な潜在力の最終的な成就であった。」(『メディア論』「映画」p.304)