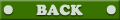1998年度 インターネット講座
メディア・情報・身体 ―― メディア論の射程
第2回・第3回講義
マクルーハンのテーゼの論点
資料02
聴覚型文化から視覚型文化へ:
「文字文化」による感覚・認識の分断化――「視覚的」文化の認識様式
- 「視覚型文化を表音アルファベットによって視覚型文化へと移し変える作業を完成させたのはローマ人たちであった。ギリシャ人は古代、ビザンチン時代とを問わず、実際行動に価値を認めず、知識の現実世界への適用を拒むことで、彼らがまだ古い聴覚型の文化にかなり就寝していることを示していた。(…)
扇形的にアルファベット文字で書くことによって、ギリシャ人の手になる突然の発明、つまり思考と科学の「文法」の発明が可能になったのであった。そして、こうした文法、または個人的社会的手続きを明文化する作業は、視覚以外の感覚機能や関係の視覚化を意味していた。」(『グーテンベルクの銀河系』p.39)
- 「「ギリシャ世界は、アリストテレスとともに口述教授から読書の習慣へと移ったといっても言い過ぎではあるまい」(…) 「しかし、その後、幾世紀にもわたり「読み」とは音読を意味したのである。事実、速読み訓練所の手によって読みの行為において目と発話speechとを切り離すよう、<離婚仮決定decree
nisi>が下されたのは今日になってのことである。それに対して「遅読slow reading」があるわけだが、左から右へと読んでいくことで、われわれはのどの筋肉が前兆的な語形生を行うという発見が遅読の主因とされてきた。」『グーテンベルクの銀河系』p.130
- 「純粋な遊牧民族では文字をもったものはなかった。それはちょうど彼らが建築物、つまり「囲われた空間」を発明しなかったのに似ている。なぜならば書字行為は非視覚的空間および感覚の視覚的囲い込みだからである。したがって、それは自然に行われている感覚の相互作用から視覚だけを切り離し、抽象する行為となる。そして発語speechが全感覚の外化(音声化)であるのに対し、書字行為は発語を抽象化する行為である。」『グーテンベルクの銀河系』p.70
- 「アルファベットの発明は、車輪の発明と同様、複数の空間が行う複雑で有機的な相互作用を単一な空間に翻訳、もしくは還元する営みであった。表音文字は話し言葉の実体である五感の同時的使用をただ視覚のみでとらえられるコードへと還元したのだった。今日このような翻訳は、われわれが「伝達媒体」と呼ぶ各種の空間形式相互のあいだで激しく行われている。」『グーテンベルクの銀河系』p.72
- 「均質性、画一性、そして反復性――これら三つが聴覚・触覚的複合母体のなかから出現した新しい視覚的世界を形成する基本的なベース音であった。」『グーテンベルクの銀河系』p.92
- 「つまり、もしわれわれが住む世界の全ての面を単一の感覚の言葉に翻訳し続けて止まない装置が作り出されたとする。するとそこに現れるのは、首尾一貫し内的統一をもつがために科学的と呼ばれるのにふさわしい歪曲である。ブレイクが「単一のヴィジョンとニュートンの眠り」からの解放を求めたのは十八世紀ではあったが、そのときすでにこの単一言語による翻訳が発生しているとブレイクは考えていたのだった。一つの感覚だけに支配を許すのが催眠術のABCである。文化についても同じことがいえるのであって、単一の感覚のなかに閉じこめられれてねむりに陥ることがある。眠れる文化は他の感覚によって挑戦を受けるとき初めて目覚めるのだ。」『グーテンベルクの銀河系』p.116
- 「口語文化が他の人間にとって字義とはあらゆる可能な意味のレヴェルを包括するものであった。例えばアクイナスは文字の中にそれらを読みとった。だが十六世紀の視覚的人間はレヴェルとレヴェルを、機能と機能とを剥離させることで専門分化の道を歩むよう強要されたのだった。聴覚的場auditory
fieldはさまざまな要素が動じ存在的に落ち合い、発生する場であり、それに対し視覚的様式は線形的、連続的である。」『グーテンベルクの銀河系』p.172
- 「表音アルファベットとその派生文字は知覚の際、一時点には一つという分析的な意識を強調する。この強烈な分析性は、知覚領域におけるあらゆる他のものを意識化に押し込むことによって達成されたものである。
私たちは二千五百年余にわたり、ジェームズ・ジョイスのいう”ABCイズム”で生きてきた。知覚領域を断片化し、動きを静止的な点に分割した結果、私たちは人類史上類のない応用性の知識、テクノロジーの力を獲得した。これに払った代価として西欧人は個人的にも社会的にもほとんど全面的に潜在的な認識状態に生きている。」(マクルーハン「メディアの文法」、『マクルーハン理論』p.24)
- 「表音アルファベットは独特の技術である。象形文字や音節文字など、色々の種類の文字があったけれども、意味論的に無意味な文字が意味論的に無意味な音声に対応するように用いられる表音アルファベットはただ一つしかない。視覚の世界と聴覚の世界の、この厳しい分割と並行は、文化の問題としていえば、粗雑で容赦がなかった。表音文字で書かれた言葉は、象形文字や中国の表意文字のような形式では確保されていた意味と知覚の世界を犠牲にする。(...)
二〇〇〇年前の古代ローマの属領ガリアでそうであったように、今日アフリカでアルファベット文字を身につけて一世代もすれば、少なくとも、まず部族の網から個人を解き放つに十分である。この事実は、アルファベットで綴られた言葉の「内容」には関係がない。それは人の聴覚経験と視覚経験が突然に裂けた結果である。表音アルファベットのみがこのような経験の明確な分割を行い、その使用者に耳の代わりに目を与え、その使用者をこだまする言葉の魔術の陶酔と親族の網目から解き放つのである。」(『メディア論』「書かれた言葉」p.85)
- 「文字文化の大変な価値については、明らかに西欧世界の達成した事柄が証言している。けれども、われわれは専門分化的な技術と価値の構造を買うのに高い代価を払いすぎたのではないか。そういう反対意見を出したくなる人もたくさんいる。確かに、表音文字文化によって合理的な生活を線状に構造化することで、われわれは相互に噛み合う論理的一貫性に捉えられてしまった。(...)
例えば、意識は理性的存在のしるしであると見なされるけれども、意識の瞬間に存在する認識の全分野になんら線状的あるいは連続的なものなどない。意識は言語的なプロセスではない。これも一つだ。けれども、幾世紀にもわたる表音文字文化の時代を通じて、われわれは論理と理性のしるしとして推論の連鎖を好んできた。中国の文字はこれと対照的で、表意文字一つ一つに存在と理性についての直観全体が賦与され、視覚的な連鎖に心的な努力と組織のしるしとしての役割をあまり与えない。西欧の文字文化をもった社会では、何が何から「続いて生ずる」というのが、あたかも、そのような連続を作り出す原因のようなものが作用しているかのように感じられ、いまなお、いかにももっともなこととして受け入れられるのである。」(『メディア論』「書かれた言葉」p.86-87)
- 「結びつけられた線状の連続は、真理ならびに社会の組織に普遍的な形式となっているが、これまでにそれをマスターしたのはアルファベット文化だけであった。あらゆる種類の経験を画一の単位に分断し、より早く動き変われる形態を生み出すこと(応用知識)、これが人間と自然を支配する西欧の力の秘密であった。そういうわけで、われわれの西欧の工業計画は不本意ながらきわめて軍事的であり、逆に、われわれの軍事計画は工業的であった。どちらも、すべての状況を画一で連続したものにすることによって変形し統率するという技法を用いる。それはアルファベットによって形成されるものだ。この技法はギリシア・ローマの段階ですでに表面に出ていたが、グーテンベルクの活版印刷技術の発展が画一と反復をもたらすとともに、ますます強烈になった。」(『メディア論』「書かれた言葉」p.87)
- 「文明が文字文化の上に築かれるのは、文字文化というものが視覚(アルファベットによって時間と空間の中に拡張された視覚)によって文化に画一的な加工をするものだからだ。部族の文化において、視覚価値は押さえられ、優位な聴覚生活によって経験は配列される。聴覚は冷たい中性的な目と違って、過度に審美的で繊細で全体包括的である。口誦の文化では、行為と反応が同時である。表音文字の文化は、人がある好意に出る場合、その間情や情緒を抑圧する手段を与える。反応せず、関与せず、行動する――これが西欧の文字文化人に特異な利点である。」(『メディア論』「書かれた言葉」p.87-88)
- 「西欧のような社会では、個人が集団から分離する。空間において分離すれば「私生活の自由」、思想において分離すれば「視点」、労働において分離すれば「専門主義」となる。このような現象は、文字文化、ならびに、それに伴う細分化された工業的及び政治的な諸制度によって、文化的、技術的に支えられてきた。けれども、印刷されたことばが均質化した社会的人間を生み出す力は現代にいたるまで着実に増大し続け、「マス・マインド」とか市民軍の「マス・ミリタリズム」とかのような逆説を有無にいたっている。機械化の極限まで押し進めると、文字はしばしば文明と正反対の効果を生み出すように見えることがあった。」『メディア論』「数」p.108)