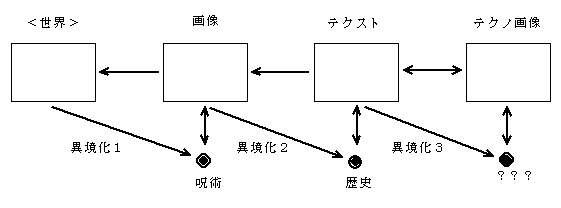
[図a]
1998年度 インターネット講座
(99/02/17 更新)
われわれが今生きている文化において、「文字言語」が依然として中心的役割を果たしており、また、これまでの文字文化の遺産を圧倒的に受け継いでいる状況にあるということは、明白な事実です。しかしまた同時に、われわれが技術メディアのいわば洪水のただ中にあるということもはっきりしています。こういった状況にあって、文字言語と技術メディアはどのような関係にあるのか、「読む」「書く」という行為、つまり書かれた言葉によって世界を捉えるという行為は、技術メディアによってどのように位置づけられるものとなるのか、という問題を、今回は、これまでも何度か引き合いに出してきたドイツのメディア論者フルッサーの提起するモデルから考えていきたいと思います。
フルッサーは、技術メディアによってもたらされるものを「テクノ画像」と呼び、文字言語以前の「画像」から、文字言語による「テクスト」を経た延長上にそれを捉えています。こういった展開の捉え方は、これまで述べてきたような「音声言語」→「文字言語」→「技術メディア」という基本的な図式に、確かに沿っているように見えるのですが、非常に重要な相違点もそこに見いだすことができます。実は、これまでフルッサーについて言及したときには(第8回講義参照)、あえてフルッサーの見解を多少読み替えて、「音声言語」→「文字言語」→「技術メディア」という基本的なメディア論の図式に適合させてきたのですが、ここでは、ひとまずフルッサーの論議をていねいに追っていきたいと思います。(以下、ヴィレム・フルッサー『テクノコードの誕生』東京大学出版会、129頁以降による)
まず、フルッサー自身が示している、非常に興味深い展開の図式をそのままここに掲げてみましょう。([図a](p.130))
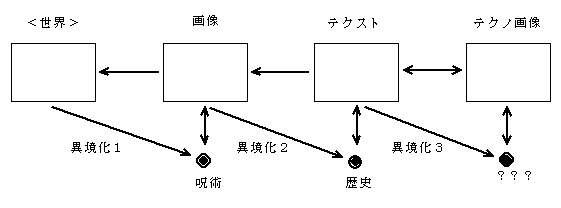
[図a]
まず、一番左側にある<世界>というのが、われわれが生きている世界で、ここではいわば出発点となっています。とはいっても、まず最初の段階では、われわれの今生きている世界という言い方をするとすれば語弊があるでしょう。というのも、ここでの<世界>とは、まだわれわれ人間が今のようにテレビや写真といった技術メディアはおろか、文字言語も持っていないし、世界を描き出すいかなる手段をも持っていない段階での世界を意味しているからです。つまり、そこでは人間はほかの動物と全く同じように、世界の中にとけ込んでいる一個の存在に過ぎません。そこでは人間はいわば、楽園のアダムとイブのように、<世界>と一体となっています。([図b])

[図b]
しかし、人間は何の意識もなく世界のうちに溶け込んだままとどまることはあり得ず、世界を対象化して(つまり、客体として)捉えるようになります。そのことは、人間の踏み出した次の段階への一つのステップではありますが、世界との一体性を一つのユートピアのように感じるとすれば、それは「<世界>から追い出されること」、楽園からの追放といってもよいかもしれません。<世界>から外へと出てしまうことを、ここでは「異境化」と名付けていますが、これはドイツ語のVerfremdung=「疎遠な」fremdなものとなること、よそよそしいものとなること、に対してあてられた言葉です。つまり、人間が<世界>を対象として見るようになるということは、これまで一体であった<世界>に対して距離を取ることであり、その意味で<世界>が人間にとって「疎遠な」ものとなるということです([図c]:〈異境化1〉)。
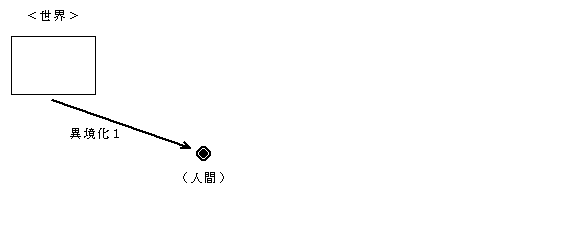
[図c]
人間は<世界>から離れることによって初めて、<世界>を(例えば、原始人が洞窟に絵を描いたように)「画像」として対象化します。そのときの、人間の「画像」に対する位置づけ(あるいは、「画像」の人間に対する意味)は、「呪術(魔術)Magie」的なものであり、そこでは<世界>そのものではなく、「画像」が<世界>を代替するものとなり、「画像」を描くことによって<世界>に働きかけるような意味を持つものとなっています。([図d])
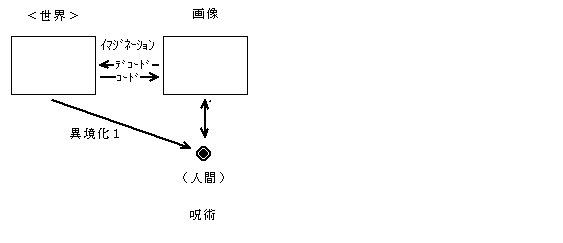
[図d]
この働きによって、人間はいったん<世界>から離れながらも、「画像」を媒介として、再び世界を捉えようとしているのです。(「画像」から<世界>に向かう矢印は、そのことを意味しています。)
このときの「画像」と<世界>とのあいだの関係をフルッサーは「イマジネーション」という言葉によって捉えています。つまり、(第8回講義で取り上げたように、「画像」を見て<世界>を思い描くデコードの能力であると同時に、<世界>という時空的四次元性を「画像」という二次元のものにコード化する能力が、ここでの「イマジネーション」です。[註1] その働きをさらに明確にいうならば、「イマジネーションとは、直接認識できなくなった世界と認識したいと欲する人間とのあいだの断絶を、画像によって架橋し、媒介する能力である」(p.142)ということになります。
さて、「画像」は<世界>と、そこから離れてしまった人間とのあいだの媒介としての機能を、当初は十分に果たしていたかもしれません。しかし、「画像」と<世界>とのあいだのイマジネーションがあまりにも用いられ、肥大化することによって、フルッサーによれば、「画像」というコードは「奇矯」なものとなり、それによって<世界>をもはや透明なものとして媒介することができなくなります。(例えば、「画像」が<世界>を表すものとしてではなく、それ自体として崇拝の対象となる。)それは、いわば画像というコードの危機であり、人間は<世界>を捉えるために、「画像」とは異なるコードを手に入れること、「画像」を離れることが必要な状況に置かれることになります([図e]:〈異境化2〉)。
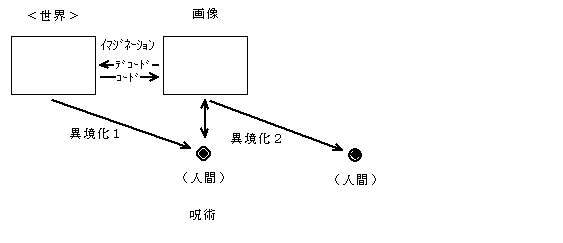
[図e]
そのようにして人間が新たに獲得したコードが、文字による「テクスト」というわけですが、ただ、これまで私が述べてきたような捉え方と根本的に違うのは、この「テクスト」は、それによって<世界>をそのまま捉えようとするものとしてではなく、人間がその前に離れた「画像」を捉えるもの、「画像」を説明するものとされているということです。「すべてのテクストは画像について述べているのであり、画像がなければテクストもない。テクストは、画像を記述し、説明し、解明するものなのだ。」(p.159) そして、「テクスト」が「画像」を捉える能力を、「画像」が<世界>を捉える「イマジネーション」に対して、「コンセプション」(つまり、概念化する能力)と呼んでいます。([図f])[註2]
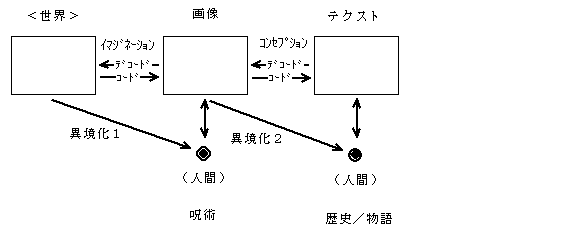
[図f]
「すべてのテクストは画像について述べている」という主張は、少し行き過ぎたもののようにも感じられます。というのも、書かれた言葉は、それに先行する何らかの絵(画像)についてのものとは限らない、というよりも、むしろそういったケースの方が特殊であるように思われるからです。確かに、フルッサーは、「画像」によって<世界>と媒介される人間のスタンスを「呪術」という言葉によって特徴づけていますから、ここでの「画像」とは、そういった何らかの呪術的意識を喚起するような具体的な絵のようにも述べられています。しかし、「画像」とは同時に、<世界>を見て人間が思い浮かべたもの、つまり「イメージ」(ドイツ語では「画像」と同じ、Bildという言葉です)でもあります。われわれは、ふつう、世界のうちにあるものを見て、その見たままのものが<世界>であると思っていますが(いわゆる素朴実在論)、それは厳密にいえば、<世界>からの刺激によって知覚された「像」(イメージ)に過ぎません。(これに関しては、特に、142頁以降参照) その意味では確かに、「テクスト」は、知覚された「像」(イメージ/画像)を概念的に説明したものということができるでしょう。(ただし、そうすると、それまでの「呪術(魔術)」という画像に対する人間のスタンスはうまく説明できなくなるので、ここがフルッサーの議論の中であまり首尾一貫していない、弱点であるように思われますが。)
さて、この段階でわれわれは世界を捉えるために、(なお「画像」という中間段階を踏んでいますが)「テクスト」を手に入れました。言い換えれば、世界を捉えるための「画像」というコードから、「テクスト」という新しいコードの段階に至ったことになります。
このコード転換に際して、「画像」の二次元的関係は、「テクスト」における文字の連なりという一次元的関係へと変えられることになります。「画像」が実際に描かれた絵ではなく、時間をともなった何らかのイメージであったとしても、ともかく「テクスト」が文字の連なりによって成り立っているコードであるということにはかわりありません。つまり、これまでも何度か言及してきた「テクスト」の線状性、一次元性、そして概念的に説明するという合理性が、なんといってもテクストの最も重要な特質として指摘できます。
そして、コードが二次元的なものから一次元的なものとなることにともなって、<世界>を捉えるにあたっての、いくつかの根本的な変化が生じることになります。その一つに、「時間」の問題があります。二次元的な「画像」においては、実際の<世界>において時間の継起をともなって生じているものも、例えば写真のように、ある一瞬の出来事として切り取られたものではなく、しばしば、異なった時間に起こったものが同一の画像におけるさまざまな要素として表される形で描かれることがあります。そこでは、静止した画像の上に、さまざまな出来事として現れる時間の流れが、いわば層をなして凝固しているとでも言えるでしょう。その絵を見るわれわれの視線は、それぞれまとまりを作っている人物などを順番にたどっていくことによって、そこにひとつの時間の流れを再び生み出すこともあるかもしれません。(例えば、「聖徳太子絵伝」)このように、「画像」として表されたもののうちにも、時間性をともなったひとつの物語を読みとることができるかもしれませんが、そこでの時間的な流れは見ているわれわれのまなざしが作り出したものと言えます。
(![]() 「画像」における時間)
「画像」における時間)
それに対して、これらの複数の情景が、「テクスト」において読まれるとすれば、そこでの時間的な流れはより自然なものと感じられるでしょう。「画像」においては、あくまでも本来時間的な継起のうちに現れるさまざまな事象が、そのひとつの画像のうえに描かれた同一の時間の断面の上に定着させられているのに対して、「テクスト」にあっては、それらの事象の時間的な連なりは、やはり時間的な継起の上に再現させられているからです。つまり、テクストにおける語りとは、文字を線状的にたどっていくという本質にしたがって、時間をともなった一つのプロセスとして語られるものを提示しているのです。
こういった、ある起点から出発し、特定のプロセスをたどって、終着点へと至るという時間をともなった線状的な流れは、ひとつの「物語」と呼ぶことができます。それは、われわれがよく知っている昔話のような物語をももちろん含んでいますが、広い意味ではある起点から終着点へと向かうあらゆるプロセスをある意図をもって語ることは、すべて「物語」と言えるでしょう。「ある意図をもって」というのは、そのプロセスで生じるさまざまな事象が、単なる出来事の無関係な羅列ではなく、ある出来事からもうひとつの出来事が因果関係をともなって生じていると見なされ、そのようにして事象どうしが相互に意味をもち、論理的に説明できるものとして提示されるものであるということを指しています。こういった、複数の事象が、相互に因果的に関わり合いながら、時間的に連鎖して起こっていくさまをわれわれが社会のうちに読みとるとき、われわれはそれを「歴史」と呼んでいます。日本語では「物語」と「歴史」は、全く異なったイメージをともなって捉えられていますが、ドイツ語のGeschichteにしても、フランス語のhistoireにしても、この同じ言葉が「物語」と「歴史」の両方を表しています。「画像」におけるように、<世界>をひとつの時間面のうえに描かれた「情景」として捉えるとすれば、そこには時間的な流れをともなった「歴史」はあり得ません。出来事の流れを「語る」ということ、つまりそこに「歴史」を見るということは、一次元的な線状性を本質とするテクストというコードが導入されることによって初めて可能になった意識なのです。上の図で、「テクスト」に対する人間のスタンスとして「歴史/物語」と示されているのは、そういうことです。
「画像」というコードから「テクスト」というコードへの転換に際してどのようなことが生じていたかを、フルッサー自身の言葉によって確認してみましょう。
「したがって、生は、画像からテクストへの翻訳によって全く新たな意味を得たのである。イマジネーションが肥大化して奇矯の狂気に陥る危険は、避けられた。いまや、すべての画像を一歩一歩(一行ずつ)説明すること、それを再び世界にとって透明なものにすることができるようになったばかりでなく、テクストによってコード化された世界のおかげで、イメージかできない全く新しい意味を世界に投射できるようになったのである。テクストの世界は、画像世界と人間との媒介者として登場するばかりでなく、その画像世界を破って単刀直入に世界を捉えようとする。歴史意識とは、呪術的立脚点を<追い越す>視点、呪術的な立脚点を新たなレベルに高め、それに新しい意味を与える視点なのだ。」(p.165)
例えば、「源氏物語絵巻」や「聖徳太子絵伝」が、「画像」でありながら、一つの物語を提示しているではないかと思われるかもしれません。しかし、それはむしろ逆です。これらの画像は、すでにテクストというコードと、それによってもたらされる「歴史/物語」の思考様式を身につけた人間が、それを「画像」というコードによって表そうとしたことによって生み出されたものと見ることができるでしょう。それによって、画像のうちにテクストの線状性がある程度持ち込まれる結果となったのです。
このように「テクスト」を介して(そして、フルッサーによれば、さらにテクストが説明する「画像」を介して)人間は<世界>を捉え、その「テクスト」のもたらす論理性・概念的把握の能力によって文化を発展させてきました。この点は、文字言語が西洋近代文化のあらゆる側面にわたって規定してきたとするマクルーハンが、繰り返し強調していることです。しかし、文字言語による「テクスト」が、これほどまでに文化を発展させてきたのではありますが、「テクスト」を介して<世界>を捉えるという行為は、ある飽和点を迎えることになりました。それは、「イマジネーション」が肥大化することによって「画像」が奇矯なものと化し、もはや<世界>を媒介する機能を持たなくなったという現象に対応するものです。つまり、「画像」を説明する「コンセプション」、すなわち概念的に把握する能力があまりにも肥大し、もはや言葉によって<世界>の像を捉えることができなくなるということです。例えば、「水」という言葉によって、大地に流れる川の水、それによってのどを潤す水を具体的に指し示している限りにおいて、この「水」という書かれた言葉は<世界>(あるいはその「像」)を透明に媒介するものとして機能しています。しかし、「水」という言葉があまりにも概念化され、その概念が一人歩きするようになったとき、その言葉はもはや<世界>(あるいはその「像」)とのあいだの媒介ではなくなります。つまり、その意味において、生き生きとした<世界>を捉えるものではなくなってしまいます。
「テクストには、考えられている画像から自立して、ますます概念的なもの、思い描けないものになってゆく傾向が、内在している。ところで、テクストとは画像に意味を与えるもの、概念とは表象に意味を与えるものだから、テクストはますます無意味なものになってゆく。そこで、ある臨界点を超えると、テクストはもはや画像への媒介(間接的には世界への媒介)を果たすものではなくなり、世界への道を閉ざす固い壁になってしまう。西洋のエリート層がこの臨界点に達したのは一九世紀の中葉であり、われわれの中でも、解説や理論、イデオロギーや教説への信仰(要するに進歩としての歴史への信仰)を失った者は、次々と臨界点に達している。テクストを読む際に何かを思い描くことがもはやできもしないし期待もされず、テクストの背後にもはや世界を見るのではなくそれを書いた人間を見るようになれば、それは、臨界点に達したと言うことだ。だから、臨界点におけるテクストの逆転は、テクストが世界にとっては不透明になり、世界をコード化する人間にとっては透明になるということを意味する。」(p.194-195)
この時点において、<世界>を捉えることが十分にできなくなってしまった人間は、肥大化し奇矯化したテクストから離れて、<世界>を捉えるための新たなコードを求めようとします([図g]:〈異境化3〉)。
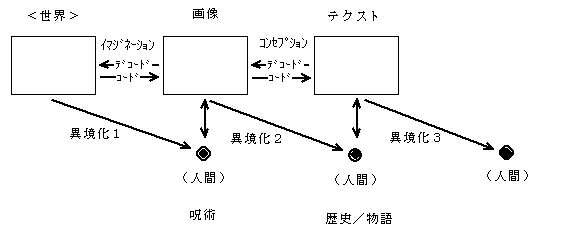
[図g]
この「テクスト」が臨界点を迎えるという危機のはじまりを、フルッサーは、19世紀半ばの西洋のエリート層のうちに見ていますが、とりわけ19世紀末から20世紀初頭にかけての言語危機(例えば、ホーフマンスタール、カフカ、ヴィトゲンシュタイン)の時代にそれをもっとも顕著に見て取ることができると思われます。
この問題に言及するとすれば、まず最初にふれなければならないのが、ウィーンの作家フーゴー・フォン・ホーフマンスタール (1874-1928) の「手紙」(あるいは「チャンドス卿の手紙」)でしょう。ホーフマンスタールは、日本ではたとえば『エレクトラ』『バラの騎士』『ナクソス島のアリアドネ』『アラベラ』といったR.シュトラウスのオペラの台本の作者としてしか一般には以外と知られていないようですが、この時代のドイツ文学における巨頭(しかも貴族的な優雅さをもった)の一人です。早熟の天才であったホーフマンスタールが、まだ十分に若い頃、1901年から1902年にかけて書かれた「手紙」は、17世紀の初頭、フィリップ・チャンドスというイギリスの貴族がフランシス・ベイコンに宛てられた架空の手紙という形を取るエッセイとして書かれています。その手紙の中で、「私」は、言葉がもはやこれまでのように当然のごとく何かを指し示すものとして感じることができなくなり、自分にとって完全によそよそしいものと化して、それによってもはや何かを意味することができなくなるような状態について語っています。
「簡単に申し上げますと、小生の場合は次のようなものであります。小生は何かあることを他と関連させて考えたり、語ったりすることができなくなってしまったのです。
まず小生には、高尚なことや一般的なことについて語り、その際、すべての人々がいつも少しも躊躇しないで、達者に使いこなしている言葉を口にすることが、だんだんできなくなってきたのでした。「精神」とか、「魂」とか、または「肉体」とかいったような言葉を、ただ口に出すのさえ、なんとも言えず不快に感ぜられました。(...) それはなんらかの判断を表明するためには必然口にしなければならない抽象的な言葉が、小生の口の中で、まるで腐敗した茸のように、こなごなになってしまったからです。」(『ホーフマンスタール選集3』河出書房新社、p.10-11)
ここでは語る言葉としていわれていますが、「手紙」の中でも早熟の作家であるチャンドス卿が26歳の時に過去の作品を振り返って述べているように、これは実質的に作家の書く言葉にとりわけ当てはまると考えてよいでしょう。この「手紙」は実際、ホーフマンスタールの創作の転機となっていますが、だからといってもちろん、ここでほんとうにホーフマンスタールが全く書けなくなってしまったというわけではありません。第一、この「手紙」自体、「それはなんらかの判断を表明するためには必然口にしなければならない抽象的な言葉が、小生の口の中で、まるで腐敗した茸のように、こなごなになってしまったからです」と言われながらも、見事な言葉で書かれているのですから、ここにはある種の自己矛盾が存在することを指摘しないわけにはいきません。
とはいえ、この「手紙」はホーフマンスタールの創作活動のみならず、ドイツ文学全体における一つの決定的な転換点を告げるものとして位置づけることができるでしょう。つまり、言葉とともにあること、いわば言葉の内側にあることをほとんど意識することもないという素朴な状態のうちにとどまることがもはやできなくなり、語るということ、言葉を用いるということを客体化し、そのようにして言葉から離れてしまわざるを得なくなった状況を指し示しています。
同年代のプラハの作家フランツ・カフカ (1883-1924) の作品は、必ずしも言葉そのものについて述べられたものではないにせよ、すべてそういった言葉の状況にさらされているといってよいでしょう。彼の作品において描き出されている世界の異様さ、世界がある歪みを帯びて現出するさまは、世界を捉えようとする素朴な言葉がもはや保たれえず、そこから離れて言葉自体がいわば異形のものとなっていることにも由来しているように思われます。カフカの作品としては一般的にはそれほど知られていないものかもしれませんが、カフカがどのような言語の危機意識にとらわれていたかが如実に示されている作品として、「祈る人との対話」と「酔っぱらいとの対話」(ともに1909年に初めて出版)から少し引用してみたいと思います。
実際、なにを言っているのだ。あんたがどんな状態なのか、分かってきたぞ、いや、あんたを初めて見たときから、分かっていたのだ。ぼくには経験がある。だから冗談に言うのじゃない、それは陸の船酔いなのだ。あんたは物の真の名を忘れて、いま大急ぎで仮の名を物の上にばら撒いている、それがこの船酔いの実体なのだ。早く、早く! とあんたは苛立つ。しかし物から離れるやいなや、あんたはまたその名を忘れてしまう。野原のポプラをあんたは『バベルの塔』と名付けた、それがポプラだということをあんたは知らなかった、あるいは知ろうとしなかったからだ、あのポプラはまたしても名をもたずに揺れている、こんどは『酔っぱらったノア』とでも名づける気だろう。(「祈る人との対話」『カフカ全集1』新潮社、p.9-10)
家の玄関から小股に歩いて外へ出ると、月と星星と巨大な穹窿をそなえた天が、そしてリング広場から市庁舎とマリア様の柱像と教会が、ぼくの上に襲いかかってきた。(...)
「いったいどういうことなのだ、おまえたちが現実であるかのようなふりをしているというのは。おまえたちはぼくが非現実で、緑色の舗石の上に滑稽な姿で立っているのだと、ぼくに信じさせたいのか? だがな、おまえ、天よ、おまえが現実だったのはずっとむかしのことなのだ、そしてリング広場よ、おまえはかつて現実だったことはないのだ。」(...)
「ありがたいことに、月よ、おまえはもう月ではない、だが、むかしから月と命名されているおまえを依然として月と呼ぶのは、たぶんぼくの怠慢なのだろう。ぼくがおまえを『ふしぎな色の、忘れられた堤燈』と名づければ、おまえが急に意気阻喪してしまうのはなぜだ。そして、『マリア様の柱像』と名づければ、ほとんど後退りするのはなぜだ、それからマリア様の柱像よ、ぼくがあんたを『黄色い光を放つ月』と名づければ、あんたの威嚇的な態度はもうぼくの目から消えてしまうのだ。」(「酔っぱらいとの対話」『カフカ全集1』新潮社、p.13)
カフカはこれを書く時点ですでにホーフマンスタールの「手紙」を呼んでいたと言われていますが、ここでもまさに同じ状況が語れています。しかも、カフカにとっては、抽象的な言葉だけでなく、きわめて具体的な、世界の中のある特定の物を指し示す「名」でさえ、もはや自明のものではなく、自分の手のあいだから滑り落ちていくのです。
さて、とりあえず二人の作家が20世紀の初頭という同じ時期に感じ、それに対してそれぞれの仕方で彼らが取り組んできた言語の危機的状況にごく簡単にふれてきました。これらはもちろんかなり極端な現れ方をした危機意識ではあります。もう少し日常的なレベルであれば、例えば、あまりに抽象的な概念が一人歩きすることによって、言葉が生々しい世界からはほとんど遊離してしまうとか、ある言葉が過剰供給されることによってその言葉が、過剰供給の状態にあるということ自体のほかに、ほとんど何ものをも意味しなくなってしまうとかいった状況をあげることができるでしょう。あるいは、あるテクストを読むとき、そのテクストの内容を読むのではなく、誰がどのような状況の下にどのような意図でそのテクストを書いたのかという、いわばテクストの外側の部分を見て取るような視点を取るとすれば、それはもはやある<世界>を媒介するものとしての素朴な「テクスト」ではもはやなくなっていると言えるでしょう。
しかし、「テクスト」がこういった臨界点に達してしまい、人間がその「テクスト」から距離を取るという状況が生じた結果、最初に提示した図にあるように、次の新しいコード(つまり、「テクノ画像」の「テクノコード」)へと必然的にいたると言えるでしょうか。先取りして言うならば、「テクノ画像」とは、具体的には写真とか、さまざまな標識とか、テレビの映像とか、映画とかを指していますが、「テクスト」がもはや<世界>の媒介としてまともに機能しなくなったから、「テクノ画像」を用いるようになったという説明は、あまり必然性を感じさせるものではないようにも思えます。あるコードを使用していくことによって臨界点に達し、そこから離れていく、そして次のコードへといたる、という弁証法的な展開の図式は確かにわかりやすいものではあります。しかし、「テクスト」がある臨界点に達し、われわれがそこから離れざるを得なくなったということは事実であるとしても、その次にわれわれが達するところは、新たな段階における「テクスト」であるかもしれません。実際、ホーフマンスタールがそうであったように。フルッサーが示している図式は非常に単純化されたものであり、実際には、それぞれのコード内でつぎつぎと同じような展開が生じており、ある段階でつぎの全く新しいコードへと踏み出すことになったのだと説明することができるかもしれません。あるいは、ここでいわれていることは新しいコードへの転換が生じているひとつの説明であって、もちろんほかにもさまざまな条件が関わっているのだということもできるでしょう。いずれにしても、ここで示されているようなコードの転換が生じていること自体は事実ですから、少なくともそれを説明するための一つの視点として、さらに先を見ていくことにしたいと思います。
肥大化し奇矯化したテクストから人間が離れ、テクストに変わって<世界>を媒介するものとされるコードを、すぐ前にふれたように、フルッサーは「テクノ画像」と名付けています。とりあえずの規定をするならば、写真、テレビの画像、映画など、人工的に(これまでの言葉を使えば)技術メディアによって生み出された画像です。これらの「テクノ画像」も、最初のコードとしての「画像」と同じくやはり画像であり、一般的な理解においては、ひとつの絵(「画像」)が<世界>を捉えようとするのも、写真(「テクノ画像」)が<世界>を写し取ろうとするのも、少なくとも<世界>を捉えるという最低限の意図においては、基本的には同じことであるようにも思えます。しかし、ここがフルッサーの技術メディア(テクノ画像)に対する独自の見解が示されているところなのですが、「テクノ画像」は<世界>をそのまま写し取ろうとするものではなく、「テクノ画像」の前の段階のコードである「テクスト」を説明し、それに意味を与えるものである、つまり「概念」に意味を与えるものである、いや、そういったものであるべきであると述べているのです。次の図([図g] : これは一番最初に掲げたものと、基本的に同じものですが)は、このことを表しています。
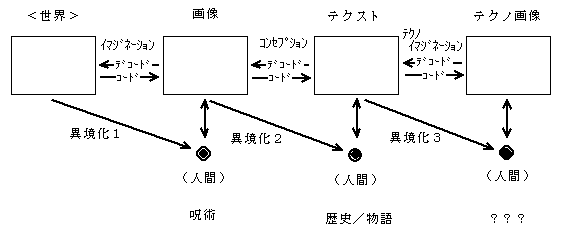
[図g]
こういった独自の視点を強調するフルッサー自身の言葉を見ておきましょう。
「テクノ画像は他のあらゆる画像と同様に記号からなるものだから、意味を与えることがその特徴なのである。ただし、その意味は、他のどんな画像の意味とも異なる。それは、情景に意味を与えるのではなく、概念に意味を与えるのだ。これは、他のあらゆる画像と全く異なる存在論的地位を持ち、全く異なる系譜に位置づけられる。これは、革命的に新しいコードなのだ。」(p.174)
この「革命的に新しいコード」の特質を説明するためには、ふつうの写真や映画といったものよりも、次のような例の方がはっきりするでしょう。
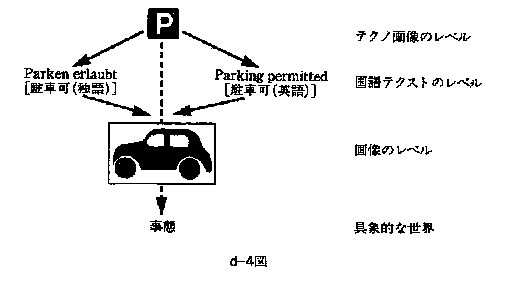
この図は、上から順番に「テクノ画像」→「テクスト」→「画像」→<世界>という意味の指示関係を模式的に表しています。われわれは、Pという標識(テクノ画像)も、「駐車可」(あるいは、ドイツ語のParken erlaubtや、英語のParking permitted)という各国語による「テクスト」も全く同じように、自動車が駐車しているという一つの事態(あるいは、その「像」)を表しているように考えているかもしれませんが、この図は、「テクノ画像」と「テクスト」が全く別のレベルにあり、別の機能を果たしていることを示しています。
「それ[テクノ画像]は、画像に意味を与えるテクストに、意味を与えるのだ。それは、アルファベットのテクストから生まれたものであり、テクストの構造を内在させている。それは、テクストを通して間接的に、画像に意味を与えるに過ぎない。しかし、その際、テクストによる媒介は省略されるのだ。テクノコードが<国際的>なのは、それがありとあらゆる国語によるテクストに意味を与え、どんな国語も不要にするからである。テクノコードは、さまざまの画像の画像ではなく、さまざまのテクストの画像である。しかし、その際、それらのテクストを自己の内部で解消し、唯一の普遍的コードに高めるのだ。それは新たな意味における<文字言語>である。音声言語をアルファベットによって書きとどめたものではなく、文字言語が何であれ、画像によってそれに意味を与える言語、すなわち、文書で鼻くその意味をコード構造とする言語である。」(p.183)
繰り返すことになりますが、ここでとりわけ重要であるのは、われわれがふつうある技術メディアによる像(テクノ画像)を現実の描写と考えているのに対して、フルッサーは「テクノ画像」はあくまでも「テクスト」に意味を与えるものであると位置づけていることです。テクノ画像が「革命的」といわれている一つの点は、同じ事態の「像」を指し示すために、「テクスト」がそれぞれ異なった言語を用いなければならないのに対して、「テクノ画像」においては同じ画像(ここではPという標識)を用いることによって、それぞれの言語を迂回しながらも、あたかもほとんど直接的に一つの事態(あるいはその「像」)を指し示すかのように機能するということにあります。つまり、そこでは「テクストによる媒介は省略される」ことになります。それによって、言語の違いという大きな障壁が克服され、その意味で「国際的」なものとなりうるというわけです。
ここで取り上げているフルッサーの著作が実際に書かれたのは1973年から1974年にかけてのことですが[註3]、現代のわれわれにとって、そういった意味でのテクノ画像としてもっともわかりやすいのは、おそらくコンピュータのユーザ・インターフェース上に見ることのできるさまざまなアイコンでしょう。ご承知のように、もともとアイコンは、マッキントッシュのユーザ・インターフェース上で用いられており、文字による入力ではなく、アイコンをいわば触覚的に動かすことによってコンピュータを操作するという考え方が多くのマッキントッシュ・ファンを生み出した大きな理由の一つといえるでしょう。そして、これもご存じの通り、アイコンを操作するという考え方は、Windowsのインターフェースとなって取り入れられ、ますます押し進められることになりました。つまり、ここではテクノ画像がテクスト(文字入力)を凌駕し、放逐してしまうという現象が起こっているのです。
この例においては、とりあえず言語の障壁が著しく減少するという意味での「国際的」な特質がはっきり示されます。例えば、Windows95/98あるいは世界的に用いられているソフトウェアのアイコンはどの言語圏であれすべて同じですから、ファイルを開いたり、保存したり、操作の後一つ前の状態に戻したり、といった基本的な作業は、ここで用いられている「テクノ画像」によって、たとえギリシャ語やロシア語やフィンランド語のWindowsであれ、一応可能でしょう。その場合、その過程で「テクストによる媒介の省略」が行われており、例えば「ファイル保存」のアイコンという「テクノ画像」が、実際にファイルを保存するという現実の事態へとそのままいたっているように見えます[註4]。ということは、われわれがある技術メディアの画像(テクノ画像)を見て素朴に思っている考え方、つまり、写真に写っている大学の建物を見て、(本物そのものではないけれど)これは大学だと思い、ホラー映画か何か恐ろしい映像を見て、本物ではないけれど、現実にあるかのような体験をし、矢印にクエスチョンマークのついたアイコンを見て、これを押せばコンピュータの操作についての情報(つまり「ヘルプ」ですが)がでてくるといった考え方、つまり「テクノ画像」がある(仮想的)現実の事態の反映となっているという考え方と、基本的に同じではないかと思われるかもしれません。
しかし、そうではありません。テクノ画像は、いかに「テクストによる媒介を省略」しているように見えても、それは機能的にそのようになっているだけで、あくまでも言語(テクスト)を迂回しているのです。例えば、アイコンの「ゴミ箱」にファイルをドラッグして捨てるということは、われわれは自分が知らない言語の画面上でも確かにできますが、ファイルの削除というコンピュータ上の操作を行うとき、われわれは「ファイルを削除する(再び使うことも可能だが)」ということを自分の言語で考えており、そのようにして表面的には見えない形ではありますが、「テクスト」を通ってテクノ画像からそれが指し示す一つの事態へといたっているのです。その意味で、「ゴミ箱」というテクノ画像は、あくまでも「テクスト」を前提としたものであり、「テクストの構造を内在させている」のです。
そして、このときの「テクノ画像」のコードを読み解いて、それが意味する「テクスト」へといたる能力のことを(図では、「テクノ画像」から「テクスト」へといたる矢印)、フルッサーは「テクノイマジネーション」と名付けています。アイコンの例では、一つのアイコンがどのようなテクストを指示しているかは自明のようにも思えますが、それにしてももちろんある種の訓練によって習得したものです。多くのいわゆる「マニュアル」で、そのテクノ画像の意味する「テクスト」が説明されていることは、まさにそのことを指しています。「画像」と<世界>とのあいだ、また「テクスト」と「画像」のあいだのコード/デコードの能力(つまり、「イマジネーション」と「コンセプション」)が学び取られたと同様に、「テクノイマジネーション」も学び取る必要があるということです。
図においては、「テクノ画像」に対する人間のスタンスのところには、「???」とあります。これはフルッサーによれば、まさにその記号の表すとおり、われわれとテクノ画像との関わりが、まだ十分に判らないままテクノ画像が用いられているということなのですが、いずれにせよ「歴史/物語」はこの段階においてはいわば克服されているということが示されていることになります。「歴史/物語」の終焉という言説は、ポストモダンの思想において共有されているものといえるでしょうが、これはメディアの展開を思想史的に論ずる文脈においても、同じ事柄を二つの側面から捉えるような仕方で取り上げられているといってよいでしょう。(これについては、次回、ハイパーテクストと「歴史/物語」をめぐって、取り上げたいと思います。)
私がこれまで述べてきたような「テクノ画像」についての位置づけは、実はフルッサーのテクストにおいては、まだほんの作業仮説として提示された段階にすぎず、さらにテクノ画像についての詳細な議論が続いているのですが、技術メディアのあり方としてどのような可能性があるかを考察するこの講義では、とりあえず、これまでのコードの展開の図式を提示したところまでに関して扱うことにしたいと思います。
フルッサーのいうように、例えばある写真ないしは映画もある「テクスト」を指示するものであり、それらの「テクノ画像」を見たときに「テクスト」へといたるための能力を養う必要があるということになります。そういった写真や映画に対する捉え方に対しては、もちろんさまざまな立場から異論が出されることでしょう。例えば、確かに写真や映画を読み解く(デコードする)ためには、そのための特別の見方を身につける必要があるということに関してはその通りであるにしても、読み解かれたものは「テクスト」ではなく、写真や映画を製作する人間の描き出そうとした情景そのものであるということもできるでしょう。その際しばしば問題になる芸術性の問題についても、フルッサーは批判的な視点から取り上げていますが、ここではそれにはふれないで、もっと日常的なテクノ画像について考えてみることにしましょう。
「テクノ画像」が(仮想的に)<世界>へとストレートにいたることが目指されているもっとも典型的な例は、いわゆるヴァーチャル・リアリティ的な使い方をされている場合であると思われます。その場合われわれは、「テクスト」を介在させて、概念的にとらえるという作業を行っているのでしょうか。おそらくそうではないでしょう。そういう「テクノ画像」の使い方も可能だということです。「テクノ画像」が「テクスト」を意味するものである、というのは必然的にそうであるというのではなくて、むしろフルッサーの提起する要請です。このことは、たとえばフルッサー自身、「テクノコードの正しい使い方がまだ学ばれていない」(p.182)と述べていることのうちに暗に示されています。
何が正しい使い方で、何が誤った使い方かということをここで結論づけることはできません。私自身、フルッサーがテクノコードの正しくない使い方と見ているであろう、技術メディアによる像(例えば映画)によってヴァーチャル・リアリティ的な体験をするというテクノ画像のあり方も、テクノ画像の一つの重要な可能性であると思っています。おそらく、技術メディア(テクノ画像)がテクストを指し示すものであるか、あるいは直接に<世界>を指し示すことを求めるのか――言い換えるならば、技術メディアが概念的な把握を経るものとなるか、あるいはむしろ感覚性を志向するものとなるか――ということは、どういったタイプの技術メディアであるかによってある程度異なると思われます。例えば、テクノ画像の例として最初にあげたような、駐車可を表す標識Pのような記号的な性格が顕著であるものは、事態を概念的に捉えるテクストをまず指し示していると考えることにさして抵抗はありません。しかし、映画のように、感覚性がきわめて強調されるようなメディアもあります。フルッサーの見解がきわめて興味深いのは、こういった映画のように、一般的には概念的な把握ではなく、感覚的な捉え方をするものと考えられているようなものにも、「テクスト」を説明するという機能を見ている点にあります。フルッサーのように、テクノ画像(技術メディア)がテクストを説明するような場合にそれは正しい用いられ方をしているのであって、それ以外はテクノ画像の正しい用い方ではないのだという主張をするとすれば、テクノ画像の位置づけは非常に明確なものとなりますが、その可能性はかなり限定されたものとなります。しかし、これまで考えられているような統合的な感覚性が前面に押し出されたような技術メディアの捉え方に、フルッサーの主張するような可能性を意識的に付け加えて考えるとすれば、技術メディアのあり方の可能性はより広がると言えるでしょう。
すでにマクルーハンについてとりあげた第2回、第3回の講義で述べたように、技術メディアは、アルファベットという表音文字の線状性・論理性によって構築されてきた西洋文化(とりわけ近代の西洋文化)のあり方を基本的に批判する立場から位置づけられているといえます。こういった基本的なスタンスは、フルッサーの見解においても共通しています。また、技術メディアがやはり感覚性に関わるものであるという点についても、「テクノ画像」がやはり「画像」であり、そこでは「テクノイマジネーション」が問題となるという言葉を見てもすぐ分かるように、技術メディアは「テクスト」(文字言語)ではなく、その前の段階(音声言語/画像)に近いものであるとされていることになりますから、やはり共通の立場を見いだすことができます。マクルーハンに典型的に見られる、文字以前の統合的感覚性の回復という意味での技術メディアの称揚は、それに対置される「テクスト」の意味をあまりにも過小評価することになりがちです。しかし、現実には、技術メディアが今日これほどわれわれの社会・文化の中で大きな位置を占めるようになっても、文字言語がなお重要なメディアとして存続することになるのは間違いないでしょうから、単に文字言語の線状性・論理性を克服した技術メディアの位置づけを強調するのであれば、それは現実を十分に説明するものとはなり得ないでしょう。
「文字言語(テクスト)」と「技術メディア(テクノ画像)」の関係は、「音声言語」と「文字言語」との関係に似たような状況にあるように思われます。「文字言語」が生み出され、印刷技術によって文字言語的な思考様式が支配的になっていったとしても、依然として「音声言語」は失われることはないし、ある特定の文化圏や状況においては、音声言語的な思考様式・振る舞いが前面に出ることがしばしばあります。とはいえ、その場合の「音声言語」も、文字を知る以前の言葉の文化そのものに見られるものではなく、やはり、いったん文字言語を知ってしまったことによって生じる認識様式・思考様式の変化を被っているはずです。
同じように、「技術メディア」がどれほど「音声言語」の段階の統合的な感覚性を回復し、「文字言語」の線状的論理性を乗り越える特質をもつものであっても、「文字言語」はもちろん消滅するわけではなく、「音声言語」とともに、いわば技術メディアの文化の中に吸収されて機能することになります。その際、文字言語は、技術メディアを知る以前の純粋な「文字言語」ではもはやなくなってしまうでしょう。こういったことは、コンピュータを使って文章を書いたり、既成の電子テクストを使ったり、Web上の電子図書館を体験したりしている人にとっては、すでに実際にかなり感じ取られている現象だと思われます。技術メディアが感覚的特性をきわめて明確にもっているということは確かに事実なのですが、他方で、J. D. ボルターが指摘しているように(第5回および第6回講義)、音声言語から文字言語をへて技術メディアへいたる展開は、増大する論理性としても見ることができます。技術メディアがこのように、感覚性と論理性という両極をあい備えるものであることは、第6回の講義でもふれました。フルッサーの技術メディアの位置づけは、この点でも重要な意味をもつものと考えられます。つまり、技術メディアに感覚性を認めながらも、同時にそれを「テクスト」の論理性・概念性に関わるものと位置づけている点です。いずれにせよ、技術メディアのあり方を捉えるためには、それがもっている感覚性と論理性という両極の両方をともに考慮に入れる必要があります。