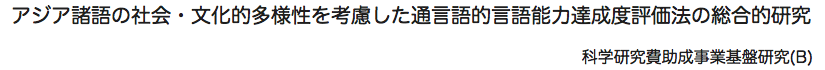2017年3月 刊行
「アジア諸語学習者におけるCEFR自己評価と社会・文化的コミュニケーション能力の測定指標の開発」
富盛伸夫(東京外国語大学、科研代表者)、
YI Yeong-il(東京外国語大学大学院修士課程)
【『アカデミック日本語能力到達基準の策定とその妥当性の検証ー成果報告書(2017)-』より転載】
1. 本研究の動機と背景
2. 本研究の目標と実施方法
3. 学習者アンケート調査(2014)の観察から(定量的分析」
4. アジア語圏の社会・文化的特質の学習者意識(直感的分析)
5. 社会・文化的コミュニケーション能力測定指標の開発に向けて
6. 考察と展望
4. アジア語圏の社会・文化的特質の学習者意識(直感的分析)
本分析への補完的調査として、富盛の担当する2014年度・2015年度後期科目「EUの言語政策と言語教育政策の研究」を受講する学生たち(合計110名)がアンケート調査に回答して本研究にも協力してくれたが、その学生の一部11名から記述式の意見が回収できた。以下にその興味深いいくつかをここに取り上げて学生たちの学習者意識についてコメントしたい。
(1) EU言語の均質性に対する非EU言語の多様性の認識:
・多くの学生から第一に指摘されたことは、«EU言語に対してアジア諸語の文字学習の負担と習熟進度の差が大きい»点である。«現代中国語の漢字やハングルについては比較的短期間に学習の成果が現れる» が、一方で、«大陸アジア諸語の多くは文字や声調等が関与して難易度の高さ»が強く意識されている。データから、書き言葉の運用についての標準偏差は高く平均値が低いという結果からも、学生の強い難易度意識の根拠が明白である。
・EU言語の類型的特質(文字、音声、統語構造や構文等)に対してアジア諸語学習では、«同程度の学習時間に対して同程度の達成度が見られない»との印象を学生は持っているようである。いわゆる4技能の学習進度上のばらつきも24ヶ月以上では達成度が一定程度に高まるが、言語学習そのものに動機付けの強い東京外国語大学学生の特徴かもしれない。一方で、アジア諸語の多くは、標準偏差値が高く、つまり、クラス内での学生間の達成度にばらつきが大きく、EU言語などと異なる言語特徴の違いが引き起こす困難さについての意見が多かった。この点についても本データから裏付けられる。
(2) 言語使用場面(Domain)の要素に関わる認識:
・アジア諸語を学ぶ被調査者の側から、CEFRでは導入レベルA1で課せられるタスクに対する反発«A1やA2レベルで挙げられるはがきや手紙でのやりとりなど社会・文化的コードの習得はハードルが高い»などの意見が見られた。書記法上の難易度に関しても«EUでは普通の挨拶状であっても、日本語では多くの漢字や定型的表現、敬語などの使用が要求される以上、A1レベルには不適切である»という留学生たちからの指摘は貴重である。
・社会・文化的コードについては、«社会・文化的コードを強く含む待遇発話は、B1へ持ち越すか、あるいは別のアジア的枠組みの可能性もある»というコメントが数名から出された。ここではEUの均質性との乖離が意識されている。
・特にアジア諸語に深く関与する社会・文化的コミュニケーション上の語用論的要素が関与する有意差が抽出できそうである。店頭での売買等商取引や依頼や断り、提案などの語用論的、談話的ストラテジーが必須な言語習慣はアジア諸語に顕著で、そのレベルまで習熟するにはAレベルでは不可能»というような意見もあった。本研究としては、アジア語圏の社会・文化的コミュニケーションの特質、特に語用論的要素が関わる指標抽出という課題設定が展望として可能である。
(3) アンケート回答者の心理の問題:
・«自己評価を厳しく、あるいは低く見積もって回答する傾向が日本語話者には多いのではないか»という気づきもあった。日本人のいわゆる国民性や文化的傾向と一般に帰されがちであるが、自己評価の信頼性に揺れが生まれる可能性は排除できないかもしれない。学習者・回答者の自己評価と実際の能力の測定の相関性の研究を行う必要があろう。
(4) CEFR受容の柔軟性確保と互換性の問題:
・«他の国際的な測定尺度やローカルな評価システムと整合性を求めるあまり自由度が高くなりすぎると、EUあるいは世界と共通の評価枠組みとしてのCEFRの信頼性がなくなる危険もある»という意見は傾聴に値するが、他方で、非EU諸国にCEFRを導入する場合には、各国の一定程度のカスタマイズが必要かもしれない。日本で進めているCEFR-Jの開発は、日本の外国語教育の実態に合わせて企画されていることも事実である。
自由記入式で答えた学生の気づきのうち、(1)については我々の分析とも一致している。(2)で指摘された言語使用場面(Domain)の要素に関わる問題では、アジア諸語の社会・文化的コードの違いに関して、本研究の課題に直接的に関与する認識が寄せられたといえる。(3)の回答者の心理的側面については別途の研究課題として成立しうる[20]。(4)については、本研究の問題設定(3)のCEFRの受容と通言語的妥当性そのものの指摘であり、学習者の意識の確かさを感じさせる。
- [20日本外国語教育学会第17回大会の研究発表「フランス語学習者におけるCEFR-Jを用いた自己評価と客観評価との関係」(杉山香織、川口裕司)を参照。