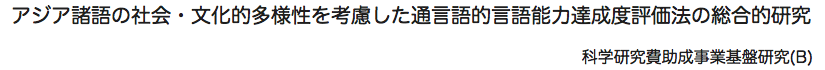研究計画
研究計画
(1) 研究計画に対応した3つの作業班を組織し、分担者は専門研究領域において計画遂行に向けて協働した。
(A班)アジア諸語地域の社会・文化的多様性を考慮した通言語的かつ透明性の高い言語能力評価システムの開発研究を目的として、アジアの諸大学での外国語教育システム立案者や言語教育従事者(教師等)に対する現地調査により、Webや二次資料の情報では得られない信頼度の高い情報が入手できた。また国際シンポジウムや国際ワークショップの開催により、「アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム」(CAAS)加盟大学およびアジア諸大学からの研究者とともに、CEFRの能力評価記述文(descriptors)の妥当性を評価した。
藤森弘子(日本語担当)、南潤珍(韓国語担当)、田原洋樹(ベトナム語担当)、上田広美(カンボジア語担当)、野元裕樹(マレーシア語担当)、岡野賢二(ビルマ語担当)、萬宮健策(ウルドゥー語担当)、丹羽京子(ベンガル語担当)、吉枝聡子(ペルシャ語担当)、矢頭典枝(アジア英語担当)、拝田清(オセアニア地域、世界英語論担当)
(B班)EU等ですすめられている社会文化的コミュニケーション能力の育成と異言語・文化間の仲介(mediation)の評価法開発にかかわる最新研究動向を把握し、CEFRの非EU言語への適用妥当性の再検証および社会文化的コミュニケーション能力評価法開発にかかわる最新動向調査を行なった。その成果をA班と共同し国内外の学会・研究集会で成果発表を行なった。
富盛伸夫(研究総括、EUの言語教育政策担当)、根岸雅史(英語教育、CEFR、CEFR-J担当)、成田節(ドイツ語圏のCEFR研究担当)高垣敏博(スペイン語圏のCEFR研究担当)、矢頭典枝(アジアの英語変種研究、社会言語学担当)
(C班)国内の先進的な外国語教育に取り組む高等学校や教育委員会に聞き取り調査を行い、中等教育との接続および中等教育及び社会的ニーズに対応した外国語能力到達度評価法に関する研究を行なった。
山崎吉朗(研究協力者:一般財団法人日本私学教育研究所主任研究員、中等教育における外国語教育研究)、富盛伸夫(生涯教育における到達度評価法)、根岸雅史(中等教育英語教育)
(2) 東京外国語大学が参加する「アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム」(CAAS)加盟大学との研究協力体制は本研究でも活用した:シンガポール国立大学言語研究センター、フランス・国立東洋言語文化学院、ライデン大学日本語専攻科、韓国外国語大学外国語教育研究所等。
(3) 国内外の言語能力評価法研究分野の専門家との協力体制により講演会、シンポジウムへの参加を含む研究協力が得られた:国内のCEFR研究グループ(東京外国語大学CEFR-J、JLC日本語スタンダーズ等)、立命館アジア太平洋大学、神田外語大学など。
(4) 統括評価班を設置しプロジェクトの円滑な遂行のため、分担者が委員となる運営委員会を組織し定期的に開催(計5回)したほか、随時メールなどによる稟議で意思疎通を図った。代表者富盛が総括的責任を担い、研究計画に従って円滑かつ効果的に運営できるように常時情報の共有を図り全体的な研究遂行の管理・調整を行なった。代表者は研究に支障が出ないように研究拠点の確保などに配慮し適切な対応をすることができた。