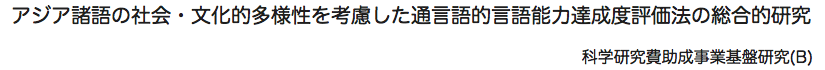研究活動の成果公開と総括
研究活動の成果公開と総括
成果報告書「「アジア諸語の社会・文化的多様性を考慮した通言語的言語能力達成度評価法の総合的研究」の概要と活動実績」P.145〜以下から抜粋
2015(平成27)年度
本プロジェクトでは上記の研究集会開催の活動以外に、対外的成果発信に重点をおいてきた。
2015(平成27)年11月29日に開催された外国語教育学会(JAFLE)第19回研究報告大会において、富盛伸夫とYI Yeong-ilは本科研の研究成果として「アジア諸語学習者における言語別CEFR自己評価の傾向と社会・文化的コミュニケーション能力の測定に関わる諸問題―学習者アンケート調査(2014)の分析から―」を発表し、東京外国語大学で行なったアジア諸語学習者アンケートの分析を通して、言語類型の異なりや語用論的ストラテジーを配慮した「社会・文化的コミュニケーション能力」に対応した通言語的能力評価尺度設定の問題点を論じた。
2016(平成28)年度
アジア諸語の社会・文化的多様性を考慮した言語能力の評価方法の研究、および異文化間言語コミュニケーション能力の記述に有効な指標を抽出する試みを行うため研究交流を推進した。当初の計画にもとづき、国際研究集会(特別講演会)を開催し研究成果の公開を図った。ミャンマー等のアジア諸国で言語教育研究者に本科研の活動内容を公開し聞き取り調査を行うことにより、CEFR受容の進捗状況を把握するとともに、アジア諸語の教育で現場教師と学習者が直面する言語・文化的諸問題の解決取り組みの方策を検討することができた。
2016(平成28)年12月18日に開催された外国語教育学会(JAFLE)第20回研究報告大会において、富盛伸夫とYI Yeong-ilは研究成果として「TUFS言語モジュールの会話文を活用したアジア諸語の社会・文化的特質の指標化」を発表し、学習コーパスから新たなCEFR Descriptorsを作成するための指標化について成果公開した。
国際シンポジウムの成果物として、『アカデミック日本語能力到達基準の策定とその妥当性の検証 ―成果報告書(2017)―』が2017年3月に刊行された。(科学研究費助成事業 基盤研究(B)課題番号26284070 研究代表者:藤森弘子「アカデミック日本語能力到達基準の策定とその妥当性の検証』成果報告書 pp.29-46 に掲載。)
外国語教育学会での成果発表「アジア諸語学習者におけるCEFR自己評価の傾向と社会・文化的コミュニケーション能力に関わる諸問題-学習者アンケート調査(2014)の分析から-」は、紀要『外国語教育研究』No.19 (2016), pp.1-18. に掲載された。
2017(平成29)年度
最終年度として、前年度までの実績に基づき、研究課題の遂行を進めた。特に、語用論的ストラテジーや談話構成などアジア諸語地域の多様な社会的・文化的特質を踏まえた適切な言語コミュニケーション能力測定方法を重点的に研究し試案を公開した。
国際的連携を強化しつつ研究成果は関係学会や国際集会(台湾師範大学)での発表を通じて問題提起をするとともに、台湾および中国における言語教育へのCEFR導入についての情報収集と意見交換ができた。加えてウェブサイト上での成果公開に努めた。
«The 4th International Workshop on Advanced Learning Sciences (IWALS-4 Taipei, 2017) »での発表(招待講演)
日時:2017(平成29)年7月10日
会場:台湾師範大学
発表タイトル:«Is CEFR applicable to Asian languages? - Proposals of necessary improvements from a socio-cultural point of view -» (英語)
発表者:Nobuo Tomimori, Tokyo University of Foreign studies
外国語教育学会での成果発表「TUFS言語モジュールを活用したアジア諸語の社会・文化的特質の指標化」は、紀要『外国語教育研究』No.20 (2017), pp.207-217. に掲載された。
2017(平成29)年9月26日開催の「言語教育(CEFR)国際ワークショップ ―CEFRの受容と適用可能性をめぐって―」の成果公開は、本報告書の第二部およびWebサイトで公開している。
総合的自己評価と総括
2015(平成27)年度は東京外国語大学語学研究所を拠点として、国際シンポジウムや国際ワークショップを前倒しに開催するなど当初の計画以上に順調に遂行された。アジア諸語教育に関わる各分担者はアジアの多様な社会・文化的コンテクストを通言語的枠組みの中に捉えるために必要となるコンテクスト分析、談話ストラテジーやポライトネスの表れ方など、語用論的研究を協働して推進し次年度の研究準備をすすめた。
2016(平成28)年度以降は研究成果を共有するために発信活動にも努力し、Webサイトを構築した。また、ミャンマー等の現地で言語教育研究者に本科研の活動内容を公開し聞き取り調査を行うことにより、CEFR受容の進捗状況を把握するとともに、アジア諸語の教育で現場教師と学習者が直面する言語・文化的諸問題の解決取り組みの方策を検討し成果を公開することができた。
国内調査では中等教育と大学教育との接続に関わる問題を先進的な複数のアジア諸語教育に取り組む長崎県教育委員会と県内離島の高等学校で聞き取り調査を行い、分析結果を公開した。
2017(平成29)年度は外国での成果発表や研究活動の集約としての国際ワークショップを開催するなど、研究成果を対外的にも発信し研究交流にも務めた。研究代表者富盛と研究参加者は協働して、年間数回の書面アンケートあるいは直接の聞き取り調査により、語用論的ストラテジーや談話構成、また欧米地域とは異なる言語行動やphaticな要素などアジア諸語の多様な社会的・文化的特質を分析的に把握した上で、CEFRの能力記述項目に反映するような指標抽出の試みを行なった。
3年間の研究期間の成果を国内外の関係学会・研究集会およびWeb上で公開したことで問題の喚起を図るなど、研究の進展は順調であったと評価している。
総括して、当初の目的と計画に従って課題研究の円滑な実施につとめることができ、研究活動は全体として順調に進展したといえる。