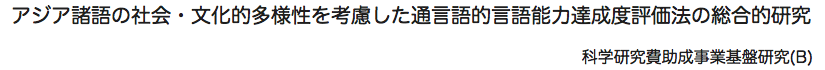研究課題と問題設定
研究課題と問題設定
ヨーロッパ連合(以下、EU)では、その将来を担う次世代にヨーロッパ市民意識と資質・能力の育成をはかるため一連の教育改革を進めている。とりわけ、EU域内学生のモビリティを担保し外国語教育改革の基盤をなす政策が「ヨーロッパ共通参照枠組み」(Common European Framework of Reference for Languages、以下 CEFR)であり、2003年にガイドラインが示されてから約15年を経て、その理論面・実践面の実績(行動中心複言語主義、コミュニケーションタスクと解決能力の育成など)は急速に進展し言語教育の現場そのものを変容させた。他方、ヨーロッパの言語的あるいは社会文化的に均質な土壌に育まれた言語コミュニケーションの同質性はそのままCEFRの基底概念に反映されている。
現在まで、日本語を含め非EU言語へのCEFRの適用可能性の先行的研究は十分ではなく、かつ、文字体系・音声・文法など言語類型的特徴の差異や社会・文化的ギャップを考慮した通言語的測定尺度としては成熟していない。我々にとって喫緊の課題は、非EU言語の教育現場にも適用可能な新たな評価方法の開発が重要であり、日本やアジア諸国の言語教育の当事者が研究活動を焦点化することで、EUの研究者がなしえない、より汎用性のある通言語的な共通枠組みを開発し、EUはじめ日本のみならず関係国際機関などに提案する可能性を拓くことができるのではないかと考える。
本研究の目的は、
第1に、アジア諸語を主たる対象とし、その社会・文化的多様性を考慮した言語コミュニケーション能力評価方法を研究することにより、より汎用性の高く通言語的かつ透明性の高い言語能力評価システムを研究する。
第2に、実施約15年を経たCEFRの再検証とEU内で進む社会・文化的コミュニケーション能力を勘案したCEFR改訂に関する最新動向を調査の上、本研究に活用し国際的に提案する。
第3に、外国語教育に関する高等教育と中等教育との接続や生涯教育への応用など、現代日本社会のニーズにも対応した成果を社会に還元することも研究の展望としてもっている。
なお、研究の分野・範囲を示すキーワードを記すと以下のとおりである。(順不同)
(1) 外国語教育 (2) 言語能力評価法 (3) CEFR (4) 通言語的透明性
(5) アジア諸語 (6) 社会・文化的特質 (7) 言語類型 (8) 異文化間コミュニケーション能力
(1) 言語教育におけるCEFRの位置づけと研究の意義:言語・民族・国境等を超えた広域の共同体であるヨーロッパ連合(以下、EU)では、その将来を担う次世代にヨーロッパ市民意識と資質・能力の育成をはかっている。近年、高等教育の抜本的改革「ボローニャ・プロセス」が進み、各国独自に培われてきた知的再生産を担う高等教育が標準化され変質しつつある中で、EU域内学生のモビリティを担保し外国語教育改革の基盤をなすものが、言語能力評価のための「ヨーロッパ共通参照枠組み」(Common European Framework of Reference for Languages、以下 CEFR)であり、その開発は2003年にガイドラインが示されたが、現在約10年を経てその理論面・実践面の実績(行動中心複言語主義、タスクと解決能力の育成など)は急速に進展し、言語教育の現場そのものを変容させたが、他方、ヨーロッパの言語文化の均質的な土壌に育まれた言語コミュニケーションの同質性はそのままCEFRの構成概念に反映されている。CEFRの世界化が進むに従い、日本語を含め非EU言語へのCEFRの適用可能性の先行的研究はされているものの、文字体系・音声・文法など言語類型的特徴の差異や社会・文化的ギャップのために未だ通言語的測定尺度としては確立されていない。喫緊の課題として、EUでは遅れている非EU言語の教育にも適用可能な新たな評価システムの開発が重要であり、日本やアジア諸国の言語教育の当事者がその点に研究活動を焦点化することで、より汎用性のある通言語的な共通枠組みを開発し、日本のみならずEUはじめ関係国際機関や学会などに提案する可能性が拓ける。
(2) 先行する研究活動の実績:研究代表者(富盛伸夫)はすでに1990年代から本課題にかかわるアジア諸語を含む多言語の対照言語研究に基づく言語教育研究グループを組織して活動を始め、平行して「外国語教育学会」で会長職にあった2004年以来、言語教育政策とCEFRに関わるシンポジウム「早期言語教育 -可能性と現状-」「検定試験と外国語教育」等を開催して研究交流を行い、本研究課題の企画に関する有益な示唆を得た。(学会紀要『外国語教育研究』12号, 2009年所収の「ヨーロッパ連合(EU)における高等教育改編と言語教育政策の問題点について」等を参照。)本研究の分担者の多くも、外国語教育学会他でEUの言語教育政策(CEFR及び日本の外国語教育への適用)に関する複数の研究発表を行っている。
代表者は2006年度より文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「拡大EU諸国における外国語教育政策とその実効性に関する総合的研究」を推進し、13名の研究参加者がEUにおける教育現場での聞き取り調査を行ってCEFRの実践上の問題点や実効性の研究を行い、その成果は研究集会と成果報告書とWebで公開した。
続いて本研究の代表者は2009年度より文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「EUおよび日本の高等教育における外国語教育政策と言語能力評価システムの総合的研究」を14名の言語教育の専門家とともに推進し、ボローニャ・プロセスが進行中のEUの大学等における言語教育の質的変容と新しい能力評価法の調査研究を実施して、成果をWeb上と刊行物で発信した。
2011年には東京外国語大学社会言語教育センターと共催で国際シンポジウム「高等教育における外国語教育の新たな展望 –CEFRの応用可能性をめぐって−」を、2013年には「言語教育と異文化教育」を開催、報告集を刊行してCEFRの再検討と文化間コミュニケーション教育の重要性を確認した。(http://www.tufs.ac.jp/common/wolsec/symposium.htmlを参照)
本申請時点で最終年度となる文部科学省科学研究費補助事業基盤研究(B)「アジア諸語を主たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」では13名の分担者が現地調査で得られた知見を元に定期研究会や学会で研究発表を行い順調に遂行されている。2014年3月には中間報告書(『アジア諸語を主たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究』研究プロジェクト中間報告書(2012-2013))を前半2年間の成果物として刊行したほか、欧米やアジア諸国からの研究者を講師にシンポジウムと講演会等が活発に行ない研究活動の実をあげている。(http://www.tufs.ac.jp/common/fs/ilr/ASIA_kaken/houkokusho.html)
(3) 本課題研究の着想と展開の経緯:先行する科研で行ったアジア諸国での調査では、現地研究者のCEFR導入に対する慎重な態度が強く見られた。理由はCEFRが自分の教えるアジアの言語教育には適合しないと考えるからだと判断した。2014年10月現在、東京外国語大学、神田外語大学、四天王寺大学、立命館アジア太平洋大学の留学生を含む学生約900名を対象に、EUのCEFRの能力記述に従って自己評価アンケートを実施し解析中である。EU諸語とアジア諸語を学ぶ学生との間には、CEFRで示す能力評価と学習進度との相関性が全く異なることがわかってきた。つまり、CEFRの設定する難易度の低いA1やA2がアジア諸語の多くにとっては相対的に高く、初・中級の学習進度に適応しないのである。音声、文字、文法、語彙等の習得進度の違いのみならず、さらに社会・文化的要因の強いことが確認された。アジア諸語を主な対象とする言語教育には、談話ストラテジー、語用論的理解、非言語的行動を含めた文化コミュニケーション能力の測定方法と学習プログラムの研究が必要であることがわかったため、現時点までの科研課題の範囲と目標を設定した。