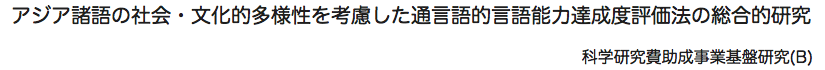2017年3月 刊行
「アジア諸語学習者におけるCEFR自己評価と社会・文化的コミュニケーション能力の測定指標の開発」
富盛伸夫(東京外国語大学、科研代表者)、
YI Yeong-il(東京外国語大学大学院修士課程)
【『アカデミック日本語能力到達基準の策定とその妥当性の検証ー成果報告書(2017)-』より転載】
1. 本研究の動機と背景
2. 本研究の目標と実施方法
3. 学習者アンケート調査(2014)の観察から(定量的分析」
4. アジア語圏の社会・文化的特質の学習者意識(直感的分析)
5. 社会・文化的コミュニケーション能力測定指標の開発に向けて
6. 考察と展望
2. 本研究の目標と実施方法
本研究はCEFRの非EU言語への適用可能性を検証することを目的としており、その問題設定は以下のとおりであった[8]。
(1) CEFRが適用範囲をEU域内の諸言語から、それ以外の言語類型に拡大するとき、どのような問題が生じるのか?
(2) 非EU言語地域には多様な社会的・文化的特質をもつ言語習慣があることを考慮するならば、CEFRの世界的拡大に際してどのような要素を考慮すべきか?
(3)非EU言語にも広く適用しうる、通言語的かつ透明性の高い妥当な言語能力測定尺度を構想しうるのか?あるいは、言語的特質に応じた個別的枠組みを想定すべきなのか?
本科研の研究課題の実行作業を通して、学習者アンケート調査などのデータをもとに現時点でのCEFRについて通言語的評価法としての有効性を再検討し、類型的特質の異なるアジア諸語の学習進度との相関を調べた上で、展望としては言語類型に応じた新たな能力記述項目の策定とCEFRレベルの再検証をする。
具体的には、研究データの検証作業(Validation)を3つの段階に分けている。
(1) 特にアジア諸語学習者に焦点をあててアンケート調査を行い、その結果を分析する「定量分析(Quantitative Analysis)」。2014年の東京外国語大学の学生を主とするCEFR自己評価アンケート調査がこの目的で企画・実施され、その結果の検証が、本稿を含め、すでに進行中であり、成果の一部が公開されている。
(2) 次に、言語学習者(学生)からの直接の声・意見の聴取を行う調査で、記述式の回答を収集し分析している。この「直感的分析(Intuitive Analysis)」は数値換算しにくいが、学習者の鋭い観察や指摘が本研究にとっては貴重な示唆となる。
(3) その上で、「定性分析(Qualitative Analysis)」といえる方法が、言語教育担当教員からの能力記述文についての、あるいは、アジア語圏の社会・文化的コミュニケーションに関わるコメントの総合的判断である。
本稿では、主に(2)「直感的分析」から(3)「定性分析」へとつなぐ研究の動向をまとめて論じてゆくことにする。
- [8]富盛伸夫, YI Yeong-il (2016)の記述を参照。本稿3章と4章の分析はこれに依る。