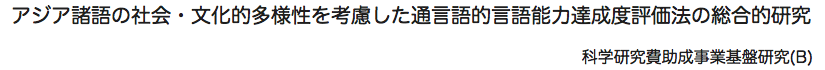2017年3月 刊行
「アジア諸語学習者におけるCEFR自己評価と社会・文化的コミュニケーション能力の測定指標の開発」
富盛伸夫(東京外国語大学、科研代表者[1])、
YI Yeong-il(東京外国語大学大学院修士課程)
【『アカデミック日本語能力到達基準の策定とその妥当性の検証ー成果報告書(2017)-』より転載】
1. 本研究の動機と背景
2. 本研究の目標と実施方法
3. 学習者アンケート調査(2014)の観察から(定量的分析」
4. アジア語圏の社会・文化的特質の学習者意識(直感的分析)
5. 社会・文化的コミュニケーション能力測定指標の開発に向けて
6. 考察と展望
1. 本研究の動機と背景
EUの言語政策のひとつとしてよく知られるCEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment、以下CEFR)は、日本を含む世界各国で急速に進む高等教育の質保証と認証基準の流れもあり、世界各地で適用が拡大されつつある。CEFR自体はEU統合の象徴的な教育改革(Socrates計画、Lingua計画に続く具体的な施策)の一環をなし、2001年に言語能力評価のための参照枠組みとして欧州評議会から正式に公布[2]され、約15年を経る現在、EUの言語教育現場に大きく影響を及ぼしてきた。
本稿執筆者を含む共同研究[3]ではこれまでに数年にわたり現地調査を行った結果、EU域内でCEFRが実践される過程で理念と現場の若干の齟齬を生みつつあるという観察と、ボローニャ・プロセス[4]の進行とともにCEFRの実質化が伴っているのかどうか、という問いかけが生まれている。さらに、本稿末尾に述べるようにEU内でCEFR自体の改編や見直しが提案される一方で、外へ向かうCEFRのグローバル化に伴う問題として、各国でのCEFRの導入にあたり言語教育政策的側面でいかなる波及的影響を及ぼすか、が注目されている。Parmenter and Byram (2010) は日本での受容の調査報告を受けて、CEFRが単なる言語能力をレベル評価するための簡便な測定尺度として導入される一面があることを指摘している[5]。
本稿の執筆者には、CEFRと並行して導入されつつあるGPA評価方法との関わりで、学習者・学生たちには、利用の仕方如何では深刻な能力評価方法として映る危険性が感じられてならない。とりわけ、CEFRが生まれ故郷であるEU地域の言語・文化・社会的特質を受け継ぐ以上、CEFRのアジア諸語への適用可能に際しては、非EU世界のそれとの隔たりの自覚が生まれつつある。さらに非EU諸国、特にアジア諸国でのCEFR導入について、アジアの諸言語には現在のCEFRをそのまま適用しうるのか、といった反発も見られる[6]。CEFRが世界的に拡大していく前提として、CEFRは世界各言語地域の多様な言語・社会・文化の実情に合わせて変容する可能性をもつか、EUローカルな体質から脱皮できるかどうかという、CEFR自体の可変性・柔軟性が問われているといえよう[7]。
本研究でははじめに、主に東京外国語大学で2014年に行った学習者アンケート調査の結果を出発点として、書記体系や音声組織・文法構造や談話ストラテジーが大きく異なるアジア諸語について学習者・学生の評価を言語類型上の特徴から再検し、続いて多様な言語・社会・文化的特質を勘案した新たな能力評価記述文策定のための指標の開発に向けた試みを報告する。
- [1]この発表および論考は科学研究費助成事業基盤研究(B) [50122643] 2015−2017年度「アジア諸語の社会・文化的多様性を考慮した通言語的言語能力達成度評価法の総合的研究」(研究代表者富盛伸夫)の成果の一部を公開するものである。
- [2] 参考文献リストの特に Council of Europe (2001) を参照。
- [3] 本発表に関わる共同研究は、先行する以下の科学研究費研究プロジェクトで遂行された。科学研究費助成事業基盤研究(B) 2012−2014年度「アジア諸語を主たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」(研究代表者富盛伸夫)。
- 科学研究費補助金基盤研究(B) 2009−2011年度「EUおよび日本の高等教育における外国語教育政策と言語能力評価システムの総合的研究」(研究代表者富盛伸夫)。
- 科学研究費補助金基盤研究(B)2006−2008年度「拡大EU諸国における外国語教育政策とその実効性に関する総合的研究」(研究代表者富盛伸夫)。
- [4] 富盛伸夫(2009)を参照。
- [5] 富盛伸夫(2014b)のpp. 63-72. を参照。
- [6] 各国高等教育機関への調査の一端が、富盛伸夫(2014a)、富盛伸夫(2015)所収の共同研究者の報告に掲載されている。
- [7] EU域内の非印欧語的類型をもつ言語、例えばハンガリー語への適用事例はSzirmai(2015)参照。