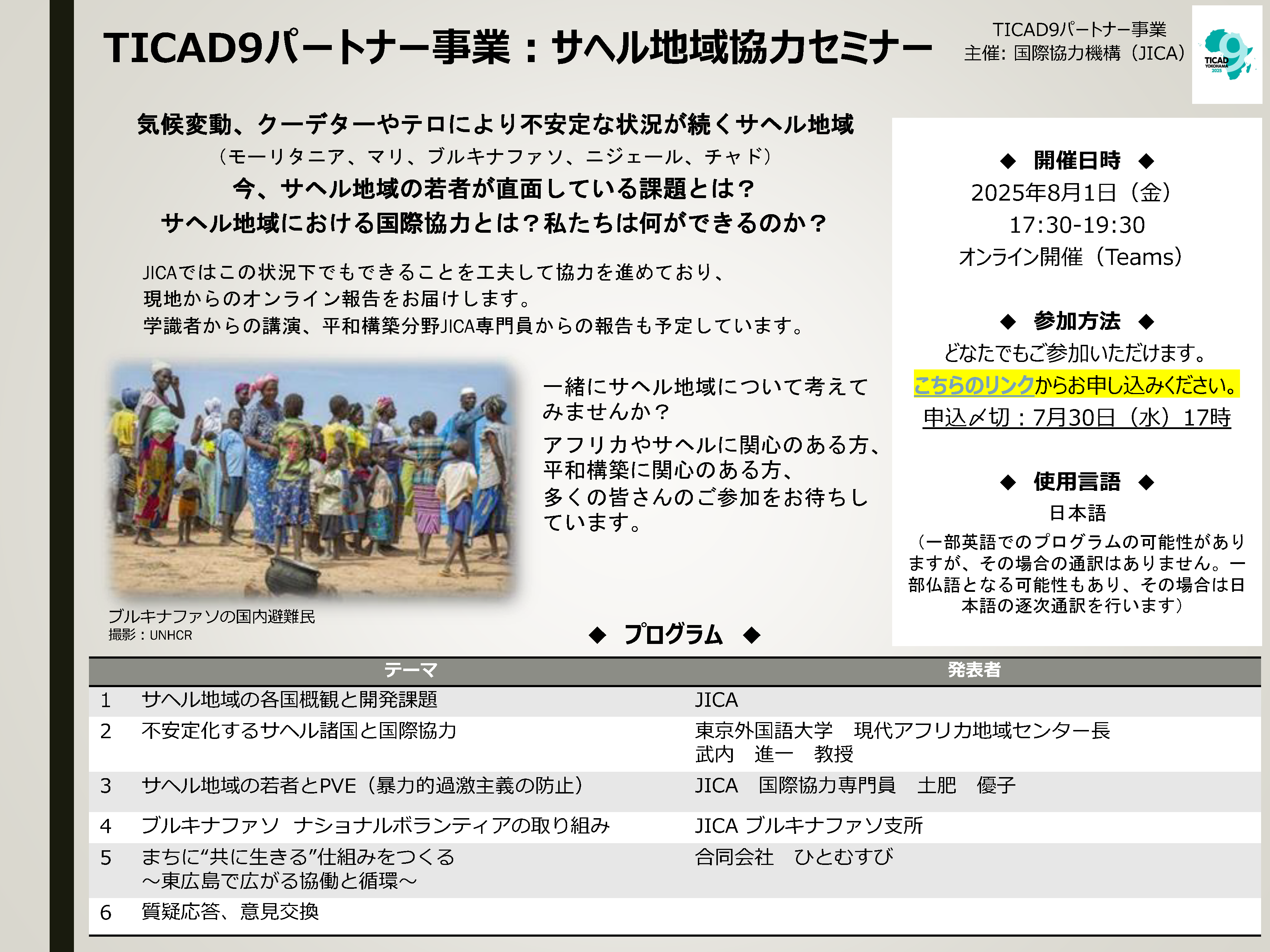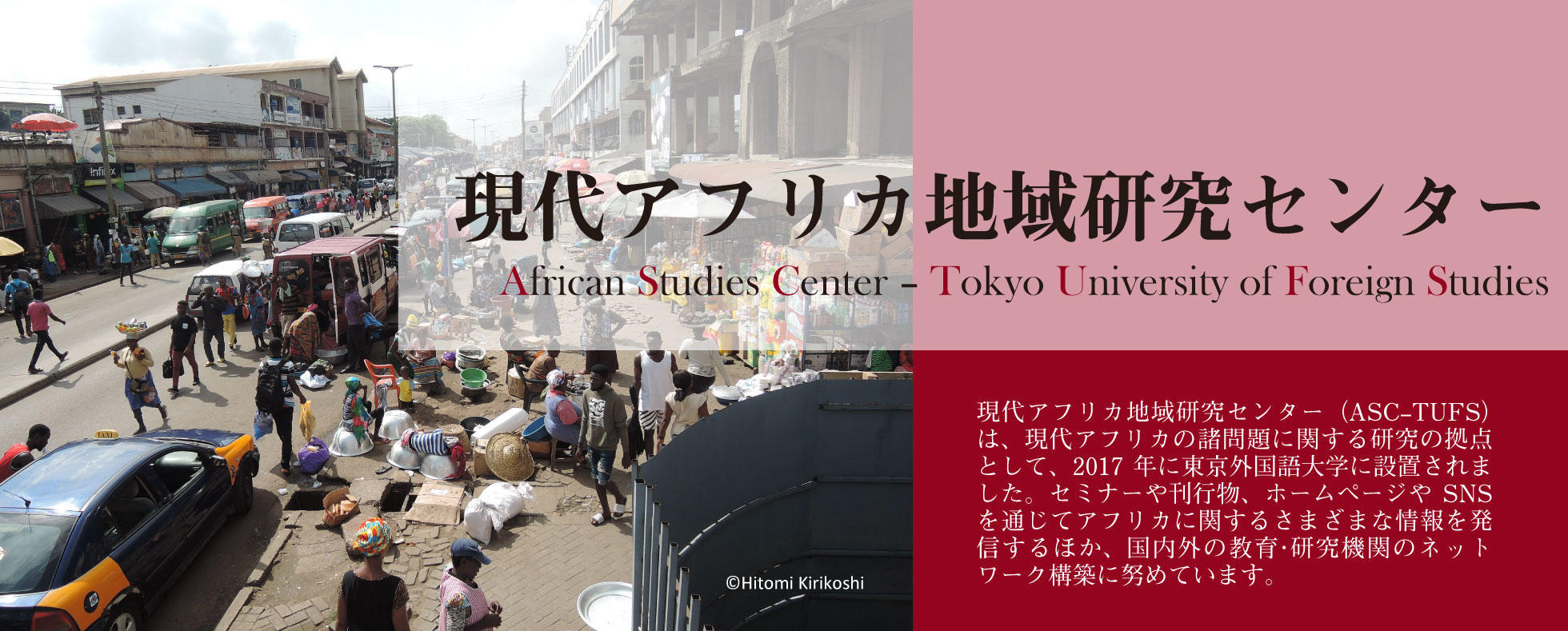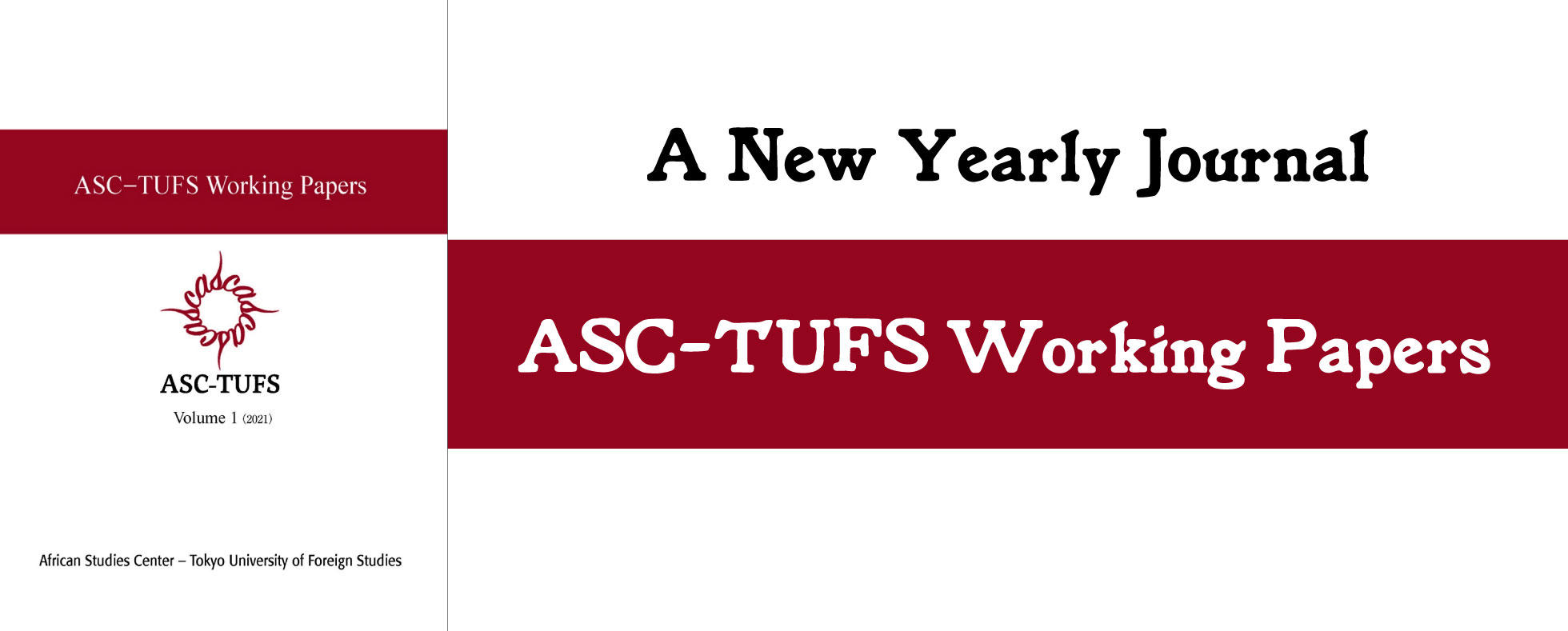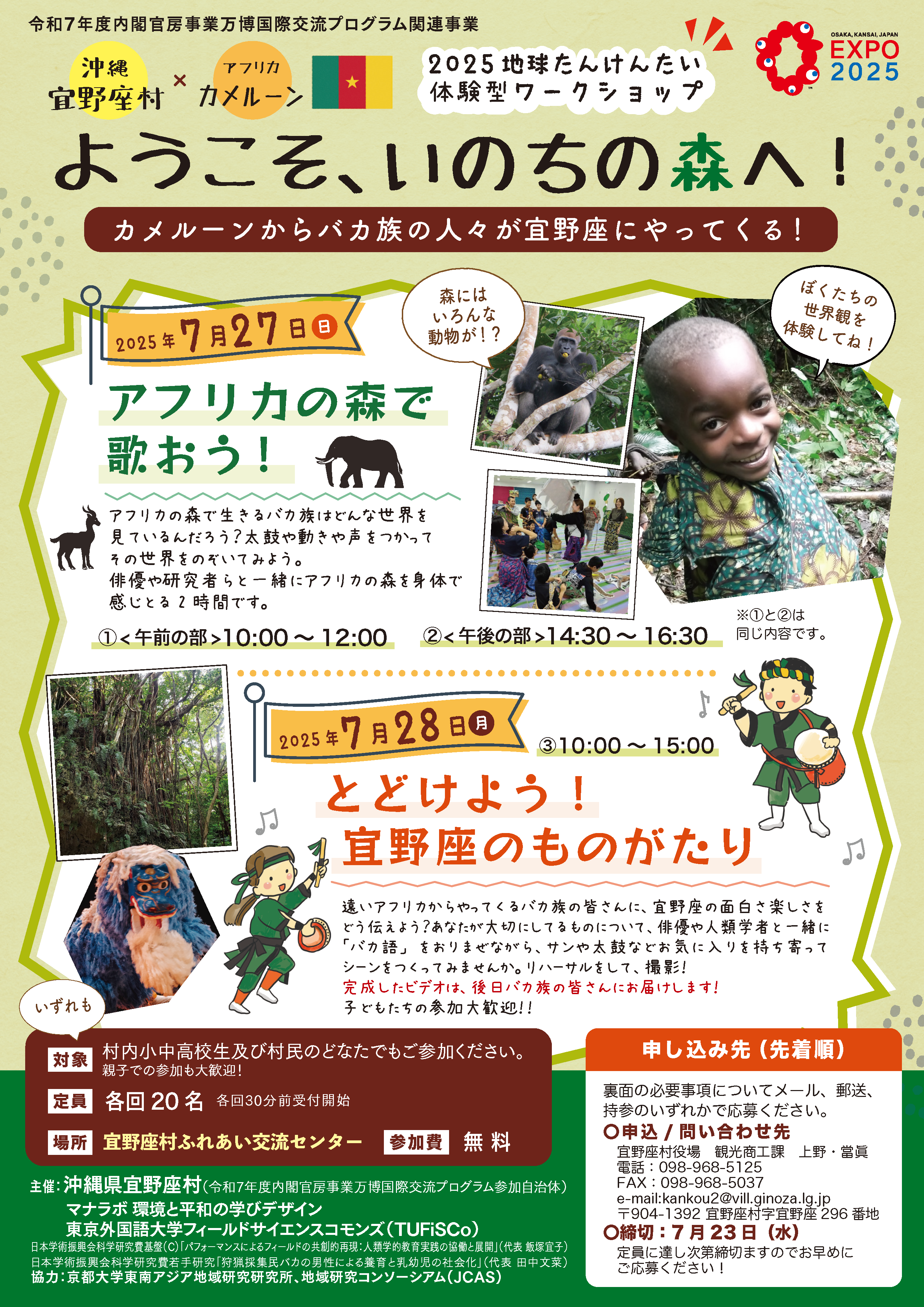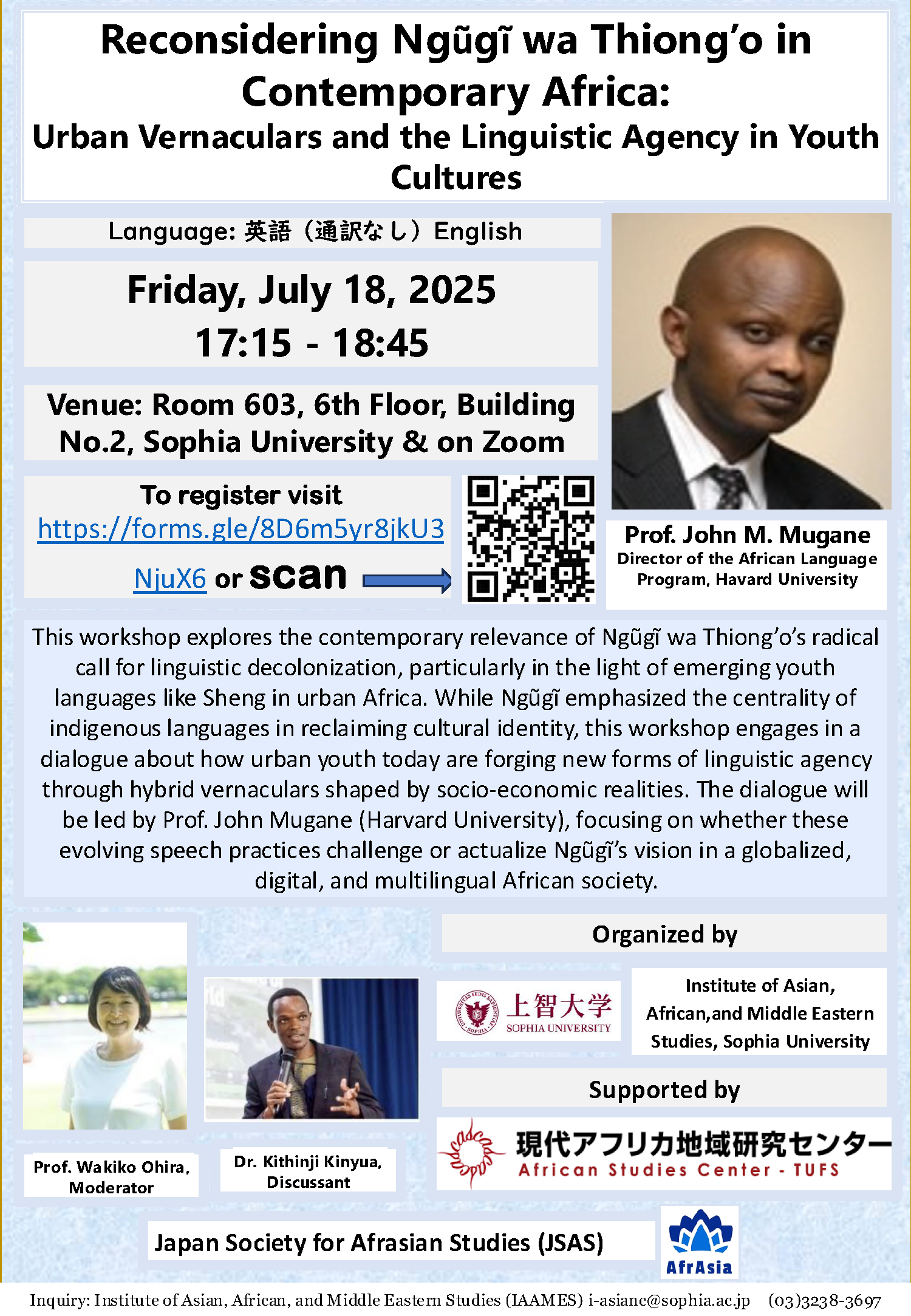【お知らせ】Scholarships for International African Students from PUR
〆切 2025年7月31日
[Only for International African Students living in Rwanda]This information has been provided by Protestant University Of Rwanda(PUR), TUFS partner institution under the academic exchange agreement.
------
We(PUR) are now sharing the call for scholarship applications for our Bachelor's Programme in Peacebuilding and Development (English programme). The scholarships are available to international (non-Rwandan) African students and refugee students currently residing in Rwanda.
The application deadline is 31 July.
Scholarships for International African Students to Study Peacebuilding and Development
Application Deadline: 31 July 2025
We(PUR) are pleased to announce the availability of scholarships for five qualified African international students who wish to pursue the 3-year Honours Bachelor's degree in Peacebuilding and Development. (Programme description available here: https://tinyurl.com/3d8e4x4r). Successful applicants will be expected to join the programme at the start of the new academic year in mid-September 2025.
This scholarship programme is designed to provide young people from African countries--particularly, though not exclusively, those in the Great Lakes Region--with high-quality training in peacebuilding and development. The goal is to foster a cross-border network of peacebuilders.
Profile_DPCS2025.pdf
Scholarship Benefits
Recipients of the scholarship will be exempt from payment of:
· Annual registration fees
· Tuition fees for three years
· Internship and dissertation fees
· In addition, they will be entitled to basic health insurance coverage.
Please note: Travel and living expenses in Huye are not covered by PUR and must be borne by the student or their sponsor. The estimated minimum on-campus living cost for one academic year is approximately USD 500.
Application Requirements
Eligible applicants must:
· Be no older than 30 years of age
· Have completed secondary education with at least two principal passes or equivalent
· Demonstrate a proven commitment to peace and development-related activities
Application Documents
Applicants must submit all of the following documents, compiled into one PDF file:
· Completed PUR application form (Download from: https://tinyurl.com/3d8e4x4r)
· Notarised copy of national examination certificate
· Copies of secondary school transcripts (last 3 years)
· Copies of other training certificates/diplomas (if applicable)
· Copy of passport or National ID
· Motivation letter written in English by the applicant
· Two recommendation letters written in English or French
Submission
Please send your complete application and any inquiries to: peacescholar@pur.ac.rw
お知らせ