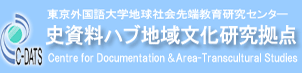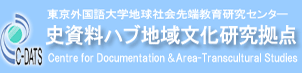|
|
|
|
研究プロジェクト/総括班シンポジウム/教育活動/総括班会議報告
|
|
|
|
|
| 日本 |
|
デジタルライブラリー正式公開
Digital Library Network System for C-DATS (Dilins)
電子図書館プロジェクトの概要について |
|
|
|
日印協会 2003年10月20日〜
-日印関係史研究のための雑誌マイクロフィルム化完了
報告:松本脩作 (本COEアドバイザー)
-日印協会所蔵の戦中期南アジアに関する資料の保存・公開について
報告:松本脩作(本COEアドバイザー)
|
|
|
|
インドワラ会 2004年6月21日〜
-「インドワラ会」関係資料、利用が可能に
報告:松本脩作 (本COEアドバイザー)
|
|
|
湊十分所文書の調査、史料集編纂作業
- 在地固有文書班」活動報告
|
|
|
| イギリス |
|
School of Oriental and African Studies (University of London) 2003年6月10日〜
- SOAS/TUFS Postgraduate Symposium (20 and 21 February, 2006)
|
| インド |
|
Institute of Chinese Studies at the Centre for the Study of Developing Societies, Delhi
- Postgraduate Students' Workshop (28-29 January, 2005)
|
|
|
|
中国
|
|
徽州文書(中国)整理保存、目録化事業
- 「在地固有文書班」活動報告
|
モンゴル
|
|
National Archives of Mongolia
モンゴル国立中央文書館所蔵のデジタル化と目録化
- 「在地固有文書班」活動報告 |
|
インドネシア
|
|
Nanggroe Aceh Darussalam Provincial Museum
2006年8月4日〜
史資料を中心とするアチェ文化財復興支援
- アチェ文化財復興支援室活動報告
- 東京外国語大学アチェ文化財復興支援室
『パレンバン写本カタログ』の講評会(2006年7月28日、インドネシア写本学会国際シンポジウム)
- 「在地固有文書班」活動報告
|
|
|
Hasanuddin University
日本占領下の南スラウェシに関するインタビュー記録のデジタル化
- 「オーラル・アーカイヴ班」活動報告参照
|
ベトナム
|
|
École Française d'Extrême-Orient 2006年8月2日〜
パーンドゥランガ・チャンパー王家文書デジタル化並びに目録作成事業
- 「在地固有文書班」活動報告
|
カンボジア
|
|
National Archives of Cambodia
カンボジア閣僚会議議事録(1897−1937)のマイクロフィルム化
- 保存共有事業の対象文書の紹介(新着史資料「カンボジア公文書館マニュスクリプト」)
- 「在地固有文書班」活動報告
|
ミャンマー
|
|
Universities Historical Research Centre, Myanmar
2003年5月21日〜
折りたたみ写本を中心とするビルマ史資料の保存・調査研究
- 保存共有事業の対象文書の紹介(新着史資料「ビルマ(ミャンマー)折畳み写本」)
- The International Symposium on Preservation of Myanmar Traditional Manuscripts を開催 (ミャンマー宗教省と共催)
会場: 国際仏教振興大学(ヤンゴン)
- 「在地地固有文書班」活動報告参照
|
バングラデシュ
|
|
Muktijuddha Gabeshna Trust , Bangladesh
- バングラデシュ独立戦争に関するオーラル・ヒストリー
報告:佐藤宏(本COEアドバイザー)
|
インド
|
|
Centre for Women's Development, New Delhi
2005年4月25日〜
インドの女性写真のデジタル化
- 「表象文化資料班」活動報告
|
トルコ
|
|
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey 2003年8月25日〜
旧Hakkı Tarık Us Library所蔵資料の保存・共有
- 「印刷媒体資料班」活動報告参照
|
モロッコ
|
|
La Biblioteca M. Dazud de Tetuán 2006年11月6日〜
ダーウード図書館所蔵アラビア語、欧米語資料のデジタル化
- 「印刷媒体資料班」活動報告参照
|
|
|
2006年
12月16日
|
国際シンポジウム
「アジア・アフリカ史資料学の現在と地域文化研究」
| 写真 (クリックで拡大) |
 |
 |
趣旨説明と活動報告: 藤井 毅(本学教授、拠点リーダー)
第1セッション テーマ「文書修復の現在」
司会: 斎藤照子 (本学教授)
• 講演者1: 安江明夫(国立国会図書館顧問)「地域研究と資料保存――保存管理者の視点――」
• 講演者2: 青山 亨 (本学教授)「アチェ文化財復興支援室の活動について」
第2セッション テーマ「アジアにおけるアーカイブズの構築」
司会: 二木博史 (本学教授)
• 報告者1: ウー・トーカウン(U THAW KAUNG, ミャンマー大学中央図書館元館長、福岡アジア文化賞2005年度学術賞受賞者)「失われた宝石の再発見――ミャンマー貝葉文書、折畳み写本の収集と保存――」[英語]
• 報告者2: デンベレル・ウルズィーバータル(Demberel ULZIIBAATAR, モンゴル国家文書管理局長)「モンゴルにおける文書館の建設と発展」[モンゴル語]
• コメンテーター: 斎藤照子(本学教授)、宮脇淳子(本学非常勤講師、本COEアドヴァイザー)
第3セッション パネルディスカッション テーマ「デジタル化資料はオリジナル資料をこえられるか」
座長: 臼井佐知子(本学教授)
参加者: 高松洋一(本COEポスト・ドクター研究員)、新江利彦(同)、井上聡(東京大学史料編纂所助手)、相原佳之(東京大学・博士課程)
第4セッション テーマ「伝統的図書館とデジタル図書館」
司会: 新井政美(本学教授)
• 報告者1: イスケンデル・パラ(Iskender PALA, イスタンブル文化大学教授)「トルコの文化および歴史に関する文字史料を図書館で利用するという問題」 [トルコ語]
• 報告者2: ハスナー・ダーウード(Hasna DAOUD, モロッコ・ダーウード図書館館長)「テトワンの私的図書館が持つ文化的財産――ダーウード図書館を例として」 [アラビア語][佐藤健太郎氏が代読]
• 報告者3: 加藤さつき(本学附属図書館情報図書館課情報サービス係長)「C-DATS・電子図書館プロジェクト――Dilinsにおける史資料の多言語目録構築とデジタル化を中心に」
• コメンテーター: 石川武敏(国立国会図書館関西館資料部アジア情報課長)、松本脩作(大東文化大学非常勤講師、本COEアドヴァイザー)
第5セッション テーマ「オーラル・アーカイヴの可能性」
司会: 野本京子(本学教授)
• 報告者1: シュクマル・ビッシャス(Sukumar BISWAS, バングラデシュ解放戦争研究センター編集主幹)「バングラデシュ解放戦争史研究とオーラル資料の役割」(英語)
• 報告者2: A・ラシド・アスバ(A. RASYID Asba, インドネシア・ハサヌディン大学地域多元文化研究センター長)「南スラウェシにおける日本占領――インドネシアにおけるオーラル・ヒストリー研究――」(インドネシア語)
• コメンテーター: 佐藤 宏(東京外国語大学非常勤講師, 本学COEアドヴァイザー),山口裕子(吉備国際大学非常勤講師)
第6セッション 総括討論
司会: 藤井 毅
参加者: 外国からの参加者、各班代表者
シンポジウムの報告
ジャーナル9号掲載のシンポジウムペーパーはこちらより
|
2006年11月27日
|
若手研究者シンポジウム(イスタンブル)
「日本における中東研究・多文化研究の最前線」Middle East and Multi-Cultural Studies in Japan: The State of the Art
Photograph (click to expand)
|
 |
 |
Opening Remarks by Prof. Masami Arai
[1st Session]
• Masako Matsui (Lecturer, Keio University, Tokyo)"Capitulations and Tariff Questions in the Early Nineteenth Century"
• Fumiko Sawae (Lecturer, Tokyo University of Foreign Studies) "Islamist Women and Public Sphere in Turkey"
• Commentators:
Prof. ?evket Pamuk (Bo?azi?i University)
Prof. Metin Heper (Bilkent University)
[2nd Session]
• Housam Darwisheh (Ph.D. Candidate, Tokyo University of Foreign Studies) "The Parliamentary Experience of the Muslim Brotherhood in Egypt"
• Taku Osoegawa (Researcher, The Institute of Energy Economics, Tokyo) "How did the Lebanese Government Deal with the Crisis in Lebanon?"
• Commentators:
Prof. Abdul-Rahim Abu-Husayn (American University of Beirut)
Prof. Hilal Khashan (American University of Beirut)
[3rd Session]
• Takayuki Nakamura (Ph.D. Candidate, Tokyo University of Foreign Studies) "Essai sur la communication creole." (English translation will be provided)
• Commentators:
Prof. Jale Parla (Istanbul Bilgi University)
Prof. Ayhan Kaya (Istanbul Bilgi University)
Lecture
• Prof. Osamu Nishitani (Tokyo University of Foreign Studies) "Deux notions occidentales de l'Humanite : Anthropos et Humanitas"(English translation will be provided)
Concluding Remarks and Thanks by Prof. Hidemitsu Kuroki
シンポジウムの報告 報告者:新井政美(本学教授)
|
2006年
2月20日〜21日
|
若手研究者シンポジウム(ロンドン・リエゾンオフィス)
"SOAS/TUFS Postgraduate Symposium"
cosponsored by Centre of South East Asian Studies (SOAS), JSPS London Office and C-DATS(TUFS)
Conference Announcements
Dr Justin Watkins, Chair SOAS Centre of South East Asian Studies and workshop co-organiser
Welcome: Prof Peter Robb, Pro-Director, SOAS
Prof Koji MIYAZAKI, Vice-President of TUFS
Prof Masaru OSANAI, Director JSPS London Office
• SHIOYA Momo (TUFS) Rituals and Social Relations in Java: A Case Study of Gossip and Conflict.
• Dorothea SCHAEFTER (SOAS)
The Return of Indonesian Exile Writing: Writing in Exile during the New Order (1965-1998) and its return after 1998.
• TAKASE Nobuaki (SOAS)Mustsu Munemitsu: British Influence on Japanese State-Building in the Nineteenth Century.
•YANG Ikmo (TUFS)
The Tokugawa Shogunate's Daimyo Kaieki (attainder): Based on the 'Bakufu Nikki'.
• NAKAGAWA Tamiko (SOAS)
Reading Late Edo Erotic Prints.
• SHINE Toshihiko (TUFS)
Resettlement Programs in Vietnam's Central Highlands: Current Status and Problems.
• Julian BROWN (SOAS)
Down in the Basement: Cham Art in Context.
• HAYASHI Makiko (SOAS)
Constructing the Legal Profession in Meiji Japan.
•MA Jing (TUFS)
Study of Economics Magazines in the Later Stages of the Meiji Era: Using Jitsugyo no Nihon as an Illustration.
SOAS/TUFS Symposium Public Lecture
• Professor Ben ARPS (University of Leiden)
Propaganda on and off the dance-floor: theorectical considerations and a Javanese case.
• Prof Masaru OSANAI (JSPS London Office)
JSPS Briefing
• CHU Xuan Giao (TUFS)Methods of Historical Anthropology and the Field of Japan.
• Tullio LOBETTI (SOAS)
Personal and Social Dimensions of the Akinomine Practice on Haguro Mountain.
• YOO Jongshin (TUFS)
The Spread of Otogibanashi in Modern Japan: With Focus on Otogi Recitation.
• May JURILLA (SOAS)
Entertainment after the war: Aliwan and the Tagalog novel.
• Mulaika HIJJAS (SOAS)
Reading the Romantic Syair: Women's Popular Literature in Nineteenth-Century Riau.
• Sarah HICKS (SOAS)
Swinging between traditions: tracing the origins and menaings of narrative motifs in the traditional Malay romantic poem Syair Selindung Delima.
•Francesca Di MARCO (SOAS)
A Society in Transition: Postwar Japan and Suicide's Evolution From a Ritual Act to a Spectacular Performance.
• HSIEH Chia-ling (TUFS)
The Part-Time Labour in Japan: Through the Eyes of a Taiwanese Woman.
• Duncan ADAMS (SOAS)
Resisting Analysis: Sexual Desire in Mishima Yukio's Forbidden Colours.
• Thu NANDAR (TUFS)
The Role of Witnesses in Thet-Kayit Contracts in Early Modern Myanmar.
• SAITO Ayako (TUFS)
The Concept of Citizins and Non-Indigenous Residents under the Ne Win Regime: From the 1982 Burma Citizenship Law and Related Materials.
Concluding Remarks and Thanks
SOASのページへのリンク
シンポジウムの各報告は「史資料ハブ地域文化研究拠点」研究叢書
Postgraduate Symposium, London, 20-21 Feburary 2006 : proceedings of the SOAS/TUFS / edited by Justin Watkins and Masami Arai, 2006.として出版されました。 出版物の一覧はこちら
|
2005年
1月28日〜29日
|
日印共催ワークショップ(デリー・リエゾンオフィス)
"The India-Japan Research Scholars Workshop"
1月28日
Session I. Chair: V.Ramalakshmi, DU
Takasu Yumiko: A Study of the Priestesses (noro) in the Amami Islands from the 17- 19th Century
Discussant: Kum Kum Roy, JNU
Session II. Chair: V.Ramalakshmi,
Debashish Chaudhuri: Separatism in China’s Xinjiang
Session III. Chair: Srimati Chakrabarti, D.U.
Yang Sunyoung: The Reform Movement against Licensed Prostitution in Modern Japan: The Case of the Japanese Women's Christian Temperance Movement
Discussant; Brij Tankha, DU
Session IV. Chair: Brij Tankha
Dharitri Chakravartty: State Education Policy and the Ainu in Modern Japan
Arfina Haokip: Manipur and the I.N.A’s Imphal Campaign
1月29日
Session I. Chair: Rajni Palriwala
Ko Mijung : Family (Iye) and Gender in Early Modern Japanese Society
Discussant: Tanika Sarkar, JNU
Session II Chair: Tanika Sarkar
Lakshmi Arya: A Rape Case in the Mysore Court in the 19th Century
Session III. Chair: Brij Tankha
Han Junga: ‘Modernisation’ in Okinawa through the Reform of Women's Manners and Customs
Discussant: Rajni Palriwala, DU
Session IV. Chair: Alka Acharya
Oshima Fumi: Islam and Nationalism in Contemporary Turkey: The “Turkish-Islamic Synthesis” and the Islamic Policy of the Military Regime (1980-1983)
Discussant: Muhammad Mujeeb, Jamia Millia Islamia University
Session V Chair:
Mori Shintaro: Migrancy, Nationalism and Prophecy in Jubran Khalil Jubran
Discussant: Noman Khan, DU
Session VI. Chair: Suresh Sharma, CSDS
Special Lecture by Prof. Mushirul Hasan, Vice-Chancellor Jamia Millia Islamia University: Islam and Modernisation
- 「リエゾンオフィスにおける活動−大学院生による研究報告会−」
報告:吉田ゆり子(本学教授)
シンポジウムの各報告は「史資料ハブ地域文化研究拠点」研究叢書
Debating the past : conference of research scholars from Japan and India / edited by Brij Tankha, Toshie Awaya, Yuriko Yoshida, 2005. として出版されました。 出版物の一覧はこちら
|
2003年
12月19日
 |
国際シンポジウム
Creating an Archive Today
Decisions, Uses, Documentation
12月19日(金)
第1セッション アーカイヴの創造 Creating the Archive
• "Amalgam and anomaly: The case of the India Office Records"
グレアム・ショウ (英国図書館東洋・インド省コレクション 理事)
• 「記憶の破壊から記憶の再生へ:アジアにおけるアーカイブズ形成の課題」
安藤正人(国文学研究資料館/総合研究大学院 教授)
• "Education & memory: School Heritage Galleries in Singapore"
ウマー・デーヴィー (前・シンガポール国家遺産評議会 遺産開発部 副代表)
第2セッション 非収奪型ネットワークの形成 Creating Non-Exploitative Networks
• "Shared patrimony: An archival Double Entendre"
ジェームズ・ナイ(シカゴ大学 南アジア言語・地域研究センター 代表 / 南アジア専門司書)
• "Scholarly research, library collections, and the rise of digital information : Three decades of troubled history"
デイヴィッド・メイガー(コロンビア大学図書館 地域研究部長 / 南・東南アジア専門司書)
• "Oral history in Indonesia: The case of the 1965 massacre"
アスフィ・ワルマン・アダム(インドネシア科学研究所)
12月19日(金)
第3セッション 「新しい」歴史の可能性 Creating (New) Histories
• "Another history, another view: Nineteenth-century Javanese Islamic didactic texts"
菅原由美 (本COEフェロー)
• "History without archives: On the possibility of writing Thai social history before the nineteenth century"
ロレイン・ゲーシック (ネブラスカ大学 助教授)
• "Courts, ship-rolls and letters: Reflections of the Indian labour diaspora"
クリスピン・ベイツ (エディンバラ大学 講師)
• "After the record: Reflections of an Indian historian"
シャーヒド・アミーン (デリー大学 教授)
開催趣旨 (PDF) / 報告要旨(PDF)
シンポジウムの各報告は「史資料ハブ地域文化研究拠点」研究叢書
Creating an archive today / edited by Toshie Awaya, 2005.
として出版されました。出版物の一覧はこちら
|
|
|
|
2003年
10月25日〜26日
 |
国際シンポジウム
脱帝国と多言語化社会のゆくえ―アジア・アフリカの言語問題を考える― Post-Empire and Multilingual Societies in Asia and Africa
大会趣旨説明: 藤井毅(東京外国語大学) ・ 原聖(女子美術大学)
司会: 山下仁(大阪大学)
基調講演
•サイド・アフメド・モハメド・ハーミス Said Ahmed Mohamed KHAMIS (ドイツ・バイロイト大学アフリカ言語・文学科)
「Ukuzaji wa Lunga ya Kiswahili Baada ya Uhuru Tanzania (独立後タンザニアにおけるスワヒリ語の育成)」 使用言語:スワヒリ語、通訳: 竹村景子(大阪外国語大学)
第1セッション「東南アジアの脱帝国化と多言語性」
司会: 渡邊日日(東京大学)
• A.B.シャムスル A.B. SHAMSUL(マレーシア・ナショナル大学マレー世界文明研究所)
「『多くの意欲的民族、ひとつの国語』、マレーシアにおける民族形成と言語問題」 使用言語:英語、通訳・高野さやか(東京大学大学院博士後期課程)
• 陳培豊(台湾・成功大学)
「近代臺灣的兩個国語『同化』政策 (近代臺灣における二つの国語同化政策)」 使用言語:臺灣語、通訳・中川仁(明海大学)
• コメント1: 藤井(宮西)久美子(宮崎大学)
• コメント2: アラム・バクティアル Alam BACHTIAR (インドネシア大学日本研究センター所長)
• コメント3: 名和克郎(東京大学)
第2セッション「帝国の言語政策、その歴史的検証」
司会: 土屋礼子(大阪市立大学)
• 永原陽子(東京外国語大学)
「ドイツ帝国のアフリカ植民地支配と言語問題」
• 砂野幸稔(熊本県立大学)
「フランス植民地帝国とセネガルの諸言語」
• コメント1: 藤井毅(東京外国語大学)
• コメント2: 安田敏朗(一橋大学)
第3セッション「アフリカの脱帝国と多言語性」
司会: 定松文(広島国際学院大学)
• 米田信子(大阪女学院短期大学)
「ナミビアの言語問題」
• エルンスト・コツェー Ernst KOTZ? (南アフリカ・ポートエリザベス大学)
「南アフリカの多言語公用語の意義」 使用言語:アフリカーンス語、通訳: 桜井隆(明海大学)
• ママドゥ・シッセ Mamadou CISS? (ダカール・シェク・アンタ・ジョップ大学言語学科)
「Langues et politique linguistique au S?n?gal (セネガルの諸言語と言語政策)」 使用言語:フランス語、通訳: 砂野幸稔(熊本県立大学)
総合討論
司会: 原聖(女子美術大学) ・ 松村一登(東京大学)
シンポジウムの各報告は「史資料ハブ地域文化研究拠点」研究叢書
脱帝国と多言語化社会のゆくえ : アジア・アフリカの言語問題を考える / 21世紀COE史資料ハブ地域文化研究拠点・史資料総括班+多言語社会研究会編, 2004. として出版されました。出版物の一覧はこちら
|
2003年
10月11日
〜11月15日
 |
連続セミナー
Identiry, Strife, Community/Nation
講師: アニル・セーティー (Anil Sethi, Ph.D.)
場所: 東京外国語大学本郷サテライト3階セミナー室
開講日程:
• 第1回 10/11(土)
"Hindu Water, Muslim Water": Syncretism, Commensality and Community in Late Nineteenth and Early Twentieth Century Punjab
• 第2回 10/18(土)
Serving the Panth: Sikh Publicists and the Sikh Past, c.1880-1920
• 第3回 11/01(土)
A Momentous Marker: the Partition of India Revisited
• 第4回 11/08(土)
The Tinder and the Spark: the Vexed Historiography of Communalism
• 第5回 11/15(土)
The Contemporaneous Ascendancy of Religious / Ethnic Nationalisms: Whither Civic Nationalism?
|
2003年
1月21日更新
 |
基調シンポジウム
アジア・アフリカ地域研究と史資料:
現状と課題〜研究者・図書館・文書館のネットワーク形成に向けて〜
•藤井毅(拠点リーダー)
「基調スピーチ」
• 安藤正人(国文学研究資料館・教授)
「アジア研究とアーカイヴズ:日本における現状と課題」
• 北村由美(京都大学東南アジア研究センター資料部図書室・助手)
「東南アジア研究センターにおける資料収集活動」
• 松本脩作(大東大学非常勤講師・COEフェロー)
「日本におけるアジア地域研究関係史資料とネットワーク」
•コメンテイター:斎藤照子(東京外国語大学外国語学部・教授)、内島秀樹(東京外国語大学図書館専門員)
全体討論
|
|
|
|
|
若手研究者研究助成金
本COE では、本学大学院地域文化研究科博士後記課程学生を対象として、年間5 名程度に対して研究助成金を支給している。平成14年度〜18年度に交付された研究は、以下のとおりである。
平成14(2002)年度助成金受給者及び研究課題
• 井口由布 「マレーシアにおける国民的”主体”の形成について」
• 友常勉 「皮革産業の<近代化>とマイノリティの移住行動について:日本、北米、印度における19/20世紀の諸島の近代皮革産業を対象として」
• 足立享祐 「植民地支配のイデオロギーと在地語コミュニケーション(植民地支配下での在地語出版物の動態に関する基礎研究;19世紀マラーティー語圏を中心として)」
• 金恵媛 「高齢期の親子間の支援関係にみる世代的特性;川崎市在住の「在日」高齢者及びその子世代に対する事例調査を通じて」
• 金成蘭 「ベトナム社会主義建設過程に於ける宣伝活動:ベトナム共産党紙『ニャンザン』を中心に」
• Purna Ratna Shakhya 「チベット−ネパール貿易について」
• 高村加珠恵 「”差異”の消費:タイ、マレーシア国境に於けるチャイニーズの視点から」
平成15(2003)年度助成金受給者及び研究課題
• 友常勉 「移民マイノリティ労働と皮革関連産業:日本、北米における皮革関連産業の比較研究」
• 高村加珠恵 「共有される空間の”記憶”:タイ、マレーシア国境におけるチャイニーズの視点から」
• 伊藤寛了 「オスマン語定期刊行物の収集:オスマン帝国末期からトルコ共和国初期におけるイスラームを巡る議論の解明に向けて」
• 井口由布 「マレーシアにおける国民的”主体”の形成について」
平成16(2004)年度助成金受給者及び研究課題
• 窪田道夫 「中国における外国人医療−市場化の拡大と技術的・文化的ハードルの存在−」
• フスレ(呼斯勒) 「内モンゴルに対する中国共産党・国民党の政策(1945〜49年)」
• 楊善英 「関東大震災と廃娼運動―日本キリスト教婦人矯風会の活動を中心に」
• Chu Xuan Giao(チュ・スワン・ザオ) 「民間信仰と近代―九州の一地方の事例から―」
• Thu Nandar 「コンバゥン王朝後期におけるメイッティラー地方の農村社会関係―農地訴訟の事例を通して」
• リンチン 「内モンゴルにおける中国共産党の極左政策―対モンゴル人政策を中心に―」
• 梁益模 「徳川政権の大名政策―改易政策を中心に―」
• 趙正圭 「明治天皇地方巡幸研究(六大巡幸を中心に)」
• 伊藤寛了 「トルコ共和国初期における「イスラーム復興」の思想的側面の解明:1940年代後半を中心に」
• 高須由美子 「徳之島手々村の神女祭祀組織―17世紀〜19世紀を中心として」
• 野辺優子 「ベトナム映画・映像に関する資料収集」
平成17(2005)年度助成金受給者及び研究課題
• 仁欽 「1950〜70年代の内モンゴルにおける民族政策に関する研究−漢人移民に対する政策を中心に−」
• サイジラホ 「内モンゴル東部における民間の治療文化の研究」
• 村田はるせ 「アフリカ文学(フランス語)、人種の異なるカップルについての表現方法の変遷」
• ナラン 「内モンゴル草原砂漠化に関する生態人類学的考察」
• 中村隆之 「マルチニックにおけるクレオール・アイデンティティの現在」
• 窪田道夫 「中国の医療制改革」
• ガンバガナ 「日本の対内モンゴル政策と内モンゴル人の対応について(1937-1945年)−モンゴル自治邦を中心に−」
• 柳善英 「日本キリスト教婦人矯風会と廃娼運動」
• 斎藤紋子 「『バマー・ムスリム』−ビルマ人仏教徒中心の社会における創造された『民族』−」
• 藤作健一 「国際要因としてのEUと中国の政治経済体制の変容」
平成18(2006)年度助成金受給者及び研究課題
• 窪田道夫 「中国の医療制度改革−市場の失敗とセーフティネット−」
• 関本紀子 「フランス植民地期におけるベトナムの交通の発展とそれに伴う社会・経済的影響」
• 小田原琳 「自由主義期イタリア『南部問題』論に見る社会認識パラダイム−イギリス人ジャーナリストジェシー・ホワイト=マーリオの仕事を手がかりに−」
• 浅井万友美 「チベット近代史における仏教」
• 柳宗伸 「文化運動としての御伽噺に関する研究−大正・昭和期の柳田国男の『昔話』構築過程におけるお伽噺の果たした役割の実証的考察を中心に−」
• ガンバガナ 「内モンゴル自治運動における興蒙委員会の役割」
• 仁欽 「1950〜70年代の内モンゴルにおける民族政策に関する研究−漢人移民に対する政策中心に−」
• 高美正 「神道家の思想から見たジェンダー」
17年度・18年度受給者研究要旨 List of students and Summary (PDF: Japanese)
16年度受給者研究要旨 List of students and Summary (PDF: Japanese)
14年度・15年度受給者研究要旨 List of students and Summary (PDF: Japanese)
|
|
|
|
平成18年度
|
2007年3月7日 301拠点本部
|
|
1. 日本学術会議シンポジウムについて 2. 成果報告書(年次報告書、事後評価報告書)の提出について 3. 事業の最終的取り纏めと整理について(日程、拠点本部の体制、出版物の扱い、成果物の公表、Web出版、オーラル班資料、取り纏め会をやるか否か、PD研究員の勤務) 4. 英文HP原稿 5. 予算の最終的取り纏め 6. その他
|
2006年12月13日 301拠点本部
|
|
1. 国際会議の最終的打ち合わせ 2. その他
|
2006年11月1日 301拠点本部
|
|
1. 国際会議の内容と日程の確認 2. 予算の執行状況について 3. 出版事業の現状について 4. 拠点HP(日本語、英語版)について 5. 研究成果物の公開準備について
|
2006年9月27日 301拠点本部
|
|
1. 12月開催の国際会議について 2. 11月開催のリエゾンオフィス会議について 3. 会計報告
|
2006年7月19日 301拠点本部
|
|
1. 附属図書館に関わる案件 2. 出版事業について 3. 12月16-17日開催の国際会議について 4. 第3四半期予算について
|
2006年5月31日 301拠点本部
|
|
1. 海外事業協定文書の承認 2. 大学院博士後期課程助成金受給者の決定 3. 出版事業について 4. HPの更新について 5. 東南アジア集書事業の進め方について
|
2006年4月26日 301拠点本部
|
|
1. 2005年度成果報告書の内容の確認 (会計報告を含む) 2. 今年度助成金公募について 3. 国際会議の開催体制について 4. 拠点アドヴァイザーの確定 5. 出版事業について 6. 拠点事務局体制
|
|
平成17年度
|
2007年3月7日 301拠点本部
|
|
1. 日本学術会議シンポジウムについて 2. 成果報告書(年次報告書、事後評価報告書)の提出について 3. 事業の最終的取り纏めと整理について(日程、拠点本部の体制、出版物の扱い、成果物の公表、Web出版、オーラル班資料、取り纏め会をやるか否か、PD研究員の勤務) 4. 英文HP原稿 5. 予算の最終的取り纏め 6. その他
|
2006年3月29日 301拠点本部
|
|
報告事項 1. 人事異動および定年に伴う退職について 2. 来年度の「交付申請書」の内容について 審議事項 1. 今年度の会計処理について 2. 来年度予算について 3. 国際会議・最終年度の外部自己評価の実施について 4. その他(助成金受給者報告会の開催、出版計画など) 5. リエゾンオフィス事業について 6. ガレリアの地図模型について 7. Dilinsの継承体制について
|
2006年2月25日 301拠点本部
|
|
1. 来年度のPD研究員採用候補者の確定について 2. 今年度予算の執行状況について 3. 今年度の事業成果報告書について 4. 来年度予算の編成について 5. 来年度の事業計画について
|
2006年2月5日 301拠点本部
|
|
1. 今年度予算の執行状況について 2. 来年度PD研究員の採用について 3. 来年度国際会議の開催体制について 4. 来年度予算の編成と拠点事業の取り纏め日程について 5. その他の報告・連絡・依頼事項
|
2005年12月28日 301拠点本部
|
|
1. 第3四半期予算の執行状況について 2. 事務手続きについて 3. 来年度の国際会議開催体制について 4. ジャーナル・出版事業について 5. 来年度PD研究員の公募について 6. 大学院後期課程授業開講について 7. その他
|
2005年11月16日 301拠点本部
|
|
報告事項: 1. 本年度の会計処理について 2. 事務手続きについて 3. リエゾンオフィス利用事業について 4. 出版事業について 5. その他 審議事項: 1. 来年度の国際会議の開催体制について 2. フランス極東学院 Po Dharma さんよりの提案 3. 来年度PD研究員/大学院後期課程助成金の公募体制/ 3. 来年度リエゾンオフィス事業について
|
2005年9月28日 301拠点本部
|
|
報告および確認事項: 1. 附属図書館員の海外研修(帰国報告) 2. 事務・予算処理手続きについて再確認 3. 図書納入事務、並びに関連事項について 審議事項: 1. 今年度第3四半期までの予算執行について 2. リエゾンオフィス事業 3. 来年度国際会議の体制について 4. 海外事業協定 5. 大学院生助成金受給者で報告書未提出の者の扱いについて 6. 英文HPについて 7. 学術振興会特別研究員 8. その他
|
2005年7月27日 301拠点本部
|
|
1. インドネシア・ハサーヌッディーン大学との協定書の承認 2. リエゾンオフィスの活用事業 3. 最終年度国際会議の開催準備態勢について 4. 海外物品管理追加協定書について 5. 出版事業について 6. その他 a) 間接経費について b) 京大東南アジア研究所・地域研究企画交流センターよりの依頼について c) 英文HPについて
|
2005年6月29日 301拠点本部
|
|
1. 会計報告 2. 今年度総括班予算について(直接経費と間接経費について) 3. 大型史資料・マイクロフォームの購入について 4. デジタル化経費について 5. 出版事業について 6. 附属図書館員の海外研修について 7. リエゾンオフィス国際セミナーについて 8. HPの更新について 9. 最終年度国際会議の開催準備について 10. 学振特別研究員拠点特別枠の推薦について
|
2005年5月25日 301拠点本部
|
|
報告事項: 1. 予算編成について 2. アメリカアジア学会の年次大会の参加について 3. 出版事業の工程について 審議事項: 1. PD研究員の二次公募の結果について 2. 後期院生助成金について 3. その他
|
2005年4月27日 301拠点本部
|
|
1. 昨年度実績・会計報告書について 2. 今年度の予算執行について 3. 学術振興会特別研究員拠点枠の推薦について 4. 海外拠点・協定締結先の物品管理について 5. エゾンオフィスでの若手研究者ワークショップ開催について 6. 出版計画について 7. その他
平成16年度
|
|
平成16年度
|
2005年3月30日 301拠点本部
|
|
報告事項: 1. 今年度予算の締めについて 2. 「来年度交付申請書」関係書類の提出について 3. 「中間評価後修正報告書」の提出について 4. 今年度成果報告書及び自己評価関連書類の提出について 5. ウェブサイトの更新状況について 6. 津波・地震支援事業の現況 7. 東南アジア文献収集事業について 8. 来年度の出版計画について 9. 電子図書館事業について 審議事項: 1. 若手助成金計画案の承認 2. PD研究員第二次公募計画案の承認と時給単価等の確認 3. 拠点割り当て学術振興会特別研究員の推薦について 4. 来年度予算執行について 5. 最終年度の国際会議について 6. 21世紀地域文化研究班(井尻班)について
|
2005年3月2日 301拠点本部
|
|
報告事項: 1. 今年度予算の執行状況について 2. JCASとの共催研究会について 3. 後期課程大学院生助成金受給者報告会の結果について 4. 電子図書館担当者の海外研修について 5. 本学21世紀COE総合シンポジウム報告 審議事項: 1. 来年度事業計画と予算案について 2. PD研究員の面接結果について 3. 学振特別研究員 4. 後期大学院生助成について 5. liaison office活用事業+アメリカアジア学会年次大会活用案 6. 事業分担者の構成について 7. 最終年度の国際会議について 8. 出版計画について 9. JCASとの共同事業について 10. ボンベイ大学図書館との共同事業に関わる協定について 11. 来年度開催を予定している国際会議について 12. 「東京外国語大学オーラル・アーカイブズ」開設案について
|
2005年1月26日 301拠点本部
|
|
1. SOASリエゾンオフィスについて 2. 予算処理について 3. PD研究員の公募 4. デリーリエゾンオフィスセミナーについて 5. 助成金受給者の報告会 6. インドネシア緊急事業について 7. ジャーナルの今後の編集方針について 8. 出版計画について 9. その他
|
2004年12月1日 301拠点本部
|
|
1. 中間評価の結果と今後の予定について 2. 予算執行状況について 3. 年次計画案策定について 4. 来年度の事業計画と予算案策定について 5. その他 6. 関連情報 - 12月3日(金)10:00〜「著作権勉強会」(AA研306セミナー室) - 12月11日(土)13:00〜 オーラルアーカイブ班シンポジウム
|
2004年10月27日 301拠点本部
|
|
報告事項: 1. リエゾンオフィス(デリー)の使用状況について 2. 予算執行状況について 3. 在地固有文書班における図書のデジタル化について 4. マイクロフォームリーダープリンターの購入と設置について 5. 出版計画について 6. その他 - 拠点ウェブサイトについて 未報告事項: 1. 英文ウェブサイトについて 2. 来年度の出版計画について 3. 拠点メンバーの異動について 審議事項: 1. SOASとの協定更新について 2. モロッコとの新協定締結について
|
2004年9月29日 301拠点本部
|
|
報告事項: 1. 拠点事務員の交代について 2. 拠点事業と権利関係について 審議事項: 1. 予算の執行状況について - 余剰金と追加配分について - 今後の執行計画について 2. 拠点が購入した雑誌について
|
2004年7月28日 301拠点本部
|
|
1. 予算執行状況について - 概要 - 出勤簿管理 - 備品購入計画 ・ マイクロフォームリーダープリンター ・ 大型コレクション 2. その他 - パンフレット改訂版発行について - 合同シンポジウムについて - 地域研究コンソーシアムについて - リエゾンオフィスの活用について
|
2004年6月16日 301拠点本部
|
|
報告事項: 1. 全体会議と議事録について(事業メンバーの所属) 2. その他 - 国際会議事業の進展状況 - 史資料保存共有事業の進捗状況 - PD研究員の研究室と備品について - 海外事情研究所よりの要望について 審議事項: 1. デジタルライブラリーの細目決定 2. 博士後期課程助成金受給者の決定 3. 予算執行について 4. 出版事業体制について 5. その他 - リエゾンオフィスの活用 - 拠点パンフの作成 - HP更新と英語版の改訂
|
2004年6月3日 海外事情研究所
|
|
15:00〜16:50 拠点全体集会
|
2004年4月28日 COE拠点本部
|
|
1. ポスドク研究員の採用について 2. 拠点全体集会について 3. 拠点本部事務体制について 4. その他
|
|
平成15年度
|
2004年3月18日 COE拠点本部
|
|
1. 今年度予算について 2. SOASリエオゾンオフィスの開設と大阪市立大学との共同利用について 3. 若手研究者助成プログラムについて 4. 予算交付申請書の確認 5. 地域研究コンソーシアムについて 6. 言語COEとの合同シンポジウム開催について 7. 2007年までの活動方針の確認
|
2004年2月25日 COE拠点本部
|
|
1. SOASリエゾンオフィスについて 2. 地域研究コンソーシアムについて 3. 出版事業について 4. 広報活動について 5. フェロー、若手支援プログラムについて 6. 予算について 7. その他
|
2004年1月28日 COE拠点本部
|
|
1.中間評価書類について 2.年度末の諸事業、予算の閉めについて 3.本部の運営体制(アルバイトなど)について 4.HPと広報体制について 5.その他
|
2004年1月21日 COE拠点本部
|
|
総括班臨時会議 1.中間評価用書類の内容確認
|
2004年1月9日 COE拠点本部
|
|
総括班臨時会議 1.平成16年度予算交付申請調書について
|
2003年12月24日 COE拠点本部
|
|
1.フェロー、研究支援者の処遇について 2.今年度事業報告 3.今年度事業計画
|
| 2003年12月10日 COE拠点本部 |
|
総括班臨時会議 1.フェロー、研究支援者の処遇について
|
2003年11月26日 COE拠点本部
|
|
1.報告事項(各事業の推進状況 / 12月国際会議の準備状況) 2.若手研究者支援について 3.予算処理について 4.来年度事業について
|
2003年10月29日 COE拠点本部
|
|
1.報告事項 (総括班・事務局より / 図書館より) 2. 謝金支払いと雇用について / 3. 海外リエゾンオフィス事業について 4. 研究報告書の刊行について 5. 来年度事業について
|
2003年9月24日 COE拠点本部
|
|
1.事務局体制について 2.事業報告(各研究班・ジャーナルおよび報告書の発行、国際会議の準備状況、リエゾンオフィスの開設、協定の締結状況、図書館書架の設置、助成金について)
|
2003年8月27日 COE拠点本部
|
|
1. 総括班会議運営細則について 2. 国際会議の準備状況について 3. 広報体制について 4. リエゾンオフィスの実質的開設について 5. 業務担当責任者の任期について 6. その他
|
2003年7月30日 COE拠点本部
|
|
1.予算執行について(予算再配分、海外支出分の扱い、執行状況、図書資料購入費、報告書刊行費、その他) 2.夏期休業以降の各種事業の展開について (国際会議、アフガン復興事業など) 3.その他(外国人フェローの件、総括班事業など)
|
2003年6月25日 COE拠点本部
|
|
1. デジタルライブラリー/アーカイヴの進捗状況の報告 2. ジャーナル2号発行、ならびに研究報告の発行計画について 3. 国際会議・全国会議の報告 4. 予算執行のあり方について 5. 研究活動の推進方法 6. リエゾンオフィスについて 7. 日本学術振興会特別研究員21世紀COE特別枠の 拠点本部からの推薦について 8. その他
|
2003年6月11日 COE拠点本部
|
|
総括班臨時会議 1. 海外出張日当・宿泊費の減額について 2. 国際会議について 3. リエゾンオフィスについて 4. 合同国際会議について 5. 学術振興会21世紀COE特別枠特別研究員の推薦について 6. 予算執行方針 7. ジャーナル・報告書の発行 8. 総括班の運営体制 9. その他
|
2003年5月28日 COE拠点本部
|
|
1. 若手研究助成金受給者の決定 2. 海外出張について 3. 国際会議とリエゾンオフィスの開設について 4. 学術振興会21世紀COE分の決定手順について 5. ジャーナルとパンフレットについて 6. 予算執行について 7. ウェブサイトについて 8. 展示ヒアリングについて
|
| 2003年5月21日 COE拠点本部 |
|
総括班臨時会議
1.若手研究者への助成金交付決定に関して
|
2003年4月23日 COE拠点本部
|
|
1. 総括班主催国際シンポジウム
2003年4月16日 COE拠点本部
1. 事務局体制の再編と問題点 2. COE史資料HUB―附属図書館支援業務 3. 助成金募集要項 4. 拠点形成費補助金
|
|
平成18年度
|
2003年3月17日 COE拠点本部
|
|
1. 来年度予算案
|
2003年2月19日 COE拠点本部
|
|
1.今年度予算執行状況 2. HPと広報体制の見直し 3.ジャーナルの発行について 4. リエゾンオフィス 5.デジタル・ライブラリー/アーカイブス構築プロジェクト 6. 研究体制の見直しについて 7.大学院生への研究助成 8.来年度の計画について
|
2003年1月15日 COE拠点本部
|
|
1.予算執行について 2.今年の事業に関して > 3.出版事業に関して 4.今年度の成果報告に関して
|
2002年11月26日
研究科長室
|
|
1.PD助成受給者の決定 2.研究会開催について 3.その他
|
2002年11月13日 研究科長室
|
|
1. ニューズレター、ワーキングペーパー、報告書の発行体制について HPの件、広報体制について > 2.予算執行について 3.各研究班の活動について 4.COE活動記録の採録(活動日誌、研究班研究会の概要) 5.来年度に予定される活動の大綱作成に入る(国際会議、展示、etc.) 6.史資料の購入・発注状況
|
2002年11月6日 研究科長室
|
|
第2回総括班会議
|
2002年10月23日 研究科長室
|
|
1.執行予算案最終案について 2.事務局体制の確立について:人材と必要人数、機器の導入 3.年度内の事業推進について 4.経費・諸手続きに関わるマニュアル作成について 5.HPと広報体制について
|