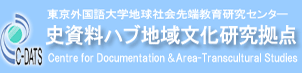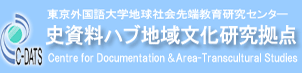|
平成18年度
|
|
--------
|
|
本拠点の支援協力により下記の書籍が刊行されました。
Malavika Karlekar (ed.) Visualizing Indian Women 1875-1947, New Delhi:
Oxford University Press, 2006.
ベトナムにおけるアメリカの宣伝活動ポスターの収蔵・公開を開始しました。
閲覧希望の方は拠点事務局にご連絡ください。
お問い合わせ先 「史資料ハブ地域文化研究拠点」事務局
〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1 東京外国語大学研究講義棟301 TEL&FAX 042-330-5540
リストについてはこちら
|
|
平成16年度
|
2004年6月19日
〜21日
|
|
国際シンポジウム "Thinking Malayness"
(表象文化研究班とアジア・アフリカ言語文化研究所の共催)
企画 : 宮崎恒二(アジア・アフリカ言語文化研究所)
 キャロル・フォーシェ(アジア・アフリカ言語文化研究所) キャロル・フォーシェ(アジア・アフリカ言語文化研究所)
会場 : アジア・アフリカ言語文化研究所大会議室
| セッション 1 〜 マレー世界の定義 〜 |
|---|
| 座長 : キャロル・フォーシェ (シンガポール大学講師、アジア・アフリカ言語文化研究所の客員研究員) |
|---|
| 1) | 「マレー語、 マレー性、マレー研究 : 研究組織への反映」 |
|---|
| シャムスル・アムリ・バハルディン (マレーシア国民大学教授、同大学マレー文明研究所ならびに西洋研究所所長) |
|---|
| 2) | 「移動、推移するアイデンティティー、そして想像」 |
|---|
| シンシア・チョウ (コペンハーゲン大学アジア学科講師) |
|---|
| 3) | 「サイバースペースにおけるマレー語・マレー人とマレー性」 |
|---|
| リザル・ユソフ (マレーシア国民大学博士課程) |
|---|
| 4) | 「マレー世界と呼ばれる風下の地」 |
|---|
| リワント・ティルトスダルモ (インドネシア科学院社会文化研究センター上級研究員、アジア・アフリカ言語文化研究所客員教授) |
|---|
| セッション 2 〜 マレー人意識 : その連続性と変容 〜 |
|---|
| 座長 : 永田脩一 (東京福祉大学教授) |
|---|
| 5) | 「現代のDunia Melayu運動におけるマレー性の新旧の両側面」 |
|---|
| 富澤寿勇 (静岡県立大学国際関係学部教授) |
|---|
| 6) | 「マラッカ海峡を越える同族意識の復活」 |
|---|
| ナタリー・フォー (パリ第7大学助教授) |
|---|
| 7) | 「音楽とマレー性の連続変異型」 |
|---|
| ジェフリー・ベンジャミン (ナンヤン工科大学準教授) |
|---|
| 8) | 「マレー的関係の再考 : 支配者と親族集団」 |
|---|
| レオナルド・アンダヤ (ハワイ大学マノア校教授) |
|---|
| 9) | 「港市政体におけるマレー概念 : 18世紀のジョホール-リアウ・スルタン領土の事例」 |
|---|
| 西尾寛治 (立教大学非常勤講師) |
|---|
| セッション 4 〜 少数民族と国民国家 〜 |
|---|
| 座長 : 内堀基光 (アジア・アフリカ言語文化研究所教授) |
|---|
| 10) | 「スリランカにおけるマレー人の民族意識 : 若干の観察」 |
|---|
| スワン・バジラチャヤ (秀明大学講師) |
|---|
| 11) | 「問題視されるシンガポール・マレー人 - そのイメージ形成 」 |
|---|
| スリアニ・スラットマン (シンガポール国立大学助教授) |
|---|
| 12) | 「マレーシアにおけるマレー人とマレー性の再考 : 境界に位置するマドゥラ人」 |
|---|
| ファウジ・スキミ (マレーシア国民大学博士課程) |
|---|
| 13) | 「フィリピンにおけるマレー性」 |
|---|
| 床呂郁哉 (アジア・アフリカ言語文化研究所助教授) |
|---|
| セッション 5 〜 十字路に位置するマレー性 〜 |
|---|
| 座長 : オマール・ファルク・バジュニド (広島市立大学教授) |
|---|
| 14) | 「マレー世界に住むこと : タイ=マレーシア国境における中国系学校における実践」 |
|---|
| 高村加珠恵 (東京外国語大学大学院博士課程) |
|---|
| 15) | 「Nayu dok pehe nayu (マレー人はマレー語を理解しない) : タイにおいてマレー人である苦悩」 |
|---|
| サロジャ・ドライラジョ (シンガポール国立大学助教授) |
|---|
| 16) | 「南タイにおける性道徳と宗教的言説」 |
|---|
| 西井涼子 (アジア・アフリカ言語文化研究所助教授) |
|---|
| セッション 6 〜 争いの中の民族意識と土着主義 〜 |
|---|
| 座長 : 石川登 (京都大学東南アジア研究センター助教授) |
|---|
| 17) | 「危機的状況における民族と階級 : 中部ジャワにおける労働者と経営者」 |
|---|
| マリオ・ルッテン (アムステルダム大学教授) |
|---|
| 18) | 「マレー、土着主義、「文明化のプロセス」 : 争われる領域における権利と要求」 |
|---|
| ビビアン・ウィー (香港市立大学助教授) |
|---|
| 19) | 「サンバス・マレー人の歴史と帰属意識」 |
|---|
| パバリ (ポンティアナク・タンジュングプラ大学講師) |
|---|
| セッション 7 〜 文化の生産と実践におけるマレー表象 〜 |
|---|
| 座長 : 左右田直規 (東京外国語大学外国語学部講師) |
|---|
| 20) | 「文化生産の弁証法的性格 : ママンダ劇の事例」 |
|---|
| ニヌック・クレーデン (インドネシア科学院社会文化研究センター上級研究員、インドネシア大学講師) |
|---|
| 21) | 「近代の花:映画女優と脱植民地期におけるマレー意識の創出」 |
|---|
| ティモシー・バーナード (シンガポール国立大学助教授) |
|---|
| 22) | 「完璧を求めて-ムラユの力」 |
|---|
| ヘンドリック・マイヤー (カリフォルニア大学リバーサイド校教授) |
|---|
| 23) | 「マレー世界におけるプンチャック・シラット-マレー人の社会倫理と攻撃性」 |
|---|
| ジャン-マルク・ドゥグラーヴ (フランス国立東洋言語文化研究所研究員) |
|---|
| セッション 8 〜 イスラームとマレー性の関係に関する考察 〜 |
|---|
| 座長 : 立本成文 (京都大学名誉教授、中部大学教授) |
|---|
| 24) | 「マレー人の宗教的ジレンマ : 近年の問題点」 |
|---|
| アジザン・バハルディン (マラヤ大学準助教授、同大学文明間対話センター長) |
|---|
| 25) | 「マレー性 : イスラームと民族性・宗教性の緊張関係ならびに調和」 |
|---|
| オスマン・バカル (ジョージタウン大学モスリム・クリスチャン相互理解センター客員教授) |
|---|
なお、各発表論文ならびに討論の内容については、シンポジウムの報告を参照されたい。
|
|
平成15年度
|
2003年7月18日
18:00-20:00
|
|
第2回研究会
演題:「東アジアのマンガ文化 〜グローバル化の現状〜」
発表者:澤田ゆかり(東京外国語大学外国語学部)
会場:東京外国語大学研究講義棟4階 海外事情研究所
|
2003年6月19日
18:00-20:30
|
|
第1回研究会(21世紀地域文化研究班との合同開催による特別講演会)
演題: 「『戦争広告代理店』の著者に聞く」
発表者: 高木徹(NHK)
会場: 東京外国語大学研究講義棟2F226教室
NHKディレクターである高木徹氏が自ら手掛けた番組「民族浄化〜ユーゴ・情報戦の内幕」を下地に、米国PR会社が紛争時のボスニア・ヘルツェゴビナ政府の外交からマスコミ対応、大統領の演説原稿作成までを手掛けていた実態について講演した。
実際にマスメディアの体現者である氏の言葉に、いまや世界中で必須事項となりつつある情報戦の実状を実感するとともに、歯止めの効かないその流れの中で、いかに自分が受け手として情報を享受していくのかという問いをあらためて考えさせられた。
講演後には「日本のPR戦略のセンスの欠如はどうやって克服すべきか」、あるいはまた、「そういったPRがうまくなることによって世論が納得してしまうことが、長期的に見てよいことなのかどうか」、といった質問や意見が参加者から続出し、活発な議論が交わされた。
|
2003年6月10日
12:10-13:00
|
|
第2回検討会議
場所: AA研棟6階611号室(宮崎研究室)
話題: 各地域におけるメディア事情とその特色
|
2003年5月20日
12:15-13:00
|
|
第1回検討会議
場所: AA研棟6階611号室(宮崎研究室)
話題: 本年度の活動計画
|
|
|
|
|
|
|
|
平成14年度
|
2002年12月10日
|
|
第1回研究会
白石さや(東京大学)「マンガ・アニメのグローバル化の現場から」
|
|
|
|
| 2002年10月28日 |
|
第1回班会議
収集方針、研究補助者、国際会議などについて
|