「ほんの少し度数が上がると」―美術館ができること
ピエリア・エッセイ

久米 順子
昨年の3月、ウィーンにあるレオポルド美術館の企画展「ウィーン1900年 モダニズムの誕生」がちょっとしたニュースになった。エゴン・シーレやグスタフ・クリムトといった同美術館が誇るコレクションのうち、15点の作品が斜めに傾いた状態で展示されたからである。傾きは作品によって異なり、その横には、角度の数字とその意味が記された。たとえばクリムトが描いた《アッター湖畔》の傾きは2度。この画家が愛した避暑地の生態系は、平均気温が2度上昇すれば崩壊する。シーレの《日没》は4度。地球の平均気温が4度上がると、この作品で描かれたアドリア海沿岸の光景は失われるだろうから。こうした予想はオーストリア気候変動センターの科学者たちの知見に基づくもので、同美術館との共同作業として、地球の温暖化が私たちの生活にどのような影響をもたらすのか、自然のバランスがどのように崩れるかを鑑賞者に伝えて考えさせる企画展示だった。題してA Few Degrees More (Will Turn the World into an Uncomfortable Place)「ほんの少し度数が上がると(世界は不快な場所になる)」。
当然のことながら、19世紀生まれのクリムトもシーレもすでに物故画家であり、作品を傾ける許可を画家本人から美術館側が得たわけではない。それなのに、こんな風に扱うなんて、芸術作品に対する侮辱――だろうか?
実はこの一見、過激な展示は、その前年に起こったある事件に対する、レオポルド美術館側の応答だった。石油精製会社の協賛による無料観覧日を狙って、過激派の環境活動家が同美術館の目玉作品のひとつ、クリムトの大作《死と生》に黒い液体をぶちまけたのである。化石燃料の使用が環境破壊を促進することに社会の注目を集めるための襲撃だった。
近年、美術作品を狙ったこの種の「環境テロ」は欧米を中心に頻発している。油彩を中心とする西洋美術作品は一点物であることが多く、地球と同じくひとたび損なわれれば取り返しがつかないというアナロジーが人々の危機感を喚起しやすいのだろう。気候変動に与するような経済活動にしがみつく大企業の支援が多くの有名美術館を潤していることも理由の一端である。さらに、美術館が気候変動のような喫緊の社会の課題に向き合わず、旧態依然とした「美の神殿」の地位に安住しているように見えがちなことも関係しているかもしれない。
実際には、アーティスト(描く人、作る人)、キュレーター(作品を鑑賞者に見せる人)、教育普及や広報の担当者ら、社会の課題に強い問題意識を抱いている美術館関係者は少なくない。先のレオポルド美術館の展示は、そのひとつの例である。別の例として、アメリカの美術史家及び美術批評家であるクレア・ビショップによる現代美術館論を挙げてみよう。「大きければ大きいほどよく、そうなればなるほど、より金回りがよくなる」という資本主義的な価値観が美術界にもはびこる現状のただ中で現代美術館にできることを彼女は問う。そもそも美術館がどんなものかを楽しく伝えるモラヴィア美術館の仕掛け絵本もまた、社会と繋がろうとする美術館側の試みである。
わたし自身は、もの言わぬ作品を人質にとっての抗議活動には否定的である。しかし、美術館がその成立以来、展示を通して既存の価値基準を示し、再生産する機能を担う一方で、自分の声が社会に届いていないと感じる人々による異議申し立ての場としても機能してきた事実は見落としたくない。その意味で、ロンドンでベラスケスの《鏡のヴィーナス》が切り裂かれた事件(1914年)も、東京で展示中の《モナリザ》へのスプレー噴射(1974年)も、女性活動家による抗議だったことは示唆的である。……あれ、紙幅が尽きてしまった。続きは、また。
久米 順子(くめ・じゅんこ)総合国際学研究院准教授 美術史
文献案内
クレア・ビショップ『ラディカル・ミュゼオロジー――つまり、現代美術館の「現代」ってなに?』村田大輔訳、月曜社、2020年
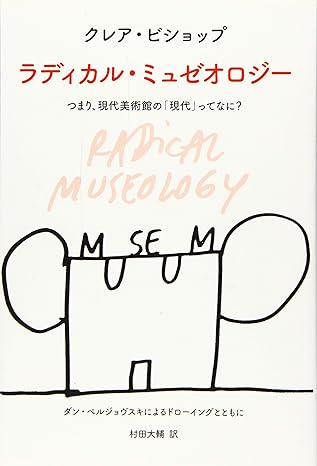
モラヴィア美術館編『美術館って、おもしろい!――展覧会のつくりかた、働く人たち、美術館の歴史、裏も表もすべてわかる本』阿部賢一、須藤輝彦訳、河出書房新社、2020年

ピエリア pieria 2024年春号
特集「気候変動と人の営み」第Ⅰ部 立ち現れた光景 掲載

