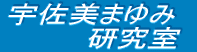 |
Home>研究業績>論文 |
| 論 文 |
| 2014年 | |
| 2014d | 「ポライトネスから見た母語話者のことばと学習者のことば」、『韓国日語教育学会2014年度第26回国際学術大会予稿集』.13-32 .10頁.2014年12月. |
| 2014c | 「初対面二者間会話における話題導入と展開のプラクティス」、『第71回 言語・音声理解と対話処理研究会資料』、人工知能学会、新宿:東京、23-28、6頁、2014年9月. |
| 2014b | 「ディスコース・ポライトネス理論とその応用について ~ ミスコミュニケーションの予防や解決のために ~」、『信学技報』、vol. 114、no. 67、 HCS2014-6, pp. 49-54、6頁、2014年5月. |
| 2014a | 「ディスコース・ポライトネス理論の新構想と異文化コミュニケーション――日中比較を中心に――」徐一平編 『中国日本語教学研究文書之10』 大連理工大学出版社: 大連、19-46、8頁. |
| 2013年 | |
| 2013c | 「会話データの作成・分析―「総合的会話分析」と「基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese:BTSJ)」」『日本語学』32(14)、明治書院: 132-147 16頁. 2013年11月. |
| 2013b | 「異文化間ミス・コミュニケーションとディスコース・ポライトネス理論」韓美卿編『日本語・日本語教育 ⑤』、J&C:291-304.14頁.2013年5月. |
| 2013a | 宇佐美まゆみ・中俣尚己「『BTSJによる日本語話し言葉コーパス(トランスクリプト・音声)2011年版』の設計と特性について」『第3回 コーパス日本語学ワークショップ予稿集』、国立国語研究所 言語資源研究系・コーパス開発センター:217-228.12頁.2013年2月. |
| 2012年 | |
| 2012e | 「ディスコース・ポライトネス理論と異文化間コミュニケーション」『2012 中国日本語教育研究会年会論文概要集』、西安外国語大学、西安、中国:24-33. 10頁. 2012年12月. |
| 2012d | 「母語話者の日本語会話」『コミュニケーションのための日本語教育研究』、星陵会館、大学共同利用機関法人国立国語研究所 日本語教育研究・情報センター:13-20. 8頁. 2012年11月. |
| 2012c | 「意識していない日本語コミュニケーションの教材化」、「特別パネルセッション:「自然会話を素材とする教材」の開発とその活用法-会話能力向上のために-」『インドネシア中等および高等教育機関における日本語学習者の会話能力向上をめざして』、インドネシア日本語教育学会:277-285. 9頁. 2012年9月. |
| 2012b | 「母語話者には意識できない日本語コミュニケーション」野田尚史編『日本語教育のためのコミュニケーション研究』、くろしお出版:63-82. 20頁. 2012年5月. |
| 2012a | 「視点としての日本語教育学―学際的複合領域研究群の構築に向けて―」『超域的日本語教育国際学術検討会-<視点としての日本語教育学の提唱>ならびに<学際的複合領域研究群の構築>-発表論文集』、中国文化大学、台北、台湾:1-12. 12頁. 2012年5月. |
| 2011年 | |
| 2011f | 「異文化間ミスコミュニケーションとディスコースポライトネス理論」『韓国日本言語文化学会国際学術発表大会論文集』:13-20.8頁.2011年11月. |
| 2011e | Discourse Politeness Theory and second language acquisition,” In Wai Meng Chan, Kwee Nyet Chin and Titima Suthiwan. (eds.) Foreign Language Teaching in Asia and Beyond: Current Perspective and Future Direction. De Gruyter Mounton:45-70. 26頁. 2011年10月. |
| 2011d | 特別寄稿「ディスコース・ポライトネス理論と日本語教育-視点としての日本語教育学へ-」『中日文化論叢』28:1-27.27頁.2011年7月. |
| 2011c | 「高齢者との円滑なコミュニケーションのために-高齢社会のコミュニケーション環境とポライトネス理論の観点から」『月報司法書士』472:2-10.9頁.2011年6月. |
| 2011b | 「「ね」のコミュニケーション機能とディスコース・ポライトネス」現代日本語研究会編『合本 女性のことば・男性のことば(職場編)』、ひつじ書房: 241-268. 28頁. 2011年5月. |
| 2011a | 「ディスコース・ポライトネス理論と日本語教育-視点としての日本語教育学へ-」『<日本語・日本文学・日本文化学>国際学術検討会-超域的かつ包括的な日本語教育」を目指して-発表論文集』、中国文化大学、台北、台湾:1-20.21頁.2011年5月. |
| 2010年 | |
| 2010 | 「ポライトネスとジェンダー 隠されたヘゲモニー」中村桃子編『ジェンダーで学ぶ言語学』、世界思想社:160-175.16頁.2010年4月. |
| 2009年 | |
| 2009e | 「視点としての日本語教育学-日本語教育学の新しいパラダイム-」、『2009年度「台湾日本語教育研究」国際シンポジウム-日本語教育のジャンルのひろがりを求めて』会議論文集、pp.27-34. 18頁. 2009年12月. |
| 2009d | 「視点としての日本語教育学‐日本語教育学の新しいパラダイム‐」『2009年度「台湾日本語教育研究」国際シンポジウム‐日本語教育のジャンルの広がりを求めて』会議予稿集、pp.19-26、2009年12月6日 |
| 2009c | (2009c)「自然会話分析のための文字化入力支援及び基本的な分析項目の自動集計ツールとその使い方」、『日本語学会2009年度秋季大会予稿集』、pp.193-194、2009年10月4日 |
| 2009b | 「人間関係とポライトネス」(パネル「人間関係の日本語史シンポジウム」)、『日本語学会2009年度春季大会予稿集』21-28. 8頁. 2009年5月 |
| 2009a | 「『伝達意図の達成度』『ポライトネスの適切性』『言語行動の洗練度』から捉えるオーラル・プロフィシェンシー」鎌田修・山内博之・堤良一編『プロフィシェンシーと日本語教育』、ひつじ書房:33-67. 35頁.2009年5月. |
| 2008年 | |
| 2008e | 吉岡泰夫・相澤正夫・田中牧郎・宇佐美まゆみ・早野恵子・徳田安春・三浦純一・西﨑祐史「ポライトネス理論を応用した医療コミュニケーション教育プログラムの有効性」『日本語学会2008年度秋季大会予稿集』、日本語学会:255-262. 8頁. 2008年11月. |
| 2008d | 「ポライトネス理論研究のフロンティア-ポライトネス理論研究の課題とディスコース・ポライトネス理論」『社会言語科学』11(1)(特集「敬語研究のフロンティア」)、社会言語科学会:4-22.19頁.2008年9月. |
| 2008c | 「相互作用と学習ーディスコース・ポライトネス理論の観点から」西原鈴子・西郡仁朗編『講座社会言語科学 第4巻 教育・学習』、ひつじ書房:150-181. 32頁.2008年9月. |
| 2008b | 「社会言語・言語生活」『日本語の研究』4(3)(特集「2006年・2007年における日本語学界の展望」)、日本語学会:88-97.10頁.2008年7月. |
| 2008a | 吉岡 泰夫・早野 恵子・三浦 純一・徳田安春・本村 和久・相澤 正夫・田中 牧郎・宇佐美まゆみ「良好な患者医師関係を築くコミュニケーションに効果的なポライトネス・ストラテジー」『医学教育』39(4)、日本医学教育学会:251-257. 2008年7月. |
| 2007年 | |
| 2007m | 「keyword言語社会心理学 円滑なコミュニケーションとポライトネス理論 現代日本社会における言葉遣いのストラテジー」、ベルシステム24総合研究所『交感する科学 ビジネスを深化させる最先端コミュニケーション研究』、株式会社ベルシステム24:46-69. 24頁. 2007年7月. |
| 2007l | 吉岡泰夫、早野恵子、三浦純一、徳田安春、本村和久、相澤正夫、田中牧郎、宇佐美まゆみ「医療コミュニケーションに効果的なポライトネス・ストラテジー― 敬語や方言を使う効果を中心に ―」『日本語学会2007年度秋季大会予稿集』、日本語学会: 231-238. 8頁. |
| 2007k | 「自然会話分析への言語社会心理学的アプローチ-BTSJ(Basic Transcription System for Japanese)に基づく談話コーパスとその利用-」『元智大学ワークショップ予稿集』、元智大学:4-22. 19頁. |
| 2007j | 「高齢社会のよりよいコミュニケーション環境づくりのために」『月刊総合ケア』第17巻・第3号(特集「高齢社会のコミュニケーションづくり」)、医歯薬出版株式会社:10-17. 8頁. 2007年3月. |
| 2007i | 宇佐美まゆみ・鈴木卓「基本的な文字化の原則(Basic Transcription system for Japanese: BTSJ)の英語への応用について」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度科学研究費補助金基盤研究B(2)研究成果報告書(課題番号 15320064):104-112.9頁.2007年3月. |
| 2007h | 宇佐美まゆみ・肖婷婷・戴琦・高娃・李宇霞・仇暁妮「基本的文字化の原則(Basic Transcription system for Japanese: BTSJ)の中国語への応用について」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度科学研究費補助金基盤研究B(2)研究成果報告書(課題番号 15320064):83-103.21頁.2007年3月. |
| 2007g | 宇佐美まゆみ・李恩美・鄭榮美・金銀美「基本的な文字化の原則(Basic Transcription system for Japanese: BTSJ)」の韓国語への応用について」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度科学研究費補助金基盤研究B(2)研究成果報告書(課題番号 15320064):48-82.35頁.2007年3月. |
| 2007f | 宇佐美まゆみ・木林理恵「「基本的な文字化の原則(Basic Transcription for Japanese:BTSJ)」文字化入力操作・集計自動化版の作成について」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度科学研究費補助金基盤研究B(2)研究成果報告書(課題番号 15320064):40-47.8頁.2007年3月. |
| 2007e | 宇佐美まゆみ・木林理恵「「改訂版:基本的な文字化の原則(Basic Transcription for Japanese:BTSJ)2007年3月31日改訂版」について」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度科学研究費補助金基盤研究B(2)研究成果報告書(課題番号 15320064):37-39. 3頁.2007年3月. |
| 2007d | 「改訂版:基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese:BTSJ)2007年3月31日改訂版」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度科学研究費補助金基盤研究B(2)研究成果報告書(課題番号 15320064):17-36.20頁.2007年3月. |
| 2007c | 宇佐美まゆみ・木山幸子「人間の相互作用研究の基盤となる文字化システム:会話教材作成への示唆」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度科学研究費補助金基盤研究B(2)研究成果報告書(課題番号 15320064):7-16.10頁.2007年3月. |
| 2007b | 「自然会話の教材化とディスコース・ポライトネス理論2:教材としての自然会話の価値」『第一回ルーマニア日本語教師会 日本語教育・日本語学シンポジウム報告書』ルーマニア日本語教師会.Avrin Press. 26-38. 13頁. |
| 2007a | 「自然会話の教材化とディスコース・ポライトネス理論1:対人コミュニケーション論としてのディスコース・ポライトネス理論の考え方」『第一回ルーマニア日本語教師会 日本語教育・日本語学シンポジウム報告書』ルーマニア日本語教師会.Avrin Press. 12-25. 14頁. |
| 2006年 | |
| 2006n | Lee, Eunmi and Mayumi Usami. The functions of "speech levels" and "utterances without politeness markers" in Japanese and Korean: From the perspective of discourse politeness.『言語情報学研究報告13 自然会話分析への言語社会心理学的アプローチ』東京外国語大学大学院地域文化研究科21世紀COEプログラム「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」:277-290.14頁.2006年11月. |
| 2006m | Suzuki, Takashi and Mayumi Usami. Co-constructions in English and Japanese revisited: A quantitative approach to cross-linguistic comparison. 『言語情報学研究報告13 自然会話分析への言語社会心理学的アプローチ』東京外国語大学大学院地域文化研究科21世紀COEプログラム「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」:263-276. 14頁. 2006年11月. |
| 2006l | 宇佐美まゆみ・木林理恵・木山幸子・金銀美 「「基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese: BTSJ)」の開発と『BTSによる多言語話し言葉コーパス』の構築-BTSJの理論的背景と本コーパスを用いた人間の相互作用の研究例(日本語会話の場合-」『言語情報学研究報告13 自然会話分析への言語社会心理学的アプローチ』東京外国語大学大学院地域文化研究科21世紀COEプログラム「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」:245-261. 17頁. 2006年11月. |
| 2006k | 「談話研究におけるローカル分析とグローバル分析の意義」『言語情報学研究報告13 自然会話分析への言語社会心理学的アプローチ』東京外国語大学大学院地域文化研究科21世紀COEプログラム「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」:229-243. 15頁. 2006年11月. |
| 2006j | 「改訂版:基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese:BTSJ)2005年2月25日改訂版」『言語情報学研究報告13 自然会話分析への言語社会心理学的アプローチ』東京外国語大学大学院地域文化研究科21世紀COEプログラム「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」:21-46. 26頁. 2006年11月. |
| 2006i | 「談話行動の日韓比較 -ディスコース・ポライトネス理論の観点から-」、『韓国外国語大学校日本研究所国際学術Symposium発表論文集:「 韓日言語・文化の 接点を求めて」』、韓国外国語大学校外国学総合研究Center日本研究所: 23-35. 13頁. 2006年6月. |
| 2006h | 「談話研究からの視点」『南山日本語教育シンポジウム プロフィシェンシーと日本語教育 日本語の総合的能力の研究と開発を目指して』、関西OPI研究会: 19-31. 13頁. 2006年6月. |
| 2006g | 「準自然場面における「誘い行動」の日韓比較 -ディスコース・ポライトネス理論の観点から-」『日本研究』第28号、韓国外国語大学校日本研究所:47-72. 26頁. 2006年6月. |
| 2006f | Discourse politeness theory and second language acquisition. In Wai Meng Chan, Kwee Nyet Chin and Titima Suthiwan. (eds.) Foreign language teaching in Asia and beyond: Current perspectives and future directions. Centre for Language Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore:45-70. 26頁. 2006年. |
| 2006e | Discourse politeness theory and cross-cultural pragmatics. In Asako Yoshitomi, Tae Umino and Masashi Negishi. (eds.) Usage-Based Linguistic Informatics 4: Reading in second language pedagogy and second language acquisition in Japanese context, John Benjamins Publishing Company: 19-41. 23頁. 2006年. John Benjamins Publishing Company |
| 2006d | A preliminary framework for a discourse politeness theory: Focusing on the concept of relative politeness. Studies in language Sciences (5): Papers from the fifth annual conference of the Japanese society for language Sciences. Kurosio Publishers:29-50. 22頁. 2006年6月. |
| 2006c | 「ジェンダーとポライトネス -女性は男性よりポライトなのか?-」『日本語とジェンダー』、日本語ジェンダー学会編、ひつじ書房:21-37. 17頁. 2006年6月. |
| 2006b | Discourse politeness theory and cross-cultural pragmatics. In Asako Yositomi, Tae Umino and Masashi Negishi. (eds.) Linguistic informatics V: Studies in second language teaching and second language acquisition. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS):9-31. 23頁. 2006年3月. |
| 2006a | 「話し手と聞き手の相互作用としての「共同発話文」の日英比較 -「共話」、「Co-construction」現象の再検討-」『高見澤孟先生古希記念論文集』、高見澤孟先生古希記念論文集編集委員会:103-130. 28頁. 2006年1月. |
| 2005年 | |
| 2005c | Why do we need to analyze natural conversation data in developing conversation teaching materials? -Some implications for developing TUFS language modules-. In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Usage-Based Linguistic Informatics 1: Linguistic informatics -State of the art and the future. John Benjamins Publishing Company: 279-294. 16頁. 2005年. John Benjamins Publishing Company |
| 2005b | Suzuki, Takash, Koji Matsumoto and Mayumi Usami. An analysis of teaching materials based on New Zealand English conversation in natural settings- Implications for the development of conversation teaching materials-. In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Usage-Based Linguistic Informatics 1: Linguistic informatics -State of the art and the future. John Benjamins Publishing Company: 295-315. 21頁. 2005年. John Benjamins Publishing Company |
| 2005a | 「ジェンダーとポライトネス -女性は男性よりポライトなのか?-」『日本語とジェンダー』5、日本語ジェンダー学会:1-12. 12頁. 2005年5月. |
| 2004年 | |
| 2004e | Discourse politeness theory and second language acquisition. The proceedings of the inaugural CLS international conference. CLaSIC: 719-737. 19頁. 2004年12月. |
| 2004d | 謝韞・木山幸子・李恩美・施信余・木林理恵・宇佐美まゆみ「TUFS会話モジュールの日本語スキットと『BTSによる多言語話し言葉コーパス -日本語2』における依頼行動の対照研究 -会話教育への示唆-」、In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Linguistic informatics III: The first international conference on linguistic informatics -State of the art and the future-. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS): 323-341. 19頁. 2004年10月. |
| 2004c | 関崎博紀、木林理恵、木山幸子、李恩美、施信余、宇佐美まゆみ「『BTSによる多言語話し言葉コーパス -日本語2』の作成過程と整備の結果から示されること -会話教育への示唆-」、In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Linguistic informatics III: The first international conference on linguistic informatics -State of the art and the future-. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS): 301-322. 22頁. 2004年10月. |
| 2004b | Suzuki, Takashi, Koji Matsumoto and Mayumi Usami. An analysis of teaching materials based on New Zealand English conversation in natural settings: Implications for the development of conversation teaching materials. In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Linguistic informatics III: The first international conference on linguistic informatics -State of the art and the future-. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS): 279-299. 21頁. 2004年10月. |
| 2004a | Why do we need to analyze natural conversation data in developing conversation teaching materials?: Some implications for developing TUFS language modules-. In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Linguistic informatics III: The first international conference on linguistic informatics -State of the art and the future-. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS): 263-278. 16頁. 2004年10月. |
| 2003年 | |
| 2003e | 「高齢者との対話のありかた -よりよい世代間コミュニケーションのために」『別冊「総合ケア」: 住み慣れたまちで最期まで暮らす』、亀山正邦監修/琵琶湖長寿科学シンポジウム実行委員会編、医歯薬出版: 109-121. 13頁. 2003年11月. |
| 2003g | Xie, Yun, Rie Kibayashi, Sachiko Kiyama, Hsin-yu Shih, Eunmi Lee, Kyongbun Kim, Koji Matsumoto and Mayumi Usami. A comparative analysis of discourse behaviors in Japanese natural conversation and the Japanese skits of the TUFS dialogue modules: Implications for the development of conversation teaching materials. In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Linguistic informatics I: Proceedings of the first international conference on linguistic informatics: Linguistic informatics -State of the art and the future-. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS): 219-233. 14頁. 2003年10月. |
| 2003f | Kibayashi, Rie, Kyongbun Kim , Yun Xie, Hironori Sekizaki, Sachiko Kiyama, Hsin-yu Shih, Eunmi Lee, Koji Matsumoto and Mayumi Usami. An examination of the process of developing a Corpus of Spoken Japanese: Implications for the development of conversation teaching materials. In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Linguistic informatics I: Proceedings of the first international conference on linguistic informatics: Linguistic informatics -State of the art and the future-. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS): 205-218. 14頁. 2003年10月. |
| 2003e | Suzuki, Takashi, Koji Matsumoto and Mayumi Usami. An analysis of teaching materials based on New Zealand English conversation in natural settings: Implications for the development of conversation teaching materials. In Kawaguchi, Yuji, Susumu Zaima, Toshihiro Takagaki, Kohji Shibano and Mayumi Usami. (eds.) Linguistic informatics I: Proceedings of the first international conference on linguistic informatics: Linguistic informatics -State of the art and the future-. 21st Century COE: Center of Usage-Based Linguistic Informatics, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS): 191-204. 14頁. 2003年10月. |
| 2003d | 「異文化接触とポライトネス -ディスコース・ポライトネス理論の観点から-」『国語学』54(3)、国語学会: 117-132. 16頁. 2003年7月. |
| 2003c | 宇佐美まゆみ・李恩美「初対面二者間会話における「丁寧度を示すマーカーのない発話」の日韓対照研究」『韓国日語日文学会2003年度国際学術発表大会・夏季学術発表大会発表論文集』、韓国日語日文学会: 99-106. 8頁. 2003年6月. |
| 2003b | 「改訂版: 基本的な文字化の原則 (Basic Transcription System for Japanese: BTSJ)」『多文化共生社会における異文化コミュニケーション教育のための基礎的研究』平成13-14年度科学研究費補助金基盤研究C(2) (課題番号: 13680351)(研究代表者: 宇佐美まゆみ) 研究成果報告書: 4-21. 18頁. 2003年3月. 2005年2月25日に改定の最新版は、下記からダウンロードできる。(http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/usamiken/btsj.htm) |
| 2003a | 「高齢の患者との接し方 -主に、言葉遣いを中心に」『皮膚病診療』25(13: 増刊号1)、協和企画: 13-19. 7頁. 2003年. |
| 2002年 | |
| 2002f | 連載「ポライトネス理論の展開 (1-12)」『月刊言語』31(1-13、6を除く)、大修館書店: 毎号6頁. 総頁数72頁. 2002年1月-12月. 1-6のPDFはこちら 7-12のPDFはこちら |
| 2002e | 「誰のための「国語学」か」『国語学』53(4) (「国語学会2002年度春季大会シンポジウム報告: 2. 各発題の要旨」)、国語学会: 133-134. 2頁. 2002年5月. |
| 2002d | 宇佐美まゆみ・木林理恵「母語場面と接触場面における「共同発話」の比較」『社会言語科学会第10回研究大会予稿集』、社会言語科学会: 15-20. 6頁. 2002年9月. |
| 2002c | 「対人コミュニケーションの言語問題」『多言語・多文化共生社会における言語問題』(第9回国立国語研究所国際シンポジウム第1部会報告書)、国立国語研究所: 63-75. 13頁. 2002年7月. |
| 2002b | 「誰のための『国語学』か」『国語学会2002年春季大会要旨集』、国語学会: 1-8. 8頁. 2002年5月. |
| 2002a | 「言語とジェンダー研究」『月刊言語』31(6) (30周年記念別冊「日本の言語学」)、大修館書店: 170-175. 6頁. 2002年5月. |
| 2001年 | |
| 2001f | 「ポライトネス理論から見た<敬意表現> -どこが根本的に違うのか」『月刊言語』30(12)、大修館書店: 18-25. 8頁. 2001年11月. |
| 2001e | 「会話における『協調的行動』 -ポライトネスの観点から-」、『平成13年度日本語教育学会秋季大会予稿集』、日本語教育学会: 163-168. 6頁. 2001年10月. |
| 2001d | 「対人コミュニケーションの社会心理学 -ディスコース・ポライトネスという観点から-」『月刊言語』30(7)、大修館書店: 78-85. 8頁. 2001年6月. |
| 2001c | 「ディスコース・ポライトネス」という観点から見た敬語使用の機能 -敬語使用の新しい捉え方がポライトネスの談話理論に示唆すること-」『語学研究所論集』6、東京外国語大学語学研究所: 1-29. 29頁. 2001年3月. |
| 2001b | 「談話のポライトネス -ポライトネスの談話理論構想-」『談話のポライトネス』(第7回国立国語研究所国際シンポジウム報告書)、国立国語研究所: 9-58. 50頁. 2001年3月. |
| 2001a | 「21世紀の社会と日本語 -ポライトネスのゆくえを中心に-」『月刊言語』30(1) (1月号特集「21世紀の日本語」)、大修館書店: 20-28. 9頁. 2001年1月. |
| 2000年 | |
| 2000 | 「談話研究と言語教育」『AJALT』23、社団法人国際日本語普及協会: 22-26. 5頁. 2000年6月. |
| 1999年 | |
| 1999c | 「談話の定量的分析 -言語社会心理学的アプローチ-」『日本語学』18(11)、明治書院: 40-56. 17頁. 1999年10月. |
| 1999b | 「交感的コミュニケーションとしてのあいさつ行動」『国文学』44(6)、学燈社: 83-89. 7頁. 1999年5月. |
| 1999a | 「視点としての日本語教育学」『月刊言語』28(4)、大修館書店: 34-42. 9頁. 1999年4月. |
| 1998年 | |
| 1998c | 「ディスコース・ポライトネス・ストラテジーとしてのスピーチレベル・シフト」『平成10年度日本語教育学会秋季大会予稿集』、日本語教育学会: 110-115. 6頁. 1998年10月. |
| 1998b | 「ポライトネス理論の展開: ディスコース・ポライトネスという捉え方」東京外国語大学日本課程編『日本研究教育年報 (1997年度版)』、東京外国語大学日本課程: 145-159. 15頁. 1998年8月. |
| 1998a | 「初対面二者間会話における『ディスコース・ポライトネス』」『ヒューマン・コミュニケーション研究』26、日本コミュニケーション学会: 49-61. 13頁. 1998年. |
| 1997年 | |
| 1997e | 「高齢化社会におけるコミュニケーション環境整備のために」『月刊言語』26(13)、大修館書店: 60-67. 8頁. 1997年. |
| 1997d | 「「ね」のコミュニケーション機能とディスコース・ポライトネス」現代日本語研究会編『女性のことば・職場編』、ひつじ書房: 241-268. 28頁. 1997年11月. |
| 1997c | 「自然会話分析法への言語社会心理学的アプローチ」『日本人の談話行動のスクリプト・ストラテジーの研究とマルチメディア教材の試作』、平成7-8年度文部省科学研究費基盤研究C(2) (課題番号: 07680312)(研究代表者: 西郡仁朗)、研究成果報告書: 1-5. 5頁. 1997年3月. |
| 1997b | 「基本的な文字化の原則 (Basic Transcription System for Japanese: BTSJ) の開発について」、『日本人の談話行動のスクリプト・ストラテジーの研究とマルチメディア教材の試作』、平成7-8年度文部省科学研究費基盤研究C(2) (課題番号: 07680312)(研究代表者: 西郡仁朗)、研究成果報告書: 12-26. 15頁. 1997年3月. |
| 1997a | 「自然会話の文字化資料作成とそのデータベース化に関する一考察: 日本人初対面二者間会話72会話の文字化資料の整備、データベース化作業を通して」『日本人の談話行動のスクリプト・ストラテジーの研究とマルチメディア教材の試作』、平成7-8年度文部省科学研究費基盤研究C(2) (課題番号: 07680312)(研究代表者: 西郡仁朗)、研究成果報告書: 6-11. 6頁. 1997年3月. |
| 1996年 | |
| 1996c | 「日本人の初対面会話の分析 -外国人と日本人のコミュニケーション教育のための基礎研究-」『平成8年度日本語教育学会秋季大会予稿集』、日本語教育学会: 196-201. 6頁. 1996年10月. |
| 1996b | 宇佐美まゆみ・山岡真希子「会話という相互作用における『協調的行動』の日英対照: 『共話』、‘co-construction’ 現象の再検討」(未発表原稿). |
| 1996a | 「初対面二者間会話における話題導入頻度と対話相手の年齢・社会的地位・性の関係について」『ことば』17号、現代日本語研究会: 44-57. 14頁. 1996年3月. |
| 1995年 | |
| 1995c | 宇佐美まゆみ・嶺田明美「対話相手に応じた話題導入の仕方とその展開パターン: 初対面二者間の会話分析より」、『名古屋学院大学日本語学・日本語教育論集』2、名古屋学院大学留学生別科 (日本研究プログラム): 130-145. 16頁. 1995年. |
| 1995b | 「待遇表現の指導法: 会話のストラテジーという観点から」『平成6年度研究奨励金による研究報告書』、昭和女子大学: 1-4. 4頁. 1995年. |
| 1995a | 「談話レベルから見た敬語使用: スピーチレベルシフト生起の条件と機能」『学苑』662、昭和女子大学近代文化研究所: 27-42. 16頁. 1995年2月. |
| 1994年 | |
| 1994c | 「性差か力 (power) の差か: 初対面二者間の会話における話題導入の頻度と形式の分析より」『ことば』15、現代日本語研究会: 53-69. 17頁. 1994年12月. |
| 1994b | 「場面に応じた「ね」の使い分け」『職場における女性の話しことば』(東京女性財団1993年度助成研究報告書)、現代日本語研究会: 51-60. 10頁. 1994年5月. |
| 1994a | 「言語行動における “politeness” の日米比較」『スピーチ・コミュニケーション教育』7、日本コミュニケーション学会: 30-41. 12頁. 1994年. |
| 1993年 | |
| 1993d | 「談話レベルから見た “politeness ”: “politeness theory” の普遍理論確立のために」『ことば』14、現代日本語研究会: 20-29. 10頁. 1993年12月. |
| 1993c | 「コミュニカティブ・アプローチのゆくえ」『月刊日本語』6(12)、アルク: 18-24. 7頁. 1993年12月. |
| 1993b | 「初対面二者間の会話の構造と話者による会話のストラテジー: 話者間の力関係による相違 -日本語の場合」『ヒューマン・コミュニケーション研究』21、日本コミュニケーション学会: 25-39. 15頁. 1993年. |
| 1993a | 「初対面二者間会話における会話のストラテジーの分析: 対話相手に応じた使い分けという観点から」『学苑』647、昭和女子大学近代文化研究所: 37-47. 11頁. 1993年11月. |
| 1992年 | |
| 1992c | 「言語・思考・アイデンティティー」『ことば』13、現代日本語研究会: 52-59. 8頁. 1992年12月. |
| 1992b | Landahl, Karen L., Michael S. Ziolkowski, Mayumi Usami and Brenda K. Tunnock. Interactive articulation: Improving accent through visual feedback. The proceedings of the second international conference on foreign language education and technology. The Language Laboratory Association of Japan & The International Association for Learning Laboratories: 283-292. 10頁. 1992年8月. |
| 1992a | Ziolkowski, Michael S. Mayumi Usami, Karen L. Landahl and Brenda K. Tunnock. How many phonologies are there in one speaker?: Some experimental evidence. Proceedings of the second international conference on spoken language processing. ICSLP: 1315-1318. 4頁. 1992年. |
| 1989年 | |
| 1989 | Learning in the target language and through actions for the development of communicative competence. Proceedings of lower Lake Erie region teachers of Japanese language conference: 81-94. 14頁. 1989年. |
| 1987年 | |
| 1987b | 「アメリカ人学習者の四コマ漫画の口頭説明の分析 -「わかりやすさ」「流暢さ」「正確さ」と「伝達能力」の関係分析への一アプローチ」『日本語と日本語教育』16、慶應義塾大学国際センター: 60-68. 9頁. 1987年. |
| 1987a | 「外国語教授法について考える -サジェストペディアによる英語・スペイン語クラスを受講して」『ILT NEWS』82、早稲田大学語学教育研究所: 46-58. 13頁. 1987年. |
| 1986年 | |
| 1986b | 「「TPR (Total Physical Response) -その理論と日本語教育への応用」『国際基督教大学夏期日本語講座論集』3、国際基督教大学: 91-101. 11頁. 1986年. |
| 1986a | 「美麗島における日本語教育・台湾」江副隆秀・林伸一編『外国で日本語を教える』、創拓社: 120-139. 20頁. 1986年. |