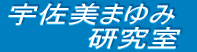 |
Home>研究活動>談話研究と日本語教育>BTSJ について |
| 平成15-18年度科学研究費補 助金(基盤研究B(2)、研究代表者 |
| 基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese: BTSJ)の開発の背景 |
| 基本的な文字化の原則(Basic
Transcription System for Japanese: BTSJ) の開発について |
| 宇佐美まゆみ(1997)「基本的な文字 化の原則(Basic Transcription System for Japanese: BTSJ) の開発について」『日本人の談話行動のスクリプト・ストラテジーの研究とマルチメディア教材の試作』平成7年 度〜平成8年度文部省科学研究費-基盤研究(C)(2)- 研究成果報告書(課題番号07680312) 研究代表者西郡仁朗、12-26頁より、1節 から3節を抜粋 |
| 宇
佐美まゆみ(2007)「改訂版:基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese:
BTSJ)2007年3月31日改訂版」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度
科学研究費補助金 基盤研究B(2)(研究代表者 宇佐美まゆみ)研究成果報告書 本稿は、2007年3月31日に改訂の最新版である。 |
BTS 中国語版(BTSC)2 |
宇 佐美まゆみ(2007)「改訂版:基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese:BTSJ)2007年3月31日改訂版」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15 -18年度科学研究費補助金 基盤研究B(2)(研究代表者 宇佐美まゆみ)研究成果報告書 本稿は、2011年に改訂の最新版である。 |
| 本 稿では、「基本的な文字化の原則(BTSJ)」によって文字化した資料を用いて行う研究の分析方法を説明する。BTSJは、その名の通り、「基本的 な....文字化の原則」であり、汎用性を念頭において構築された文字化のルールである。基本的には、「基本的な文字化の原則(BTSJ)」で記述した原 則に沿って文字化するが、研究の目的に応じて、例えば、より詳細な音声情報を付与するなど、BTSJの原則を基本にしつつも、必要であれば、独自の記号を 追加して対応することも可能である。ここでは文末のスピーチレベルと終助詞を例として、個々の研究目的に応じて分析対象をコーディングする際の工夫のし方 を提示する。 |
| 利用の手引き |
| 入力の仕方マニュアル |
| BTSJ Q&A |