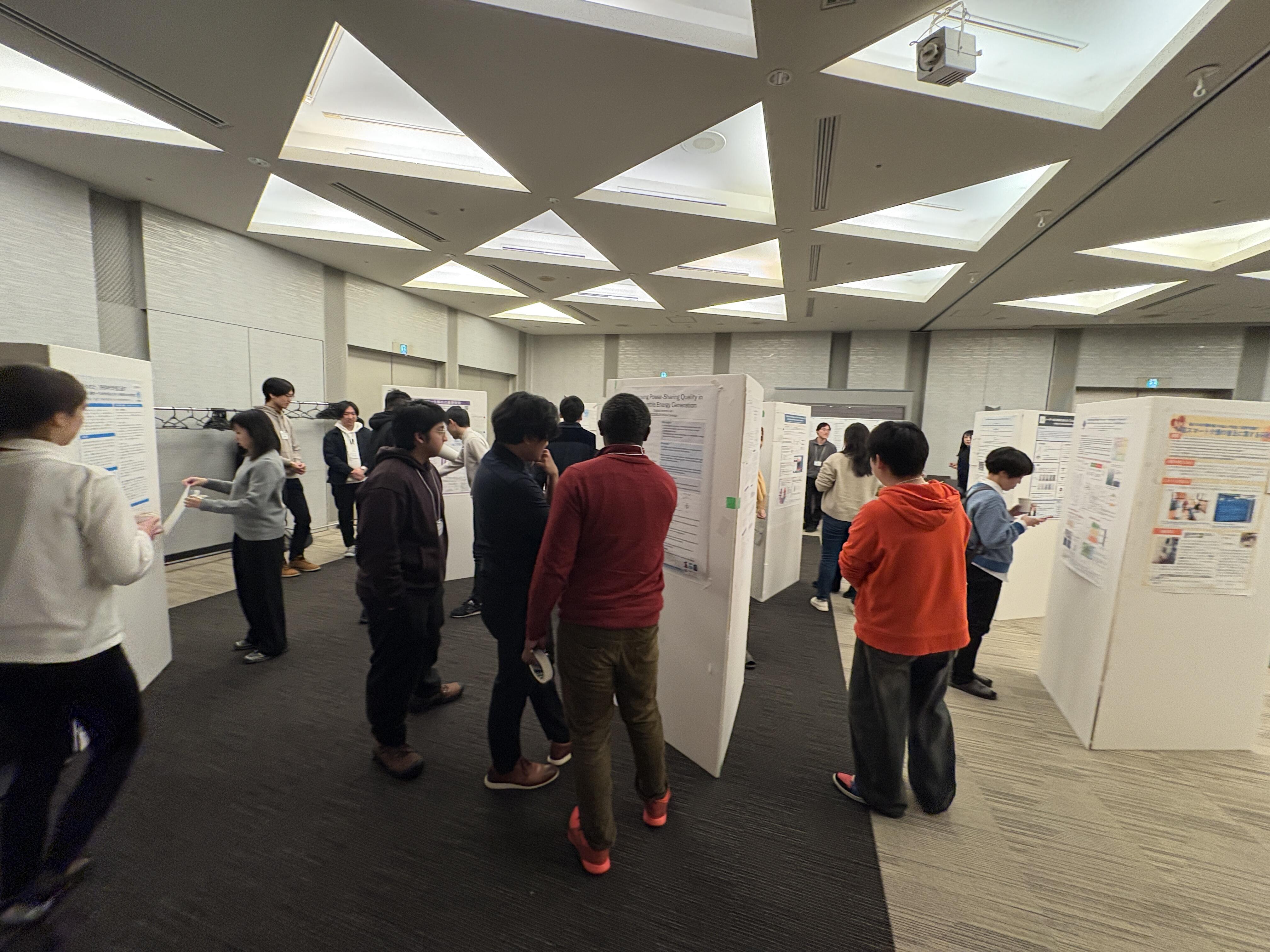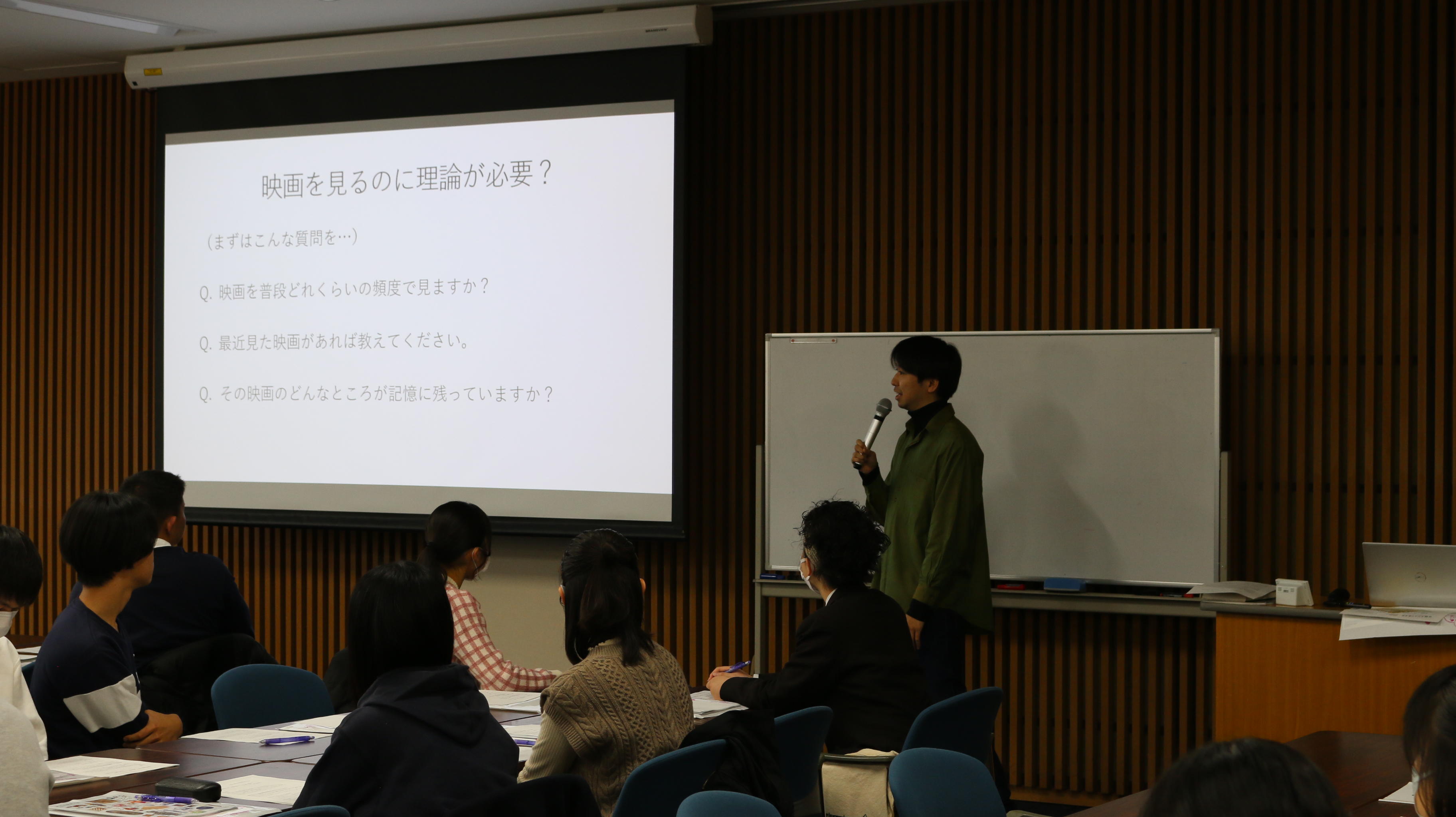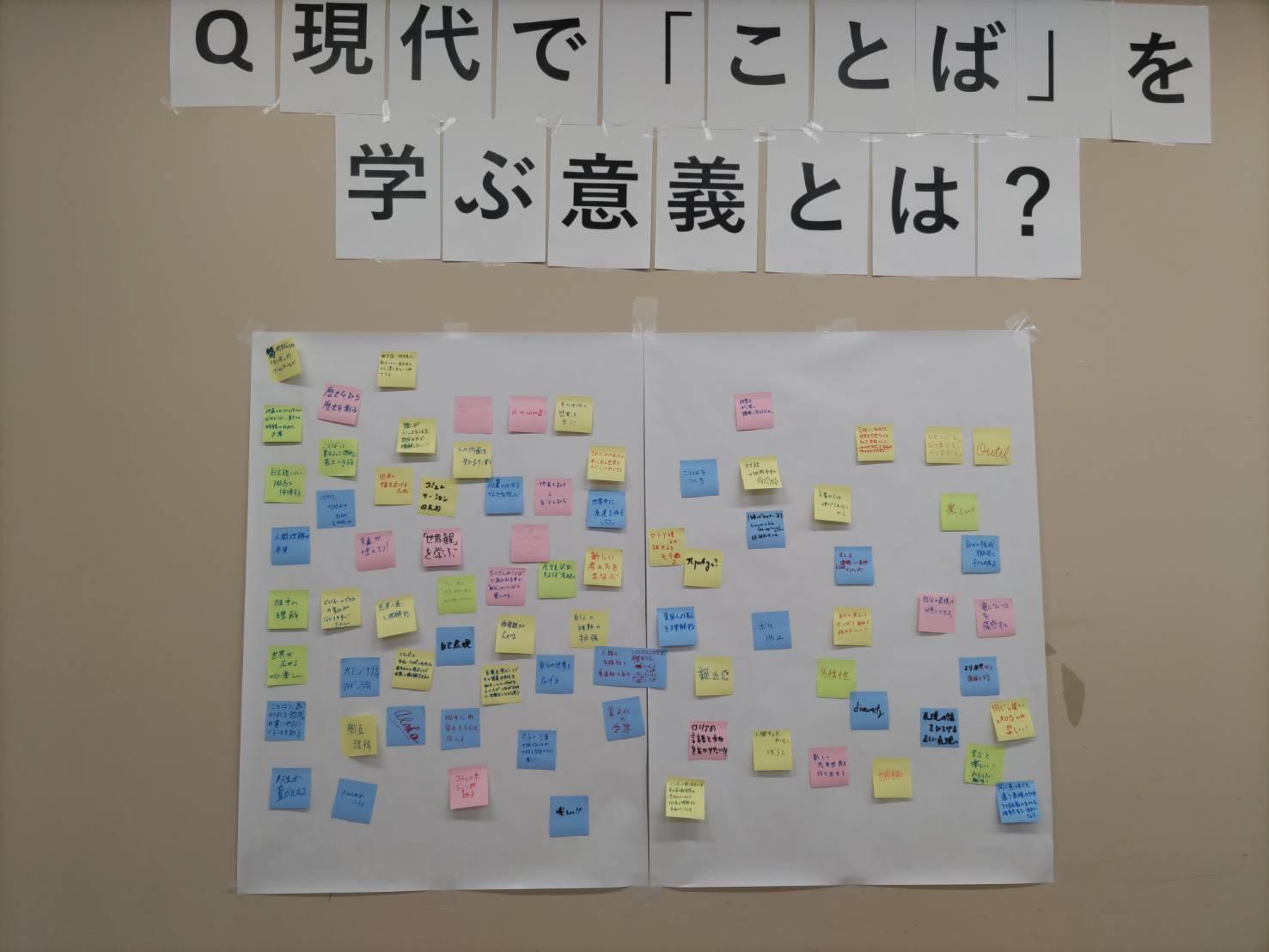宮古池間島ワークショップのブログ連載第4弾、担当は石川です。
本ワークショップにおける活動の一つは宮古語池間方言のフィールドワークだった。フィールドワークでは池間方言について話者に聞き取り調査をする。しかしながら、ワークショップの参加者は言語学を専門とする学生ばかりではない。社会や福祉について研究する者もいるし、ひとくちに言語学といっても社会言語学、日本語学、日本語教育など分野や扱う言語は様々でそれゆえ関心も異なる。
異なる背景や関心を持つ私たちは現地への渡航までにミーティングを重ね、調査内容のすり合わせを行なっていた。その中で、皆が関心を持って調査できそうだと意見が一致した内容が「池間方言のオノマトペの収集」だった。
オノマトペとは擬態語や擬声語といわれる表現のことである。猫の「ニャーニャー」、風の「ピューピュー」、大福の「モチモチ」など日本語で挙げるとキリがない。
実は最近、言語学でオノマトペ研究が熱い。赤ちゃんの言語習得や言語の起源を理解する鍵としてオノマトペが注目されている (今井・秋田 2023 など)。加えて、言語の保存のためにオノマトペに着目した研究やプロジェクトもある (竹田 2012; 横山 2019 など)。琉球諸語のオノマトペを論じた論文も見つかった (下地 2013)。このような背景もあり、池間方言のオノマトペを収集できたら面白そうだと思った。
私は言い出しっぺということもあり、オノマトペに関する文献を読んで、どのような調査票を作るか考えた。秋田 (2023: 150-152) によると、世界のあらゆる言語に存在するオノマトペを見渡してみると、オノマトペが表す内容にはタイプがあり、言語ごとにどのタイプのオノマトペが表せるかが異なる。そしてその類型は階層を成している。以下の階層に示されるようにレベル1がオノマトペで表されやすく、レベル4がオノマトペで表されにくい。
オノマトペの意味階層 (秋田 2023: 151)
レベル1: 声・音(擬声語・擬態語)
レベル2: 動き・形・様態・手触り(擬態語)
レベル3: 身体感覚・感情・味・匂い・色(擬情語・擬態語)
レベル4: 論理的関係
レベル1は声・音のオノマトペで、最も簡単なタイプだ。動物の鳴き声「ワンワン」「ニャーニャー」などがこれに当たる。レベル2は動き・形・様態・手触りのオノマトペで、日本語にはたくさん観察されるから直感的にも分かる。例えば、日本語には動きを表すオノマトペ(「ノシノシ」「テクテク」など)がたくさんある。レベル3は身体感覚・感情・味・匂い・色で、レベル1やレベル2と比べて、これらを表すことができる言語の数は減る。日本語の場合、身体感覚の一つとして痛みや痒さを表すオノマトペ(「ヒリヒリ」「ズキズキ」など)が挙げられる。レベル4は論理的関係。これを表すオノマトペを持つ言語は見つかっていないそうだ。このように、オノマトペの中にもタイプがあり、さらにそこには階層がある。これに沿って池間方言のオノマトペを調べ、日本語と対照したら面白そうだと感じた。
また、何をオノマトペで表すかということには文化的・環境的な反映もあるだろう。例えば、雨がよく降る地域では雨の様態を表すオノマトペが豊富かもしれない。日本語でも「ポツポツ」「ザーザー」「シトシト」など雨の様態を表すオノマトペはいくつも存在する。池間島は海に囲まれており、漁業が盛んだったから、もしかしたら海や波に関するオノマトペがあるかもしれない。私は海の近くに住んだことはないから、波が引く時の「ザー」、波が立つ時の「ザッパーン」くらいしか思いつかない。その土地の風土や文化の現れとして言語を理解する上でもオノマトペ収集は面白そうだと思った。
そして調査初日、調査協力者の具志堅さんとのセッション(調査協力者についてはこちらの記事を参照)。池間島について紹介していただいた後、用意してきた調査票を片手に私は意気揚々と質問を始めた。
「雨がザーザー降っている」は池間方言で何と言いますか?
あみ ぬ っふいうい(雨が降っている)
「ザーザー」のような表現は使わないですか?
はーみ ぬ っふいうい(大雨が降っている)
なんと...具志堅さんはオノマトペを使わないのだ。その後も用意してきた別の質問も聞いたが、どれもオノマトペを使わず、副詞や形容詞、複合語など別の方法を用いて様態の強度や様子を表していた。
例えば、「風がビュンビュン吹いている」だったら「風」を「ちからかでぃ(力風)」と言って「強い風」を表し、「ビュンビュン」というようなオノマトペを用いない。「お腹がキリキリ痛い」だったら「ばた ぬ やみゆい(お腹が痛んでいる)」。「ズキズキ」のように痛みの強度を表す場合は「ちゅーく やみゆい(すごく痛んでいる)」と言う。※
私の池間方言オノマトペ収集計画はこうして頓挫した。翌日からどうしよう...。たちまち焦燥感に襲われた。実は私の場合、渡航前から準備していたテーマがオノマトペだけだったのだ。宿に戻って新しい調査票を準備しなければならない。完全に計画が甘かった。「オノマトペを収集する」という目標は「日本語のようにオノマトペが豊富で日本語と同じような文脈でそれを用いる」という前提が違っていたため達成できず、失敗となった。
その日の夜、メンバーとのミーティングで翌日から何について調査するか話し合った。メンバーと協力した結果、翌日からも充実した調査を行うことができたので結果オーライであったが、この体験から、私はフィールドワークの心得を学んだ。
まず、常にプランBを考える。
他の琉球諸語にもオノマトペは存在するし、日本語もオノマトペが豊富だ。だから池間方言にもオノマトペが豊富にありそれを豊富に用いるという前提で調査を行おうとしていた。しかし、言語の多様性は想像を超えてくる。同じ系統の言語や同じ地域で話される言語は、共通点を持つことが多いが、当然ながら相違点もある。調査においては予測を立てつつも、予測が完全に外れることも認識しておくことが重要だと学んだ。プランB、プランCを合わせて考えておく必要がある。そして、その場に応じた柔軟性や臨機応変さが求められる。
次に、言語と話者と共に。
仮に「オノマトペ」の収集だけを目的としている人がいたとしたら、調査一日目にどうもオノマトペがなさそうだということが分かるや否や、すぐに池間島を去るかもしれない。しかし、私たちの目的はそうではない。私たちはフィールドワークを通して池間島の社会や文化を学ぶことを目的に池間島に来た。今回の言語調査もその一環である。
正直、一週間の滞在では池間島の社会や文化の本当にわずかな片鱗にしか触れることができない。もっと長い時間、その言語、そしてその話者と共に時間を過ごすことでその言語を理解し、記述していくことが重要なのだと感じた。オノマトペ表現がなくても、何か別の表現方法が豊富かもしれない。別の点で池間方言の特徴が見えてくるかもしれない。池間方言と共に過ごし、言語使用の中に身を置いてこそ深く理解できることなのではないかと感じた。
「オノマトペ収集」は失敗したが、この失敗体験も含めて池間島でのフィールドワークは実りあるものとなった。日本国内の別言語を学ぶことによって、言語の面白さ、多様さに改めて気付くことができた。次、池間島に行く時には池間方言のどんな面白いところを知ることができるだろうか?とても楽しみだ。
※ オノマトペの使用には性差といった話者の特性に関する要因も絡んでいることが世界の言語では報告されている。例えば南アフリカで話されるズールー語では女性の方がオノマトペを用い、東アフリカ・コモロ諸島で話されるンヅワニ語では女性に対してはオノマトペを用いない (秋田 2017: 83-84)。池間方言についても他の話者に聞き取りをすると違う結果が得られるかもしれない。また、日本語文を訳してもらう方法ではなく自由に発話してもらう方法を取ったら結果が変わるかもしれない。
参考文献
秋田喜美 (2017)「外国語にもオノマトペはあるの?」In 窪薗晴夫 編『オノマトペの謎: ピカチュウからモフモフまで』岩波書店.
秋田喜美 (2023)「第5章 言語の進化」In 今井むつみ・秋田喜美『言語の本質: ことばはどう生まれ、進化したか』中央公論新社.
今井むつみ・秋田喜美『言語の本質: ことばはどう生まれ、進化したか』中央公論新社.
下地賀代子 (2013) 「南琉球・多良間島方言のオノマトペの形式」『沖縄国際大学日本語日本文学研究 17 (2)』13-32.
竹田晃子 (2012) 『東北方言オノマトペ(擬音語・擬態語)用例集: 青森県・岩手県・宮城県・福島県』国立国語研究所.
横山晶子 (2019) 『シマノトペ』言語復興の港.