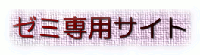ゼミ・ガイダンス
2026 年度向け
来年度(2026 年度)のゼミ生受け入れに向けたゼミ・ガイダンス動画(約 24 分)をこちらに公開しました。ゼミ登録を希望する人は必ず視聴し、条件等を理解した上で手続きを進めてください。
【注意】
・うまく開けないときは、ブラウザで Google トップページに行き、外大のメールアドレスを認証させてから再度リンクにアクセスしてください。
概 要
ドイツ語学のゼミです。「ドイツ語学」については、誤解が多いのですが、いわゆる「語学」としてのドイツ語のことではなく、ドイツ語を対象とする「言語学」という意味です。両者の関係は、計算と数学の関係にたとえれば想像しやすいでしょうか。
計算では、足し算なり引き算なりの演算の手順を覚え、訓練を積み、即座に答えが得られるようになることを目標にします。語学でもまた、語彙や文法のルールを学び(手順)、実践を積むことで(訓練)、自分の考えを言い表したり、他人の考えを理解したりできるようになろうとします(実用的な能力の習得)。これに対し、数学では個々の演算をいかに早く正しく行うかではなく、そもそもどうして演算というものが可能なのか、自然数同士の足し算では答えも必ず自然数になるのに、引き算では必ずしもそうならないのはなぜなのかといった、より根源的な問いに向き合います。言語学でも同様に、いわゆる「語学力」を高めることは目標ではなく(それは専攻語の授業等で磨いてください)、そもそも人はどうして言葉を使うのか、その表現の仕方が諸言語間でどのように共通し、どのように異なっているのか、また、それはなぜなのか、といった問いに関心を向けます。その際、対象として特にドイツ語に重点を置くのがドイツ語学というわけです。
もっとも、こうした言語学(ドイツ語学)の問いは、いわば究極のものであり、それだけではあまりに広大で漠然としています。そこで実際に取り組む問いはもっと範囲の絞られた、具体的なものになります(下記「卒論・卒研について」参照)。ゼミでは、3年生の段階で各自追求するテーマを決めてもらい、少しずつ調査・考察を進めながら、最終的に卒業論文につなげてもらうようにしています。与えられた課題に取り組めばよいというものではないので、大変に思う人もいるかもしれませんが、あまり心配しなくて結構です。語学としてドイツ語を学習する中で、これまでは「そういうものだから仕方ない」と割り切って覚えてきたものの、本音のところでは「どうしてそうなのだろう?」と不思議に思っていることはあるでしょう。そういう「不思議だな」という気持ちを素直に解きほぐしていけば、案外、簡単にテーマは見つかるものです。また、授業は3年生・4年生合同で行うので、3年生は4年生のやり方を参考にすることもできるでしょう。希望する人には、大学院の演習にオブザーバーとして参加することを勧めますし、学内外の各種研究会も案内します。
卒業論文・卒業研究について
これまでに指導した卒論テーマです:
- ドイツ語文中における „auch“ の特殊な位置の分析
- ドイツ語の名詞化における接尾辞 -ung と接尾辞 -ion の競合と区別
- ドイツ語の sein zu Infinitiv 構文と他のモダリティ表現の比較 ―知覚動詞 hören との共起例の調査を通じて―
- ドイツ語のbekommen受動に関する分析
- ドイツ語不定冠詞の性質と効果に関する再考:名詞の定性という観点から
- 英独翻訳時の過去時制選択法則性について考える ―ドイツ語・英語の現在完了形に着目して―
- ⽇本語とドイツ語のキャラクター命名傾向の違い ―ポケモンの命名傾向の分析―
- ドイツ語ラップの押韻における音声類似度と押韻頻度の関連性
- ドイツ語名詞一語文の機能 ―冠詞の共起を手がかりに―
- ドイツ語における「左右」の意味の広がり
- ドイツ語 man の間投詞用法について
- よりよく伝わるドイツ語の発音のために〔卒業研究〕
- Denglisch の傾向調査~ 独語書籍をもとに ~
- ドイツ語発音練習教材の作成〔卒業研究〕
- ドイツ語移動動詞steigen の意味について ― 方向前置詞句との共起を手掛かりに ―
- Absentiv 不在構文について ― 反使役文から派生した状態受動との類似性からの考察 ―
- ドイツ語結果構文における前置詞 zu がもたらす意味について
- 機能動詞としてのfinden ― 本来的意味の有無と文法化 ―
- オーストリアにおける小辞 eh の機能について ― ドイツ語心態詞の語用論的分析 ―
- 移動動詞kommen の意味 ― 直示的・非直示的用法の考察 ―
- 動詞領域の結束性と否定辞の配置 ― wagen とzu 不定詞の従属連鎖を例に ―
- 強調の接頭辞sau とその使用について
- ナチズム下のジョーク
- ドイツ語圏スイスの言語状況について ― 香港との対照分析 ―
- 逆接表現 und doch と aber doch の比較
- 現代ドイツ語の前綴り ver- による形容詞派生動詞の意味と自他
- 日独慣用句における赤・黒・白の色彩語比較対照
- ドイツ語の二重完了形の機能と出現条件についての分析―動詞の語彙的アスペクトの観点から―
- ドイツ語オノマトペによる類像性仮説の検証
- 要求を遂行する文における心態詞dochの分布
- 壁塗り交替:ドイツ語と日本語の対照
- ドイツにおける移民社会の様相 ― トルコ系移民を中心に ―
- ドイツ語二人称代名詞と親称、敬称語彙の使用について ― 大学における若年層を対象に ―
- 日本語の複合動詞とドイツ語の分離動詞の対照 ― 後項動詞「~込む」と前つづり「ein-」の意味機能について ―
- 動物名称を使った慣用表現に関する日独比較 ~ Hund/犬・Pferd/馬・Katze/猫の比喩的概念 ~
- 形容詞述語の意味構造と相関詞esの出現の義務性・任意性 ― 事実性の観点から ―
- ドイツ語の他動詞構文と再帰構文 ― 主格のもつ意味役割及び動詞の意味が変わらないものを対象に ―
- ドイツ語の他動詞における与格の実現条件
- 五感に関する身体部位を含むイディオムの日独比較 -口と鼻に関する考察-
- 翻訳にみる人称表現の日独語対照 -マンガの会話表現を例にとって-
- ドイツ語における移動動詞の完了助動詞選択について
- 名詞指示内容の非実在性と冠詞の選択について
- ソルブ語標準語の形成過程とドイツ語の影響
- 現代ドイツ語におけるnichtとkeinの用法について -コーパス調査を基に-
- ネイティブのイントネーションを習得するためには -Praatを利用したドイツ語の新しい発音指導法の提案-
- バイエルンのギムナジウムの教育指導要領にみる方言教育
- ドイツ語における日本語からの借用語の性決定方法 -ドイツ語の性決定方法は適用できるか-
- 日本語オノマトペはドイツ語でどう表現されるのか -小説を用いた日独対照-
- ドイツ語程度副詞 sehr と ganz -強め方の違い
受講上の注意
- 受講条件
CEFR の B1 相当のドイツ語力が必要です。専攻言語としてドイツ語を履修した人は 3 年次への進級要件を満たすことで、自動的にこのレベルに達していると見なします。教養外国語による履修の場合は、個別に相談に応じます。
- 卒論のテーマについて
ドイツ語に関わるものであれば、基本的には何でも構いません。3年進級時に明確になっていなくてもよいですが、早くから意識しておいたほうがよいでしょう。文法論、語彙論のほか、音韻論、語用論、歴史言語学、方言学、社会言語学なども、ドイツ語を対象とする限り立派なドイツ語学のテーマとなります。また、ドイツ語学プロパーでなく、他言語(英語や日本語など)との対照研究や学際的研究(翻訳論、文学作品の言語学的分析、言葉と音楽など)も OK です。
- ゼミ・ガイダンスについて
上述の方面で卒業論文を書きたいと思う人であれば、基本的にどなたでも受け入れます。これまで希望者が 1 学年 10 名を超えたことはなく、ゼミ選抜は想定していません。ただし、10 ~ 11 月にゼミ・ガイダンスは行います。ゼミ入りを希望する人は、必ず出席してください。日程等の詳細はこのサイトで周知します。
- サブ・ゼミとしての受講
OK です。

ベルン = '19.03.05. 科研費研究プロジェクトの一環としてスイスに赴き、首都ベルンの文書館にて同国出身の 19 世紀の言語哲学者 Anton Marty の遺稿調査を実施しました。