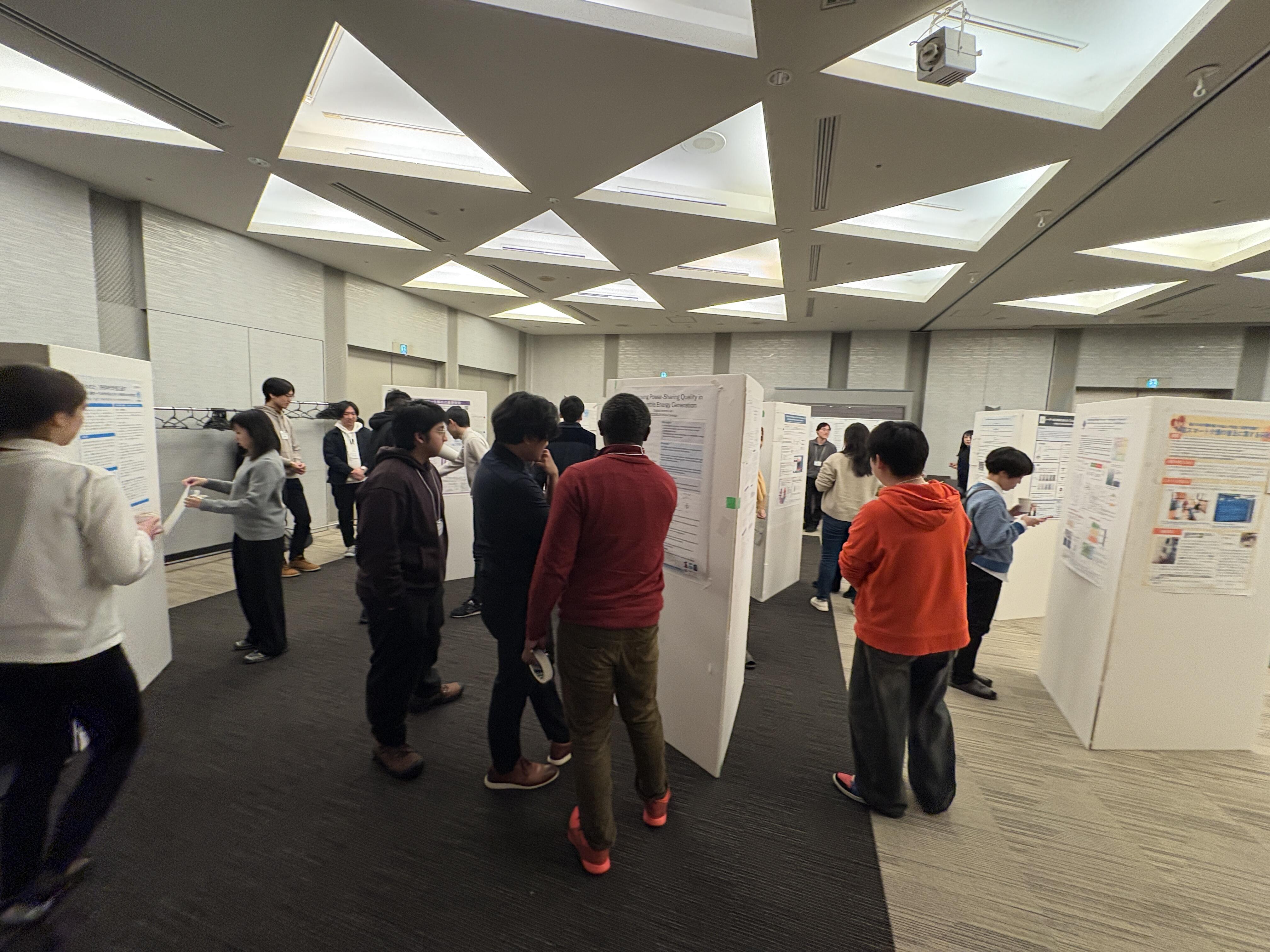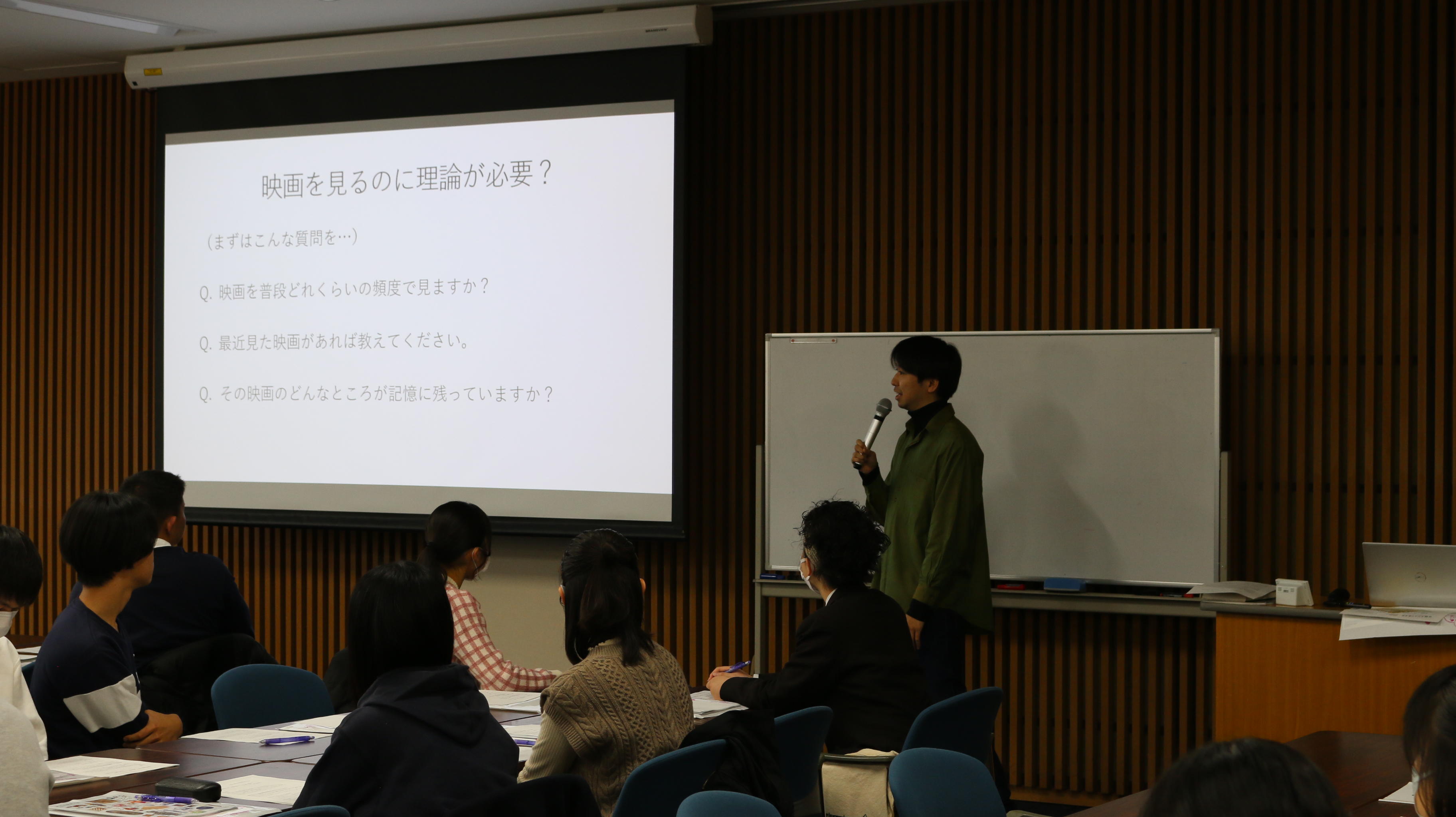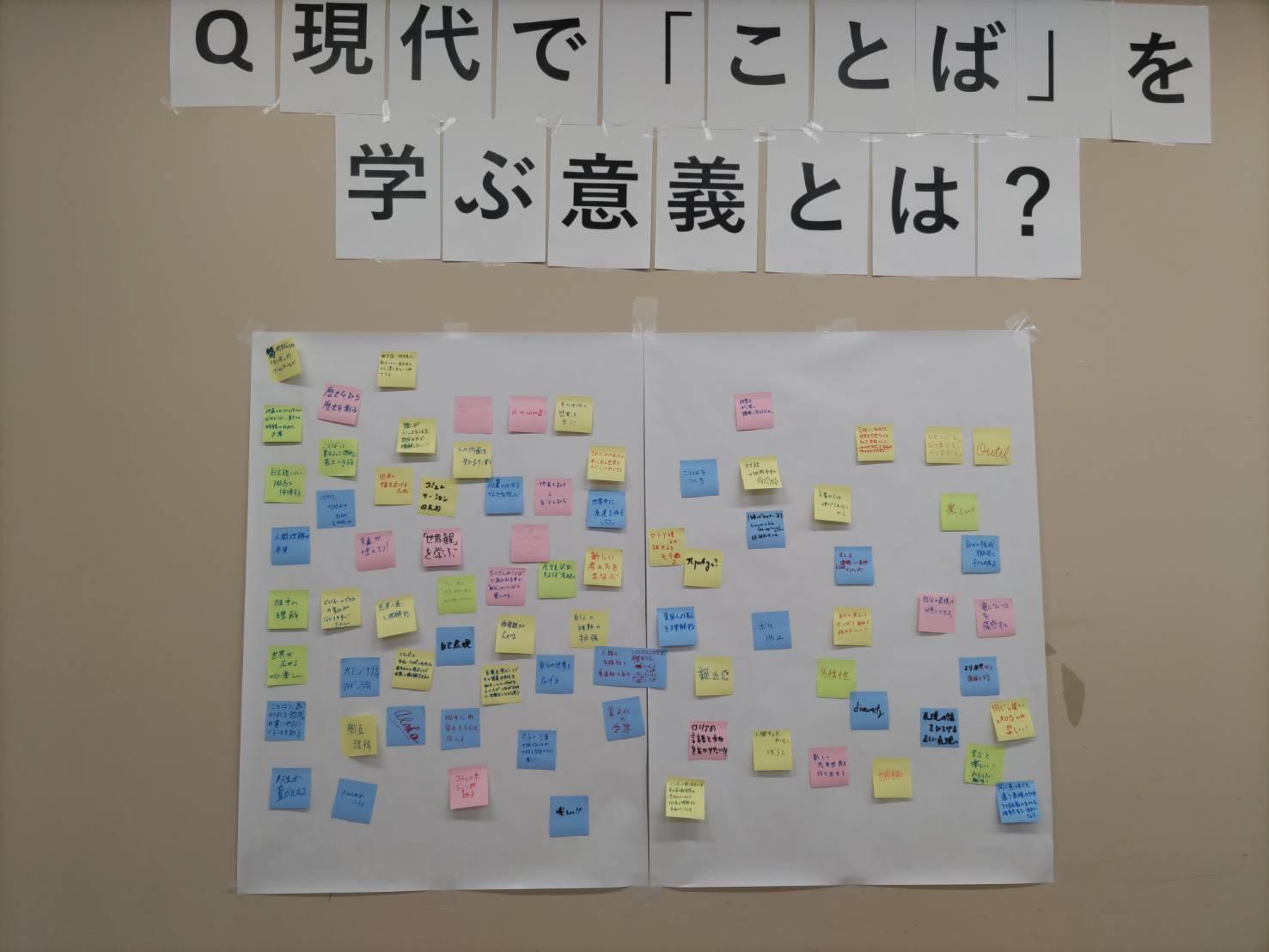この度、MIRAI-5期生の井上共誇さんが、以下のとおり論文を発表しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発表日:
2025年9月6日
区分:
口頭
発表した学会:
International Conference on Gender Studies: "Que(e)rying Gender"(https://genderstudies.lcir.co.uk/gender-nonconformity-conference/)
題目名:
"An Analysis of Henry James's The Bostonians in the Light of Asexuality"
概要:
ヘンリー・ジェイムズ (1843-1916) の作品を、ジェンダーとセクシュアリティの観点から読み解く試みが近年増えている。「意識の描写」や「視点の技法」を駆使し、多義的な読みを可能にするジェイムズの文体が、登場人物のジェンダーやセクシュアリティの揺らぎ、そしてその揺らぎが元となり複雑に絡み合う人間関係の綾を描くのに非常に適したものであることが、その原因の一つとして挙げられることに、まず疑いはないだろう。だが、それに加えて、現代社会に蔓延する閉塞感とオープンな視点を求める動きもまた、ジェイムズ作品をジェンダーとセクシュアリティの観点で読み解くという今日の傾向を助長する要因だと考えられる。19世紀末のアメリカとイギリスで、ジェンダー、セクシュアリティに対する認識が社会の中で多様化しはじめたとき、その変化に揺れ動く人々の心を具に描いた作品がこの時期のジェイムズ作品に多く見られる。これらの多様化する価値観が社会に混在しているという状況にもかかわらず、それらを捉える認識の枠組みは固定されたままであるという現実は、当時と比べ現代でもさほど変わっていない。それゆえ、認識の固定化を解放する手段の一つとして、ホモセクシュアル、ヘテロセクシュアルといったような二項対立的な議論を超えて開かれた読解をすることの意義は熟考に値する。
本発表では、ヘンリー・ジェイムズの中期の小説 The Bostonians (1886) を題材とする。ホモセクシュアル、ヘテロセクシュアル、アセクシュアルなどの多様なセクシュアルティとそれらが形成する愛の形が作品の中で紡ぎ出されているという観点でこの作品の解釈を行うことで、ジェイムズの問題設定の背後にある、家父長制が優位を保つ社会でのジェンダー規範を解体する読みを試みる。また、そのための主な方法論として、同じくヘンリー・ジェイムズの中編小説 'Beast in the Jungle' (1903) について、イヴ・コゾフスキー・セジウィックが『クローゼットの認識論』で主張した同性愛的解釈を批判的に発展させたNick Adler による "Beast Imperative" (2022) の主張に触れる。その上で、 Adler がこの作品の主人公、ジョン・マーチャーのアイデンティティにアセクシャリティの可能性を見出したように、The Bostonians の主人公、オリーヴ・チャンセラーにもアセクシュアリティの可能性を見出す解釈を行う。
発表の動機:
自分自身の研究テーマの一つであるジェンダー、セクシュアリティについて、専門領域の文学の枠組みを超えてinterdisciprinaryに議論できる機会だと思い参加しました。
本人コメント:
interdisciplinary な学会ということで、文学だけではなく、教育、歴史、映画、ファッションなどを専門にする研究者が参加する学会でした。また、オンラインという特性から、多くの国からの参加者と意見を交換でき非常に刺激的な機会となりました。専門、地域に違いはありますが、根本にある思想は共通したものがあると感じました。ジェンダー、セクシュアリティを語る際の視点の固定化をなくすことで、寛容で開かれた「場」を社会に作ること。私の信念を共有する研究者との出会いは、今回の最大の収穫でした。一番初めのセッションのトップバッターのプレゼンテーションを務めさせて頂いたのですが、パソコンがなぜか固まりスライドを動かせなくなるという惨事が起き、ヴィジュアルエイドなしで発表しました。伝わりやすいようにアイコンタクト、ジェスチャー、発音、イントネーションなどにいつも以上に気を配りました。スライドが作動せず、明らかに動揺している私にハートのリアクションを飛ばしてくださったりと皆さんがとても暖かくて感動しました。
これは余談ですが、真顔で Oh my goooo!! と連呼したのは人生初でした(笑)