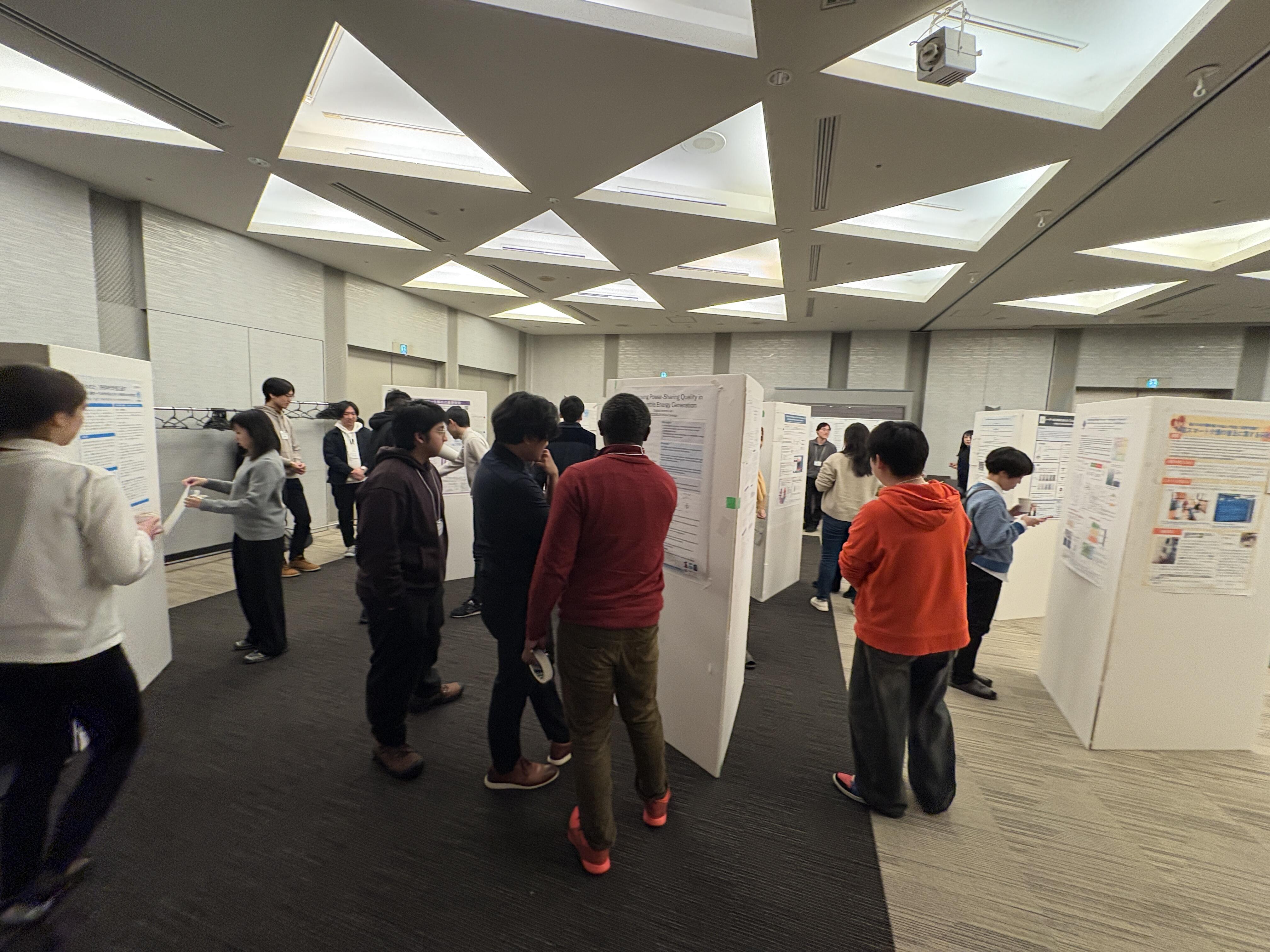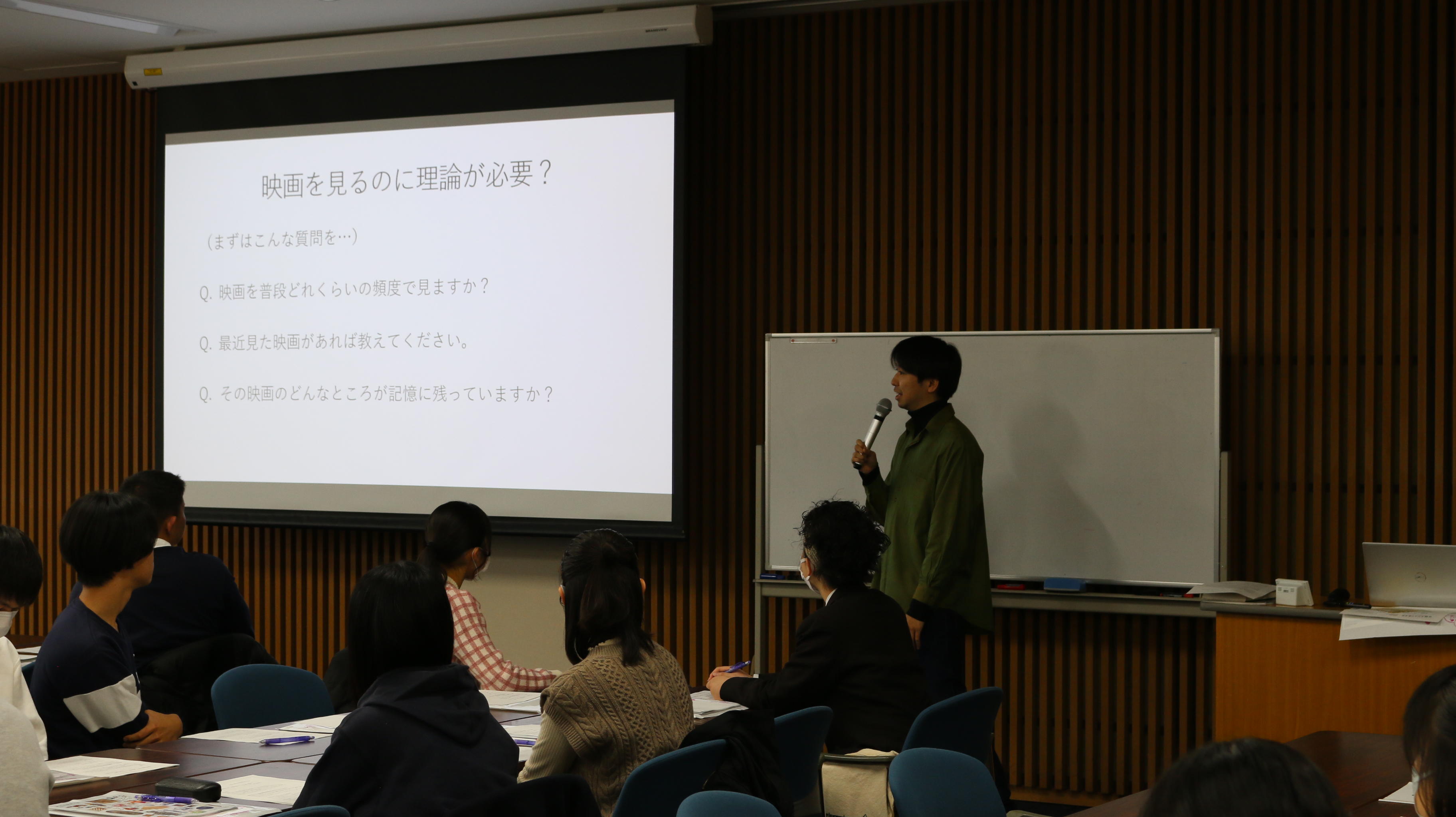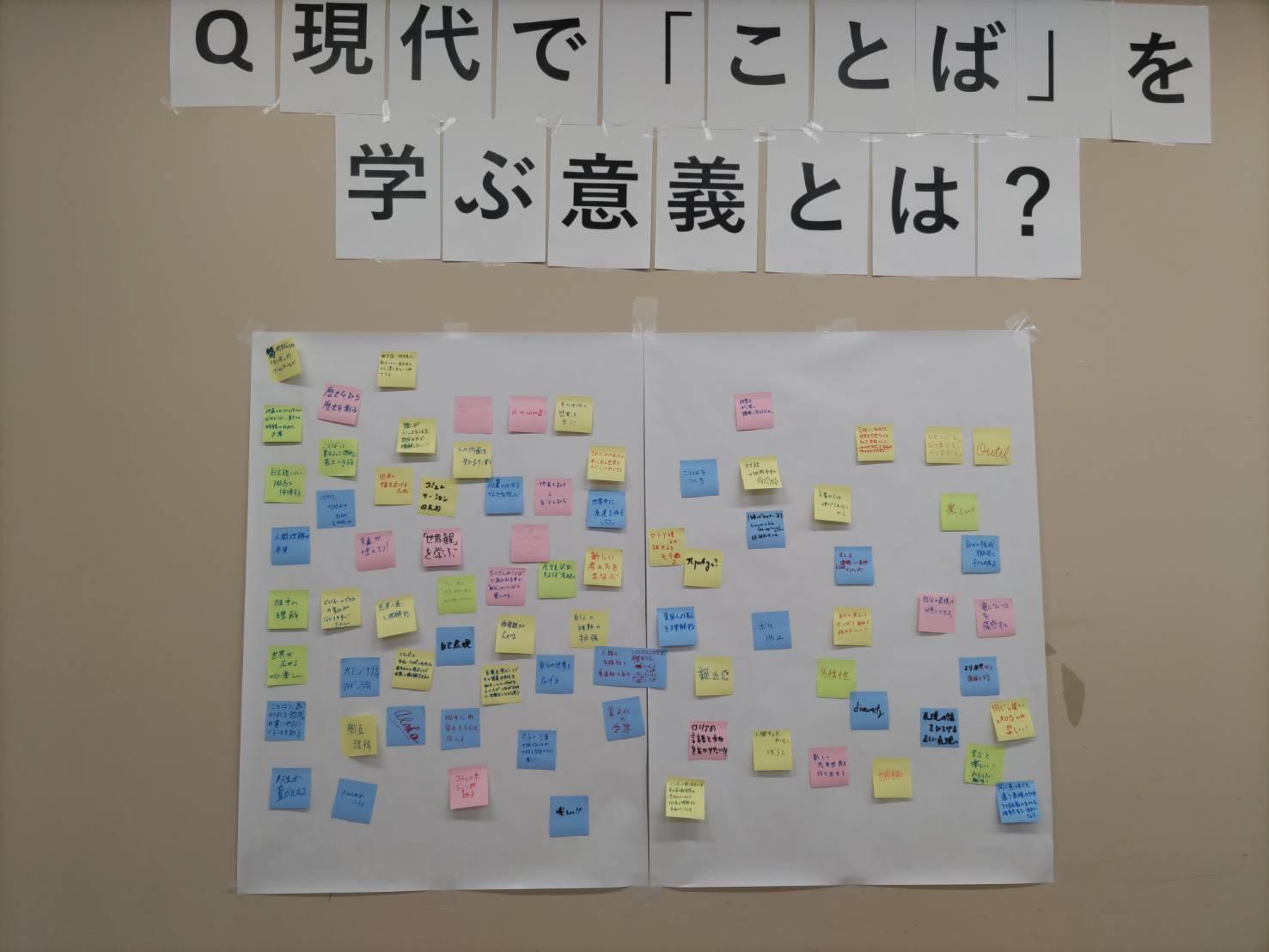宮古池間島ワークショップブログです。今回の担当は小林美奈です。
私たちは方言・文化調査のために去年12月16日から22日まで池間島に滞在しました。
池間島とは沖縄県の宮古島市平良池間に属する離島です。私たちは羽田空港から出発し、飛行機で3時間半ほどで、2000キロ離れる宮古空港に到着しました。憧れの南国島との初対面は肌寒い雨の中でした。空港から車で池間大橋を渡り、一時間ほどして、一軒の空き家となった民家に到着し、ここが私たちのこれから一週間の家でした。
一週間の滞在で、私たちは「きゅーぬふから舎」や「池間公民館」などで現地の方々とふれあい、様々な話を聞くことができました。方言と文化の調査以外に、浜辺を散歩し、珊瑚拾いをしたり、ゴミ拾いをしたりもしました。「池間湿原」探険や「池間遠見番所」見学もしました。美しい海を眺めながら、池間の歴史を聴き、天然記念物のヤドカリとも出会えました。また、皆さんが、一緒に買い物したり、食事をつくったりをし、一週間の生活で、かけがえのない時間を過ごすことができました。
たくさんの話題の中から、今回ご紹介したいのは、私が特に印象に深く残るおばぁとあぶら味噌の話でした。
池間島に到着した日の夜、現地の方があぶら味噌を届けてくださり、まだ落ち着かない私たちの心を和ませてくださいました。それから一週間の期間中も毎日ご飯のお供としてそのあぶら味噌を食べていてやみつきになってしまいました。

あぶら味噌とは、味噌が具と一緒に炒められたものです。ここでは調味料としてではなく、おかずとして沖縄で古くから親しまれてきました。池間島でも、16世記から琉球王国の統治下であったため、沖縄から流入し、家庭常備菜として池間島の生活伝統にもなじまれてきたと言われています。
ちなみにあぶら味噌は、油が入ってるの?と気になって調べてみました。沖縄や、宮古で、豚のラド油で味噌と具を炒めて作るため、あぶら味噌との名前になったと言われています。沖縄でアンダンス―と呼ばれています。
インタビューの際にあぶら味噌について島のおばぁに話を聞きました。
少し前までは手作りの味噌を作っていました。ゆでた大豆に米麴を混ぜ、大きなカメ壷に入れ、約2−3ヶ月寝かせると、おいしい味噌が出来ました。昔から池間島の家は大体味噌作り用に一斗カメ、二斗カメ、三斗カメなど、もっと大きなカメも持っていました。
 あぶら味噌の作り方は、各家庭によってそれぞれなようです。おばぁは話を続けました。
あぶら味噌の作り方は、各家庭によってそれぞれなようです。おばぁは話を続けました。
池間島はカツオ漁が隆盛した時代がありました。その影響か、池間島のあぶら味噌は、カツオを使っています。家庭では、カツオのなまり節を粗く砕いて、使っています。私はカツオのなまり節と豚肉を刻んで作っていました。いつもたくさん作っていて、孫や友達にもあげていました。
おばぁは、若いころ沖縄に行った時のことも話してくださいました。
沖縄で台湾から来た学生が落花生をくれました。あまりにもおいしかったので、池間島に帰った後、真似して落花生を栽培しました。収穫した落花生で初めて落花生のあぶら味噌を作りました。とても美味しくて、孫たちに喜ばれました。
このように独創的なアイディアによって家庭ごとのオリジナリティが出るのも手作り味噌の醍醐味かもしれません。あぶら味噌は冷蔵庫のない時代では保存食とされてしていました。ごはんに乗せて食べたり、他の料理の味付けに使ったり、昔から愛され続けてきました。私たちは帰る前日のパーティで、島の方に刺身にかける味噌ソースの作り方を教えていただきました。作り方は簡単で、味噌を水で溶かしてかけるだけでした。ソースかけの刺身はみんなも初めてで、とてもおいしくいただきました。

今回私たちは人数分のあぶら味噌をいただき、家族にもよいお土産ができました。わさび醤油とあぶら味噌で食べ比べてみようと思い、刺身を買ってきました。味噌の甘みと生の鰹節のうまみが飲み込んだ後口に残る香ばしさ......池間島の日々を思い出しながら、しみじみと味わいました。
(MIRAI2期生 小林美奈)