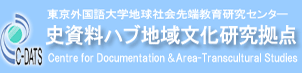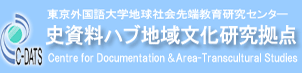2006年12月16日,17日
14:00-16:00
|
|
●第II分科会 国際会議
「アジア・アフリカ史資料学の現在と地域文化研究」
事業分担者の井尻秀憲が班を代表して「21世紀地域文化研究」の概念化に関してパネリストとして報告した。
|
2006年10月30日
|
|
●第I分科会
下記イベントの報告集をまとめ、『9・11後5年、アフガニスタンは今』(東京外国語大学大学院・国際協力講座編)として刊行した。セミナーのすべての講演を図版と写真入りで収録し、巻末に配布資料と参考資料とを付した。
|
2006年10月6日
|
|
●第I分科会 COE+国際協力講座+連携講座 拡大セミナー
「9・11後5年、アフガニスタンは今」
15:00 - 18:00 於:東京外国語大学研究講義棟102番教室
○第1セッション「国際復興支援と日本」
田邊隆一 元アフガニスタン支援調整特命全権大使
藤枝修子 開発途上国女子教育協力センター
松島正明 元JICAアフガニスタン事務所長
コメンテーター:阿部晴樹 JICA・連携講座客員教授
○第2セッション 「アスガニスタンの現況」
福元満治 ペシャワール会広報担当理事
伊勢崎賢治 東京外国語大学
八尾師誠 東京外国語大学
9.11とアフガン攻撃から今年で5年になる。イラク戦争とその後のイラク泥沼化で後景に退いてしまったアフガニスタンは今どうなっているのか。日本は国際的な復興支援体制の中で最大の資金拠出国としての役割を担っているが、その支援はどのようになされているのか、そして不穏が伝えられるアフガニスタンの現況は? 2つのセッションを組んで検討した。
第1セッションでは、田邊元特命全権大使から、国際復興支援の枠組みとそのなかでの日本の役割について、藤枝氏からは、日本の支援のひとつの特徴ともされている女子教育支援の状況について、また実際の支援活動を束ねるJICAの現地事務所長を務めた松島氏からは、カブール周辺の最近の状況や援助状況についての報告があった。これに、コーディネーターの阿部氏から的確な問題点の指摘と質問がなされた。
第2セッションでは、公的枠組みとは別に、援助の現場に関わる観点からアフガニスタンの現況についての報告を受けた。まず、20年以上にわたってアフガニスタンの医療援助を行っているペシャワール会(中村哲代表)から、福元氏に会の活動とここ二、三年の現地の状況についての報告がった。ついで、外務省の依頼で武装解除の任にあたった本学教授の伊勢崎氏から、最近ととみに混迷が伝えられるアフガニスタンの治安状況とその問題点について、生々しい報告があった。最後に、本学が関わる文化財保護事業を担当している八尾師氏から、事業遂行の現状と問題点について報告があった。
なお、これに加えて、インターセッションとして本学大学院生でアフガニスタン取材の経験が長い牧良太氏が、フォト・プロジェクションを解説を交えて行った。
悪天候だったにもかかわらず、学内外から多数の人びとの来場をえ(120名)、関心の広さをうかがわせた。
| 当日の様子 (クリックで拡大) |
 |  |
| 会場風景 | 第1セッションの様子 |
 |
| 第2セッションの様子 |
|
2006年10月4日
18:30-20:30
|
|
●第II分科会
「安全保障分野でのグローバル・パートナーシップ」
渡邊啓貴(東京外国語大学外国語学部教授)
「マイノリティの自治と自決権」」
西立野園子(東京外国語大学外国語学部教授)
社会系列共同研究室(研究講義棟541号室)
|
2006年7月14日
|
|
●第I分科会
前年度の二つの企画「〈人間〉の戦場から」および「グローバル化と奈落の夢」の討議内容をまとめ、さらにいくつかの論考と資料を加えて、研究双書の一冊として『グローバル化と奈落の夢(The Nightmare of Globalization)』(西谷修・中山智香子編)を上梓した。
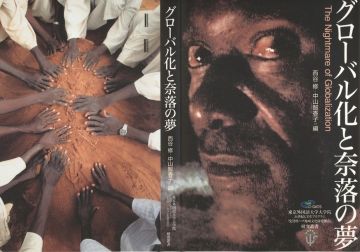
二つの企画がともに海外からメインゲストを迎える国際企画であったこと、また現代メディアの状況が議論のひとつの軸になっていたことから、海外に対してもこの成果の一端を発信すべく、シンポジウムおよびワークショップの部分を英訳して日英二ヶ国語版として出版した。
|
2006年7月6日
18:30-20:30
|
|
●第II分科会
「上海調査と21世紀地域文化研究の方向性」
澤田ゆかり(東京外国語大学外国語学部教授)
社会系列共同研究室(研究講義棟541号室)
|
2005年10月14日
~15日 |
|
●第I分科会
映画上映 + 討論会 + ワークショップ
《 グローバル化と奈落の夢 》
1) 映画 『ダーウィンの悪夢』 上映会 + 討論
日時 : 10月14日 (金) 16:45 - 20:15
会場 : 東京外国語大学 研究講義棟2F 226教室
16:45 映画紹介と趣旨説明 (西谷)
17:00 - 18:45 映画 『Darwin's Nightmare』 上映
19:00 - 20:15 Hubert Sauper 監督を迎えての質疑
質疑参加者
フーベルト・ザウパー (映画作家)
西谷 修 (東京外国語大学)
中山智香子 (同)
協賛 : 山形国際ドキュメンタリー映画際事務局
2) ワークショップ
日時 : 2005年10月15日 (土) 10:30 - 12:30
会場 : 東京外国語大学 本部管理棟2F 中会議室
討論参加者
フーベルト・ザウパー
桜井均 (NHKエグゼクティヴ・プロデューサー)
日置一太 (NHKスペシャル・プロデューサー)
大森淳郎 (NHKスペシャル・プロデューサー)
真島一郎 (東京外国語大学 AA研)
船田クラーセンさやか (東京外国語大学 外国語学部)
共同司会
西谷 修 (東京外国語大学大学院)
中山智香子 (東京外国語大学大学院)
今年春フランスで好評を博し、山形国際ドキュメンタリー映画際に出品されたフーベルト・ザウパー監督『ダーウィンの悪夢』を軸に2日間の催しを行った。
初日は上映会と監督を囲んでの討論。
| 1日目・上映会の様子 (クリックで拡大) |
 |  |
| 上映風景 | ザウパー監督 |
 |  |
| 会場の様子 | タンザニアの学生 |
今回も会場には本学や他大学の学生の教員ほか、映画の噂を聞いて駆けつけた関心をもつ人びと、周辺の市民の方々など、多彩な顔ぶれが集まり、300部用意した資料が足りないほどだった。
映画はタンザニアのビクトリア湖畔の町ムワンザが舞台。生態系の宝庫で「ダーウィンの箱庭」と呼ばれたこの大湖に、大型肉食魚ナイルパーチが放たれたことから状況は一変。魚の白身は輸出食品となり、フィレがヨーロッパや日本(!)に輸出されるが、湖畔の住民の生活は崩壊した。アルコールに浸る男たち、広がる売春とエイズ、粗悪なドラッグに頼って路傍に眠る子どもたち…。工場の国際基準を称賛するEUのミッションは、魚を運ぶロシアの輸送機、だがその輸送機は往路アフリカの戦地に密輸兵器を積んでくるのだという。グローバリゼーションの奈落を深海の悪夢のように描くドキュメンタリー。
( 公式HP→ http://www.hubertsauper.com/ )
衝撃的な映画上映のあと、真剣なまなざしを向ける観衆を前に、ザウパー監督は取材について、作品制作について、作品に盛り込めなかったことについて予定時間を超えて熱心に語った。アフリカに見るグローバル化の一端についても議論がなされ、最後にタンザニアからの留学生の感謝をこめた発言もあった。
2日目は、今年NHKスペシャルで『アフリカ・ゼロ年』という4回の番組を制作したスタッフと、本学のアフリカ研究者を交え、グローバル下のもとでのアフリカについて、ドキュメンタリーのあり方についてなど、2時間だが密度の高い討議を行った。
| 2日目・ワークショップの様子 (クリックで拡大) |
 |  |
| NHKアフリカ取材班と | ザウパー監督 |
 | |
| 船田 (前列奥) 真島 (前列手前) | |
二日間の記録は、6月の企画の記録とともに来春COE活動報告としてまとめる予定。
|
2005年6月13日
~17日 |
|
●第I分科会
写真展+シンポジウム
<人間>の戦場から ~ 視角の地政学 · Ⅱ ~
写真展
日時 : 6月13日(月)13:00より17日(金)18:00まで
会場 : 東京外国語大学 研究講義棟1階ガレリア
シンポジウム
日時 : 2005年6月17日(金) 15:00~18:00
場所 : 東京外国語大学 研究講義棟 226番教室
シンポジウム報告者
イヴリン・ホックシュタイン (Polaris)
栗田禎子 (千葉大学)
岡真理 (京都大学)
企画・進行
西谷修 / 中山智香子 (本学)
第1回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞で、アフリカを取材した優れたシリーズ写真で入賞したケニア在住の Evelyn Hockstein さんを招き、その写真展を開催するとともに、「アフリカ、戦争、貧困、難民、女性/いま<人間>であることが試される戦場/メディアの壁を超えてグローバル世界の現況を見る」をテーマに、二人の専門家の報告を交えて討議した。
招待者はすべて女性で、それぞれ違った立場、違った角度から発言したが、充実した意義深い報告がなされ、会場を埋めた200余人の聴衆も熱心に聞き入った。アフリカの難民キャンプの取材、その写真を通してわれわれに伝えられる現場、グローバル化のなかで起こっている事態、触発されるれわれわの関心そのものに隠れた地政学、そこで問われる「人間の尊厳」、それを単にアフリカの問題としてでなく、われわれ自身の現在そして過去の問題へと共鳴させること…、などをめぐって広がりのある議論が展開され、その反響は多くのアンケートに残された。
講義時間に重なっていたが、外部から多数の聴衆が訪れ、とりわけ調布市からの参加が目立ち、この種の企画に対する地元からの関心の高まりが感じられた。
 |  |
| 写真展の様子 (6月13日/クリックで拡大) |
 |  |
| シンポジウムの様子 (6月17日/クリックで拡大) |
|
2004年11月22日
15:00~17:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「戦後の国際農業交渉 ──回顧と展望」
講師: 遠藤保雄 (国際連合食料農業機構日本事務所長)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
2004年11月19日
10:30~19:40
|
|
●第I分科会
ビデオ上映とパネル・ディスカッション
沖縄、記憶と映像Ⅴ
『島クトゥバで語る戦世』を見る |

ポスター (クリックで拡大) |
<上映会> 10:30~18:00
『島クトゥバで語る戦世』 全編6時間一挙上映
<パネル・ディスカッション> 18:00~19:30
パネリスト
比嘉 豊光 (写真家、琉球弧を記録する会)
仲里 効 (APO代表、『EDGE』編集長)
司会・コメンテーター
西谷 修 (東京外国語大学)
|
 昨年度の企画「沖縄、未来のドキュメンタリー」の延長として、沖縄戦を生き延びた生存者の証言を各地の方言で記録した『島クトゥバで語る戦世』(「琉球弧を記録する会」製作、2003年)全編6時間の一挙上映を行い、製作者代表の比嘉豊光氏と、昨年の山形国際ドキュメンタリー映画祭の沖縄特集を企画した仲里効氏を招いて、この作品の製作意図、意義などについて議論した。 昨年度の企画「沖縄、未来のドキュメンタリー」の延長として、沖縄戦を生き延びた生存者の証言を各地の方言で記録した『島クトゥバで語る戦世』(「琉球弧を記録する会」製作、2003年)全編6時間の一挙上映を行い、製作者代表の比嘉豊光氏と、昨年の山形国際ドキュメンタリー映画祭の沖縄特集を企画した仲里効氏を招いて、この作品の製作意図、意義などについて議論した。 |
|
2004年11月1日
~11月4日
|
|
●第I分科会
国際シンポジウム/セミナー/写真展
(画像をクリックすると大きな写真がご覧頂けます)
Ⅰジェームズ・ナクトウェイ/広河隆一 写真展
11月1日~4日 10:00~18:00
場所:東京外国語大学研究講義棟ガレリア
Ⅱシンポジウム《視角の地政学》
11月3日(水、祭日) 10:00~18:00
場所:東京外国語大学研究講義棟101教室
●第1セッション: ブロードキャスティング 10:00~12:30
ハッサム・イブラヒーム(アルジャジーラ)
永島啓一(NHK放送文化研究所)
石田英敬(東京大学、情報記号論)

●第2セッション: フォト・ジャーナリズム 14:00~16:30
ジェームズ・ナクトウェイ(Ⅶ)
広河隆一(DAYS JAPAN)
 
●総合討論 : 戦争とメディア~視角の地政学 17:00~18:00
司会・コメント:西谷修/中山智香子(東京外国語大学)
Ⅲ、セミナー《J・ナクトウェイ氏を迎えて》
11月4日 13:00~17:00
場所:東京外国語大学事務棟2階中会議室
第1セッション PCSセミナー 13:00~14:30
第2セッション 自由討論 15:00~17:00

なお、報告集作成に先立って、シンポジウム第1セッションは雑誌『世界』(岩波書店)2005年2月号に、第2セッションの要旨は雑誌『DAYS JAPAN』1月号に掲載される予定です。
|
2004年10月28日
15:00~17:00
|
|
●第I分科会
「経済発展と教育改革」
講師: 鈴木洋一 (国際協力機構・本学客員教授)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
2004年9月29日
17:00~19:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「インドネシアの地方分権化の現状とその課題」
講師: 佐々木弘世(国際協力機構)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
2004年6月30日
17:00~19:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「利用されるハイエク―ニューディール期以降の「リベラリズム」の位相―」
講師: 中山智香子
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
6月3日
13:00-18:00
6月4日
10:00-18:00
6月4日
16:30-18:10
|
|
●第I分科会
写真展とパネル・ディスカッション
「9・11後の世界とフォト・ジャーナリズム
 ~メディアウォールを突き崩す~」 ~メディアウォールを突き崩す~」
| パネリスト: | 広河隆一 ("DAYS JAPAN"編集長) |
| | 安田純平 (フリージャーナリスト) |
| コメント: | 西谷 修 |
| 司会: | 中山智香子 |
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟1F 115番教室
グローバル世界における〈視角の地政学〉研究の一環として行われたこの企画では、
グローバル秩序の作り出す「メディア・ウォール」(とりわけ9.11以後顕著になっている)を超えて、
秩序形成の争点とされる地域の現実にアプローチし、鳥瞰図ではない現場の視角を開くために行われている困難な試みを、
世界の現状と日本のメディア状況をコンテクストにとりあげた。

とりわけ、この4月に創刊された日本発のフォト・ジャーナリズム月刊誌『DAYS JAPAN』があり、
大メディアの穴を埋めて戦地を取材するフリー・ジャーナリストたちがいる。

今回は同誌創刊者で世界的なフォト・ジャーナリスト広河隆一さんと、
先ごろイラクから帰還した安田純平さんを招いてパネル・ディスカッションを行うと同時に、
ご両人の協力で写真展を開催した。研究講義棟1Fガレリア奥で慎ましく展示された20枚ほどの写真は、
小規模ながら多くの学生の関心を引き、115番教室で行われたパネル・ディスカッションには300人を超える聴衆が集まり、
通路やステージを埋めるだけでなく廊下や庭にも溢れ出るほどで、
その悪条件のなかでも、現代のフリー・ジャーナリズムのおかれた困難な状況やその役割について、
生々しい体験談を交えて語るパネリストの言葉に、聴衆は熱心に聞き入った。

短い時間だったが活発な質疑応答も行われた。爆撃される側の「残酷」な写真について、
戦争に加担している日本であればこそ「それに目を背ける権利はわれわれにはない」という広河さんのコメントが会を締めくくった。
|
2004年5月13日
17:00~19:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「中国オートバイ産業のサプライヤーシステム
 -競争環境と能力蓄積による組織の進化-」 -競争環境と能力蓄積による組織の進化-」
講師:大原盛樹(ジェトロ・アジア経済研究所)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
2004年1月22日
17:00~19:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「2004年東アジアの経済展望」
講師:樋田 満(ジェトロ・アジア経済研究所)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
12月18日
17:00~19:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「途上国の金融財政問題―ラオス、ベトナム、カンボジアの現状と課題―」
講師:古川久継(UFJ総合研究所国際本部チーフ・コンサルタント)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
11月27日
17:00~19:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「大恐慌を巡る学説の推移」
講師:畑瀬真理子(日本銀行)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
2003年11月27日
10:40~12:10
|
|
●第I分科会
公開講演特別研究会
「通貨外交と日本の役割」
講師:緒方四十郎
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
2003年10月26日
13:30-18:00
2003年11月2日
14:00-18:00
2003年11月6日
16:00-18:00
|
|
●第I分科会
10月26日(日) 13:30-18:00 本学研究講義棟115番教室
シンポジウム 《世界化を再考する--P・ルジャンドル氏を迎えて》
第一部 ピエール・ルジャンドル氏講演(同時通訳付き)
 13:30 紹介:西谷 修(東京外国語大学)
13:30 紹介:西谷 修(東京外国語大学)
13:45 ピエール・ルジャンドル講演
「西洋が西洋について見ずにいること」
15:00 コメントと討論:大澤真幸(京都大学、社会学)/渡辺公三(立命館大学、文化人類学)
第二部 ビデオ上映
16:00 『西洋的人間の製作』
(ピエール・ルジャンドル製作1996)
11月2日(日) 14:00-18:00 本学本郷サテライト
ワークショップ《ドグマ人類学の可能性・Ⅰ》
発表者:嘉戸一将(京都大学助手、法思想)/佐々木中(東京大学大学院、宗教学)/橋本一径(ナント大学大学院、表象文化)
コメンテーター:ピエール・ルジャンドル
11月6日(木) 16:00-18:00 日仏会館
ワークショップ《ドグマ人類学の可能性・Ⅱ》
基調報告:ピエール・ルジャンドル
参加者による討論
以上三つの企画は、世界の近代化=西洋化に関して、法制度的と無意識的主体形成の観点から、斬新な見解を提示してきたフランスの精神分析家にして法制史家ピエール・ルジャンドル氏(バリ第Ⅰ大学、高等研究実習院・宗教学部門元教授)を招いて行なった一連の企画。
 ルジャンドル氏の仕事は、制度性の観点から西洋的なものの基本構成を問い直し、その世界的な効果や、現在のグローバル化のなかで問題になる制度移転や文化摩擦あるいは宗教問題について、きわめて刺激的な観点を呈示するもの。日本ではあまり知られていないルジャンドル氏だが、10月26日のシンポジウムでは、その斬新で根本的な「ドグマ人類学」の論旨の展開に、115番教室をいっぱいに埋めた聴衆が熱心に聞き入った。また、それを受けた渡辺、大澤両氏とのやりとりも密度の高いものだった。同時に上映されたルジャンドル氏製作のビデオ上映も、講演内容を視覚的に補強して強いインパクトを与えたことが、アンケートからも伺われた。 ルジャンドル氏の仕事は、制度性の観点から西洋的なものの基本構成を問い直し、その世界的な効果や、現在のグローバル化のなかで問題になる制度移転や文化摩擦あるいは宗教問題について、きわめて刺激的な観点を呈示するもの。日本ではあまり知られていないルジャンドル氏だが、10月26日のシンポジウムでは、その斬新で根本的な「ドグマ人類学」の論旨の展開に、115番教室をいっぱいに埋めた聴衆が熱心に聞き入った。また、それを受けた渡辺、大澤両氏とのやりとりも密度の高いものだった。同時に上映されたルジャンドル氏製作のビデオ上映も、講演内容を視覚的に補強して強いインパクトを与えたことが、アンケートからも伺われた。
若い研究者を招いて本郷サテライトで行なわれたワークショップも、法学、宗教学、科学史=認識論というそれぞれの観点から、ルジャンドル氏の仕事に触発された研究が発表され、その活用の可能性が示された。会場が狭すぎた感もあるが、またそれだけに熱気も溢れていた。
日仏会館で行なわれた最後のワークショップは、ルジャンドル氏の日本訪問の所感表明から始まり、今後の共同作業についての展望を開くものになった。
この他、本学COEプログラム以外の主催で、日仏会館での講演会(10月27日)、大阪民族博物館地域研究センターでのワークショップ(11月2日)が行なわれたが、いずれも好評を博し、今後さまざまや研究分野でルジャンドル氏の業績が浸透し活用されることが期待される。その意味では、この企画は大きな成果を残したといえる。
|
10月23日
17:00~19:00
|
|
●第I分科会
特別研究会
「日本の金融改革」
講師:太田 勉(日本銀行)
──東京外国語大学府中キャンパス
研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室にて
|
2003年
10月17日-18日
12:00-20:00
19日
13:00-18:00 |
|
●第I分科会 映画上映とパネル・ディスカッション
《沖縄、未来のドキュメンタリー》
沖縄というきわめて特殊な場所(日本という国民国家の境界にあり、日本国家への統合とアメリカ軍による占領統治を経て日本に復帰するという歴史を経た、つまり国民国家の境界を往き来し、世界のグローバル化を受けて東アジアに接する地域として再びその特質を際立たせている)が、20世紀後半にまた映像の特別の対象となってきた点に着目し、「近代国家」「帰属」「歴史」「戦争」「記憶」「メディア」といった多角的な観点から、沖縄の映像記録の検証を通して「近・現代」の日本と世界の現在を考える、ということを趣旨とした企画。
この企画は、本研究班メンバーがCOEプログラムの始まる前から「沖縄、記憶と映像」と題して行なってきた企画を発展させたもので、これをCOEの他の活動と連携させることで、いっそう充実させることができるようになった。
今年は、国際的にも評価の高い山形国際ドキュメンタリー映画祭と、映画紹介を通じての文化活動では定評のあるアテネ・フランセ文化センターの協力、それにこれまでも関係をもってきたアート・プーデュース沖縄(APO)といった外部の文化施設やプロジェクトとも連携し、われわれのCOEプログラムを本格的に他の社会活動と連動させるとともに、その活動と成果を広く社会に公開・還元してゆく試みともなった。
10月17日-18日 アテネ・フランセ文化センター
10月19日 本学マルチメディア教室
|
| |
|
|
2003年
10月4日-5日
13:00-18:00 |
|
●第I分科会 シンポジウム
《「世界システム」の変容と「地域研究」の再定義》
東京外国語大学大学院に地域文化研究科が設置されて30余年。アメリカ合衆国の軍事的・政治的な世界戦略の要請を受けて誕生した「地域研究」という学問ジャンルは、「近代的世界システム」が全面的な危機と転換の局面に立ち至った今日、根本からの再定義を求められている。従来の、文化本質主義的な諸地域間の比較-〈inter〉的なありようから、それぞれの地域への定位の仕方を内部から外部へと自己超出的に打ち破っていくような〈trans〉的なありようへ。「地域研究」が直面している学問論的状況を批判的に検討するシンポジウム。
本研究班の基本的な問題設定を提示するシンポジウムで、第一日目は「グローバル化」ばかりでなく「帝国」が語られる21世紀初頭の世界での「地域研究」のあり方を抜本的に考え直す問題提起がなされ、それをめぐって活発な討議が行なわれました。そして第二日目には、20世紀後半のアメリカの世界戦略のなかで設定された地政学的な「地域研究」を問い直して、それぞれの地域に根ざした研究のあり方、「文化」はその枠組みたりうるか等々をめぐって議論が展開された。発表と議論の全体は報告書にまとめられる予定。
本学事務棟中会議室
|
2003年10月3日
14:00-16:00
|
|
●第II分科会
「21世紀の紛争と国際倫理」
中本 義彦 氏 (静岡大学人文学部助教授)
海外事情研究所 (研究講義棟4F 427号室)
|
2003年7月8日
18:00-20:00 |
|
●第II分科会 第4回定例研究会
「中国の民族問題―国際法の視点から」
講師:孫 占坤(明治学院大学国際学部助教授)
海外事情研究所(研究講義棟427号室)
|
| |
|
|
| 2003年7月1日13:00-15:00 |
|
●第II分科会 21世紀社会保障研究会 第1回研究会
「福祉国家の権力構造における分配体制―エスピン=アンデルセン『福祉資本主義の三つの世界』第5章をもとに―」
報告者:大橋 史恵(東京外国語大学院生)
東京外国語大学沢田ゆかり研究室(研究講義棟852号室)
|
| |
|
|
2003年6月26日
17:00-19:00
|
|
●第I分科会 「トルコにおける投票流動性:社会的亀裂と経済状況」
講師:間 寧(アジア経済研究所所属)
東京外国語大学府中キャンパス研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室
トルコの選挙における投票の動きに注目し、膨大なデータの中からトルコの政党政治の内実を少しずつ浮き彫りにしていく手法は経済分野専門外の参加者には大変新鮮だった。IMFの影響やトルコ軍部の干渉についてなど、さらに話を伺いたくなる興味深い報告で、活発な質疑応答が交わされた。
冒頭で実際にどういう政党があるのか、また政党政治の成立の歴史など簡単に紹介していただければトルコにおける政党政治の独自性をよりスムーズに把握できたのではと言う意見もあった。
|
| |
|
|
| 2003年6月19日18:30-20:30 |
|
●第II分科会 第3回定例研究会
「時間とヨーロッパ政治―歴史政治学一試論」
講師:小川 有美(立教大学法学部教授)
海外事情研究所(研究講義棟427号室)
|
| |
|
|
| 2003年6月19日 |
|
●COE特別講演会「『戦争広告代理店』の著者に聞く」
東京外国語大学研究講義棟2F226教室
NHKディレクターである高木徹氏が自ら手掛けた番組「民族浄化~ユーゴ・情報戦の内幕」を下地に、米国PR会社が紛争時のボスニア・ヘルツェゴビナ政府の外交からマスコミ対応、大統領の演説原稿作成までを手掛けていた実態について講演した。
実際にマスメディアの体現者である氏の言葉に、いまや世界中で必須事項となりつつある情報戦の実状を実感するとともに、歯止めの効かないその流れの中で、いかに自分が受け手として情報を享受していくのかという問いをあらためて考えさせられた。
講演後には「日本のPR戦略のセンスの欠如はどうやって克服すべきか」、あるいはまた、「そういったPRがうまくなることによって世論が納得してしまうことが、長期的に見てよいことなのかどうか」、といった質問や意見が参加者から続出し、活発な議論が交わされた。
|
|
|
|
2003年5月27日
18:00-20:00 |
|
●第II分科会 第2回定例研究会
「21世紀の中国経済―グローバル化のもとでの変容」
講師:今井 健一(日本貿易振興会アジア経済研究所)
研究講義棟542号室
|
| |
|
|
2003年5月1日
|
|
●第I分科会 「エジプトの経済改革ーサクセスストーリーの失墜」
講師:山田俊一(日本貿易振興会・アジア経済研究所所属)
東京外国語大学府中キャンパス研究講義棟4F国際コミュニケーション演習室
今年度のCOE特別研究会初日。山田俊一氏が精密な資料をもとに、エジプトにおけるIMFの改革を検証した。エジプト経済について知識のない参加者が多数を占める中、氏自らの体験や、IMFの改革とエジプトに根ざす文化の軋轢なども交えての幅広い内容となった。「数多くのデータを加工せず、そのまま示した手法がとてもよかった。エジプトの再分配政策についてさらに話を聞きたい」など、参加者にも大変好評だった。
|
| |
|
|
2003年4月15日
18:00-19:30 |
|
●第II分科会 第1回定例研究会
今年度前期の活動計画について,各メンバーの研究構想報告
研究講義棟542号室
|
| |
|
|
2003年1月23日
|
|
●第I分科会 21世紀地域文化研究特別研究会・全体会議
|
| |
|
|
2002年12月8日
|
|
●第I分科会 COEプレイヴェント・シンポジウム
「沖縄《復帰》後30年」写真展、ビデオ上映、ディスカッション
討論参加者:
川満信一(詩人、批評家、元「沖縄タイムズ」記者
仲里効(APO代表、『EDGE』編集人)
宮城公子(名桜大学国際学部助教授、比較文学)
上村忠男(東京外国語大学地域文化研究科教授、思想史)
西谷修(東京外国語大学地域文化研究科教授、思想文化論)
米谷匡史(東京外国語大学語外国語学部助教授、日本思想史)
|