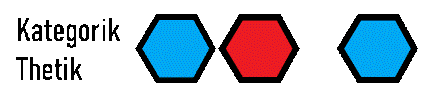これまでの研究
本プロジェクトへ至る経緯
藤縄は科学研究費補助金の研究課題として近年、単なる命題構成素に留まらない「所有」概念の作用を追求してきましたが、その過程で Kuroda (1972) によって導入された複合判断・単独判断が、「利害関係」や「疑似動作主性」にまで解釈を広げ得る日・独語のさまざまな「所有」表現間の対応関係を決定する鍵となっているとの手応えを得ました。そこで Marty の著作に当たってみたところ、彼は決してKuroda (1972) のように2種類の異なる主語を想定しているのではないこと、むしろ西欧伝統の「主語」の相対化を指向していること、その際、述語的諸概念のうち「存在」を単独判断の基礎として特に重視していること、意味・形式間のミスマッチの可能性(「疑似複合判断文」)も自覚していることなど、Kuroda (1972) からは読み取れなかった Marty 言語理論のさまざまな特色を発見しました。この発見からの展開として、2015年に田中がミュンヘンの研究者チームと企画した「国際言語学サマースクール」でドイツ語命令文・希求文の分析案を披露したところ、日独語における指示と述定の問題に取り組んできた田中も、言語哲学に造詣の深いミュンヘン・チーム Abraham & Leiss も、広範に問題意識を共有することが判明しました。
以来、藤縄・田中とミュンヘン・チームは相談を重ね、同じく意味と形式の関係に強い関心を寄せ、「日独言語学サマースクール」2011年次開催にも携わった吉田および言語哲学分野でも実績のある室井の賛同を得られたことから、語用論に携わる2名の有望な若手研究者・筒井と大喜を加えて体制を強化し、本格的な国際共同研究として本研究を企図しました。
藤縄と田中は国内外の学会・研究会(一部は本研究の他のメンバーも同席)で構想を紹介し、ミュンヘンチームと複合判断・単独判断を主要テーマとする論集 Tanaka/Leiss/Abraham/Fujinawa (eds.)(2017) を Buske 社から出版しています。2018年12月には、オーストリア言語学会でのAbraham の主催するセッションにLeiss ・藤縄・田中・室井が参加しました。
本プロジェクトに関連する業績リスト
- 藤縄康弘 (2017): 「主語・述語の文法と主語・述語の論理 ― Anton Marty の言語論を通じて ―」招待講演,国際日本研究センター第 22 回研究会, 2017年9月, 東京外大.
- 田中愼 (2017): 「ドイツ語 V2 と日本語「は」との機能的構造的等価性:二重判断の言語化」招待講演,国際日本研究センター第 22 回研究会, 2017年9月, 東京外大.
- Tanaka, Shin/Leiss, Elisabeth/Abraham, Werner/Fujinawa, Yasuhiro (eds.)(2017): Grammatische Funktionen aus Sicht der japanischen und deutschen Germanistik. Hamburg, pp.289. 〔査読有〕
- Tanaka, Shin (2017a): Kasus und Raumwahrnehmung im Sprachvergleich. A. Ogawa (ed.), Raumerfassung – Deutsch im Kontrast. Tübingen, pp.97–110. 〔査読有〕
- Tanaka, Shin (2017b): Deiktisch basierter Aufbau der Sprache: deutsch-japanischer Kontrast. A. Krause et.al. (eds.), Form und Funktion: Festschrift für Angelika Redder zum 65. Geburtstag, Tübingen, pp.207–216. 〔査読有〕
- Tanaka, Shin (2017c): Das kategorische Urteil im Spiegel der Grammatik: Deutsch-JapanischKontrast. S. Zeman et.al. (eds.), Im Spiegel der Grammatik, Tübingen, pp.263–276. 〔査読有〕
- 筒井友弥 (2017): 「心態詞 ja の含意に関する試論 ― „Du hast ja vielleicht Recht“ の解釈に ついて」 『研究論叢』(京都外大)88, pp.167–181. 〔査読有〕
- Fujinawa, Yasuhiro (2016): Haben-Perspektive im Deutschen und Japanischen. Zur Fundierung elementarer Kategorien für Kulturvergleiche aus linguistischer Sicht. A. Ogawa (ed.), Wie gleich ist, was man vergleicht? Ein interdisziplinäres Symposium zu Humanwissenschaften Ost und West, Tübingen, pp.217–235. 〔査読有〕
- 吉田光演 (2016): 「生成文法と形式意味論から見る構造と意味のインターフェース」招待 講演,京都ドイツ語学研究会第90回例会,2016年9月, 京大サテライト.
- Tanaka, Shin (2016): Prädikation im deutsch-japanischen Vergleich. Verbzweitstellung (V2) und die Partikel -wa. A. Ogawa (ed.), Wie gleich ist, was man vergleicht? Ein interdisziplinäres Symposium zu Humanwissenschaften Ost und West, Tübingen, pp. 273–281. 〔査読有〕
- Muroi, Yoshiyuki (2016): Adjektive und Nomina – Deutsch und Japanisch im Vergleich. A. Ogawa (ed.), Wie gleich ist, was man vergleicht? Ein interdisziplinäres Symposium zu Humanwissenschaften Ost und West, Tübingen, pp.240–262. 〔査読有〕
- 筒井友弥 (2016): 「ドイツ語の心態詞と話法詞の境界づけ その3 ―「思想」の概念によ る「命題」の再考 ―」 『Brücke』(京都外大)17, pp.1–10. 〔査読有〕
- Fujinawa, Yasuhiro (2015a): Kasus im deutsch-japanischen Vergleich. Varianz und Invarianz aus sprachtypologischer Sicht. 招待講演,言語学サマースクール,2015年8月,ミュンヘン大.
- Fujinawa, Yasuhiro (2015b): Zur Kodierung der externen Possession im deutsch-japanischen Kontrast. Y. Nishina (ed.), Sprachwissenschaft des Japanischen, Hamburg, pp.73–95. 〔査読有〕
- 吉田光演 (2015): 「ドイツ語指示詞 derjenige の統語論的・意味論的考察」 『欧米文化研究』22, pp.79–97. 〔査読有〕
- Tanaka, Shin (2015a): Kasusalternation und Perspektivenwechsel im deutsch-japanischen Kon- trast. Y. Nishina (ed.), Sprachwissenschaft des Japanischen, Hamburg, pp.97–109. 〔査読有〕
- Tanaka, Shin (2015b): Latente Gemeinsamkeiten, latente Unterschiede. Varianz und Invarianz aus sprachtypologischer Sicht. 招待講演,言語学サマースクール,2015年8月,ミュンヘン大.
- 筒井友弥(2015): 「ドイツ語の心態詞と話法詞の境界づけ その2 ―「含意」としての心 的態度 ―」 『Brücke』(京都外大)16, pp.1–16. 〔査読有〕
- Daigi, Yuta (2015): Existenzkonstruktion als Sprechakt – Akzeptabilität der es gibt-Konstruktion. Germanistik Kyoto 16, pp. 79–96. 〔査読有〕
- Fujinawa, Yasuhiro (2014): bekommen + Partizip II als Antikausativ. Was uns seine Polysemie über Passive und verwandte Phänomene lehrt. Japanische Gesellschaft für Germanistik (ed.), Beiträge zur Generativen Linguistik, München, 2014, pp.54–73. 〔査読有〕
- Yoshida, Mitsunobu (2014): Syntax und Semantik der selbstständigen ob-Verbletzt-Sätze im Deutschen. Interface zwischen Syntax, Semantik und Pragmatik. Japanische Gesellschaft für Germanistik (ed.), Beiträge zur Generativen Linguistik, München, 2014, pp.74–89. 〔査読有〕
- 吉田光演 (2014): 「日本語・ドイツ語・英語の指示詞の比較に関する一考察」『欧米文化 研究』21, pp.31–46. 〔査読有〕
- Tanaka, Shin (2014): V2-Puzzle. Funktionale Beschreibung aus „japanischer“ Sicht. Japanische Gesellschaft für Germanistik (ed.), Beiträge zur Generativen Linguistik, München, 2014, pp.90– 104. 〔査読有〕
- Muroi, Yoshiyuki (2014): Aspekte moderner Sprachskepsis: Dargelegt anhand literarischer Texte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wirkendes Wort 64-2, pp.299–315. 〔査読有〕
- 室井禎之 (2014): 「コミュニケーション論的言語哲学の可能性」田中愼〔編〕 『現代言語 学からみた言語哲学』(=日本独文学会研究叢書104号), pp.48–59. 〔査読無〕
- 筒井友弥 (2014): 「ドイツ語の心態詞と話法詞の境界づけ その1 ―「命題」と「モダリ ティ」―」 『Brücke』(京都外大)15, pp.15–30. 〔査読有〕
- 大喜祐太 (2014): 「ドイツ語における存在表現の意味解釈 ― 実主語と副詞句の指示性を 中心に」 『KLS Proceedings』(関西言語学会)34, pp.157–168. 〔査読有〕
- Daigi, Yuta (2014): Untersuchung der Existenzkonstruktionen es hat und es gibt im Schweizerhochdeutschen. Sprachwissenschaft Kyoto 13, pp.39–56. 〔査読有〕
- 藤縄康弘 (2013): 「ドイツ語の所有・存在表現」 『語学研究所論集』 18, pp. 163–180. 〔査読有〕
- 岡本順治・吉田光演〔編〕(分担執筆:吉田光演,藤縄康弘,田中愼,ほか 3 名)(2013): 『講座ドイツ言語学第 1 巻 ドイツ語の文法論』ひつじ書房,pp.283. 〔査読有〕
- 吉田光演 (2013): 「現代ドイツ語における指示代名詞 der/das/die の特徴について」 『ドイ ツ文学論集』46, pp.67–81. 〔査読有〕
- Yoshida, Mitsunobu (2012): Zählbare Massennomina – Wie wird die Individuierung im Japanischen kodiert? R. Maeda (ed.), Transkulturalität – Identitäten in neuem Licht. Asiatische Germanistentagung in Kanazawa 2008, München, pp.168–174. 〔査読有〕
- Tanaka, Shin (2011): Deixis und Anaphorik. Referenzstrategien in Text, Satz und Wort. Berlin and Boston, pp.224. 〔査読有〕
- Leiss, Elisabeth (2009): Sprachphilosophie. Berlin: New York: Walter de Gruyter.
これまでの主な共同プロジェクト
- 科研費基盤 (C) 15K02471「状況の主体的位置づけとしての所有概念とその言語的実現に関する日・英・独語比較研究」(2015-17) (代表者:藤縄)
- 科研費基盤 (C) 23520497「ヴァレンス拡大とその形態統語論的実現に関する日・英・独語間の語彙意味論的比較研究」(2011-13) (代表者:藤縄)
- 科研費基盤 (C) 24520470「直示と指示・照応の面から見たドイツ語指示表現の研究」(2012-14) (代表者:吉田)
- 二国間交流事業「動詞カテゴリの構造と機能についての日独対照研究」(2012-13) (代表者:吉田)
- 科研費基盤 (C) 16K02656 「「『経験』と『知識』に基づく文法」構築のための機能類型論的国際共同研究」(2016-18) (代表者:田中)
- (公財)俱進会研究助成金「日独言語学共同研究」(2015) (代表者:田中)