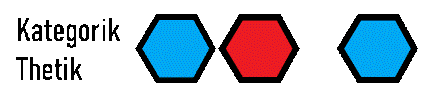「主語」および「複合判断・単独判断」に関する学術的背景
主語の必要性
主語が述語とともに文の構成に欠かせない要素であるという認識は、西欧言語学では自明であり、例えば生成文法では、度重なる理論的修正にもかかわらず、「拡大投射原理(=すべての文には主語がある)」(Chomsky 1982) が公理として一貫しています。一方、日本語など他の言語を対象とする研究者のあいだでは懐疑的ないし慎重な見方が根強くあり、仮に主語の存在が認められるにしても表面的に必須でないことから、三上 (1953) 以来の「主語無用論」も一部でなお熱烈に支持されています。このような状況において主語の必要性を論ずれば、不毛な論争に陥るか、個別言語学の枠内に留まるかになりがちで、なかなか建設的な議論には発展しません。
主語の必要性の議論が困難であるもうひとつの背景として、主語・述語関係の意味論への態度が総じて批判的でないことも挙げられます。意味論的に見た場合、述語は1~数個の項を求める関係概念 R(x,y, …) であり、関与する項のうち最優位の x が主語であるとの認識が、上述の文法論的立場の如何を問わず、今日広く共有されていると思われます。この認識に立つ以上、述語との対概念である主語は it rains のような「周辺的」ケースを除いて常に想定されることになり、その結果、主語の意味論はもっぱら複数の項が見込まれるケースでどの項がどのような動機によって最優位になるのかという広義の態の問題に帰着します(動作主性 (Dowty 1979) やトピック性 (Li and Thompson 1976)、際立ち (salience; Langacker 1991) など)。もちろん、このような見方が即無効というわけではありませんが、こうした述語との関係性の陰で、意味論次元における主語の存在が無批判のうちに前提となってしまっています。これは、ちょうど古典物理学が空間を一種の座標軸として固定的なものとみなし、究明対象の埒外に置いていたのと同じです。現代の文法理論もある種の理性主義から出発する限りは、「主語と述語」という古典的理想像を分析に先立つ参照枠とし、その結果、現に「主語」の存在が疑われるさまざまな文法現象に直面しても、その必要性への信念は揺らぎなく、当該現象はこの理想からの個別的・単発的な変異としか位置づけられないのです。こうした現状から一歩踏み出すためには、「主語・述語関係はそもそも意味論の次元で成立したりしなかったりし得る」という相対論への発想転換が肝要です。
複合判断と単独判断
「主語」相対化の発想を動機づけるものとして、本研究は「複合判断」と「単独判断」に注目します。「複合判断」 (categorical judgment; kategorisches Urteil) と「単独判断」 (thetic judgment; thetisches Urteil) はドイツ語圏スイスの哲学者 Anton Marty (1847-1914) が師 Franz Brentano (1838-1917) の心理学に基づいて提唱した論理学の範疇です。その最大の特長は、アリストテレス以来の伝統的主述関係の具現化である「複合判断」に対し、「単独判断」をこの意味での「主語」を欠くものとして積極的に対置した点にあります。この2つの判断は、形式論理学の台頭でその後一旦は忘れ去られかけたものの、Kuroda (1972) が日本語のハ・ガに関連づけて取り上げたことにより言語学で再び注目を集め、この間、一方では生成文法における VP 内主語仮説に結実し (Kitagawa 1986)、他方では個体レベル述語・ステージレベル述語 (Carlson 1977) と主語の指示性との相関性 (Ladusaw 1994) や文構造と情報構造の関係に関する新たな議論 (Sasse 2006) に刺激を与えています。もっとも Kuroda (1972) による日本語への適用は、彼独自の Marty 解釈に負うところが大きく、Marty 哲学が大胆にも秘めていた「主語」相対化への契機を事実上無に帰す結果ともなっています。また、複合判断・単独判断は Kuroda (1972) 以後、言語学において注目を集めるようになったとはいえ、国内外いずれでも既存の言語学のディスクール(日本語ハ・ガの議論や正統的な生成文法理論など)に埋没ないし統合されてしまっています。ドイツ語への応用も、 Sasse (2006) などを除いて少数に留まります。
本研究は、Marty が思考と例示に用いた言語であるドイツ語に携わる国内外の研究者を組織し、 Marty 言語論をもとに、言語体系によって主語の必要性に差異がある原因や作用を一般的に問えるようにしようとするものです。「主語」相対化とそれに伴う「非デカルト派」文法理論への展開は、本研究によってはじめて本格的になされると言ってよいでしょう。
参考文献
- Carlson, Gregory N. (1977): Reference to Kinds in English. Ph.D. Dissertation. Amherst: University of Massachusetts
- Chomsky, Noam (1982): Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding. Cambridge: MIT Press.
- Dowty, David R. (1979): Word meaning and Montague grammar. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Kitagawa, Yoshihisa (1986): Subjects in Japanese and English. Ph.D. Dissertation. Amherst: University of Massachusetts.
- Kuroda, Sige-Yuki (1972): The categorical and the thetic judgment – evidence from Japanese syntax. In: Foundations of Language 9, 153–185.
- Ladusaw, William A. (1994): Thetic and categorical, stage and individual, weak and strong. In M. Harvey & L. Santelmann (eds.), Proceedings from Semantics and Linguistic Theory, vol. IV, 220–229.
- Langacker, Ronald W. (1991): Foundations of Cognitive Grammar, vol. 2: Descriptive Application. Stanford: Stanford University Press.
- Li, Charles N. & Thompson, Sandra A. (1976): Subject and Topic: A New Typology of Language. In: Charles N. Li. (ed.), Subject and Topic. New York: Academic Press, 457–90.
- 三上章 (1953): 『現代語法序説』刀江書院(復刊1972 くろしお出版)
- Sasse, Hans-Jürgen (2006): Theticity. In: G. Bernini & M.L. Schwartz (dds.), Pragmatic Organization of Discourse in the Languages of Europe, Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 255-308.