阿部 新 (ABE Shin)
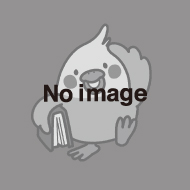
| 氏名 / Name | 阿部 新 (ABE Shin) |
|---|---|
| 所属職名 / Affiliation | 大学院国際日本学研究院/教授 Institute of Japan Studies/Professor |
| 電子メール / Email | abeshin@tufs.ac.jp |
| ウェブページ / Website | http://researchmap.jp/abeshin/ |
| 学位 / Degree |
|
| 研究分野(e-Rad分野) / Research Field(s) (by e-Rad) |
|
| 研究キーワード / Research Keywords |
|
自己紹介 / Biography
日本語教育学の分野では、言語学習のビリーフに関心があります。スペインで日本語教育に従事した際に、学習者の学習ニーズや学習動機だけでなく学習に対する信念・思い込み(ビリーフ)についても把握し、教育活動に役立てたいとの思いから、研究を始めました。
社会言語学・方言学の分野では、移住と言語・方言意識に関心があります。小笠原諸島をフィールドとして、人の移動によって起こる方言接触と方言形成をテーマとしていました。また、方言接触環境下で人々が抱く方言意識も考察しました。
どちらの分野も「意識」がキーワードとなっています。主にアンケートでデータを収集し、量的分析を行いますが、最近では質的研究も行っています。
社会言語学・方言学の分野では、移住と言語・方言意識に関心があります。小笠原諸島をフィールドとして、人の移動によって起こる方言接触と方言形成をテーマとしていました。また、方言接触環境下で人々が抱く方言意識も考察しました。
どちらの分野も「意識」がキーワードとなっています。主にアンケートでデータを収集し、量的分析を行いますが、最近では質的研究も行っています。
学歴 / Academic Achievement
-
1995年03月 上智大学外国語学部英語学科 卒業1995.03 Sophia University Faculty of Foreign Language Graduated
-
1999年03月 東京外国語大学大学院地域文化研究科日本専攻 修了1999.03 Tokyo University of Foreign Studies Graduate School, Division of Regional Culture Completed
-
2002年03月 東京外国語大学大学院地域文化研究科地域文化専攻 単位取得満期退学2002.03 Tokyo University of Foreign Studies Graduate School, Division of Regional Culture Accomplished credits for doctoral program
最近5年間の研究 /
Recent Research Projects (in the last five years)
所属学会 / Affiliated Academic Societies
-
社会言語科学会JAPANESE ASSOCIATION OF THE SOCIOLINGUISTIC SCIENCES
-
日本語学会THE SOCIETY FOR JAPANESE LINGUISTICS
-
日本音声学会THE PHONETIC SOCIETY OF JAPAN
-
日本語教育学会THE SOCIETY FOR TEACHING JAPANESE AS A FOREIGN LANGUAGE
-
ヨーロッパ日本語教師会Association of Japanese Language Teachers in Europe
-
大学日本語教員養成課程研究協議会The Association for University Training Program of Japanese Language Teachers
-
アカデミック・ジャパニーズ・グループ研究会Academic Japanese Group
-
スペイン日本語教師会Asociación de Profesores de Japonés en España
-
日本語/日本語教育研究会
-
日本語教育方法研究会Japanese Language Education Methods
-
外国語教育学会The Japan Association of Foreign Language Education
-
日本音響学会The Acoustical Society of Japan
-
日本語音声コミュニケーション学会Society of Japanese Speech Communication
-
母語・継承語・バイリンガル教育学会The Japanese Society for Mother Tongue, Heritage Language and Bilingual Education
主要研究業績 / Main Research Publications
論文 / Papers
-
日本語韻律への注意には何が影響するか ―イタリア・ロシア・中国・ベトナムの日本語学習者の「音楽経験」を比較した予備的研究―, ヨーロッパ日本語教育, 27巻, 561-566, 2024年What Influences a Language Learner’s Attention toward Japanese Prosody? Preliminary Study Comparing the “Musical Experiences” of Italian, Russian, Chinese, and Vietnamese Learners of Japanese, Japanese Language Education in Europe, 27, 561-566, 2024
-
中国の大学でライティング教育を行う日本語母語話者教員のビリーフ : 4 名の教員へのインタビュー調査から, 多文化社会と留学生交流 : 大阪大学国際教育交流センター研究論集, 27巻, 115-125, 2023年
-
中国の大学の中国人日本語専攻教員が持つ卒業論文指導に関わる文章教育観 : 重点大学の教員9 名へのインタビュー調査から, 多文化社会と留学生交流 : 大阪大学国際教育交流センター研究論集, 27巻, 103-113, 2023年
-
アクセントの産出に影響を与える要因はどのように共起するか:フランス語を母語とする日本語学習者の場合, 外国語教育研究, 25号, 20-37, 2022年
-
日本語学習者と日本語教師のビリーフを探る ―インドネシアでのフォーカス・グループによるパイロット調査から―, 海外日本語教育研究, 14号, 37-54, 2022年
-
中国の大学における日本語専攻の学生と教員が抱くライティング学習と教育に関するビリーフ : 学生と教員の違いを中心に, 多文化社会と留学生交流 : 大阪大学国際教育交流センター研究論集, 26巻, 73-84, 2022年Beliefs about learning and teaching writing among students and teachers of Japanese language majors in Chinese universities: Focusing on the differences between students and teachers, Journal of Multicultural Education and Student Exchange, 26, 73-84, 2022
-
世界各地の日本語音声指導の実態 ―2013年から2017年の調査データによる分析―, 日本音声学会第34回全国大会予稿集, 157-162, 2020年
-
CEFRと日本語教育 , 外国語教育研究, 22号, 287-294, 2019年
-
日本語教育における媒介語としての英語使用, 杏林大学研究報告, 36巻, 13-25, 2019年
-
言語聴覚療法を用いた日本語学習者に対する発音トレーニング実践の改善, 日本音響学会2018年秋季研究発表会講演論文集, 873-876, 2018年
-
ヨーロッパ日本語学習者のライティング(エッセイ)分析:総合的評価とマルチプルトレ イト評価結果を参照して, ヨーロッパ日本語教育, 22号, 75-92, 2018年
-
言語聴覚療法を用いた日本語学習者に対する発音トレーニングの試み, 日本音響学会2018年春季研究発表会講演論文集, 1355-1358, 2018年
-
日本語学習者のエッセイに見られる評価群別の言語特徴 ―I-JASにおけるヨーロッパ学習者のデータを対象に―, 第三回 学習者コーパス・ワークショップ予稿集, 32-37, 2017年
-
欧州における日本語音声教育事情 ―教師を対象としたアンケートの結果から―, ヨーロッパ日本語教育, 21号, 436-437, 2017年
-
『日本語教育学の歩き方 初学者のための研究ガイド』, 外国語教育研究, 19号, 151-157, 2016年
-
Good writing とは何か−評価を通して考える−, 2016 年度 第7回 日本語教育学会研究集会 予稿集 <東北地区>, 51-62, 2016年
-
世界各地の日本語学習者の文法学習・語彙学習についてのビリーフ—ノンネイティブ日本語教師・日本人大学生・日本人教師と比較して—, 国立国語研究所論集, 8号, 1-13, 2014年
-
ライティング評価について考える−何をどう評価するか−, ヨーロッパ日本語教育, 18号, 283-288, 2014年
-
スペイン・マドリードの日本語学習者の言語学習ビリーフの経済言語学的解釈 −大学生・大学語学センターの学生・公立語学学校の学生の比較−, 明海日本語, 18増刊号, 159-178, 2013年
-
日本語教育における言語規範 言語規範・標準語と役割語, 外国語教育研究, 16号, 156-163, 2013年
-
音声教育や日本語教員養成における音声学について日本語教師が考えていること—現状と課題を探るパイロット・スタディー—, 日本語教育方法研究会誌, 20巻2号, 2-3, 2013年
-
「よろしかったですか」等の表現の自然さに関するアンケート調査の分析, 名古屋外国語大学外国語学部紀要, 41号, 127-145, 2011年
-
言語学習ビリーフの多変量解析--調査項目のクラスター分析と数量化3類, 名古屋外国語大学外国語学部紀要, 39号, 71-90, 2010年
-
ビリーフ調査の因子分析—会話についてのビリーフと語彙学習重視・文法学習重視—, ヨーロッパ日本語教育, 14号, 284, 2010年
-
スペイン・マドリードの大学における日本語学習者の言語学習ビリーフ, 名古屋外国語大学外国語学部紀要, 37号, 25-62, 2009年
-
ビリーフ調査の多変量解析—クラス編成・授業内容構成への応用の可能性—, ヨーロッパ日本語教育, 13号, 124-131, 2009年
-
Necessity of Corpora for Japanese Dialectology -From the Viewpoint of Dialect Contact and the Consciousness of Dialect Inexistence-361-378, 2009
-
音声概説 : 日本語 (通言語音声研究 : 音声概説・韻律分析), 言語情報学研究報告, 4巻, 223-254, 2004年
-
Designing and Developing Multilingual E-Learning Materials :TUFS Language Education Pronunciation Module - Practice and its Theoretical Basis -, E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 1115-1121, 2003年
-
Designing and Developing Multilingual E-learning Materials: TUFS Language Education Pronunciation Module462, 2003
-
Design and Development of Multilingual E-learning Materials, TUFS Language Modules - Pronunciation, IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education , 591-596, 2003年
-
小笠原諸島父島の方言語彙に関する資料集, 日本のもう一つの先住民の危機言語—小笠原諸島における欧米系島民の消滅の危機に瀕した日本語—, 59-80, 2003年
-
小笠原諸島父島の方言意識・方言使用に関する資料集, 日本のもう一つの先住民の危機言語—小笠原諸島における欧米系島民の消滅の危機に瀕した日本語—, 81-121, 2003年
-
日本語方言におけるコイネー化と再コイネー化 : 過去と現在の小笠原諸島における一段動詞命令形, 言語・地域文化研究, 7号, 111-120, 2001年
-
日本語小笠原諸島方言のコイネー(Koine)の可能性 : 老年層の動詞・形容詞, 言語・地域文化研究, 6号, 1-14, 2000年
-
小笠原諸島における方言イメージ多変量解析とメディア接触・属性差の影響, 地域文化研究, 3号, 1-11, 2000年
-
小笠原における日本語の方言形成(<特集> 小笠原の言語文化), 日本語研究センター報告(<特集> 小笠原の言語文化), 6号, 149-160, 1998年
書籍等出版物 / Books and Other Publications
-
社会を築くことばの教育: 日本語教員養成のこれまでの30年、これからの30年, ココ出版, 学術書, 分担執筆, 2022年
-
第二言語学習の心理 : 個人差研究からのアプローチ, くろしお出版, 学術書, 共著, 2022年
-
Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics, Routledge, 学術書, 分担執筆, 2019年
-
県別 方言感覚表現辞典, 東京堂出版, 事典・辞書, 分担執筆, 2018年
-
複言語・複文化時代の日本語教育, 凡人社, 学術書, 分担執筆, 2016年
-
「評価」を持って街に出よう —「教えたこと・学んだことの評価」という発想を超えて, くろしお出版, 学術書, 分担執筆, 2016年
-
県別 方言感情表現辞典, 東京堂出版, 事典・辞書, 分担執筆, 2015年
-
テキストマイニングによる言語研究, ひつじ書房, 学術書, 分担執筆, 2014年
-
Good Writingへのパスポート-読み手と構成を意識した日本語ライティング, くろしお出版, 教科書・概説・概論, 共著, 2014年
-
Corpus Analysis and Variation in Linguistics, John Benjamins Publishing Company, 学術書, 分担執筆, 2009年
-
小笠原諸島における日本語の方言接触—方言形成と方言意識, 南方新社, 学術書, 単著, 2006年
-
小笠原学ことはじめ, 南方新社, 一般書・啓蒙書, 分担執筆, 2002年
-
離島とメディアの研究 小笠原篇, 学文社, 学術書, 分担執筆, 2000年
MISC / MISC
-
Aspectos de lengua y cultura de Japón: Homenaje a Ana María Goy Yamamoto, Kayoko Takagi Takanashi (ed.). Madrid: UAM Ediciones, 2023, 256 pp., Cuadernos CANELA, Confederación Académica Nipona, Española y Latinoamericana, Book review, literature introduction, etc., Single Author, 2025
-
Creencias de estudiantes y profesores sobre el apredizaje de la lengua japonesa, Revista Kōbai 紅梅, Grupo de Estudios de Japón, Facultad de Artes y Humanidades, Univrsidad de los Andes, Other, Single Author, 2022
-
ダニエル,ロング(著)『小笠原諸島の混合言語の歴史と構造ー日本元来の多文化共生社会で起きた言語接触』ひつじ書房,2018, 社会言語科学, 書評論文,書評,文献紹介等, 単著, 2021年Daniel Long The History and Structure of the Ogasawara Mixed Language: Language Contact in Japan's Original Multicultural Society. Hituzi Syobo. 2018, The Japanese Journal of Language in Society, Book review, literature introduction, etc., Single Author, 2021
講演・口頭発表等 / Presentations
-
日本語韻律への注意には何が影響するか―イタリア、ロシア、中国、ベトナムの日本語学習者を比較した予備的研究―, 第26回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム, 国際会議, ヨーロッパ日本研究協会/ヨーロッパ日本語教師会, ポスター発表, ゲント大学, 2023年What Influences a Learner's Attention to Japanese Prosody? : A Preliminary Study Comparing Italian, Russian, Chinese, and Vietnamese Learners of Japanese, The 26th Japanese Language Education Symposium in Europe, International presentation, The European Association for Japanese Studies / Association of Japanese Language Teachers in Europe, AJE, Poster presentation, Ghent University, Belgium, 2023
-
日本語を母語とする高校生の作文データベースの活用可能性―複数言語環境に学ぶ生徒の作文教育のために―, 2023 MHB 研究大会, 国内会議, 母語・継承語・バイリンガル教育(MHB)学会, 口頭発表(一般), オンライン, 2023年
-
学習者と教員の背景要因がアカデミックな日本語教育に及ぼす影響―ビリーフ・学習プロセス・学習環境の観点から狭義の言語能力育成を超えて―, 2022年度日本語教育学会秋季大会, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), オンライン, 2022年
-
中国の大学における日本語専攻の学生と教員が抱くライティング学習と教育に関するビリーフ―学生と教員の違いを中心に―, 2021年度日本語教育学会秋季大会, 国内会議, 口頭発表(一般), オンライン, 2021年
-
L2日本語における単語アクセント産出の多様性に まつわる検討―日本語学習者音声中間言語コーパスを用いた分析―, 外国語教育学会 (JAFLE) 第25回研究報告大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 2021年
-
世界各地の日本語音声指導の実態 ―2013年から2017年の調査データによる分析― , 第34回日本音声学会全国大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 2020年
-
初級日本語教育における媒介語としての英語使用―学習者向けアンケート調査の結果から― , 2020年度日本語教育学会春季大会, 国内会議, ポスター発表, 2020年
-
内容言語統合型学習(CLIL)に基づいた PEACE プログラムの構築 ―異なる日本語レベルとテーマによる実践―, International Conference on Social, Linguistic and Human Mobility and Integration (EJHIB2019), 国際会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), Japan House Sao Paulo, 2019年
-
ブラジルの高等教育機関における日本語学習者の言語学習ビリーフの多様性, International Conference on Social, Linguistic and Human Mobility and Integration (EJHIB2019), 国際会議, 口頭発表(招待・特別), Japan House Sao Paulo, 2019年
-
CEFRと日本語教育, 外国語教育学会第22回研究報告大会, 国内会議, 外国語教育学会, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 東京外国語大学, 2018年
-
言語聴覚療法を用いた日本語学習者に対する発音トレーニング実践の改善, 日本音響学会2018年秋季研究発表会, 国内会議, 日本音響学会, ポスター発表, 大分大学, 2018年
-
日本語韻律学習のための音声アーカイブ構築, Venezia International Conference on Language Education 2018, 国際会議, ポスター発表, ヴェネツィア カ・フォスカリ大学, 2018年Development of Sound Archives for Learning Japanese Prosody, Venezia International Conference on Language Education 2018, International presentation, Poster presentation, Ca' Foscari University of Venice, 2018
-
ライティング評価におけるフローチャートの開発:評価の一致を目指す場合, Venezia International Conference on Language Education 2018, 国際会議, 口頭発表(一般), ヴェネツィア カ・フォスカリ大学, 2018年A New Writing Assessment Flowchart System: Facilitating the Calibration of Assessments, Venezia International Conference on Language Education 2018, International presentation, Oral presentation (general), Ca' Foscari University of Venice, 2018
-
大学の英語教育と連携した日本語教師養成プログラムの開発―初級日本語教育における媒介語としての英語使用―, 2018年度日本語教育学会春季大会, 国内会議, ポスター発表, 東京外国語大学府中キャンパス, 2018年
-
言語聴覚療法を用いた日本語学習者に対する発音トレーニングの試み, 日本音響学会2018年春季研究発表会, 国内会議, ポスター発表, 日本工業大学宮代キャンパス, 2018年
-
日本語学習者のエッセイに見られる評価群別の言語特徴 ―I-JASにおけるヨーロッパ学習者のデータを対象に―, 第三回 学習者コーパス・ワークショップ ―学習者コーパスから第二言語習得を考える―, 国内会議, ポスター発表, 国立国語研究所, 2017年
-
ヨーロッパ日本語学習者のエッセイの日本語の言語特徴, The 15th EAJS International Conference/第 21 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム, 国際会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), リスボン新大学(ポルトガル), 2017年Linguistic features of Essays by European Learners of Japanese as a Second Language, International presentation, Symposium, workshop panel (public), Universidade NOVA Lisboa, 2017
-
スパッと決まる(!?)ライティング評価を目指して:フローチャートの活用, 第42回アカデミック・ジャパニーズ・グループ研究会, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 東京大学駒場キャンパス 21 KOMCEE EAST, 2017年
-
ヨーロッパにおける日本語学習者の日本語作文のテキストマイニング―その言語的特徴に関するパイロットスタディー―, 東京外国語大学語学研究所定例研究会, 国内会議, 口頭発表(招待・特別), 東京外国語大学語学研究所, 2017年
-
世界各地の日本語学習者が文法学習・語彙学習について考えていることを比べる ―現地教師や日本人とも比較して―, 『外国語と日本語との対照言語学的研究』第20回研究会, 国内会議, 口頭発表(招待・特別), 東京外国語大学語学研究所, 2016年
-
Good writing とは何か−評価を通して考える−, 2016 年度第7回日本語教育学会研究集会<東北地区>, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 東北大学附属図書館, 2016年
-
欧州における日本語音声教育事情−教師を対象としたアンケートの結果から−, 第20回AJEヨーロッパ日本語教育シンポジウム/第5回AIDLGイタリア日本語言語学・日本語教育学会, 国際会議, ポスター発表, カ・フォスカリ大学(イタリア・ベネチア), 2016年
-
日本語音声教育の現状と課題 —アクセントの教育を中心に—, 2016年度日本語教育学会春季大会, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), 目白大学新宿キャンパス, 2016年
-
Conducting Research on the Geographical Linguistics by Utilizing the Data Comprising Twitter Posting, The fourth meeting of the New Ways of Analyzing Variation in Asia-Pacific (NWAV-AP 4), 国際会議, ポスター発表, 國立中正大學(台湾・嘉義), 2016年
-
再考してみよう:ライティング評価−どうやって統一する? 私の評価スタイルは?−, 「評価」を持って街に出よう 出版記念シンポジウム, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), 東京大学駒場キャンパス21KOMCEE West, 2016年
-
ラテンアメリカにおける日本語音声教育事情, 国際語としての日本語に関する国際シンポジウム2015, 国際会議, 口頭発表(一般), サンパウロ大学日本研究所(ブラジル・サンパウロ), 2015年
-
ライティング評価ワークショップにおけるグループ点統一のプロセス, 国立国語研究所共同研究プロジェクト「コミュニケーションのための言語と教育の研究」研究発表会, 国内会議, 口頭発表(一般), 国立国語研究所, 2014年
-
日本語教育における音声教育について日本語教師が考えていること—音声教育の目標・具体的内容・困難点・改善希望の分析から—, 2014年度日本語教育学会春季大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 創価大学, 2014年
-
世界各地の日本語学習者の文法学習と語彙学習についてのビリーフ—ノンネイティブ教師と比較して—, 国立国語研究所共同研究プロジェクト「学習者コーパスから見た日本語習得の難易度に基づく語彙・文法シラバスの構築」研究発表会, 国内会議, ポスター発表, チュラーロンコーン大学(タイ・バンコク), 2014年
-
音声教育や日本語教員養成における音声学について日本語教師が考えていること—現状と課題を探るパイロット・スタディー—, 第41回日本語教育方法研究会, 国内会議, 口頭発表(一般), 立命館アジア太平洋大学, 2013年
-
ライティング評価について考える:何をどう評価するか, 第17回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム, 国際会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), Universidad Compultense de Madrid(マドリード・コンプルテンセ大学), Spain, 2013年
-
日本語教育における言語規範, 外国語教育学会2012年度シンポジウム「第二言語教育における言語規範」, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 東京外国語大学事務棟大会議室, 2013年
-
方言接触地域における方言意識・社会ネットワークの諸相と方言使用, 国立国語研究所共同研究プロジェクト「定住外国人の日本語習得と言語生活の実態に関する学際的研究」研究発表会, 国内会議, 口頭発表(一般), 国立国語研究所, 2010年
-
ビリーフ調査の因子分析—会話についてのビリーフと語彙学習重視・文法学習重視—, 第14回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム, 国際会議, ポスター発表, Freie Universität Berlin(ベルリン自由大学), Germany, 2009年
-
ビリーフ調査の多変量解析—クラス編成・授業内容構成への応用の可能性—, 第13回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム, 国際会議, 口頭発表(一般), Troy Culture Centre, Çanakkale Onsekiz Mart University(チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学トロイ文化センター), Turkey, 2008年
-
"Dialectal Supermarket" as a Result of Dialect Contact -Other Result than the New Dialect Formation-, 東京外国語大学グローバルCOEプログラム第1回国際シンポジウム "Corpus and Variation in Linguistic Description and Language Education" 「言語記述と言語教育におけるコーパスと変異」", 国際会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 東京外国語大学, 2008年
-
Dialect-contact in the Bonin (Ogasawara) Islands, The Japan Research Center - Universidad Aut?noma de Madrid Spring Workshop, 国際会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), The School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, London, United Kingdom, 2007年
-
The Bonin Islands: The Laboratory of the Dialect Contact -Dialect Formation and Dialect Consciousness-, (なし), 国際会議, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等, Faculty of Humanities, University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany, 2007年
-
"There is no dialect here": The Dialect Unawareness Resulted from the Dialect-contact in isolated Islands in Japan, The 5th Congress of the International Society of Dialectology and Geolinguistics, 国際会議, 口頭発表(一般), Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2006年
-
記録して残すべき文化としての島言葉, 公開シンポジウム「小笠原研究最前線」, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 東京都庁都民ホール, 2004年
-
Designing and Developing Multilingual E-Learning Materials :TUFS Language Education Pronunciation Module - Practice and its Theoretical Basis -, E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 国際会議, ポスター発表, 2003年
-
Designing and Developing Multilingual E-learning Materials: TUFS Language Education Pronunciation Module, The 3rd International Conference on Advanced Learning Technologies, 国際会議, ポスター発表, Dais Cultural and Athletic Centre, Athens, Greece, 2003年
-
Design and Development of Multilingual E-learning Materials, TUFS Language Modules - Pronunciation, IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, 国際会議, ポスター発表, 2003年
-
東京語アクセントの聞き取りテスト—東京語話者と台湾における学習者の比較—, 2003年度日本語教育学会春季大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 一橋大学, 2003年
-
特殊拍を含む音節のアクセント核の知覚—小笠原諸島の中高生と他方言・他言語話者との対照—, 第16回日本音声学会全国大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 東京女子大学, 2002年
-
東京語アクセントの聞き取りに影響を及ぼす地元意識・方言意識—小笠原諸島父島の中高生の多変量解析—, 第10回社会言語科学会研究大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 東北大学, 2002年
-
小笠原の豊かな島言葉:八丈島だけではない,その源, 第2回公開シンポジウム「小笠原諸島の言語・歴史・社会」, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 小笠原村地域福祉センター, 2002年
-
方言接触地域の名詞アクセント—小笠原諸島父島の生え抜きと移住者—, 日本方言研究会第74回研究発表会, 国内会議, 口頭発表(一般), 東京都立大学, 2002年
-
小笠原諸島父島の日本語アクセント概観—特に1拍,2拍,3拍名詞—, 第15回日本音声学会全国大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 神戸海星女子学院大学, 2001年
-
移住による方言接触・言語接触地域の日本語アクセント—東京都小笠原諸島父島の事例—, 第93回変異理論研究会, 国内会議, 口頭発表(一般), グリーンヒルサントピア(滋賀県甲賀郡水口町), 2001年
-
小笠原諸島父島における日本語方言—地域文化としての存在—, 公開シンポジウム「小笠原諸島の言語・歴史・社会」, 国内会議, シンポジウム・ワークショップ パネル(指名), 小笠原村地域福祉センター, 2000年
-
メディアと若者の言語使用—小笠原諸島の中高生—, 日本社会情報学会第4回大会, 国内会議, 口頭発表(一般), 関西大学高槻キャンパス, 1999年
共同研究実施実績 / Joint Research activities
-
高等学校等における日本語能力評価に関する予備的調査研究事業, 国内共同研究, 文部科学省, 2022年-2023年
-
文字環境のモデル化と社会言語科学への応用, 国内共同研究, 国立国語研究所, 2009年-2016年
-
学習者コーパスから見た日本語習得の難易度に基づく語彙・文法シラバスの構築, 国内共同研究, 国立国語研究所, 2011年-2014年
-
定住外国人の日本語習得と言語生活の実態に関する学際的研究, 国内共同研究, 国立国語研究所, 2009年-2012年
Last updated on 2025/7/27
