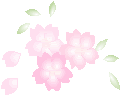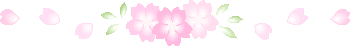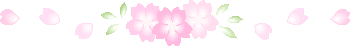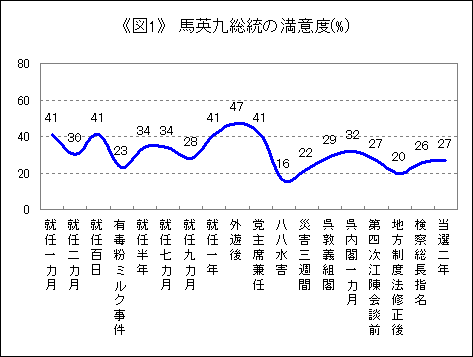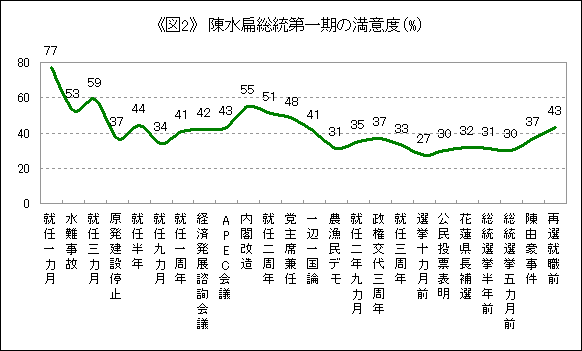|
|

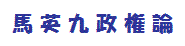 (その2)
(その2)
|
東京外国語大学
小笠原 欣幸
|
|
|
2008年5月に馬英九が総統に就任してから2年になろうとしている。馬英九政権については,民意とのずれ,反応の鈍さ,台北の視点(上から目線)といった批判が発足直後から続き,統治能力が疑問視されている。政権人事が,学者重視,昔の国民党官僚政治家重視の布陣となり,馬英九のリーダーシップが見えないことが失望を招いた。馬英九の支持率は低迷し,2008年選挙で圧勝した馬英九と国民党の勢いは消え失せてしまった。難題が次から次へと発生し,馬政権はこのまま沈没するのかどうかの瀬戸際にある。馬英九政権論の2回目の今回は,最近の選挙結果,民意の動向,政権運営の問題点を整理し,馬英九の国民党主席兼任の意図を検討したい。(2010.4.18記)
|
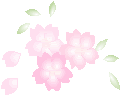
|
 1.県市長選挙と立法委員補欠選挙
1.県市長選挙と立法委員補欠選挙
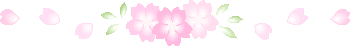
《表1》 17県市長選挙の泛藍陣営と泛緑陣営の得票率
| | 2001年 | 2005年 | 2009年 |
| 泛藍陣営 | 53.84% | 56.76% | 52.79% |
| 泛緑陣営 | 44.23% | 41.76% | 45.96% |
| 両陣営の差 | 9.61 | 15.00 | 6.83 |
【出典】中央選挙委員会の資料を参照し筆者作成。
2009年12月5日,台湾の17県市で首長選挙が行なわれた。選挙民の数は台湾全体の選挙民の4割である。17県市のうち,国民党候補の当選は12,民進党候補は4,無党籍候補は1であった。民進党は当選を1つ増やしたにすぎなかったが,両党の得票率では予想外の数字が出た。国民党の得票率は47.9%,民進党は45.3%,無党籍の候補者は6.8%であった。この17県市は本来国民党が優勢な地区であるのに,国民党と民進党との得票率の差は2.6ポイントに縮まったのである。
両者の実力を見るためには,両党の公認候補の得票率ではなく,両陣営全体の得票率を導き出す必要がある。そこで無党籍候補のうち属性の判別が可能な候補を泛藍と泛緑に組み入れて得票率を算出し,17県市の過去3回の選挙での泛藍陣営と泛緑陣営の得票率を比較した。それが《表1》 である。今回の選挙での両陣営の差は約6.8ポイントとなり,これが実態を反映した数字である。
これがどの程度の差なのか,過去のデータと対照させておきたい。2001年選挙では9.6ポイントの差があったが,2004年総統選挙では陳水扁がぎりぎりで逆転に成功した。2005年選挙では国民党が15ポイントもの大差をつけた。ここまで差が広がると勝負は一方的な展開となる。2008年総統選挙は国民党の圧勝であった。6.8ポイント差は,民進党が2012年総統選挙で逆転を狙える位置につけたと見ることが可能であろう。しかし,これは地方選挙であり,各県市の投票結果は,全国レベルの判断基準で票が動いたというよりは,候補の優劣,地方政治の構造などローカルな要因が得票率の増減に影響を与えたと解釈する方が適切である(拙稿「2009年台湾県市長選挙分析」を参照)。
他方,立法委員選挙は,確かに候補者の質・ローカルな要因にも左右されるが,県市長選挙と比べて,政権への評価がより大きく反映される選挙である。補欠選挙が行なわれた7議席は,元々国民党6議席,民進党1議席であった。投票結果は国民党1議席,民進党6議席で,民進党の大勝利となった(拙稿「2010年台湾立法委員補欠選挙」を参照)。7選挙区の得票率の平均値は《表2》のように,民進党が53.50%,国民党が42.72%である。国民党の得票率は,2008年の立法委員選挙の58.41%から15.7ポイントも減少した。投票率が大幅に低下しているので数字の解釈は注意が必要であるが,国民党の大敗北であることは間違いないし,全73選挙区のうちの7選挙区であるから,ある程度の代表性を持ちうる数字である。これが政権与党への重い警告に留まるのか,あるいは再度の政権交代の序曲となるのかは今後の展開,特に年末の五都市長選挙の結果に左右されるが,馬政権が相当追い込まれたことは間違いない。
《表2》 7選挙区における2008年立法委員選挙と2010年補欠選挙の政党別得票率平均値
| | 民進党 | 国民党 | 無党籍その他 | 投票率 |
| 2010年補欠選挙得票率平均値 | 53.50% | 42.72% | 3.78% | 40.04% |
| 2008年立委選挙得票率平均値 | n/a | 58.41% | n/a | 54.54% |
※民進党は2008年選挙において新竹県と台東県で公認候補を立てなかったので平均値の比較ができない。
【出典】中央選挙委員会の資料を参照し筆者作成。
 2.民意調査に見る政権運営の諸問題
2.民意調査に見る政権運営の諸問題
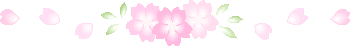
《表3》 馬英九の満意度の推移
| 調査日 | 満意 | 不満意 |
| 2008年6月17日 | 41 | 37 |
| 2008年7月16日 | 30 | 49 |
| 2008年8月26日 | 41 | 40 |
| 2008年10月2日 | 23 | 59 |
| 2008年11月18日 | 34 | 52 |
| 2009年5月21日 | 41 | 40 |
| 2009年6月4日 | 47 | 31 |
| 2009年6月10日 | 41 | 37 |
| 2009年8月18日 | 16 | 65 |
| 2009年8月31日 | 22 | 55 |
| 2009年9月10日 | 29 | 51 |
| 2009年10月7日 | 32 | 46 |
| 2009年12月16日 | 27 | 51 |
| 2010年1月20日 | 20 | 56 |
| 2010年2月3日 | 26 | 50 |
| 2010年3月18日 | 27 | 51 |
【出典】TVBS民意調査を参照し筆者作成
台湾の民意調査を見ながら,馬英九政権の2年間を簡単に振り返っていきたい。《表3》はTVBSの民意調査での馬総統の満意度(支持率に近い)の推移,《図1》はそれをグラフにしたものである。以下の数字はすべてTVBSの民意調査に依拠している(http://www.tvbs.com.tw/news/poll_center/default.asp)。
馬英九は2008年3月22日の総統選挙で58%の得票率をあげたが,就任前の4月29日の民意調査では,満意度は52%であった。得票率と満意度とを並列に論じることはできないが,満意度が早くも陰りだしたと見ることができる。この時期は,行政院長をはじめ新政権の主要閣僚の名簿が出揃った時期である。政権人事の特徴は,学者重視と,李登輝時代の旧閣僚・政務官・党官僚らの登用であった。その一方,知名度のある立法委員や地方政治家は起用されなかった。馬英九支持の評論家も「内閣は李登輝時代の二流の人材を集めただけ。みな旧官僚で,8年間の変化がわかっていない」と酷評した。
政権発足1カ月後の6月17日の調査では,満意度は41%に低下した。選挙民の高い期待を集めた馬英九が出だしから躓いたことが明らかになった。馬英九は「行政院は国家の最高行政機関」という憲法の規定を重視し,統治の日常的業務は行政院長に委ね総統は第二線に退くという態度を示した。この憲法解釈は法的には間違いではないが,1年間にわたる激しい選挙戦を見てきた選挙民にとっては違和感を抱かざるをえない解釈であり,馬英九のリーダーシップへの疑念を惹起させることになった。前出の評論家は「総統は消えてしまった。民衆には総統の姿が見えない」と批判した。
行政院長に就任した劉兆玄は,数名の閣僚がグリーンカード(アメリカ永住権)を所持していることが露呈し,いきなりその対応に追われた。中台関係について,直行便と中国人観光客の公約を直ちに実現させたが,必ずしも馬総統の評価につながらなかった。むしろ,石油価格上昇に伴う公共料金値上げをめぐる混乱,あるいは政権の目玉政策である内需拡大政策での混乱のような身近な問題が大きく影響したようである。
2008年夏に馬の満意度はやや持ち直すが,2008年秋以降,リーマンショック,中国の毒粉ミルク事件への対処の混乱で満意度が大きく低下した。グローバル金融危機により,台湾経済は,馬英九が選挙で唱えた633の公約(成長率6%,失業率3%,国民所得3万ドル)とはまったく異なる状況に陥った。金融危機は馬英九の責任ではないし,誰が政権を担っていても大きな影響を受けたことは疑いないが,行政院の説明・対応も不十分であった。行政院長,総統府報道官,行政院報道官の説明能力について,評論家らがメディアを通じて盛んに問題にした。選挙期間中,馬英九・国民党は「我々は準備ができている」という選挙コマーシャルを派手に放映し統治能力を選挙民にアピールしたが,全般的に準備不足が感じられ,この選挙コマーシャルはまがいものであったという認識が広がった。
2009年の春になると金融危機の最悪の局面は過ぎ,馬英九の就任1周年前後には支持率が持ち直してきた。WHO総会への出席が実現するというプラスの要因もあった。しかし,上昇気流に乗りそうに見えながら反落をもたらしたのは馬英九の国民党主席兼任の決定である。そして2009年8月,台風の記録的な豪雨による大災害が発生した。これは不可抗力の自然災害であったが,行政院の初期対応が遅れたうえに,緊急命令を出さなかった馬総統の判断への疑問が重なり,政権への信頼感が一気に崩れることになった。グラフから明らかなように,水害救援の不始末は馬英九の満意度への最大の衝撃となった。
馬英九は行政院長の交代に踏み切り,立法委員の呉敦義を任命した。民意に敏感な呉敦義の登場によって馬英九の満意度はまた少し持ち直した。しかし,2009年の年末にかけてアメリカ産牛肉輸入解禁をめぐる混乱が発生した。12月の県市長選挙で国民党が得票率を減らした。2010年年初には台北県,台中市などの直轄市昇格を定める地方制度法の修正が立法院のドタバタの騒ぎの中で行なわれた。最近では,所得水準が停滞している中での不動産価格の上昇問題がある。こうしたことが満意度低迷の要因となっている。
2009年9月から2010年3月までの半年間は,馬英九の満意度は20~30%のレンジで低迷が続いている。この20~30%のレンジとはどの程度の水準なのかを測るため,陳水扁の満意度と比較してみる。《図2》のように,陳水扁の政権発足後1年目から2年目の期間の満意度は30~40%のレンジにあった。この時期に関しては,陳水扁の満意度は馬英九より高かった。しかし,政権発足2年目以降,陳水扁の満意度は30%のラインに低下している。陳水扁は30%のラインから2004年総統選挙で再選を果たした。陳水扁の政権第二期は家族・周辺のスキャンダルが相次ぎ,満意度は10~20%のレンジで低迷し,そこから反転することはなかった。陳水扁の事例を参照すると,20~30%のレンジとは,上の方(30%前後)にへばりついていれば反転攻勢の可能性を残し,下の方(20%前後)で固まってしまうとそのまま反転できなくなる,というような読み方ができるであろう。
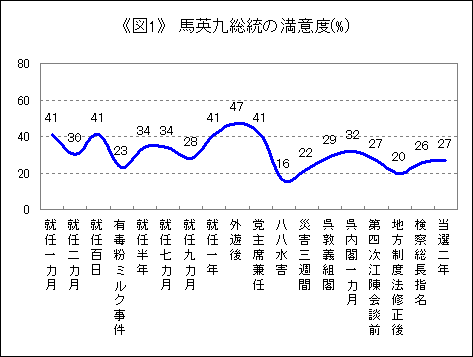
|
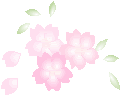

【出典】《図1》《図2》ともTVBS民意調査
を参照し筆者作成
|
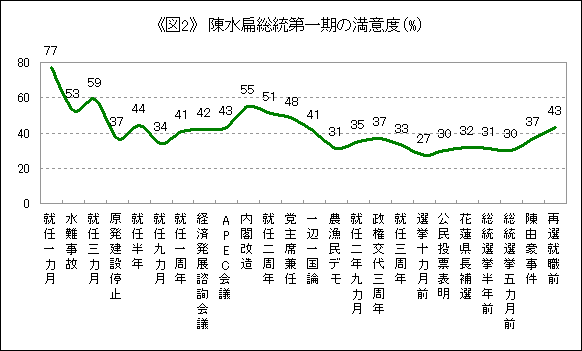

馬政権の最重要課題である中台関係は馬英九の満意度にどのような影響を及ぼしているのであろうか。政権発足1年後の2009年5月4日の調査では,「馬政府の両岸関係処理について満足か不満か」という質問への回答は,「非常に満足」と「ある程度満足」の合計が50%,「あまり満足していない」と「まったく不満」の合計が37%,「意見なし」が13%であった。馬英九の両岸政策は概して支持されていたと言える。ところが同じ日の調査で,「馬政府の両岸政策が台湾の利益を害すると心配するかしないか」という質問に対しては,「心配である」48%,「心配ない」46%,「意見なし」6%という回答であった。「心配である」が「心配ない」をわずかであるが上回る結果となっている。これは馬政権が進める中台関係の拡大を支持しながらも,馬英九が台湾の利益を損ねないのかどうか確信が持てない雰囲気があることを示している。
それから約半年後の2009年12月19日の調査で,「馬英九が政権についてから両岸では数度の協議を行い協定を結んだ。これらの協定は台湾の発展に有利と考えるか不利と考えるか」という質問がされている。その回答は,「有利と考える」30%,「不利と考える」31%,「影響なし」13%,「意見なし」26%であった。質問の仕方が異なるので直接比較は適切ではないが,「有利」と「不利」が拮抗し,半年間の間に馬英九の両岸政策への支持が低下したことが読み取れる。同じ日の調査で,「大陸の海協会の陳雲林会長が来台し会談を行ない関連する両岸協定に署名する。政府が台湾の利益を守ると信じているか」という質問では,「非常に信じている」と「ある程度信じている」の合計が35%,「あまり信じていない」と「まったく信じていない」の合計が52%,「意見なし」が13%であった。政策への否定的評価以上に馬政権への不安感が大きく上回っていることがわかる。
中台関係の満意度への影響については,政策が悪いから政権への信頼感が低下していくというより,政権への信頼感が低下しているので,その政権が打ち出す政策にも不信感を抱かざるをえないという循環が生じているように見える。
 3.政権の権力構造の問題
3.政権の権力構造の問題
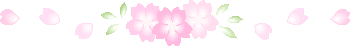
前述の満意度の推移で政権の権力行使(行政執行)の問題について簡単に触れたが,この問題とは別に,①立法院を掌握しきれない,②地方派閥を掌握しきれない,③党組織を掌握しきれないという政権の権力構造上の問題がある。馬英九は政権の中枢を同質性の高い人材で固めたものの,立法院,地方,党組織を掌握できないことが政権運営の躓きの原因となっている。
①の立法院を掌握できていないという指摘は,政権発足時に国民党が立法院の議席の約4分の3を占めていたことからすると非常に奇妙に見える。問題の核心は,馬英九および行政院が国民党の立法委員の多数の全面的支持を得ていないということにある。与党立法委員は一歩引いたところから是々非々の立場で馬政権の動きを観察している。馬英九は,国民党政策執行長(国会対策委員長のような役職)の林益世を通じて,与党の議員団を動かそうとしているが,重要案件の否決や審議未了が発生している。馬英九のために進んで泥をかぶろうとする立法委員はほとんどいない。
政権発足直後,監察委員の指名人事の一部が立法院で否決された。2010年の年初には,アメリカ産牛肉輸入解禁に関する米台合意が立法院で事実上否決された。他にもいくつかの法案が,行政院の意に反して審議が進んでいない。台湾は半大統領制であり,議会で法案を通していかなければ行政の展開は大きく制限される。人事や対外合意事項が否決されるのは,政権にとっての打撃が非常に大きい。
②の地方派閥の問題とは次のことを指す。国民党の組織は台湾の各県市に張りめぐらされているが,地方で実際に権力を持っているのは地方派閥・地方家族・地方政治家らである。これらの集団はほとんどが自己利益の追求を重視しており,国民党中央の方針や利益としばしば摩擦が生じる。馬英九が国民党の地方組織のあり方を改革しようと志すのは正当なことであるが,いかんせん現実の高い壁が立ちはだかり,地方派閥・地方政治家を無視しては選挙で勝てないのである。
雲林県,花蓮県,新竹県は,馬英九の指導力の困難を示す代表例である。雲林県では国民党現職立法委員が選挙違反により当選無効となり,補欠選挙が実施された。馬英九が介入して学者を擁立して地方派閥離れを図ったが,支持者を結集することができず,その立法委員補欠選挙で敗北した。その直後の県長選挙でまた学者候補を擁立したが歴史的大敗となった。花蓮県では,汚職で起訴され裁判中の与党立法委員が県長選挙出馬を目指していた。馬英九はそれを阻むため,現職閣僚である衛生署長の葉金川を落下傘的に県長選挙に出馬させ改革の決意を示そうとしたが,葉は何と予備選挙で敗退し,県長選挙では当の立法委員が当選した。馬英九の介入はかえって地方の反発を買ったのである。新竹県では国民党系の地方派閥同士が激しく対立し,馬英九の調停の効果もなく県長選挙が分裂選挙となり,その後の立法委員補欠選挙ではとうとう民進党に漁夫の利を許した。
これら3県に共通するのは,馬英九の介入の仕方が,政治生命をかけて闘うというような姿勢ではまったくなく,中途半端であることだ。内部事情に詳しい人は,馬英九は候補の擁立など陰で介入しているのに,表面上は関係がないふりをする,と語る。馬英九のことを「不沾鍋」(よごれがつかないテフロンフライパン)という言い方が広がっているが,そこには責任を取らないという批判的な認識が込められている。
都会エリートの馬英九は,もともと地方政治家とのつきあいが得意ではない。外省人と本省人という違いもあるし,改革志向の馬英九と保守的な政治文化を代表する地方政治家とは話がかみあわない。馬英九は雲林県の大ボス張榮味に何度も会っているが,3分で話すことがなくなるという。馬英九は総統選挙では3ヶ月間のロングステイ(地方体験滞在)を敢行し,その溝を埋める努力をした。しかし,双方の関係は,正面から対立するわけではないがよそよそしい状況が続いている。馬英九は国民党の立法委員との懇談会をたまに開催している。立法委員らはテーブルを囲んで総統と酒を酌み交わすことを期待しているが,会場は立食パーティ形式であったり,弁当であったりと実質重視の馬英九とはすれ違いがある。
馬英九は内心で地方派閥・地方政治家を黒金(金権腐敗)と見なしている(と思われている)。そう見られる当事者は当然不愉快である。総統選挙で勝てたのは誰のおかげか,というのが地方派閥・地方政治家の声であり,自分の力で勝ったというのが馬陣営の声である。次回総統選挙で馬英九の地方票がある程度減ることは確実である。この問題は,感情的にかなりこじれていて,馬英九の再選を阻む要因になる可能性がある。
③の党組織の問題は,大統領と与党との距離と言い換えてもよいであろう。馬英九の独特の人事配置と閉鎖的な政策決定プロセスにより,国民党は政権の柱であることを期待されながら政権との距離感ができている。党の中には「我々の政権という感覚を持てない」と漏らす人もいるし,「人の用い方が間違っている」とはっきり批判する与党立法委員もいる。馬英九は党組織を改革の対象に位置づけている。そのことが党の側での疎外感,落胆,反発のような微妙な感情を作り出している。ある国民党の関係者は,馬英九自身は国民党への強い愛着を抱いているが,馬英九の側近学者らは国民党への愛着はないと見ている。馬英九の側近らは,アメリカ大統領のチームのように,大統領さえ担げば党はどうでもよいと考えている,というのである。
呉伯雄が主席の時は,摩擦がありながらも呉主席(党中央)が立法院と馬政権,地方と馬政権のつなぎ役を果たしていた。国民党は年季の入った恐竜組織であり,党の各部門と党職員を動かしていくのは大変な作業である。呉伯雄の党運営は義理人情を重視し,水面下での調整を多用し,なあなあでまとめていく手法であった。派閥全盛期の日本の自民党のような手法である。また呉伯雄は,にんじんと棒(飴と鞭)を使って地方派閥・地方政治家を手なずけた。これは2008年立法委員選挙・総統選挙の勝利に大きく貢献したが,合理性を重視する馬陣営にはその手法が不満であったのであろう。
これら①②③の問題はつながっている。このことは,馬総統が行政権力を握っているといっても,権力基盤が空洞化していく危険があることを示している。それで馬英九は党主席兼任に動いたと考えられる。しかしながら,調整型の呉伯雄を追い落としたことで,馬英九があらゆることの矢面に立つことになり,馬英九はかえって泥沼にはまることになった。
 4.国民党主席兼任の企図
4.国民党主席兼任の企図
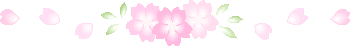
馬英九と呉伯雄は個人的に良好な関係を築いてきたが,大統領と与党党首の関係が難しいことは言うまでもない。与党議員の中で大統領派はほんのわずかで,党首につく議員が多いとなればなおさらである。国民党は立法院で圧倒的な議席を有しているし,行政院も閣僚のほとんどが国民党関係者である。だが,半大統領制は運用が難しい。国民党の立法委員は行政院に対し不満があり,また,行政院の側は党の立法委員が協力的でないと感じている。馬総統は立法院とのパイプが細く,国民党中央を通じなければ立法院を動かせない。政権発足から1年間は,馬英九=呉伯雄の連携でこの構造的問題を押さえ込んできた。この2人の協力関係が政権の要であった。しかし,呉伯雄の権威がしだいに増す中で,馬英九の側近グループ(総統府の幕僚)と呉伯雄の側近グループ(党中央の幕僚)との関係が難しくなっていたという経過もある。
2005年7月の国民党主席選挙で馬英九は王金平に圧勝し,主席に就任した。任期は4年で2009年8月までであった。ところが,馬英九の台北市長時代の特別費問題が発生し,2007年2月,起訴された馬英九は党主席を辞任した。呉伯雄が後任の党主席に就任し,任期の残りを務めることになった。その後馬の特別費問題は裁判で無罪が確定したが,党国体制のマイナスイメージを気にした馬英九は選挙期間中に国民党の党主席に復帰するつもりはないと表明したし,総統就任後も党主席を兼任するつもりは「絶対ない」と言明した。
呉伯雄は,当初は党主席の再選という考えはなかったようである。政権奪回という功を成し遂げ2009年8月の任期切れで引退し,同年12月の県市長選挙で息子の呉志揚を桃園県長に当選させるというのが2008年7月時点での呉伯雄の人生設計であった。しかし,2008年12月には,呉伯雄の陣営内では馬英九の再選を見届けてから呉が引退するという空気に変わりつつあった。つまり,呉が2009年7月の党主席選挙に再出馬し,2012年の総統選挙を党主席として闘い,2013年8月に引退という計画に傾きつつあった。呉の続投は党内の勢力バランスの維持を意味するので,続投への支持が党内でも広がりつつあった。ところが,その流れを妨げるかのように,馬英九が党主席兼任を検討しているという新聞報道が現れるようになった。
県市長選挙の公認候補の調整に取り組んでいた呉伯雄は新聞の憶測記事にたまりかね,馬英九に対し,馬が主席を兼任するつもりがあるなら自分は喜んで退任すると伝えたが,馬は兼任の意思はないと否定した。しかし,しばらくすると,馬が兼任の意思を固めたという新聞記事が出現し,劉兆玄行政院長,關中考試院長,王建煊監察院長,さらに,郝龍斌台北市長,胡志強台中市長が兼任支持を表明し,王金平立法院長も大勢を見て支持を表明した(1)。こうして呉伯雄はレームダックの状態に追い込まれ,再選を断念するほかなかった。呉伯雄の側では,息子が桃園県長選挙に出馬しようと動いていたことが弱みとなった。馬英九は公の場で「伯公の貢献は実に大きい」「国民党の歴史において非常に重要な位置を占める」「いつも決定的な時に決定的な助力を与えてくれる」と呉伯雄を賞賛しながら,背後で呉を追い込んでいったのである(2)。
呉伯雄は蒋経国時代に頭角を現した本省人(客家)政治家である。しかし,李登輝時代は,台湾省長選挙の公認をめぐって宋楚瑜と争い敗れるなど「失意の政治家」となっていた。党内の出世の展望を見切った呉は,自分より11歳若い馬英九の後ろ盾となり,馬をトップの政治家にすることを自分の夢とする人生設計を描く。呉は,1998年の台北市長選挙でも2005年の党主席選挙でも馬の出馬を後押した。呉は突発的出来事により自分が党主席に就任したが,後ろ盾に徹するという気持ちは変わらなかったし,馬政権発足後もどのようなことがあっても決して馬とは争わないと決めていた。呉は国民党への愛着が非常に強く,党のための自己犠牲を美学ととらえる価値観を抱いている人物である。馬英九からすると,これ以上ないありがたい人物である。民意も馬の兼任にはっきりと反対であった。馬の党主席兼任に対する賛否を訊いたTVBSの民意調査では,党主席兼任に対して「賛成」23%,「反対」47%,「意見なし」30%であった(2009年4月16日調査)。にもかかわらず,馬英九は宮廷権力闘争を仕掛け,呉伯雄の追い落としに動いた(3)。
党内の権力争いが激しいのは国民党も民進党も同じであるが,民進党は対立がわかりやすく,目に見える形で抗争を繰り広げる。民進党の党内権力争いは,本質的に台湾の地方派閥の争いと同じである。しかし,国民党には宮廷政治的な党内文化があり,民進党とは党内の争い方が異なる。宮廷政治の権力争いは,にこやかに会ったり一緒に活動したりしているのに,背後でわからないように情報操作を展開したり,そ知らぬ顔で別人を使って陥れたりするというやり方である。表からは争いの実態が見えにくく,刺される当事者も誰に刺されたのかわからないこともある。馬英九は,統治能力が疑問視されているが,この手の宮廷政治では達人である。連戰,宋楚瑜,王金平,そして呉伯雄が馬に追いやられた。馬に権力闘争をしかけられてはたまらないことを党内の主要人物は理解している。だから,新北市長選挙に出馬するつもりであった周錫瑋台北県長は「周おろし」の背後に馬がいることを知って泣く泣く出馬を断念したし,胡志強は民意調査での人気が馬より高いが決して馬に対抗するそぶりを見せないのである。
 5.国民党主席兼任後
5.国民党主席兼任後
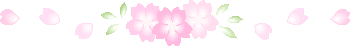
こうして馬英九は党主席兼任を果たし,呉伯雄は連戰に次いで栄誉主席という称号を与えられた。では,馬英九は兼任して何をしようとしているのであろうか。2009年6月10日の党主席選挙出馬声明で馬英九は「権力拡張のためではなく,党と政府のより緊密な協力を達成し,より有効な国政運営を促進し,『完全執政・全面負責』の理念を実践するためである」と表明したが,本心は明かしていない。台湾の政治評論家らの議論は,概ね政権運営の強化と中台関係の推進の二つの目的に収斂している。筆者は馬英九の真の狙いを知りたくて何人かの関係者に質問をしたが,いずれも推測・想像の話であった。主席兼任後に何が変わったのかを検討することで馬英九の真の狙いのヒントが得られるかもしれない。
馬の党主席兼任からまだ半年であるが,先に述べた権力構造の①②③の問題に照らしてみたい。①の立法院の掌握問題は,兼任後も変化はない。つなぎ役・クッション役の呉伯雄を外したからといって与党立法委員との意思疎通がうまく図れるわけではない。馬政権が進めたアメリカ産牛肉の輸入解禁合意が立法院で事実上否決されたのは馬の主席兼任の後である。外交合意の否決は行政院に対する立法院の最大級の行動である。兼任によって与党立法委員と馬総統との権力関係が変化したようには見えない。
②の地方派閥の掌握問題では,ぎくしゃくした関係が続いている。県長選挙と立法委員補欠選挙で,地方派閥への対抗と妥協の両方の動きが見られた。馬英九は,県長選挙での雲林県,立法委員補欠選挙での嘉義県,桃園県において地方派閥と対抗する形で意中の候補を擁立した。これは呉が主導権を握っていたらやらなかった人選である。結果は敗北に終わっているが,馬英九は自分も傷つくが相手の地方派閥はもっと傷つく「肉を切らせて骨を断つ」というような作戦を考えているのかもしれない。次期立法委員選挙が近づいてくれば小選挙区での公認権を盾に地方派閥を屈服させることができると読んでいるのかもしれない。これは義理人情の呉のやり方とは明らかに異なるので,今後馬英九が本気で地方派閥対策に乗り出すのであれば,兼任の動機の1つと言えるであろう。
③の党組織の掌握問題では,呉が続投していたならできなかったことを馬は早速実行した。盟友の金溥聰の秘書長就任である。もし馬英九が再選戦略の一環として金秘書長という人事カードを予め用意していたのであれば,呉伯雄追い落としの1つの理由となる。金秘書長の主導で,早速,国民党の宣伝担当に蘇俊賓,総統府の報道官に羅智強が起用された。蘇俊賓と羅智強は,総統選挙で金溥聰を補佐する形で宣伝戦を担った。金秘書長は国民党地方幹部の入れ替えも断行し,政権与党の戦闘力を高めるつもりのようである。ただし,金溥聰がどれほど党組織を掌握できるのかは,五都市長選挙の公認候補の決定と選挙の戦い方を見ないとわからない。馬英九は常に党改革を語るが,改革の中身と方法論は不十分である。むしろ改革への思い込みのようにも響くが,この間の馬英九の言動からすると,呉伯雄ではできないが自分ならやれると思ったのかもしれない。いずれにしても,閉鎖的な政策決定プロセスは変わっていないし,兼任による政権基盤の強化という効果はまだ現れていない。
党主席兼任のもう1つの目的とされる中台関係への影響も検討しておきたい。兼任による変化は今のところ見られないが,この先若干の変化が予想される。国共論壇は今年も開催されるので,栄誉主席の連戰と呉伯雄が出席し,胡錦濤と会談する可能性もある。しかし,過去の連戰栄誉主席と胡錦濤総書記との会談で明らかなように,栄誉主席の役割は友好親善であろう。今後呉伯雄が胡錦濤と会談しても,2008年5月の呉・胡会談のような実質的な会談にはならないと予想される。となると馬政権としては中台のパイプを1つ失う形になるが,窓口機関同士の交渉が拡大し,非公式ながら双方の政府担当者も対話・交渉に関与しているので,かつてのような国共首脳のパイプの必要性は減ったのかもしれない。他方,馬英九と胡錦濤の国共トップ会談が実現する可能性は今のところ低い。馬英九の狙いは自分が胡錦濤と会談する布石というより,当面他の人物(要するに呉)が中国との太いパイプを築くのを防ぐためであったのかもしれない。
2008年5月,呉伯雄と胡錦濤との国共トップ会談が北京で開催され,両岸協議の再開,チャーター便,中国人観光客に関する合意が成立した(4)。このとき公式会談とは別に呉・胡の2人だけの会談が40分間行なわれた。ここで,呉伯雄は台湾の国際空間とミサイル撤去問題を持ち出し,胡錦濤もそれを真剣に受け止め,台湾側の「心声」を前向きに検討するという心証を呉伯雄に与えたようである(5)。ほかに北京オリンピックの台湾の名称問題,開会式での入場の順番も話し合われたようである。こうした展開は,中台の関係改善を掲げる馬政権にとっては望ましいことであるが,政権の最重要課題が別人を通じて話し合われることに馬英九本人としては警戒感を抱いた可能性がある。中国共産党が連戰を使って馬英九を枠にはめようとする構図を馬英九は呉伯雄を活用しようやく打開したところで,今度は呉が馬に枠をはめる役になりかねないと馬陣営は判断したのかもしれない。
こうして分析していくと,呉伯雄が政権内部で影響力を増し,また,中台関係の主導権を握る可能性があるので,それを警戒して呉の権力拡大の芽を事前に摘み取るためであったという解釈も可能である。宮廷政治の観点からすれば,政権全体の強化・スムーズな政策執行よりも自分の権力が脅かされないようにすることの方が大事なので,それなりに納得のいく行動である。党主席兼任問題は,台湾式の半大統領制の制度的問題と,宮廷政治的な人の問題とが絡み合った騒動であったと見ればよいのかもしれない。(2010.4.18記)
《注》
(1)馬英九の兼任支持表明に関する新聞資料
「劉揆首度表態 挺馬兼任國民黨魁」『TVBS NEWS』2009年5月13日
「密會某院長 馬鬆口兼任黨主席」『聨合報』2009年5月23日
「王建煊 支持馬兼黨魁」『聨合報』2009年5月24日
「郝龍斌支持馬總統兼任國民黨主席」『中央社』2009年5月25日
「國民黨主席選舉 胡志強力挺馬總統」『聨合報』2009年5月31日
「馬同額競選 王金平率先相挺」『自由時報』2009年6月17日
(2)馬英九の党主席兼任に関する新聞資料
「兩個黨主席 呉伯雄調和府黨 續任機率高」『中國時報』2009年3月2日
「呉伯雄:挺馬到底 別見縫插針」『聨合報』2009年4月15日
「馬緩兵 先穩住呉伯雄」『中國時報』2009年4月15日
「馬兼黨主席 馬系立委:可免立院鞭長莫及」『中國時報』2009年4月14日
「冷眼集》呉主席提前跛鴨?」『聨合晩報』2009年5月3日
「黨魁之爭 藍委『反馬擁呉』聲高漲」『自由時報』2009年5月11日
「馬宣布選黨主席 呉:知所進退」『聨合報』2009年6月11日
(3)『中國時報』は政権の行き詰まりを主席兼任で打開することを期待する見解を社論で表明した。しかし『聨合報』はそれより慎重で,主席を兼任したからといって政治姿勢を変えなければ効果は期待できないという見解を表明した。『自由時報』は,党主席兼任は馬英九の権力拡張だとして一貫して批判記事を掲載した。
「社論-馬總統確該考慮兼任執政黨主席」『中國時報』2009年4月9日
「短 評-自己來也好」『中國時報』2009年4月14日
「不沾鍋不改,兼黨主席也沒用」『聨合報』2009年4月17日
(4)「呉胡會:92共識下 兩會速復談」『聨合報』2008年5月29日
「呉胡共識 速兌現陸客觀光及包機」『自由時報』2008年5月29日
(5)「呉伯雄:對岸若撤彈 就是善意」『聨合報』2008年6月2日
「中共高層透露:對台飛彈 不增漸撤」『中國時報』2008年6月2日
「呉伯雄評胡錦濤 『冷靜理性』」『聨合報』2008年6月4日

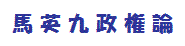 (その2)
(その2)