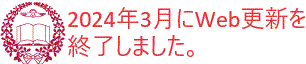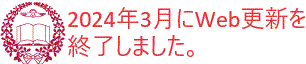
戻る │ 河津 > 2020年前期 基礎演習
2020年前期 基礎演習 河津
お知らせ
- 模擬論文を書く際の ヒント を掲載しました。8月3日
- 分からないことが
生じたら、あるはずです。迷わずZoomで尋ねましょう。一定水準以上の成果物を出した学生が合格します。7月27日
- 研究室にいて余裕のあるときはZoomに入っています。オフィスアワーに限らず訪ねてください。7月7日
- 研究の書き方は日本語演習の教科書『大学生のための日本語表現実践ノート改訂版』p62-64を参考にしましょう。7月6日
- 皆さんから授業に関して、たいへん前向きなコメントをいただいたので紹介します。5月11日
- 今学期は初回よりZoomを使った遠隔授業を実施します。Zoom利用のヒント を作成しました。
- コンピューター環境調査に協力ありがとうございます。調査結果をお知らせします。
- 対面授業ができないため、シラバスに大きな変更があります。成績評価も8月まで最善の方法を考えて進めます。
- 試験ができない場合、提出物による採点が中心となり、必然的に提出の有無や時刻など形式による影響が大きくなります。
- 事前の欠席連絡を歓迎します。事後連絡は不要です。
- 連絡は電話やEメールでお願いします。UNIPAからの連絡は避けてください。
Eメールは返事がない限り、未着(事故)と理解しましょう。
困ったら、すぐ電話しましょう。授業中でも電話しましょう。
外部リンク
ヒント
- 論理に関して、次のようなコメントを書きました。
- いろいろに解釈できます。ていねいに書きましょう。
- 根拠が正しくありません。
- 論理的でありません。「だから」や「このため」は、必然である場合に使いましょう。
- 形式に関して、次のようなコメントを書きました。
- 引用を正しく表示しましょう。
- 本文の構成を、論文らしくしましょう。
- タイトルを、論文らしい日本語にしましょう。
- 本文の表現を、論文らしい日本語にしましょう。
- 研究内容に関して、次のようなコメントを書きました。
- 何を確かめたいのか、あなたの仮説を明らかにしましょう。
- 明らかにしたい内容(仮説)に、ぴったりな実験をデザインしましょう。
- 仮説(予測)を教えてください。その仮説を明らかにするための最小限の実験を考えましょう。
- 予測されること(仮説)は何ですか。それを検証するのに、どのような実験をしますか。測定をしますか。それはどの部分ですか。何と比較しますか。
- 別の言葉で尋ねるとこうなります:あなたはどのような仮説をもち、それをどのように証明する予定ですか。
- その調査、できますか? その方法を思い浮かびますか。具体的な計画を書きましょう。
- 音声学会の全国大会予稿集から、調べる目的が明確である実験の例を見つけ、参考にしてみましょう。学会誌に掲載された論文より、単純で読みやすいとものが多くあります。
宿題
- 最終課題「疑似研究」を8月17日(月)09時までに提出しましょう。8月13日(木)09時まで指導を受け付けます。7月13日
- この先しばらく提出の必要な宿題はありません。UNIPA「課題」機能を使って、皆さんの模擬研究に助言をします。7月6日
- 7月6日(月)09時締め切りの宿題「研究題目と概要」をUNIPA「課題」に掲載しました。6月30日
- 6月29日(月)09時締め切りの宿題を「研究題目」と「先行研究リスト」の2つに分けてUNIPA「課題」に掲載しました。6月27日
→ 100点 10人、60点 8人、40点 4人 文献リストのみ評価しました。
- 6月22日(月)09時締め切りの宿題「促音:研究題目と先行研究」をUNIPA「課題」に掲載しました。6月15日
→ 100点 3人、80点 6人、60点 7人、40点 5人、0点 1人
- 6月15日(月)09時締め切りの簡単な宿題「留学生の話す小さい『っ』の音」をUNIPA「課題」に掲載しました。6月8日
→ 100点 20人、0点 2人
- 6月8日(月)09時締め切りの簡単な宿題「無声化する拍」をUNIPA「課題」に掲載しました。6月1日
→ 100点 0人、80点 7人、60点 9人、40点 6人
- 6月1日(月)09時締め切りの簡単な宿題を、5月25日にUNIPA「課題」に掲載します。5月23日
→ 100点 21人、0点 1人
- 5月25日(第3回)のための Reading Assignment をUNIPA「授業資料」に掲載しました。5月23日
- 5月18日(第2回)のための Reading Assignment をUNIPA「授業資料」に掲載しました。5月15日
- UNIPAのアンケート機能により、毎回グループワークの評価をお願いします。
授業の翌々日(水曜)13時を期限とします。5月11日
7日後の月曜09時までに報告しましょう。課題提出期限と同じです。6月15日
勉強したこと
8月3日
- 翻訳ツールで英文を作成し、その英文を日本語に自動翻訳すると、ヒントを得られるかも知れません。
- 多くの学生に共通する助言を「ヒント」として、このページの 上のほう に掲載しました。
7月27日
- 模擬研究の課題は言葉遣いや形式など論文の作法に慣れることが目的です。内容にこだわってはいけません。
- 全員に対し、Zoomによる研究室訪問を指示しました。
7月20日
- これからの3週間は、模擬研究論文を通して、アカデミックな文の書き方を学びます。
1. はじめに:先行研究を紹介する。正しい書式で引用文献リストに載せます。
2. 実験の方法:実験の再現ができる程度の情報を明確な言葉で表します。箇条書きでなく文章で書きます。
3. 結果:数値を読みやすい表やグラフにまとめます。図表のタイトルを正しい形式で付け、本文で言及します。
4. 考察:結果のおさらいを簡潔な文章にまとめます。実験により見いだすことのできた内容を論理的に述べます。
7月13日
- 学習歴の異なる集団や、母語の異なる集団を扱う調査は、その違いが見込まれる場合に、影響を見るのに最適な条件を設定して行います。
- 「...ので」は、必然的にそうなる場合にだけ使いましょう。
- 「...が」は、逆説にだけ使いましょう。また、それが不要な前置きでないか考えましょう。
7月6日
- 明らかにしたい内容に応じた実験を設定します。何をどう比較すれば知りたいことが見つかるのか考えましょう。
- 論理的に文を書きましょう。不要な言葉を減らしましょう。
- 専門用語を自作してはいけません。新しい熟語を思いついたときは、よく使われる語であるか、検索して確かめましょう。
- 括弧を使った注釈は極力避けましょう。情報は文章にして、本文に入れましょう。
6月29日
- 論文では主観的な表現を避けましょう。「私は」「とても」「意外に」「...と思った」→「半数以上が」「...であるように思われる」
- 引用文献の表示方法が正しくないと、スペースの有無が曖昧な英文のように、読めない文章になります。
- 単語を発話して分析する際は、通常はフレーム文に入れて録音します。
単語ごとに発話した場合、それは1語文であり、文頭であるが故の影響、および文末であるが故の影響が発生するからです。
フレームに入れると、話速の制御にもつながります。
6月22日
- 論文名は、どの分野のどんな研究か分かるように、詳細に書きます。どうしても字数が増えます。
- 研究のまとめかたの1つのパターン
1.「はじめに」:従来の研究を紹介したうえで、自分の実験や調査にどのような意義があるのかを述べます。
2.「実験の方法」:実験器具、被験者、手順などについて説明します。
3.「結果」:結果を数値などで報告します。表やグラフも入れますが、特徴などは文章で伝えます。結果報告のみとし、意見は書きません。
4.「考察」:結果から読み取れること、さらに予想されることを述べます。
6月15日
- 促音の実態が子音の持続時間であることを学びました。摩擦音[s][ʃ]などはそのまま伸ばし、破裂音[p][t][k]などは閉鎖区間を伸ばします。
- 信頼性の高い文献を選ぶ方法を学びました。大きな学会の出版する雑誌には、一般的に質の高い論文が集まります。
- 引用文献を表示する際の規則を学びました。
6月8日
- 母音の無声化について、自習した内容をもとに、皆が理解できる水準までグループワークをしました。
- 調べものをするときに、Webや論文、書籍が信頼できるものか、確認する必要があることを学びました。
- 電子化された研究情報は、CiNii や Google Scholar からたどりやすいことを学びました。
6月1日
- 工業製品を規格通り作るように、レポートは指示どおりに作成すべきであると学びました。
- 子音は調音点(両唇、歯茎、軟口蓋など)と調音法(破裂音、摩擦音、鼻音)により分類できます。
- 撥音「ん」は、後続する子音と同じ調音点で発音する鼻音です。
5月25日
- 『「あ」は「い」より大きい!?音象徴で学ぶ音声学入門』第5章をもとに、グループワークをしました。
- 摩擦音は伸ばして発音できる子音です。
- 破裂音は閉鎖区間を伸ばすことはできますが、音の聞こえる部分を伸ばすことはできません。
- 日本語のザ行、ジャ行は語頭(及び促音や撥音の直後)では破擦音(破裂音+摩擦音)、語中では摩擦音として発音されます。
英語の zoo を "dzoo" のように破擦音を使って言ったり、BGMのGをBZMのように摩擦音を使って言う癖があります。
5月18日
- 『「あ」は「い」より大きい!?音象徴で学ぶ音声学入門』第2章をもとに、グループワークをしました。
- グループのメンバーと、読んできた内容の共通理解を図りました。
- 授業中は読解の宿題を開かず、議論に集中するという決まりを確認しました。
- 阻害音と共鳴音がどのような音であるか考えました。
- 新しいおむつのブランド名を考え、共通して使われる音の特徴を推測しました。
5月11日
- 正しいコピペをしましょう。出典を示し忘れると剽窃(ひょうせつ)とみなされます。
正しくないコピペは、手書きの時代から当然ご法度です。問答無用です。
- 大学での議論は、口頭でも文字でも論理的である必要があります。
2つの絵を使って議論をしました。論理的に話せましたか。メイドカフェの店員 新種の蝶2種
出典:川原繁人『「あ」は「い」より大きい!?音象徴で学ぶ音声学入門』ひつじ書房, 2017年, 41頁と63頁