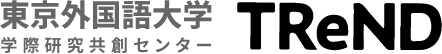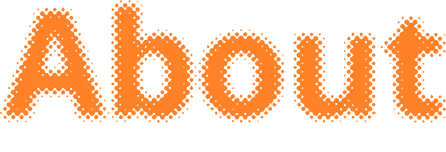
センターについて
Message
あいさつとメンバー
学際研究共創センターは、東京外国語大学の研究と社会を繋ぐ役割を担うための研究支援組織です。大学や分野を超えた研究活動の学際的展開支援活動(ディシプリンベースの専門研究を超える研究融合・協働の創発)と、広い社会への展開を作り出すため、研究・研究者・学生が、大学のキャンパスを超えて、多くの人々・企業・自治体とに繋がるようなきっかけを創出するためのプロジェクトの運営をしています。
センター⻑のあいさつ

私が専門として行う言語学フィールドワークでは、それまで持っていた知識体系の中に収まりきらない新たな言語のありように驚かされることが常でした。研究というのは、新たに得る知識や経験に意識と思考を開き、既存の枠組みを問い直しつつ、新たな知識体系へ拡大し、変質させていくプロセスです。
現在、目を向ける先々に取り扱いが難しい「やっかいな問題」が山積しています。「やっかいな問題」がやっかいである所以は、多くの要因が動的に絡む複雑さと問題に関与するステークホルダーが幅広く存在するためです。これらの問題に取り組んでいくために今重要なのは、『答えを探すこと』ではなく、何を課題として切り出すか、『問いを立てること』だと言われます。また、その問い立てのプロセスを社会の多様な人々とともに作っていくことが必要です。
そこで、学際研究共創センターでは、大学が企業や地域を結ぶプラットフォームとして多様な人々の間の交流を作り出し、そこから生まれる多様な知を課題解決や社会変革の力として社会に送り出す活動を起こしていきます。
多くの人が関わり、創発し、協働する場となるような環境作りに努めてまいりますので、TReNDセンターの活動にご期待ください。
学際研究共創センター⻑
中⼭ 俊秀
NAKAYAMA Toshihide
【Profile】消滅の危機にあるヌートカ語の研究が言語学者としての私のスタートラインでした。その後、コミュニケーションを介して言語が進化・変化するダイナミクスに関心が広がり、現在では、刻々と変化を遂げるオンラインでの言語表現パターンの形成・変化を研究しています。TReNDセンターでの研究支援は、探究マインドが自由に楽しく研究を進化させるきっかけと環境を作ることだと考えています。今と未来をつなぐ人の関係と探究のダイナミクスを創出する基盤として、多くの研究者が集まるプラットフォームを目指します。
メンバーについて
青井 隼人
AOI Hayato
いまアカデミアでは、文理を問わず、異分野交流が強く求められています。先鋭された専門家集団によって知を研ぎ澄ませていくことも相変わらず必要なことですが、それだけでは革新的なアイデアは生まれません。イノベーションとは、常に新しいものとの偶然の出会いから生じるものだからです。隣の研究室の動向に関心を向けてみる。自分の話を研究室の外の人に聞いてもらう。そんなささやかな交わし合いが、対称的な世界に破れ目をつくります。世界をひらくきっかけと出会いに、TReNDセンターまでぜひお越しください。
【Profile】1987年、岡山県生まれ。専門は、琉球諸語の音声学・音韻論。博士号取得後、アジア・アフリカ言語文化研究所で5年間勤めた後、個人研究事務所ILOLiを起業。半年間のフリーランス研究者を経て、現職。学術コミュニケーション講師および学術メンターとしてのキャリアを活かし、大学院生を主な対象とした異分野交流促進に取り組んでいる。
和泉 悦子
IZUMI Etsuko
学際研究共創センターでプロジェクトの運営支援をしています。本センターのプロジェクトは、異なる背景を持つ視点が交わり、違和感を乗り越えたその先にある、化学反応的な成果を楽しむ、そんなコンセプトを持っているなと感じています。時代の変化に伴い大学をめぐる環境も変わっていきますが、その変化によって、より豊かな関係性が生み出されるのだなと現場で実感する日々であり、その経験こそが、学際研究や共創に関わることへの動機になると感じながら業務に携わっています。
東京外国語大学の強みである多文化共生は、人や情報の変化が一層大きくなった現代に、人や社会がより良い関係性を構築することができる知識です。学際研究共創センターを通じて、研究や教育の環境が広がり、学生や教員、またセンターに集まる外部のみなさまにとって、新しい可能性の提供につながるような支援を目指しています。
【Profile】大学では、理系(物理学)を専攻していたため、東京外国語大学に職員として入ってから、人文・社会学系研究の面白さを知りました。様々な研究分野の方の交流をとおして、見え方の多様さを垣間見ることに、TReNDセンターの活動の面白さがあると思っていますので、多様な出会いをプロデュースできたらいいなと思っています。
神代 ちひろ
KUMASHIRO Chihiro
小林 真也
KOBAYASHI Shinya
本センターの関連事業である、多文化共創イノベーションリーダー育成プログラム(MIRAI)。その前身となったプログラムを修了後、現職に着任しました。MIRAIで学内外・他分野の様々なアクターと交流・協働した経験から、学際的あるいは産官学的な多セクター間連携の重要性を強く感じています。本学初となるURAの1人として、より社会に開かれた東京外国語大学の実現を目指して活動していきます。
【Profile】1998年、千葉県生まれ。東京外国語大学博士後期課程単位取得後、2025年10月よりURAとして着任(学籍は休学中)。研究の専門は、日本語のライティング教育と、授業や学習活動にゲームデザインの要素を取り入れる「ゲーミフィケーション」。
根木 優気
NEGI Yuki
久納 弘明
HISANOU Hiroaki
こと研究に限らず、インターネットが発達し市民権を得て常識となった昨今、「一人で何かを黙々とやる」ことは非効率と言わざるを得ません。 {研究}というジャンルも同様で、他分野の知識や他者への興味をクローズドしてしまうと、その両方がオープンな研究者に何歩もリードされ、リードされていることにすら気づかない状態に陥ることでしょう。 クローズドマインドで「研究の崇高さ」を語ることは、もはや時代遅れと言わざるを得ません。
学際研究共創センターは、新たな研究の価値・・・異分野でもオープンマインドで話せる場の提供より始まる高品質な共同研究、相乗効果をもたらす研究者集団としての在り方、後々社会から求められるであろう思想や理念の探求姿勢・・・を語る場である、と考えています。
【Profile】佐賀県生まれ山奥育ち。刑務所のような全寮制男子校を経験後に上京し、小学校の教員免許を取得(現在、期限切れ)。大学卒業後に3年間ミュージシャンを目指し活動するも、夢破れ東京外国語大学事務職に就職。研究活動とは無縁な人生ではありますが、音楽という「他人と共に作る」ことをしてきたからこそ、現職で感じることが多々あります。
「まずは、ここで語り合いましょう。」