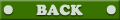ベンヤミンの『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』における「二義性」
クラウス論を通じての「ボードレール論」解釈の試み
日本独文学会 1996年度春季研究発表会
5月12日(日)
一般研究発表 (3) 発表原稿
ハンドアウト1
ハンドアウト2(続き ドイツ語)
(注意:技術上の問題で、実際に使用したハンドアウトと一部異なるところもあります)
1 「ボードレール論」の経緯と構想
今日取り上げる『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』は、もともと3部構成として構想された『シャルル・ボードレール--高度資本主義の時代における抒情詩人』と題されるボードレール研究の第2部として書かれたもので、結局第1部と第3部は執筆されなかったのですが、実際に書かれた『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』が全体の第2部にあたるものだということが、この論文の性格を決定づけています。ここでは、この事を特に重視して、書かれることのなかった第1部・第3部を含めた全体を「ボードレール論」と呼ぶことにしたいと思います。
-
(現在われわれがベンヤミンのボードレール論という名称のもとに考えるテクストといえば、まず、1969年にRolf
Tiedemannの編集により一冊のまとまった著作という形で出版された『シャルル・ボードレール-高度資本主義の時代における抒情詩人』の二つの文章、すなわち『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』そして『ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて』であり、これらに『セントラルパーク』や『パリ、19世紀の首都』の中のボードレールの章を加えることもできると思います。
-
しかし、ベンヤミンのボードレールに関するこれら一連の文章の中でも、これからとりあげる『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』は、論文の位置づけの点で、特別な意義を有していると思われます。この論文は、もともと3部構成を持つボードレール研究の構想の内、その第2部として書かれたものです。残りの第1部と第3部を、ベンヤミンは結局書き上げることはなかったのですが、本来構想されていた3部構成のボードレールの論考全体に対して、ある書簡の中でベンヤミン自身が『シャルル・ボードレール-高度資本主義の時代における抒情詩人』という標題を与えています。この同じ標題が、すでにふれたR.Tiedemann編集の1969年のボードレール論集に用いられており、また同じ編集者による全集版でもこのまとめ方が踏襲されているため、きわめて紛らわしいのですが、ここでは、ベンヤミンの当初の3部構成の全体としての『シャルル・ボードレール-高度資本主義の時代における抒情詩人』、つまり、結局は書かれることのなかった第1部と第3部、そして実際に執筆された第2部の『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』、これらの全体を「ボードレール論」
と呼ぶことにしたいと思います。)[削除]
-
この「ボードレール論」は、もともと『パサージュ論』の一つの章として計画されていましたが、1938年4月16日付のホルクハイマー宛の書簡に述べられているように、構想の段階で、このボードレール研究が「『パサージュ』の本質的なモティーフが収斂する一層包括的な叙述」(I,1073)となり、パサージュ論の「ミニチュアモデル」として、単に一つの章というよりも、独立した著作として構想されていくことになります。そして、すでにこの時期、1938年4月初旬から中旬には、「ボードレール論」は3部からなる論文として考えられていたことが書簡に見られます。この3部構成の構想を、3つの時期の書簡からハンドアウトの①、②、③にまとめてみました。※ここに示したものは、本来は書簡のうちに文章として書かれていたものを、ベンヤミン自身のキーワードを用いつつ、私が試みに図式化してみたものです。ハンドアウトの①は、先にふれたホルクハイマー宛ての同じ書簡のうちに述べられたもので、最も詳しい全体の見取り図が示されています。ハンドアウトの②の書簡が書かれた1938年8月の時点では、すでに第2部のみを寄稿論文として提出することが考えられていま
す。そのため、ここでの記述は当然ながら、第2部が中心になっており、ハンドアウトの①と同様にこの部分がAntikeとModerneの関係、および大都市における大衆の問題、という二つの中心テーマを持つことが述べられています。最後のハンドアウトの③は、第2部である『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』が完成し、ニューヨークのホルクハイマーのもとに原稿を送付した1938年9月28日に、提出された第2部の位置づけを示すために書かれたもので、全体の構成が透明な形で示されています。第2部執筆の過程において、量的・時間的な問題から、たびたび構想の変更を迫られたことがこの期間の書簡から伺えますが、もはや具体的な論点が捨象されたハンドアウトの③に見られる構想においても、最初に考えられていた基本的な方向はそのまま受け継がれていると考えられます。
2 クラウス論との並行性
-
そういった立場に立って、この構想全体の方向を言い表すとすれば、次のように要約できるのではないかと思います。第1部で、従来のボードレール像、とりわけ芸術内在的視点による彼のアレゴリーに関する見解が、テーゼとしてまず提示されます。第2部、つまり『第二帝政期のパリ』で、社会批判的視点からボードレールの限界が示されますが、その過程において、近代と古代の"Uberblendung"(これについては、後で述べますが、とりあえず「重ね合わせ」といっておくことにします)が提示されます。また、その前提として都市の「大衆」の持つ機能が示されます。そして、最後の第3部では「マルクス主義的解釈」による「解決」が提示されていたはずですが、そこではJugendstilとブランキやニーチェにインスピレーションを得た「永劫回帰」の問題が取り上げられていたと思われます。
-
このように「ボードレール論」の構想を捉えるとき、3部構成による展開、そしてその展開の方向性から、「ボードレール論」が1931年に書かれたエッセイ『カール・クラウス』との並行性を顕著に示しているように思われます。クラウス論も「全人間」「デーモン」「非人間」という標題をもつ3つの章から構成されていますが、そこでは、これらの標題の示す人物像によってクラウスという人間が描き出されるだけではなく、各段階によって体現されるベンヤミン自身の思考モデルが提示されています。つまり、第1章「全人間」では、クラウスは彼の信奉者による「弁護的apologetisch」(II,345)な姿勢によって「古典的ヒューマニズム」を体現する人物として描かれています。「全人間」像が体現するこの「古典的ヒューマニズム」は、クラウスの場合、彼の最も顕著な特徴とみなされている「論争家」と、被造物に対して深い愛情を抱く「自然の友Naturfreund」という両極的な資質をその要素としてもっています。
-
第2章の「デーモン」は、この「全人間」にアンチテーゼとして対置されます。デーモンとしてのクラウスは、「時代」を告発し、それに巻き込まれることへの防御反応を示しつつも、結局は自ら「時代」に関与することで「同罪」となり、「時代」との「共犯関係」をもっているとされます。そして、その意味で彼の持つ限界が、ここで描かれることになります。この「デーモン」の章では、「虚栄」、「世界審判」的な自然、「法」、「罪」、「精神と性」、あるいはその現れとしての「文士」と「娼婦」、といったさまざまな領域の持つ特性が、まさにデーモンの領域にあるものとして取り上げられているのですが、ベンヤミンにとってこれらがまさにデーモン的であることを指し示しているのが、それらのもつ「二義性Zweideutigkeit」です。(時間の関係で、これらの各領域における二義性の具体的内容をひとつひとつ説明していくことはできませんが、ハンドアウトの④にいくつか例をあげておきました。)※例えば、「虚栄」に関しては、自己の表現と他人の暴露という二つの要素が逆説的に交錯して「自己自身の暴露」となり、また、「虚栄」のバリエーションである「模倣」においては「憎
悪の擬態」としての「慇懃さ」と「慇懃さの擬態」としての「憎悪」が交錯するとされます。あるいは「売春」においては、性の自然と経済の自然が同時に体現されていると言われています。このように、一つの対象においてまったく異質な二つの属性が重ねあわされていること、あるいは特に、ある一つの対象が、二つの対象とその属性が逆説的に交錯した結果、生じたものであるということ--ベンヤミンにおける「二義性Zweideutigkeit」とは、このような意味を負わされた概念である、とひとまず提示することにしたいと思いますが、この「二義性」を具体的に描き出すことが、クラウス論の「デーモン」の章において、何よりも決定的なモティーフとなっています。
-
クラウス論最後の第3章の標題として掲げられた「非人間」において意図されているのは、ベンヤミンのいう「弁証法的唯物論」を具現する「現実的ヒューマニズム」の担い手としての人物像ですが、これは(ハンドアウトの⑤をご覧ください※)「饒舌においてデーモン的に混じりあっている公的領域と私的領域」(これはつまり、「時代」の現象に見られるデーモン的な「二義性」と言い換えられますが)、これを「弁証法的な対決へといたらしめ、現実的な人間性を勝利へと導くこと」(II,356)によって可能になるとされます。「デーモン」の章で具体例に即して提示された「二義性」は、まさにこの地点において、『パサージュ論』の「概要」である『パリ、19世紀の首都』の方法論的な問題設定と交差します。ハンドアウトの⑥をご覧ください。※「しかし、まさに近代が常に根源的歴史を引用する。そういったことがここで起こるのは、この時代の社会的諸状況と所産に特有な二義性による。二義性とは、弁証法が形象をとって現れたものであり、静止状態にある弁証法の法則である。この静止状態はユートピアであり、弁証法の形象はつまり夢の像である。こういった形象を
例えば、商品そのもの、つまり物神としての商品が表す。家であると同時に通路でもあるパサージュも、こうした形象を表す。売り子と商品が一体となった娼婦も、こうした形象を表す。」クラウス論の「デーモン」の章の中で、ベンヤミンがクラウスにおける「虚栄」、「法」、「罪」、「精神と性」、「売春」などのもつ「二義性」を指摘したように、使用価値をもつと同時に「物神」でもある「商品」、あるいは「家であると同時に通路でもあるパサージュ」、あるいは「売り子と商品が一体となった娼婦」が、高度資本主義における「夢の像」としての「弁証法的形象」を表すとされています。つまり、ここでの「二義性」の意味するものは、いわば弁証法が、本来の動態的なものではなく、二つの属性が交錯したひとつの形象という形で「静止状態」のうちに凝結したもの、つまり、
「弁証法が形象となって現れたものdie bildliche Erscheinung der Dialketik」として考えることができるでしょう。そして、この「二義性」は、「このエポック」つまりベンヤミンのいう高度資本主義の時代の「社会的諸状況や所産に特有」なものであり、デーモン・クラウスがその「罪」に自ら巻き込まれつつそれと戦ったとされる「時代」の「社会的諸関係や所産に特有なもの」でもあります。この「夢」の内にあるとされる「二義性」の段階が、パサージュ論「概要」やパサージュ論のNの項で言われているように、「覚醒」へともたらされる可能性を、ベンヤミンはクラウス論第3章の「非人間」において、また「ボードレール論」の書かれなかった第3部において示した、あるいは示したであろう、と考えられます。
-
しかし、実は、1935年の『パサージュ論』ドイツ語版「概要」は、これを読んだアドルノから35年8月2日付の書簡でかなり厳しい批判を受け、ハンドアウトの⑥にある"Zweideutigkeit"という概念に対しても批判的指摘を受けることになります。それ以降、"Zweideutigkeit"あるいは"zweideutig"という言葉は、私の見る限りでは、ベンヤミンの文章からほぼ姿を消していると思われるのですが、これから述べますように、この概念の中身自体は、彼の文章のうちに保たれ続けていると、私は考えます。つまり、これまで対比してきたように、「ボードレール論」の第二部としての『第二帝政期のパリ』を、クラウス論での「デーモン」の「二義性」において含意されたと同様の「静止状態における弁証法の法則」が展開される場として捉え、さらに、この「弁証法が形象を取って現れたもの」が最終的には、つまり第3部において、「覚醒」によってベンヤミンのいう「弁証法的唯物論」へと到達すべきものとして意図されていることを視野に入れるならば、『第二帝政期のパリ』のいたるところでライトモティーフのように現れる、取り上げられる事物
のもつ二重性・両極性のもつ意味が浮かび上がってきます。
3 『第二帝政期のパリ』のテクストの問題
-
このことについてテクストの具体的な個所を指摘していく前に、『第二帝政期のパリ』のテクストそのものの持つ問題、そしてそれと関連してテクストの構成について、ふれておきたいと思います。
-
現在われわれが『ボードレールにおける第二帝政期のパリ』として読んでいるテクストは、R.Tiedemannが全集のAnmerkungenでT1aという記号によって表しているタイプ原稿に基づいたものです。(ハンドアウトの⑦をご覧ください※)このテクストは、周知のように、「Ⅰ
Die Boheme」「Ⅱ Der Flaneur」「Ⅲ Die Moderne」という三つの章から構成されています。しかし、『第二帝政期のパリ』は、草稿の段階では三章構成によって書かれていません。それは、TiedemannによってM1と呼ばれているマニュスクリプトですが、これは1971年に旧東独でRosemarie
Heiseによって独立した本として発行されています。この版はT1aには含まれていない方法論的な序文と"Der
Geschmack"と題された章をもつというだけでなく、序文をのぞいて全体が15の小さな章に分けられ、それぞれの章に標題がつけられるという注目すべき独自性をもっています。Heise版のM1の各章につけられたこれらの標題を、Tiedemannはあまり重視していないようです。しかし、「ボードレール論」全体がかなり早い段階から3部構成として構想されていたのに対して、『第二帝政期のパリ』が3章構成となることを示唆するものは、最終稿のタイプ原稿の完成までありません。また、Tiedemannのいうように、これらの標題が後の構成のための参考につけられたものとしての意味しかもたないものであるにせよ、テキスト全体がベンヤミン自身によって、内容的・テーマ的に区分されているという点で、M1の構成とそれぞれの節につけられた見出し語はやはり大きな意義をもっていると考えます。そういった立場から、私は基本的にT1aのテクストの3つの章からなる構成に基づきながらも、M1での章分け・テーマ区分もかなり重視しています。ここでは二つのテキストの比較に立ち入ることはできませんので、参考までにハンドアウトの⑧に二つの版の構成を対照したものを掲げておきました。※
4 『第二帝政期のパリ』における二重性
-
ここでようやくテクストの中に入っていきますが、最初の章「ラ・ボエーム」は、「第二帝政期」を中心とする社会状況、その関連において「書くこと」のおかれた状況、をいわば俯瞰的に取り上げていると思われます。すでにこの章において、多くの箇所に人物や事柄の二重性が描かれていることを指摘できます。それらのうち特に取り上げたいのは、「職業的陰謀家」を扱った最初の部分で、いわば「魔術的」効果に依拠する暴動の扇動者、プッチストという側面と、労働者に啓蒙を行う理論的指導者という側面の二つの面・二重性を併せ持つ存在としてブランキが描かれ、このブランキとボードレールが重ね合わされているということです。このテーマは最後に再び浮上します。
-
次の第2章では、主に「遊歩者」(Flanuerという語をとりあえずこう訳すことにしますが)の視点で大都市の細部が描き出されていきます。ハンドアウトの①の書簡に示されているようにここでのテーマは「大衆」とその3つの機能に集約されます。その前史として取り上げられた「生理学」に関する記述の中で、すでにパサージュ論のドイツ語版「概要」の内に触れられていた「パサージュ」の二義性について述べられています。ハンドアウトの⑨をご覧ください。※「パサージュは通路と室内の中間物である。」この定式は、M1では「群集の人」と名づけられた部分の最後の箇所で次のような変容を遂げます。ハンドアウトの⑩をご覧ください。※「遊歩者にとって通路は室内としてあるのだが、パサージュがこの室内の古典的形式であるとするならば、その退廃形式が百貨店である。」つまり、古典的形式としてのパサージュに対して、退廃形式としての百貨店は、室内と迷路(すなわち商品の迷路)という二重性を帯びた中間物として表わされることになります。しかし、覚めた目で見れば「退廃形式」であるにせよ、この都市を歩き回る「遊歩者」にとって、いっしょに歩き回
っている「群集」「大衆」が「麻薬」として、また「ヴェール」として機能することによって、社会は美化され、何か美しいものとしてたち現れてくることになります。群集が「麻薬」的な力をもつこと、群集が「恐るべき社会的現実」に対する「ヴェール」として機能すること、そしてまた、都市のさまざまな構成要素あるいは都市全体が二重性・二義性のうちに、いわば幻のように立ち現れること--これらはすべて相互に絡み合っているのですが、--ベンヤミンがしばしば用いる"Phantasmagorie"という言葉は、こういったことを指し示しており、高度資本主義の持つもっとも顕著な特性の一つとして、あるいは、クラウス論に当てはめていうならば、「デーモン的」な特性として、用いられているといえます。ベンヤミンが強い関心を示した「ガス灯」も、そのほの暗い光で"Phantasmagorie"としての都市を浮かび上がらせてきたことによって、二義性・二重性に関わる"Phantasmagorie"をもっとも顕著に体現するものとして取り上げられています。ハンドアウトの⑪をご覧ください。※「通路が室内空間として現れることのうちに、遊歩者の幻影Phantasmagorieは集約
されるが、この現象をガス照明と切り離すことはできない。」
-
この二重性によって生み出される「幻影Phantasmagorie」は、最後の章「近代」においては、ハンドアウトの①にも見て取ることができるように、「古代」と「近代」の"Uberblendung"として描き出されています。"Uberblendung"というのは映画の一技法であり、前のシーンがフェード・アウトしながら、次のシーンがフェード・インする過程のことを指します。日本では、英語のままdissolveという言葉を使うようですが、この過程においては、二つのシーンがお互いをぼかしつつ二重写しになります。この言葉はテクストの中に何気なく使われていますが、クラウス論における「二義性」に対応する、決定的な概念であると私は考えます。
-
この"Uberblendung"="dissolve"がまず示されているものが、「ヒーローHeros」という概念です。『悪の華』の中の詩「太陽」のうちにある「風変わりな険技fantasque
escrime」という言葉のイメージを出発点にしながら、ベンヤミンは「剣をふるう詩人の像」・古代剣士の像と、「脱走兵の像」つまり近代の落ちぶれた人間の像を重ね合わせています。ハンドアウトの⑫をご覧ください。※(この引用の直前で、ナポレオン3世の時代に、軍隊がすでに零落した者たちから成っていたことが述べられているのですが)「こういったことから、剣をふるう詩人へと視線を引き戻すならば、そのまなざしは、しばしの間、脱走兵の像とuberblendenされる(重ね合わされる)ことになる。つまり、別の意味で「剣をふるい」ながら、野原をさまよう傭兵の像と。」この重ね合わせは、その根幹の要素へと捨象するならば、ベンヤミン自身が論点をあげているように、「古代」と「近代」の重ね合わせということができます。ここへと論点がさらに集約していくのが、M1のテクストで「Anwartschaft
auf die Antike古代への継承権」とされている箇所です。ここでベンヤミンは、『悪の華』のいくつかの詩のうちに近代と古代との相互浸透が見られることを指摘していますが(I,585)、この「相互浸透Durchdringung」という語も、"Uberblendung"と同義で用いられていると思われます。しかも、『悪の華』の「白鳥」を例にしつつ、この近代と古代の「相互浸透」には「アレゴリー」が決定的な意味を持っていることをベンヤミンは示しています。これらのことは、画家メリヨンとボードレールの親近性についてふれた次の箇所で端的に言い表されています。ハンドアウトの⑬をご覧ください。※
「メリヨンについて論じながら、彼(ボードレール)は近代に熱中している。彼が熱中しているのは、しかし、近代の中の古典古代の相貌である。というのも、メリヨンにおいても、古代と近代が相互に浸透しているからだ。メリヨンにおいても、このUberblendung
(dissolve) の形式、すなわちアレゴリーが、見まがいようもなく立ち現れているのだ。」このように考えてくると、ベンヤミンにとってのボードレールにおけるアレゴリーとは、あるいは、より慎重に限定するならば、この「第2部」のボードレールにおけるアレゴリーとは、クラウス論の「デーモン」の章における「二義性」がそうであったように、二つの異質な要素(とりわけ、近代と古代)が一つの像Bildとして定着させられたものであり、「弁証法が形象として現れたもの
die bildliche Erscheinung der Dialektik」あるいは「弁証法的形象das dialektische
Bild」もまさにこのことに関わってくるのではないかと思われます。
-
このアレゴリーのうちでも、ベンヤミンが「白鳥」「朝の薄明」「太陽」に言及した箇所でふれているように、これらの詩の中に見られる「脆さGebrechlichkeit」「か弱さHinfalligkeit」を表すアレゴリーは特に中心的なものとされています。ハンドアウトの⑭をご覧ください。※「近代と古典古代が、最終的にそしてもっとも内密に結びつけられるのは、このか弱さにおいてである。」この引用の箇所、つまり「古代への継承権」がテーマとなっている箇所では、没落し廃虚となった古代の都市のイメージとボードレールの時代のパリのイメージが、まさにUberblendungによって二重写しにされていますが、「か弱さ」を通じてこの二つが一つの「像Bild」に定着することになります。ハンドアウトの⑮をご覧ください。※「やがて眼前から失われるとわかっているもの、それが像Bildとなるのだ。」テクストの文脈においてこの"Bild"は、特に画家の描いた絵のことをさしていますが、これは例えばボードレールが描き出したパリについてもまったく同じ事がいえます。
-
このテクスト全体の最後の部分は、M1では「Poetische Strategie詩的戦略」とされていますが、ボードレールにおけるこの「詩的戦略」の中心にあるのは、やはり「アレゴリー」であるといってよいでしょう。両極端の間で揺れることを特権とする「船」の像についての指摘も、これまでの連関においてきわめて興味深いものの一つですが、ベンヤミンが最終的に重点を置いているのは、「都市的な由来の語」、つまり従来の抒情詩においては卑賎な語として用いられなかったボキャブラリーのうちに突然現れるアレゴリーの持つ力であるように思われます。ハンドアウトの⑯をご覧ください。※「彼のボキャブラリーのどの語も、はじめからアレゴリーになるべく定められているわけではない。言葉がこういった充填を受けるのはケースバイケースである。(一文とんで)ボードレールにおいては詩作と称されるこの奇襲Handstreichのために、彼はアレゴリーに信頼を置く。秘密を打ち明けられているのは、このアレゴリーだけなのだ。(最後の文までとんで)彼の技法はプッチストの技法なのだ。」これが、ベンヤミンのいうボードレールの「詩的戦略」ですが、このように陰謀家の秘
密主義、プッチスト的な奇襲をボードレールの詩作に重ね合わせることによって、ベンヤミンは再び、冒頭に取り上げていたブランキへと立ち戻っていきます。実は、テクストの最後の部分はM1ではもともと最初の章にあったものです。ベンヤミンの語り口の常として、次の段落への移行が、前の段落の最後の部分に用意されるということがあるので、この部分は書かれるはずであった第3部を用意するものとして置かれたと考えてよいでしょう。ハンドアウトの⑰をご覧ください。※「ボードレールはある有名な一行の中で、『行為が夢の妹でない』世界から、心軽やかに別れを告げている。彼の夢は、彼が思っていたほど見捨てられていたわけではなかった。ブランキの行為はボードレールの夢の妹だったのだ。両者はお互いに絡み合っていた。」つまり、この第2部にあたる『第二帝政期』が二重性・二義性によるPhantasmagorieとしての「ボードレールの夢」であるとすれば、第3部では「ブランキの行為」が展開される可能性が示されていたのではないかと推測されます。
-
この発表では、第2部としての『第二帝政期』とクラウス論の第2章「デーモン」に論点を絞りましたが、全体としての「ボードレール論」が『パサージュ論』の「ミニチュアモデル」として考えられていたことからも、書かれるはずであった「ボードレール論」のテーマ間の諸関係を検討することによって、バラバラな資料の集積としての『パサージュ論』を再構成する可能性も生まれるのではないかと考えています。
-
-