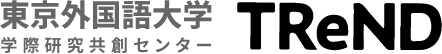取り組み
TUFS VS AI
AI時代の「人文・社会科学系学生の生存戦略」、いっしょに考えませんか。
関係機関
東京外国語⼤学 学際研究共創センター(TReNDセンター)
東京外国語⼤学 多⽂化共⽣イノベーション研究育成フェローシップ(MIRAI)
キーワード
公開プログラム
異分野融合研究
研究教育機関との連携
講演会
最終更新 2024.07.22
開催終了
概要
OpenAI が開発した ChatGPT、そして 2023年3月にリリースされた GPT-4 などの生成系AI(Generative AI)。今後、教育・研究現場の広い領域でも、人工知能が担う役割は増していくと考えられます。私たちはいま、歴史的なターニングポイントに立っていると言えるでしょう。
大学という場において現在の変化を捉えると、今後は「AIにできる作業はAIに任せて、生身の人間同士の絶妙なコミュニケーションが求められる面へと、教育・研究活動の重点がシフトしていく」と言えるかもしれません。本企画では、個性あふれる学生・研究者を擁する東京外国語大学(TUFS)という場から、人工知能を活かしたさらなる創造性の発露に向けていま私たちにできることを考えていきます。
もちろん「答え」は誰ひとりわかりません。いま、私たちにあるのは、日々の実践のなかで生じる無数のワクワクやモヤモヤです。2023年度連続企画「TUFS vs AI」では、放っておくとやがて忘れてしまう、そうした「ワクワク・モヤモヤした感じ」を「問い」へと言語化することで、参加者間で問題意識を共有・共感することを第一の目的としています。

イベント
第1回「vs ChatGPT round1 ーAI時代の大海原に漕ぎ出すにはー」
2023年5月17日(水)
まずは使ってみましょう!
今後、社会の広い領域で人工知能の存在感は不可逆的に増していくことが予想されます。このことは言語研究と地域研究を二本柱とする本学での教育・研究現場も例外ではありません。連続企画「TUFS VS AI」の初回として、まずは ChatGPTを実際に使ってみるワークショップをします。とはいえ、すぐに応用できるような「答え」はありません。そもそも、人工知能の飛躍的な発展と浸透は人類史上未曾有の出来事であり、だれにも対応策や解決策はわからないのです。第1回は、ワークショップとダイアローグを通してモヤモヤを言語化することで、未来にむけた「問い」を共有していきます。
【当日の流れ】
1. ChatGPTの概要と基本的な使い方の紹介
2. ワークショップ・セッション
3. ダイアローグ・セッション
【イベントを終えて】
第1回「TUFS vs AI」の対ChatGPT企画では、「まずは使ってみましょう!」を合言葉に、レポート課題や身近な旅行計画、俳句作品などを参加者と生成系AIのChatGPTとが共創しました。これは本学で行われた最初のAI協働実験とも言えるかもしれません。
イベント
第2回「メタバース× 生成系AIの近未来」
2023年5月24日(水)
文章だけじゃない!? AIがつくる「世界」を感じよう
・ 生成系AIがメタバースにもたらすインパクト
・デジタルテクノロジーを活用した社会課題解決の方法
| ゲストスピーカー | 宮田 和樹 氏(青山学院大学総合文化政策学部デジタルストーリーテリングラボ) |
|---|
イベント
第3回「vs ChatGPT Round2 -外大生、AI時代の大海原を漂流中-」
2023年6月14日(水)
前回のワークショップの中では、「AIらしい受け答えだった」「ありきたりな内容だった」「若干ずれた回答だった」という声が参加者から多く聞かれました。ここで一つの「問い」が生まれました。それでは、いったい私たちはAIに何を期待してしまうのでしょうか。AIとのやりとりに対して、私たちは無意識のうちにどのようなコミュニケーションのあり方を求めているのでしょうか。今回のワークショップでは、これらの根本的な「問い」をさらに深掘りしていきます。イベントタイトルの「漂流中」という言葉には、人工知能と対峙したとき、ヒトの言語能力を凌駕しうるものとして畏怖するのか、多文化を育む仲間として共生していくのか、ひとりの外大生として目指す先が見通せていないという状況を表しています。
【当日の流れ】
1. 前回までの振り返りと基本的な使い方の紹介
2. ワークショップ・セッション
3. ダイアローグ・セッション
4. 参加者による研究蓄積への追記
イベント
第4回「生成系AIにおける人間の創造性と共創」
2023年6月22日(木)
生成系AIの社会的影響は非常に大きく、教育、ビジネス、生活のあり方が大きく変化していくだけでなく、人々は自らの創造性について改めて考えざるを得なくなるでしょう。今回は、AIなどの創造性の現在地を確認しながら、人間と機械との創造性の境界や両者の共変化について、情報学者の河島氏に講演をお願いします。また、高度化する技術社会において求められる共創についてもお話しいただきます。
| 講演者 | 河島 茂生 氏(青山学院大学総合文化政策学部准教授・革新技術と社会共創研究所所長) |
|---|
イベント
第5回「AIが描く音楽の未来図」
2024年2月13日(火)
絵・小説の分野では、ジェネレーティヴAIが出力する作品の完成度が高いことが問題視されていますが、ついに音楽生成AIにおいても、知識・技術がない者でも完成度の高い楽曲を生成できるAIが出現しました。絵や小説については各所でさまざまな議論がおこりましたが、音楽についてはまだ十分な議論がなされていない状態です。当イベントでは、「音楽は好きだけど楽曲制作を全く行わない」という方からプロのミュージシャンまで、さまざまな熟練度の人が集まり、実際に使ってみて、東京外国語大学で学んだ・学んでいることを活かし、「『創造性』はどのように変革するのか」を考えるワークショップです。ゲストスピーカーとして、プロギタリストの仲宗根 朝将 氏(東京メタルシティ)をお招きし、実際に音楽を生業としている方の目線で参加していただきます。
| ゲストスピーカー | 仲宗根 朝将氏(プロギタリスト) |
|---|
【当日の流れ】
1.趣旨説明、ゲストスピーカー紹介
2.ワークショップ・セッション
3.グループディスカッション
4.総括