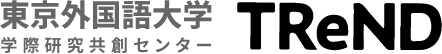取り組み
社会の中のAI:トピック別勉強会
関係機関
東京外国語⼤学 学際研究共創センター(TReNDセンター)
東京外国語⼤学 多⽂化共⽣イノベーション研究育成フェローシップ(MIRAI)
キーワード
ワークショップ
公開プログラム
異分野融合研究
研究教育機関との連携
講演会
最終更新 2024.07.22
開催終了
概要
ChatGPT、GPT-4などの⽣成系AI(Generative AI)は、全世界規模でインパクトを与え続けています。今後、教育‧研究現場の広い領域でも、⼈⼯知能が担う役割は増していくとみられます。私たちはいま、「学ぶべきことや学び方がどう変化するのか?」「⼈間的な知性を育むことの価値とは何か?」という根源的な問題に向き合わなくてはならない、歴史的なターニングポイントにいるのかもしれません。本企画では、人文学・社会科学の視点から、AI技術の社会的影響とより良い社会実装への道筋を、さまざまな研究分野との協力を通じて探求し、⼈⼯知能を活かしたさらなる創造性の発露に向けていま私たちにできることを考えていきます。

第1回「AIは翻訳の世界をどう変え得るのか?」
2022年7月15日(金)
シリーズ第1回講演会は、株式会社みらい翻訳の鳥居大祐氏と瀬川憲一氏を講師としてお招きします。「機械翻訳の社会実装 現在・過去・未来」と題して、AI自動翻訳の仕組みや強み・弱み、さらに活用事例や今後の可能性についてお話しいただきます。本学の学際研究共創センターが主催し、四大学連合(東京医科歯科大学、東京工業大学、一橋大学、本学)および西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究機構(電気通信大学、東京農工大学、本学)の教職員・学生を対象に実施します。
| 講演者 |
鳥居 大祐 氏(株式会社みらい翻訳 代表取締役社長 兼 CTO ) 瀬川 憲一 氏(CRO 兼 翻訳 DX チーフエバンジェリスト) |
|---|
【プログラム】
1. AI 自動翻訳の仕組みを概観(アルゴリズムの詳細説明は除いた形で)
2. AI 自動翻訳の強み・弱み
3. AI 自動翻訳の今後・可能性
4. 事業会社における活用事例
5. AI 自動翻訳がデフォルトになった社会で、<翻訳>はどのように変化するのか?
6. 質疑&議論
【イベントを終えて】
対面参加5名、オンライン聴講41名の計46名が参加しました。講演後の質疑応答では活発な議論が交わされ、参加者のAIへの関心の高さがうかがえました。
第2回「21世紀の情報学的転回」
2022年12月13日(火)
日本はデジタル後進国になったと言われますが、一体なぜでしょうか。潜在的技術力はあるのですから、文化的な要因が関係していると考えられます。「人間より賢いAI」という発想は西洋の伝統思考の産物とも言えますが、下手をすると、AIを操作できる一部のエリートによって一般の人々が支配されるという罠に陥る恐れもあります。この罠を回避するための「情報学的転回(informatic turn)」について、コンピューター研究者である東京大学の西垣名誉教授に講演していただきます。
| 講演者 | 西垣 通 名誉教授(東京大学) |
|---|
【イベントを終えて】
参加者からは「AIは過去のデータの蓄積から確率を求めるのに対して、ヒトは全く未知の事象について考える点が違うという話が興味深かった」「現在多くの論者が展開しているトランスヒューマニズムに対する危機感について共感した」など、さまざまな感想がありました。
四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアムとの関連
「リレートーク"生成AI"」
四大学連合(東京外国語大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、一橋大学)ポストコロナ社会コンソーシアムでは、2020-2022年にかけてさまざまな学際的な研究ワークショップや連携教育活動等を行ってきました。2023年度は、コロナ禍で加速した社会のデジタル化を受け急速に台頭しつつある生成AIについて考えるリレートークを実施します。 この企画では四大学の研究者と学生が、生成AIについて研究分野ごとの観点や今を生きる生活者の視点で自由に議論します。リレーは、研究者で繋ぐ流れと学生同士で繋ぐ流れの二本立てで進行。各回のトークにはテーマを設定し、それぞれの回の終わりに、次のゲストへの質問を考案し、バトンを繋いでいきます。議論の内容は以下のウェブサイトで公開しています。 一連の活動を通じて、異なる組織・異なる専門性の研究者が自由に議論できる土壌をはぐくみ、四大学ならではの自由で緩やかな連携の在り方を社会に発信していきます。
https://www.tokyo-4univ.jp/consortium-for-post-covid-19-society/consortium/