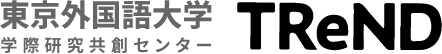取り組み
越境する知の共創:トピック別勉強会
関係機関
東京外国語⼤学 学際研究共創センター(TReNDセンター)
東京外国語⼤学 多⽂化共⽣イノベーション研究育成フェローシップ(MIRAI)
キーワード
公開プログラム
異分野融合研究
研究教育機関との連携
講演会
最終更新 2024.07.17
開催終了
概要
世界が直面する複雑な問題に対峙するためには、より俯瞰的で多様な視点を持つことが不可欠です。言語、文化、そして国際社会への深い洞察を提供する人文学や社会科学の研究は、未来への道を切り拓くための革新的なアイデアを生み出す豊かな土壌をつくります。
本プロジェクトは単なる技術・物質面の豊かさに留まらず、文化的相互理解と社会的調和が進んだより豊かで幸せな世界をめざして、教育研究機関・自治体などとの共創活動を展開しています。

「研究と社会との接合面について考えるワークショップ2022秋冬」
第1回「専門領域を超える問いの立て方を考える」
2022年9月28日(水)
今、大学や研究者は、専門分野間や学問と社会の間の境界を超えて研究の問題意識を広げ、世界の幅広い側面に研究の思考を広げることが必要とされてきています。本学では2022年4月に「学際研究共創センター(TReND)」を立ち上げました。「越境する知の共創」という研究会シリーズはこの活動の一環であり、今回はそのキックオフ企画です。
学際研究は難しいと感じている方は多いでしょう。それは構造的な問題が原因であり、それを解決するには、さまざまな社会的、政治的、文化的、感情的要因とそれらの絡み合いをまず理解し、今の状況を変えていく必要があります。この講演会・討論会・勉強会シリーズは、まさにそれを考え、アイデアを交換し、学び合い、行動につなげていく場として企画されました。
専門境界を超える研究協働を難しくしている大きな原因の一つは「問いの立て方」にあります。つまり、今の研究では、多くの問いが専門分野の枠の中に分断されているのです。今回は、『京大100人論文』や『対話型学術誌 といとうとい』を通じて、専門分野の境界を超えて学問の魅力を発信し続ける『問い作りのスペシャリスト』である宮野先生をお迎えして、専門分野の境界を越えるとはどういうことか、どのように越えるのかを考えます。
| 講演者 |
宮野 公樹 氏 |
|---|
【イベントを終えて】
講演後、参加登録者から事前にいただいていた質問事項や当日参加者からの意見などをもとにディスカッションを行いました。講演会には、15組織から63名の参加があり、「学問の本質に切り込んだ点がよかった」「自分の問いに誠実になることの重要性に共感した」など、さまざまな感想がありました。
当イベントの内容は、本学YouTube: TUFS Channelにて一般公開をしています。
講演ダイジェスト版:https://youtu.be/KKSedZtw37M
講演のみ:https://youtu.be/x2T39mbRVm8
ディスカッションのみ:https://youtu.be/R_37sNF2q5
第2回「サイエンスコミュニケーションの意味・価値を考える」
2022年11月2日(水)
大学が社会との共創を求められる中で、従来の研究活動や成果の枠組みを超えた新たなアプローチが研究者の手により生み出され始めています。講演者の松山氏は、東京大学生産技術研究所で研究・開発中の最新技術をカードにした「ひみつの研究道具箱」というゲームを開発し、普段は研究や開発の現場と接する機会がない人や子供を対象に、ゲームを通じて楽しく研究的思考を体験する場を提供しています。さらに、ゲームで生まれたアイデアを研究現場に届け、共創への一歩となるよう試行錯誤を重ねています。
本講演会では、松山氏の生み出した手法や成果・考察についてご紹介いただき、「研究と社会との共創」のあり方について考察します。
| 講演者 |
松山 桃世 准教授(東京大学生産技術研究所) |
|---|
第3回 ワークショップ「思考をなぞることを通した科学コミュニケーションの試み ~カードゲーム「ひみつの研究道具箱」を体験してみよう~」
2023年2月8日(水)
| ファシリテーター |
松山 桃世 准教授(東京大学生産技術研究所:「ひみつの道具箱」カード開発者) |
|---|
【イベントを終えて】
講師が開発した科学コミュニケーションツールの「ひみつの研究道具箱」を体験した後、このカードゲームの活かし方・進化のさせ方について意見を出し合いました。本学教員・学生のほか、他大学の学生やリサーチ・アドミニストレーター(URA)、中学・高等学校の教諭がワークショップに参加しました。
第4回「『伝える』を超えた知の共創を目指して」
2023年3月31日(金)
大学での研究の知見や面白さを、社会の中でよりよく活かすために、研究者から専門外の人へ「伝える」「説明する」という一方向からではなく、「ともに考える」「ともに作る」関係性の中で研究を見直し、共有する方法を考えるワークショップです。参加者の研究分野は問いません。
市民と知を共創する活動を実践する研究者をパネリストにお招きして、実践のお話を伺いつつ、グループワークを通して参加者自身の研究の広げ方を深掘りします。
| パネリスト |
松山 桃世 准教授(東京大学生産技術研究所:「ひみつの道具箱」カード開発者) 太田 絵里奈 特任助教(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所) |
|---|