闇と声
ピエリア・エッセイ
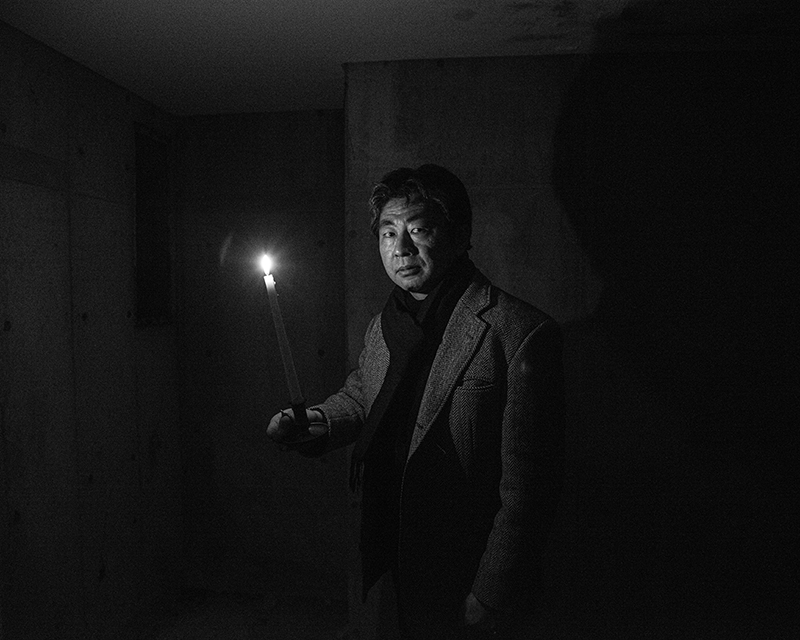
真島 一郎
爺さんが慾にかられて猫の鳴きまねをしたとたん、鼠の里が「辺り一面まっ暗闇となる」結末に、幼いころどれほど慄然としたか、その感覚をまだすこし憶えている。引き返せない終わりをつげる何かが、一瞬きーんと響いて鼠浄土の奈落に吸いこまれていった、あれは幻聴だったのか。
耳をすませる、傾ける。耳はすぐれて受動的な器官である。まったき闇の中ではすくみあがる現し身の不甲斐なさを、耳の受動性はどこかで連想させる。いやむしろ、耳こそ闇にふさわしい器官とはいえないか。白昼でも、瞳を閉じれば宇宙はただちに暗転する。耳殻の先をたどれば闇そのものにさえ触れられるかもしれない。闇の圧力に耳が耐え、慣れはじめるとき、ならばひとはそこに何を聴くのか。
*
何かの音にまぎれこみ、空耳のようにあるいは倍音のこだまとなって渡り来るだれかの声。明治三二年、闇をぬけ遠く低く寄せる焼津の磯の海鳴りに、ラフカディオ・ハーンは夥しい死者の呻き声を聴き分ける。熊本滞在期に城下の寺を訪れたさい、参道の両側に蝟集するハンセン病者のざわめきに、なぜかれは「潮騒のような音」という奇異な形容を添えたのか、その形而上学的不安の淵源は海にあった。通算一四年におよぶ日本滞在中、ハーンの耳が「音響的な日本」にどう反応し、「聴覚に始まり聴覚に終わる」テクストをどう準備したのか。西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳』は、その名の通り、ひとりの耳の働きをひたすらに追った名作だ。「「耳なし芳一」の真髄は、聴覚に全身全霊を集中させた芳一が、耳そのものをひきちぎられる音を聴きとってしまうあのおそろしい場面にこそある[…]われわれはこの物語を読み(聴き)ながら、知らない間に、芳一の耳を通して世界を聴くようになっている」。
*
声なき存在の声をよすがに闇路をたどれば、いつしか隠国(こもりく)のとば口に立っている。芥川賞受賞の翌年、中上健次は故郷の紀伊半島全域を半年以上かけて経めぐり、特異なルポルタージュ『紀州 木の国・根の国物語』を発表した。紀州とは、かつて大和に平定された隠国である。土地の霊をそのつど「呼びだす」ような記紀の方法論にしたがって、旅先の地名から漢字を取り去り「音だけにする」と、敗れて闇に沈んだ国の異貌が現れる─「地名がむき出しに自然や自然に生きる人の生活をあらわしている」。路地の作家・中上にとり、それは被差別部落をたどる遊行の業でもあった。部落の老女たちにむきあうと、かれの筆触はふしぎと相聞歌にちかい密度を帯びていく。「地霊がふるえている[…]ゆきえさんの抑揚のない低く唱吟するような声をきいていると、なにやらこの土地の霊をゆきえさんが招いている気になる。ゆきえさんは被差別者だった」。敗れた者は、この隠国に不死の人としてある。
*
拒絶や禁止の闇をこえ、幻であれ呼びもどされ生きなおされる声。アラブ革命といわれたあの「春」から、もう六年が経った。春の息吹は、遺書なき遺書の沈黙に声を聴きとった者たちの応答だった。広域におよぶ政治変動の発端は、チュニジアの地方都市にくらす貧しい青年の焼身自殺にあったからだ。現代マグレブ文学を代表する作家ベン=ジェッルーンが、この事件に想を得た小品『火によって』を発表したのは、事件後半年のことである。失業状態に絶望し、大学の卒業証書を流し台で燃やす主人公の青年。忌まわしい炎は物語の幕開けから登場する。そして破局の火柱が燃え尽きたあと、遺されざる遺書は物語の末尾にいたり闇をぬけ、妹の声へと、傷ましくも力強い変成をとげるだろう。「生きるなかで打ちのめされ、辱められ、否定され、ついに火花となって世界を燃え上がらせた人間の物語。誰も兄さんの物語を盗んだりはできない」。
闇の裂け目から、いつもと違う声を、いつも聴き分けること。夜はまだ、まともに夜であったためしがない。
まじま・いちろう 総合国際学研究院教授 社会人類学
文献案内
西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳』岩波同時代ライブラリー、1998年
中上健次『紀州 木の国・根の国物語』角川文庫、2009年
ターハル・ベン=ジェッルーン『火によって』岡真理訳、以文社、2012年
2017年春号掲載

