2011年5-6月 月次レポート(太田悠介 フランス)
ITP-EUROPA月次報告書(5-6月)
太田 悠介
ITP-EUROPAプログラムの海外派遣報告会への出席、さらに書類および投稿論文の提出のために予定されていた6月中旬の一時帰国を控え、日々は足早に過ぎてゆきました。最終的には何とか無事にすべての課題を終えることができました。それ以外にも短い日本滞在中には合間をぬって、指導教員である西谷修教授のゼミや日仏会館で開催されたジャン・ピエール・デュピュイ氏講演会への参加、修士課程以来お世話になっている中山智香子教授の指導のもと沖縄国際大学を中心として行われたゼミ合宿に同行するなど、この機会を有意義に活用するように努めました。
今期のフランス滞在最後の時期となった5月末から6月初旬にかけては、大半の時間を一時帰国を念頭に置いた作業に費やしました。そのための多忙な日々を過ごすなかで、西谷教授が国立行政学院(ENA)で行った「核」の問題をめぐる発表に友人たちと参加できたのは、ひとつの大きな収穫でした。法制史や宗教史を横断しながら狭義の法学にとどまらない「西洋」の制度性の解明を目指し、その独自の思想を「ドグマ人類学」という名のもとで展開しているピエール・ルジャンドル氏、労働法を専門としながらナント先端研究所(Institut d'Études Avancées de Nantes)の創設を主導して現在同研究所の所長を務めるなど実務面でも能力を発揮しているアラン・シュピオ氏をはじめとして、科学哲学、生物学、東洋史などを専門とする研究者、さらには弁護士やジャーナリストなど、ナント先端研究所の研究員を中心に多岐にわたる顔触れが揃いました。
質疑応答のなかで、とりわけ原子力発電と自動車との間には一種のアナロジーが存在するのではないかという指摘は、個人的にはきわめて示唆に富むように思われました。というのも、自動車と自動車に依存した社会との批判はフランスではアンドレ・ゴルツ(1923-2007)、イヴァン・イリイチ(1926-2002)などによってかつて盛んに論じられたテーマであり、エコロジーと概括される領域の思想家たちが有していた近代社会批判の射程を現時点であらためて見直す必要に気づかせてくれるからです。
原子力発電と自動車の共通点のひとつは、両技術がその維持のために必要な「社会的費用」を「外部化」することによって初めて成立可能であるという点です。原子力エネルギーの利用は、もし事故のリスクとそれに伴う社会的なコストを計算するならばその実現はきわめて難しく、したがって事故を「想定外」と仮定することによってしか原子力発電所は論理的には稼働不可能であることになります。自動車もある意味ではこれと同様の問題を抱えています。自動車が市場で売買される際の価格には、歩行者ではなく自動車を中心とした社会が必要とするコスト(道路の整備、完全に商品化した石油への依存、事故の補償、渋滞による都市機能の麻痺、排気ガスによる大気汚染等)が含まれておらず、このコストを考慮した議論が自動車を所有しない非受益者も含めてなされることなしには、自動車は原理的には走行してはならないはずです。このように、技術のもたらす全体的な「社会的費用」の検討を経ずに、その技術がもたらす効用という限定的な側面だけに光を当てて経済的な収益性がはじき出されるという点は、核エネルギーの「平和利用」と自動車との間に共通する問題として指摘できます。イリイチやゴルツはかつて「コンヴィヴィアルな道具」や「開かれたテクノロジー」という概念を用いて、技術を使用する者の技術への依存を生む「他律的」技術ではなく使う者の「自律性」を増す技術について語っていましたが、これらの概念の含意が今あらためて問われているように思われます。
私自身の研究テーマに引きつけるならば、フランスではエコロジーの流れは、マルクス主義の「生産至上主義」、「労働者中心主義」に対する懐疑の高まりを背景として登場します。またほぼ同時期に『消費社会の神話と構造』(La Société de consommation, 1970)に代表されるジャン・ボードリヤール(1929-2007)の仕事などによって、社会の機軸が「生産」から「消費」へとシフトしたという認識が広まり、マルクス主義の文脈において相対的に軽視されてきた「消費」に光が当たるようになります。こうした同時代の潮流の変化も踏まえながら、アルチュセール、バリバールらが行っていたマルクス主義の理論的な改鋳を検討したいと考えています。
5月の中旬には、以前本学の中山教授監訳のもと1章分の翻訳を担当したジョバンニ・アリギ『北京のアダム・スミス』が出版されました。初めて本格的に取り組んだ訳稿であったため、監訳者の中山教授の丁寧な指導なくしては完成しなかったと思います。それでも、今回あらためて自分の訳文を見直してみると、やはり依然として拙い箇所が散見されます。原文に忠実な正確な訳を心がけると同時に、それをより洗練された日本語表現に仕上げることになお一層留意することを、今後翻訳を手掛けるにあたってのさらなる課題としたいと思います。
2001年から始まったアフガニスタンおよびイラクへのアメリカを中心とした多国籍軍の介入のベトナム戦争を思わせる泥沼化、さらに2007年のサブプライム・ローンの破綻に端を発するアメリカ発の金融危機の世界的な波及を直接のきっかけとして、「アメリカの没落」と「中国の台頭」が盛んに語られるようになりました。『北京のアダム・スミス』はこの東アジアの隆盛を、ジェノバ-イベリア(15世紀~17世紀前半)、オランダ(16世紀後半~18世紀後半)、イギリス(18世紀中盤~20世紀前半)、アメリカ(19世紀後半~最近の金融危機)のヘゲモニーの成立と移転の過程をたどり直すという長期的な世界史的パースペクティブに基づいて、説明を試みる著作です。
本書のもっとも基本的なアイデアはアダム・スミスに由来するもので、アリギはスミスに依拠しつつ、現在の中国に代表されるアジアの勃興とかつての西洋の勃興との間に質的な差異が存在することを指摘します。それによれば、中国が農業から工業へ、さらに工業から対外貿易へと順次移行するというスミスが理論化した市場経済の発展の「自然的」経路を進むのに対し、西洋の発展経路はむしろこれと「逆向き」の「非自然的」経路であって、軍事力の優位に基づく非ヨーロッパ地域への進出によって蓄積された対外貿易の富が国内の工業、農業の発展のために用いられるというマルクスが問題化したような資本主義的な経路であったとされます。アリギは現代の「中国の台頭」をこの「自然的」経路の延長線上に見出し、スミスこそがアジアの興隆を理解するための鍵を与えてくれるとして、『北京のアダム・スミス』を表題に選んでいます。
『北京のアダム・スミス』は2009年に他界したアリギの遺著であり、その思想の集大成とも言うべき質と量を備えた大著です。訳書にはさらにアリギの生涯を振り返る盟友デビッド・ハーヴェイによる生前最後のインタビュー、さらに他の思想家たちとの対照を通じてアリギの思想的位置づけを明示した山下範久氏の解説が収録されています。書店等で見かけた折に手に取っていただければ幸いです。
6月で本年度のITP-EUROPAプログラムのもとでの留学を終えました。昨年の7月から一年間の留学をご支援いいただいたほか、ボローニャでの口頭発表という貴重な機会も与えていただきました。最後になりましたが、プログラムに関連する諸先生方、事務局の皆さまに、この場をお借りしてあらためてお礼申し上げます。
追記:今回のレポートで紹介したジョバンニ・アリギ『北京のアダム・スミス』については、6月26日付の日本経済新聞と7月3日付の朝日新聞にそれぞれ川北稔氏(http://www.nikkei.com/life/culture/article/g=
96958A96889DE1E3E2E5E3E4EAE2E0E7E2E4E0E2E3E39F8893E2E2E3;p=9694E3E4E2E4E0E
2E3E2E5E3E2E4)による書評と姜尚中氏(http://book.asahi.com/review/TKY201107050197.html)による書評が掲載されており、いずれもインターネット上で無料で閲覧可能です。また『北京のアダム・スミス』のいわば前篇にあたるアリギの前著『長い20世紀』についても、この著作の監訳者土佐弘之氏による紹介(http:
//www.kobe-u.ac.jp/info/book/0901_01.htm)と柄谷行人氏による書評(http://book.asahi.com/
review/TKY200903310111.html)を読むことができます。
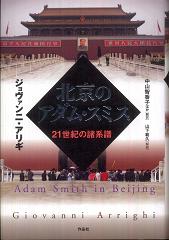 (『北京のアダム・スミス』書影)
(『北京のアダム・スミス』書影)


