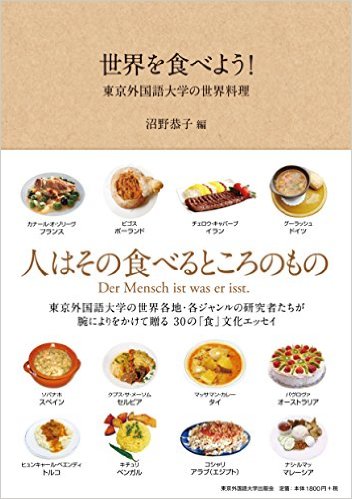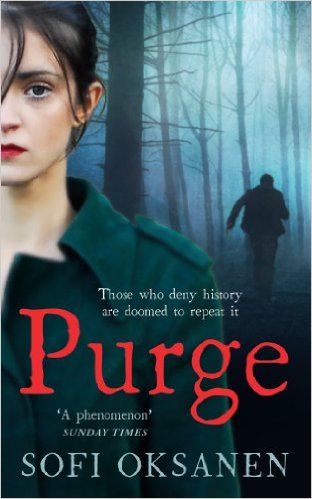ロシア語学がご専門の小林潔さんより興味深いエッセイの翻訳をご提供いただきましたので全文をここに掲載します。最初に小林さんの解説、その後にイリーナ・カペリアンさん(Irina Kapelian)のエッセイが続きます。
【解説】小林潔
2015年10月22~25日、フィンランドでロシアをテーマ国とした第15回ヘルシンキ国際ブックフェアが開催された。フェアのスローガンは 「ロシアを読もう! Читай Россию!」。ロシアから30人以上の作家が参加し、来訪者も4日間で8万人に達した大イベントであった。
↓
http://www.messukeskus.com/Sites3/Kirjamessut/en/Pages/News.aspx?url=/UutisetTiedotteet/HelsinginKirjamessutavautuu15ttakertaa.en-us.aspx
本ブックフェアについては、既にカペリアン氏の報告が 『ロシア文化通信 群』 に拙訳で掲載されている(イリーナ・カペリアン、小林潔訳「ロシアを読もう! ヘルシンキ・ブックフェア2015」 『ロシア文化通信 群』群像社、第47号、2015〔平成27〕年12月、4面)。
本エッセイは、フェアの熱狂からしばらく経って、あらためてフェアの意義を考察したものである。フィンランドという、ロシアと国境を接し、歴史的にも複雑な関わりがあり、現に人口の1%にあたる5万人がロシア語話者という国において、どのようにロシアが捉えられているか、どのような態度でロシア(語)文学に接しているかは、日本のロシア関係者にとっても興味深いと思われる。
原文はロシア語。著者のカペリアン氏はペトロザボツク出身、父はロシア人、母はフィンランド人で、ペテルブルク大学心理学部とヘルシンキ大学教育学部の両国高等教育機関を卒業したバイリンガルである。現在はヘルシンキの社会人学校Eiran aikuislukioで教員をつとめており、訳者も彼女の授業参観に出向いたことがある。
↓
http://www.sukuni.fi/irina/
なお、フィンランドのロシア語教育については、例えば以下を参照。
須佐多恵「フィンランドにおけるロシア語教育――異言語、そして母語として――」 『ロシア語教育研究』(日本ロシア語教育研究会)第3号(2012〔平成24〕年11月):59-69頁。

【エッセイ】イリーナ・カペリアン、小林潔 訳
「ブックフェアのページに真実を探求して」
ヘルシンキ・ブックフェアの出来事や事実はだんだん記憶から薄れていくが、何かとても意義深いものだったという感覚は多くの人に残っている。
あまりに選択肢が豊富で、選ぶのが難しいほどだった。というのも、14ものステージと800ものプログラムがあったからだ。ロシア文学・文化はその輝きをもって我々の目を眩ませる。いや、その塵埃によって、だろうか。「ロシアを読もう!」なるブースもあった。この名称を滑稽に感じる人もいるだろう。ロシアを書籍のように通読できるのかと。おそらく、最初から最後まで読みさえすれば、という話で、誰かが開けてくれたページからということではないだろうが。

ロシアでは不条理に満ちたカフカ的な状況が続いている。それを陰鬱で抑圧的な状況だと見る人もいる。出来事を頭や心で受け入れるロシア人の感覚は鈍くなっており、何かを疑ってかかろうとか、本質にまで達したいという気持ちはほとんど見受けられない。自分が真実だと思うことをずけずけ言ってのけ、言い方を気にすることもなければ、相手がどう感じるか気にかけることもない。そんなのは何ということもない、「真実」とは無縁の単なるニュアンスに過ぎない、ずけずけ言って何が悪い、というわけだ。まさに、自分の真実のほうが他の誰の真実よりも正しいことがわかっていて、それらを一つに纏める可能性も認めないというわけである。作家たちにさえこの可能性を認めず、彼らにレッテルを貼ってしまう。とはいえ、ロシアではこれまでずっと作家に特別なステータスがあった。
それは西側で今でも保たれている。作家にステータスがあるなど信じられないという人がいたとしても、ブックフェアのロビーに足を踏み入れ、長蛇の列の最後尾に並べば、疑いはことごとく消え去ったはずだ。ロシアの作家が登壇することになっているホールに入るための大行列が出来ていたのである。これほど多くの人々を行列に並ばせたものは何だったのだろうか。単なる好奇心、作家を直に見たいという望みだったのか。ある女性は、「ロシアで何が起きているか知りたいんです。できれば作家の口から直接聞きたい。作家なら信用できて真実が聞けるかもしれないじゃありませんか」と私に語った。世の個々の出来事からせめて部分的にも真実を引き出そうとする人がまだ残っているのだ...。
信じられないことに、ロシア人作家の話を聞きたいという人の多くが会場に入れなかった。私も中に入れてもらえなかったので、立ったまま、このフェアで捨て値で買ったフィンランドのリッカ・ペロ (Riikka Pelo 1972 - ) の小説 『日々の暮らし』 をぎゅっと抱きしめた。見事な叙述、素晴らしい言語、マリーナ・ツヴェターエワと娘アリアドナ・エフロンとの重苦しい――フィンランドの女流作家が深く感じ取った――物語だった。この小説はフィンランドの国家賞をとったのに、程なくセールにまわされてしまった。これはどんな文学がフィンランドで読まれているかという問題の一つである。なんといっても、この小説は、フィンランドの読者に、ロシアについての真実を垣間見させる可能性大なのに。ロシア性、真実の探求、ロシアのメンタリティ、心乱れるロシアの魂についての真実である。そう、心乱れる魂も今は流行ではないのである。
相反する感情に捉えられたまま、私はのろのろとソフィ・オクサネン (Sofi Oksanen 1977-) の話を聞きに出向いた。が、自分でも驚いたことに、全てかつて耳にしたことがあるものばかりのように思えた。彼女の小説 『ノルマ』 の髪のテーマは、ゴシック・ファッションで世界一の美女とされる作家の口から発せられたものであっても、心を動かされない。少なくとも今は。本屋で特売になったら、もちろん 『ノルマ』 を読むつもりだ。ただし、これまで一度もオクサネンの作品がセールになったのを見たことはない。この才能ある女流作家の長編 『粛清』 はフィンランドの大きな文学賞を受賞し、反ロシアの翼を広げて世界中に飛び立っていった。でも、こんな皮肉を言っては半ば不当かもしれない。オクサネンが提唱してフィンランドでようやくソルジェニーツィンの 『収容所群島』 が翻訳出版されたことを強調しておこう。彼女のこうした業績もやはり真実探求の一環である。しかし同時に、ブックフェアのテーマがロシアであることに多くの人が警戒感を抱いたのも、まさに恐怖心を煽るようなオクサネンの感情的な文体ゆえであった。例えば、「モスクワとクレムリンはフィンランドに隊列を送り出す。純粋で申し分なき知性を持ったフィンランドの読者をプロパガンダで押しつぶすために」といったような文体だ。
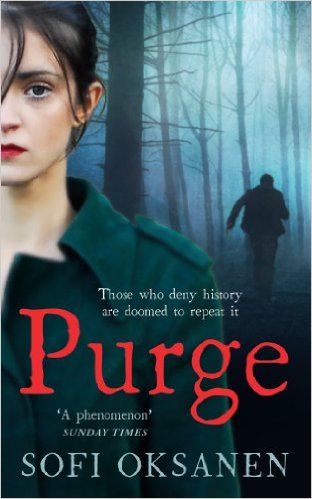
「モスクワ」という言葉は、フィンランド人の耳にはしかと厳しく響く。モスクワは権力の権化であり、西側には馴染みのない政策の源である。そうした政治のこだまである。だからモスクワの作家達も警戒されたのだろう。きっとそれゆえに、ブックフェアでは、ロシアを捨てたモスクワ出身者への関心が高まり、彼らの言葉はより信頼されたのだろう。彼らがもたらす情報はより明確で、西側の既存のステレオタイプにより適っていたのである。
モスクワの生まれでロシアの反体制派であるアルテーミー・トロイツキーは、現在タリン在住だが、私にとって彼はなにより、ロシアン・ロック音楽史の大御所である。西側にとっては、彼は評論家で、プーチン主義にあからさまに対立し、反ロシア的な風潮を作っている。相変わらず押し出しが良く、遙か昔にテレビのお茶の間ロックショーで見た通りのままの、堂々たる反対派の大人物だ。彼はコラムを書き、ラジオ番組を持ち、ロシア社会について講演をしている。ロシアをどうしたらいい? ワルラム・シャラーモフとアレクサンドル・ソルジェニーツィンのおかげで知られるようになった囚人風の言い回しでトロイツキーは応える。「信じるな! 恐れるな! 求めるな!」と。そして曰く「自分の国が好きだ。とても好きだが、その未来を俺たちは失ってしまった――それは確信している」。これにトロイツキーは疑いの余地を残していない。だが、作家に宿命づけられていたのは常に疑いと狂奔だったではないか。
さて、ボリス・アクーニン(グリゴーリー・チハルチシヴィリ)は相変わらず「自身の国を理解」しようとしている。アクーニンはもはやモスクワ文学界と縁を絶っており、フランスで暮らしたりイギリスやスペインで生活したりしている。ブックフェアで行われた「読者との集い」では、それぞれの国の気候が特定のジャンルの作品を生み出すようだと語っていた。そう言えばアクーニンは、学術的な本をロンドンで、探偵小説をスペインで、所謂シリアスな現代小説をフランスで書いている。北イタリアにも行ってみたそうだが、執筆にはあまりに穏やかすぎる場だったという。ひょっとすると、単に特定の国と心を結びつけたくないだけなのかもしれないが。
ブックフェアにはこんなシーンもあった。ミハイル・シーシキンとボリス・アクーニンにインタビューしたのだが(ふたりともロシアから出て、口をそろえてロシアの現状を批判し、プーチン政権を攻撃していた)、とても興味深かったのは、政治状況を語りたいか語りたくないかという点でふたりの気持ちが正反対だったことである。シーシキンは全ての質問を文字通り無理矢理に政治に向け、文学の話題について半句でも彼からコメントを引き出すことは難しかった。一方、溌剌としたアクーニンからロシアの現状についてコメントを得ることは半句でも難しかった。答を用意していなかったのだろうか。もっとも、創作にとって周囲と魂との不和は有益である。
シーシキンは「人生という書物のページを繰って、幸福がこみ上げるのを探している」。フィンランドのマスコミでの多くのインタビューから判断する限り、彼の真実は酷で直線的だ。そもそも真実かどうかも、彼の長編 『ヴィーナスの毛(ホウライシダ)』 では疑われている。小説の主人公である通訳は皆の陰にいて人生の出来事を聞き、書き留める。そしてこれらの出来事を我々は彼が書き記したままに読む。正しいか正しくないかは大事ではない。話の半分は作り事か、自分のだと偽ったものだ。尋問で語られたある出来事、焼失した家や銃殺された身内の話は実際にあったのかもしれないが、話した者に起きたことではない。彼は単に、他人の不幸が自分を西の楽園に連れて行ってくれると考えているだけだ。その経歴は「真実」とは隔たっている。我々読者にとって何が大事なのか。真実か、それとも、我々が聞くつもりのことを再確認させる嘘なのか。
優しい「真実」がきれいな服で歩いていた。
寄る辺なき至福の障がい者たちの為に着飾って。
粗野な「嘘」がこの「真実」をおびき寄せた。
うちに泊まっていけと。
何千ものフィンランド人に親しまれ愛されているウラジーミル・ヴィソツキーのしわがれ声が私の思いに合わせてホールに響いた。
客観性を保つべく、ザハール(エヴゲーニー)・プリレーピンの 『修道院』 から引用する。「人生を描くには真実だけでは足りない。事実、それらの列挙、意味づけさえも、人生の滑稽なごくわずかな外面を覆うにすぎない。真実を描くとは虚偽を手にするということだ」それで、調書に記されるように無味乾燥な真実は退屈で陰鬱なのではないか。プリレーピンはブックフェアには来ていなかったし、『修道院』もいまだフィンランド語に訳されていない。翻訳が待たれる。
ペテルブルクはフィンランドにより近い。政治色を抜きにした文学の枠組みの中の町としてより容易く思い浮かべられるだろう。その美しさを引き立てるのはドストエフスキーとプーシキンとの神秘的な邂逅だ。ロシア文芸のディノザウルスたるアンドレイ・ビートフのプログラムは盛りだくさんであった。彼は暗黒の1937年レニングラート生まれである。彼の考察は読者側の不理解にもふれた。作家の思いを読者は時に理解しないと。実際、両者はそんなに離れているのだろうか。作家と、何らかの自分の真実を求める読者とは乖離があるのか。
彼は疲れ、出来事から若干距離を置いていて、文学と、そこでの作家の位置について語る。「作家も孤独であるし、読者も孤独である。しかし、本を読むことで孤独でなくなる者もいる。実際、文学の課題とは二つの孤独を一つにすることなのではないか」――これがビートフの問いである。この言葉は、作家がブックフェアの長い一日の終わりに疲れ切って自分の本を布鞄にしまうのを見ていた時だけに、ひときわ鋭く沁みるものであった。彼は一人だった。だが、ここにいるのは、読者が取り囲んでいるべきクラスの作家である。息を殺して待つ。『プーシキンの家』 の著者であり、無検閲文集 『メトロポール』 の創刊者の一人たる彼が更に何か言わないだろうか、と。
ブックフェアで私が注目したのは、ペテルブルクの作家であり、中世ロシア文学の研究者でもあるエヴゲーニー・ヴォドラスキンであった。彼は、全ての時代が文学にとって適しているわけではない、戦争や革命の時代というのは素材としては良いかもしれないが、環境としては文学に向いていない、そういうのは社会評論の時代だという考えを披露し、自分自身で反駁してみせた。彼の長編『ラヴル』のフィンランド語訳が特にフェアの開幕に合わせて刊行された。本書は偉大な文学の一つである。「驚きなのは、肯定的な主人公の出てくる本が無条件に受け入れられているという事実である。つまり、まだ全てが失われたわけではないということだ」とヴォドラスキンは語っている。このような聖なる主人公が現代に暮らす小説を書くつもりはあるか、という質問に対しては、こう答えている。「文学では義人よりも人でなしを書く方が遙かに簡単だ。現代の聖人に巡り合えたらすぐに書くことにしよう」。
作家は我々を魅了し、美を作りだすものだし、自由の感覚を広めることができる。詩の一行が持つ力だけで平和を打ち立て、また打ち壊すことができる。作家というのは、自著のページから生も死も愛も約束することのできる者である。我々皆が求める真実を約する者である。
ブックフェアに参加したひとりひとりがその出来事から真実の一粒なりとも引き出そうとした。それができた人にとってヘルシンキ・ブックフェア2015は今後もずっと記憶に残ることだろう。
(2015年12月30日)