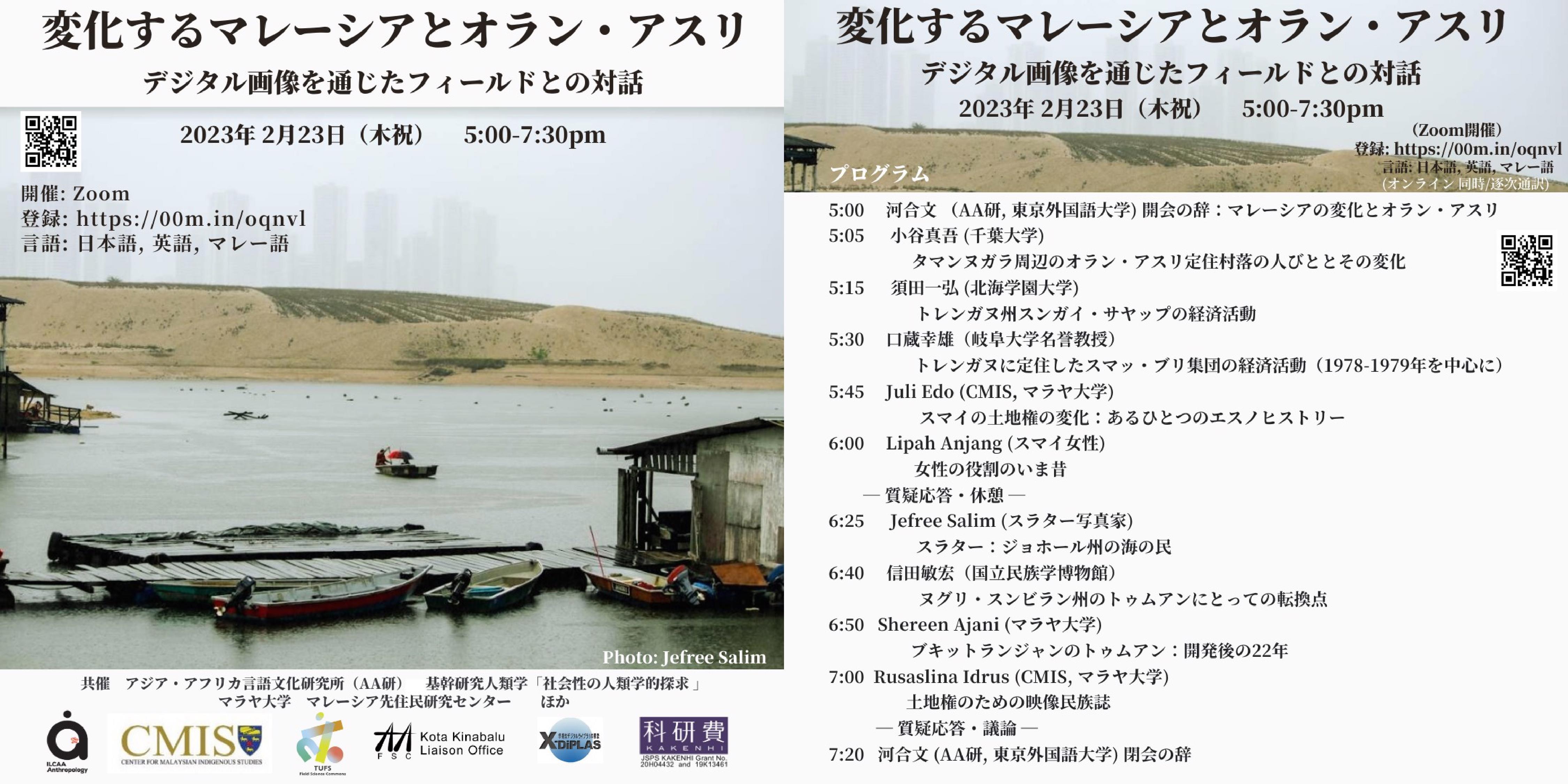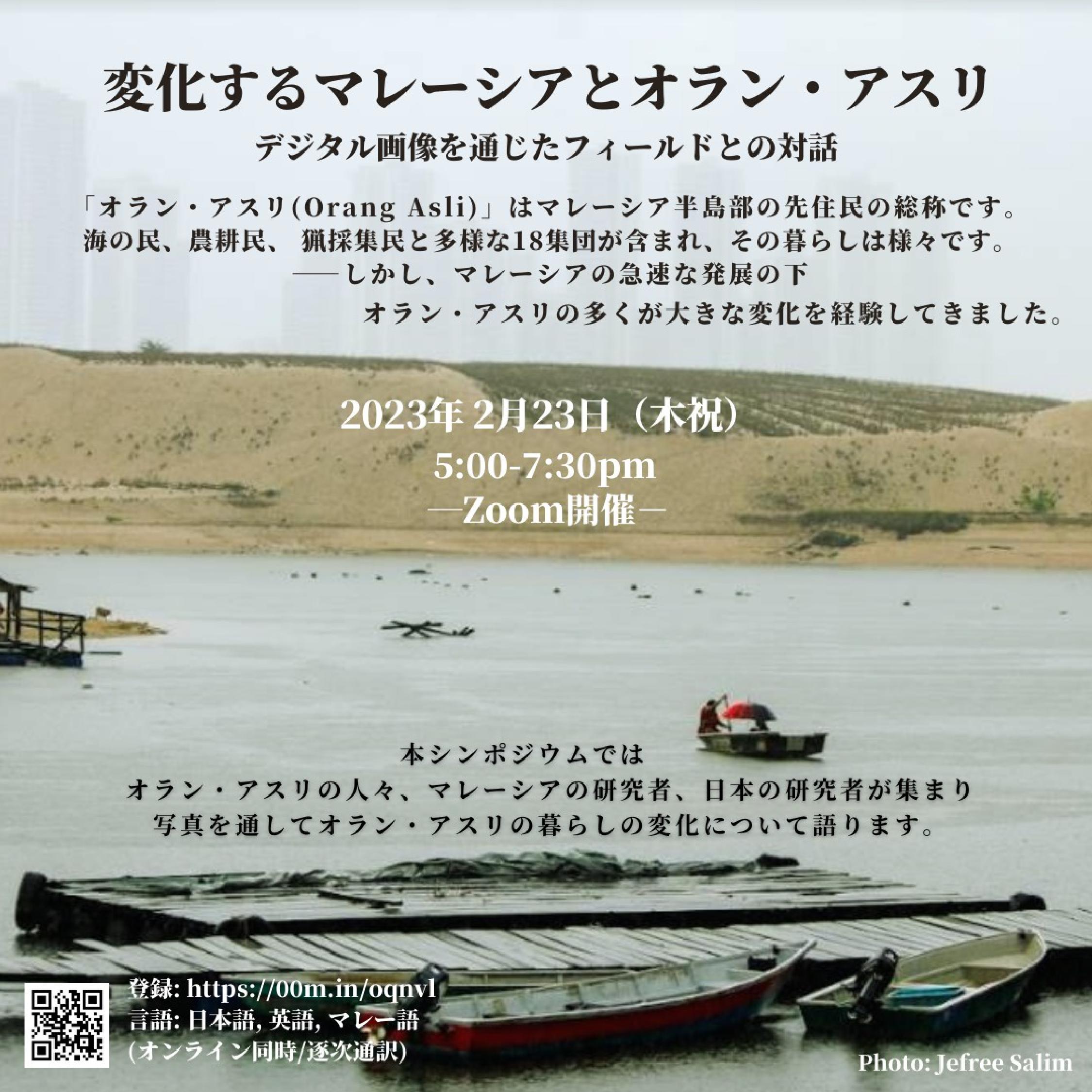変化するマレーシアとオラン・アスリ:デジタル画像を通じたフィールドとの対話
【概要】
「オラン・アスリ(Orang Asli)」はマレーシア半島部の先住民の総称です。海の民、農耕民、狩猟採集民と多様な18集団が含まれ、その暮らしは様々です。しかしマレーシアの急速な発展の下、オラン・アスリの多くが大きな変化を経験してきました。本シンポジウムでは、オラン・アスリの人々、マレーシアの研究者、日本の研究者が集まり、写真を通してオラン・アスリの暮らしの変化について語ります。
【プログラム】
17:00. 河合文(AA研) 「開会の辞:マレーシアの変化とオラン・アスリ」
17:05. 小谷真吾(千葉大学) 「タマンヌガラ周辺のオラン・アスリ定住村落の人びととその変化」
17:15. 須田一弘(北海学園大学) 「トレンガヌ州スンガイ・サヤップの経済活動」
17:30. 口蔵幸雄(岐阜大学名誉教授) 「トレンガヌに定住したスマッ・ブリ集団の経済活動(1978-1979年を中心に)」
17:45. Juli Edo(マラヤ大学名誉教授) 「スマイの土地権の変化:あるひとつのエスノヒストリー」
18:00. Lipah Anjang(スマイ女性) 「女性の役割のいま昔」
18:15. 質疑応答・休憩
18:25. Jefree Salim(スラター写真家) 「スラター:ジョホール州の海の民」
18:40. 信田敏宏(国立民族学博物館) 「ヌグリ・スンビラン州のトゥムアンにとっての転換点」
18:50. Shereen Ajani(マラヤ大学) 「ブキットランジャンのトゥムアン:開発後の22年」
19:00. Rusaslina Idrus(マラヤ大学) 「土地権のための映像民族誌」
19:10. 質疑応答・議論
19:20. 河合文(AA研) 「閉会の辞」
参加費:無料
場所:オンライン会議室
使用言語:日本語,英語,マレー語(オンライン同時/逐次通訳)
共催:AA研基幹研究「社会性の人類学的探究:トランスカルチャー状況と寛容/不寛容の機序」,マラヤ大学Center for Malaysian Indigenous Studies(CMIS),TUFS フィールドサイエンスコモンズ(TUFiSCo),AA研コタキナバル・リエゾンオフィス(KKLO),人間文化研究機構 共創先導プロジェクト(共創促進研究)「学術知デジタルライブラリの構築」(X-DiPLAS),科研費基盤研究 (B)「ボルネオ島カヤン諸族の言語活動にみるインドシナ諸言語・文化の影響」 (研究代表者:奥島美夏(天理大学)課題番号:20H04432),若手研究「半島マレーシアの狩猟採集民における移動と社会」(代表者:河合文(AA研)課題番号:19K13461)