本構想が生まれた経緯
本案は、学部・大学院改革推進委員会での議論、また地域・国際講座でのアンケートと議論を通じて生まれた。 改革推進委員会発足当初、提案者は制度改革にはきわめて消極的であった。「教育は制度ではなく人である」と信じていたからである。現在も基本的にこの考えは変わっていない。しかし、半年以上にわたる改革推進委員会での議論、あるいは地域・国際講座でのアンケート・議論を通じ、大学をめぐる社会環境、本学が直面している諸問題、解決すべき課題についての認識が深まるにつれ、本学のあるべき将来像がしだいに明確な形をとって浮かび上がってきた。言い換えれば、本構想は、先験的に立てられた主義・原理(複数学部論など)に基づいたものではまったくなく、この間の議論をくぐり抜ける中からいわば自ずと立ち現れてきたものである。
なぜ学部再編か
高垣案を除き、野間、亀山、高橋案はこの点について基本的に認識を共有している。一言で言えば、現在の外国語学部が実際にはきわめて豊かな知的資源を持ちながらも、その性格が不鮮明であることによりその資源を十分に生かし切れておらず、逆にさまざまな弊害を生み出すに至っている、との認識である。大学をめぐる社会状況が今後いっそう厳しさを増していくなかで 、外大像のこの不鮮明さは致命的なものとなりかねないとの認識をわれわれは共にしている。
外大像が不鮮明であるとの認識は、単なる理念論、抽象論のレベルでのことではない。それは外大の入口から出口まで、すなわち (1) 入試 、(2) カリキュラム 、(3) 就職・進学のすべての局面における現実の問題として顕在化しているのである。(1) 我々はどのような人々を対象に入学を呼びかけるのか、(2) 入学してきた人々にどのようなカリキュラムを提供するのか、そして(3) 彼らをどのような人材として社会に送り出していくのか、これらの点が不明確であるということこそが最大の問題となっている。学部再編の問題は単なる「制度いじり」では決してない。それは、「外語の存在感ないし存在理由を社会にどうアッピールしていくか」(亀山案)という問題なのである。
であるからこそ、改革の方向性も次の一語に尽きる。すなわち「教育目標の明確化」(野間案)である。
なぜ本案か
だが問題は、どのような形で「教育目標を明確化」するのか、何をもって「外語の存在感ないし存在理由」とするのかという点にある。この点で、野間、亀山、高橋の3案は大きく異なっている。 野間案も亀山案も、現在の地域・国際講座を母胎とした新学部に大きな期待を寄せている。野間案の「先端国際学部」、亀山案の「国際政策学部」がそれである。だが、野間案、亀山案に対してわれわれが抱く最大の不満もそこにある。もっとも野間案については、野間さんが再三公言しているとおり、ディシプリンと英語を重視したその「先端国際学部」の中身は実際にはほぼ白紙であり、その具体的な設計図はわれわれ地域・国際講座に委ねられている。それゆえ、問題は亀山案の3学部構想、とりわけ「世界文化学部」と「国際政策学部」の分立構想に集約されることになる。
亀山案において、「国際政策学部」は国際関係と地域研究の2本立てで構成され、対象となる受験生は、「国際社会での活躍をめざす受験生」あるいは「地域研究に関心を持つ学生」であるとされている。とはいえ、亀山案の重点が前者に置かれていることは明白である。その名称が如実に示しているとおり「国際政策学部」のめざすものは、亀山案が競合相手と考える慶応大学政策学部同様「政策的志向」であり、将来国際機関、メディア、国際協力などの分野において主として英語を駆使して活躍することを望む受験生を対象に、彼らをこうした人材として育成していくことに最大の役割が期待されている。そして今後いっそう増大するだろう社会的要請と受験生の期待に応えることになるが故に、「本学部は、対社会的には、長い将来にわたって本学をリードする存在となる」と展望され、全学あげてその「充実化」への協力が約束されることになるのである。
だが果たしてこれが本学のめざすべき方向性であろうか。それは、本学が有する大きなリソースを十分に活用していくものであるのか。
高橋案も「政策的志向」を排除はしない。むしろ国際公務員養成などの「高度職業人教育」は一つの明確なコースとして設定されている。しかし現在の本学が有する知的資源とその潜在的な可能性を考えたとき、現在の地域・国際講座を再編してつくられる「国際政策学部」をこうした方向性に純化ないし特化させていくことにはきわめて大きな疑問をもたざるをえない 。
なぜか。一つの例を引こう。
それではここで、こうしたスペイン文学とラテンアメリカ文学の連続性にかかわるエピソードをひとつ紹介します。実はあるところで、ホセ・マルティという人の編集・翻訳を頼まれました。ホセ・マルティというのはキューバの独立の父です。キューバ独立の父で、政治的なエッセーなどが多いんですけども、文学者としてもラテンアメリカのモデルニスモの先駆として非常に評価の高い人でして、政治家としても文人としてもとても巨大な存在なんですね。このホセ・マルティという人の、三巻本の選集がある出版社で進行中です。そのうちの第一巻が、文学的な作品を集めたもので、その翻訳を仲間と一緒にやっているわけです。
ところで、このホセ・マルティの文章がすごいんです。一緒にやっているラテンアメリカの専門家たちは、難しくてどうしようもない、レトリックが、華麗と言えば華麗だけども面倒くさくて、こんな大げさに言わなくてもいい、としきりに嘆きます。僕はそんなとき彼らの愚痴を聞きながらにやにやしておりました。というのも、マルティの文体はまさに僕が日ごろ読んでいるスペインのバロック期(黄金世紀の後半)の作家の文体そのものだからです。
ホセ・マルティというのは一九世紀後半の人ですが、大変な文章家としてラテンアメリカ文学の中で高く評価されているんです。そして彼の文体がまさにスペインの黄金世紀のバロック期の偉大な作家たちの文体そのものなんですね。従って、僕にとっては、日常的に読んでいる文体なんだけれども、ラテンアメリカの専門で、しかも政治とかそっちのほうをやっている人にとっては装飾過剰の難解きわまりない文章らしいんです。ここからも、スペインの黄金世紀、バロック期とラテンアメリカの文学のつながりということが見て取れるのではないかと思います 。(ゴシックは引用者)
あらためて解説するまでもなかろう。この一文は、亀山案に対するきわめて雄弁な批判となっている。ホセ・マルティの文章を読み込めない「ラテンアメリカの専門で、しかも政治とかそっちのほうをやっている人」のキューバ研究がどれほど浅薄なものでしかないかは明らかだろう。いささかの無理を承知で牛島さんの表現を借りて言うならば、19世紀末のキューバ独立を研究する際にも、「スペイン文学とラテンアメリカ政治の連続性」、「スペインの黄金世紀、バロック期とラテンアメリカの政治のつながり」を考慮に入れなければならないのである。
事は現代的テーマについても同様である。現在のキューバのカストロ政権と、米国政府およびマイアミの反カストロ勢力の対立を論じる際にも、これを単なる「国際関係」、あるいは政治、経済体制をめぐる問題に限定してしまうのであればきわめて皮相な分析に終わりかねない。というのも、カストロ政権も反カストロ勢力も、自らの正統性の証としてキューバ独立の父ホセ・マルティを等しくその旗印に掲げているからである。換言すれば、カストロ派と反カストロ派は、ホセ・マルティの表象をめぐってもまた闘争しているのである。そうであるならば、この「文化」的側面を欠落させたキューバ政治論が著しく厚みを欠いたものに終わるだろうことは明白である。
キューバに限らず、ラテンアメリカと米国との関係についてはきわめて膨大な研究の蓄積がある。だがそのほとんどは、いわゆる「社会科学」的な方法に基づき外交、政治、経済面での関係に焦点を合わせて分析したものであり、これら両者の関係の奥底にある相互認識のありように関する研究は、その重要性にもかかわらずきわめて少ない。そうした中、ラテンアメリカが米国をどのようにイメージし認識してきたのかを、その連続性と変化を歴史的に辿りながら検討した研究が筆者の知る限り2つある。そしてこの2つの研究がともに資料として用いているのは、ラテンアメリカの文学者、詩人が著した作品群である。
同様な例は他の地域についてもいくらでも挙げることができようが、ここでは一点だけ、スペイン語の新聞一つ読むのにも「文学」の素養が絶対に必要であることを強調しておきたい。毎日の事件報道を読むだけならまあいいだろう。だがひとたび論説、評論、コラムに目を移せば、そこには文学的な修辞を凝らした文章が待ち受けている。これら文章との格闘なしに、現在のスペイン人、あるいはラテンアメリカの人々のものの見方、考え方をどうやって理解できるというのか。
一言で言えば、現代の一見きわめて散文的な国際問題ですらも「文化」と切り離してしまってはならないということである。
そのことを教育面から述べるならば、われわれが本学で養成すべきは、両者の教養を併せ持つ人材であるということになる。亀山案の表現を借りれば、それはまさに「グローバリゼーション及びローカリゼーションという両極における社会的・文化的変動の波を敏感に察知できるアクティブな社会的意識(モチヴェーション)をもち、かつ、それにふさわしい能力を備えた人材の養成」(傍点引用者)にこそ他ならない。
概念図
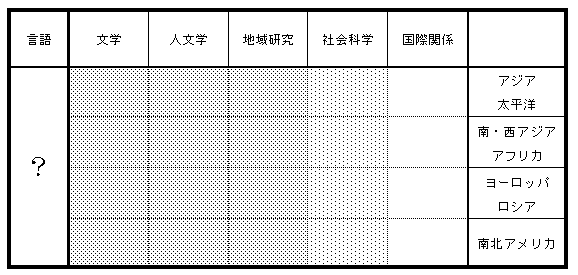
以上のような考えをもとに描いてみたのが上の概念図である。
(補論)この図で各分野と各地域の間に引かれた点線はあくまでも目安である。点線で囲まれた各部分は明確な境界を持つ独立した単位ではなく、近接領域と連続している。また縦、横それぞれの方向に自由かつ柔軟な形で伸張可能である。なお、地域をまたいで縦断する縦列全体がそれぞれの共通理論系となる。
カリキュラムを編成していく場合にも、それぞれ点線で囲まれた部分をコアとしつつ、時代の流れの中で提起される新たな諸課題を敏感に察知して、縦横へ自在に伸張しながら授業科目を柔軟に組み替えていく恒常的な努力が必要とされる。「教官の知的変革」(亀山案)と教官の集団的なFaculty Developmentが必須とされる所以である。
外大の独自性と言えるのは、図で濃い網掛けをかけた部分なのではないか。ここはまた地域言語が重視されるべき部分である。それに対して右側、特に「国際関係」は高度職業人コースへと密接に連結していく分野であり、英語が中心となろう。 外大全体で見た場合、日本語を含む様々な言語の研究教育に携わる言語学部(Faculty of Languages)と、地域と分野の両面で広域的な文化研究を研究教育の柱とする「地域文化学部」(「広領域文化学部」(Faculty of Transcultural Studies)と呼んでもいいかもしれない)が本学(Tokyo University of Languages and Transcultural Studies )の二本の太い柱となる。言語と文化の研究教育拠点、ここにこそ亀山案の言う「東京地区の他の国立大学にない独自性」がある。それを可能とする豊かな知的人材を本学はすでに有している。
入口・中身・出口 それでは、この「地域文化学部」では (1) どのような人々を受け入れ(=入試)、(2) どのような教育を行い(=カリキュラム)、(3) どのような人材を育てて社会に送り出していく(=就職・進学)のか。
この点は、改革推進委員会で議論され合意された方向性をわれわれも共有しており、委員会の提案としてすでに教授会にも提示されている。簡単に述べれば以下のようにまとめることができよう。
(1) 少子化に伴う18歳人口の減少の中で、留学生、社会人、リカレントに大きく門戸を広げる。
(2) 本学で、何が、どのように学べるのかを明確化したカリキュラムを編成する。
(3) 本学が送り出す人材は大別して「国際的な教養人」、「高度職業人」、「研究者」となる。
このうちで (1) と (3) の入口と出口について示したのが下の概念図である。
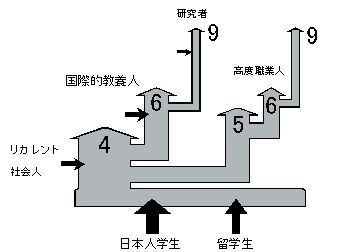
本案では、「言語学部」と「地域文化学部」のそれぞれで、上の図のような進路が考えられている。つまり、それぞれの学部で、「国際的な教養人」、「高度職業人」、「研究者」の3種類の人材を養成するものとされている。
これに対して亀山案の根底には、(言語学部についてはひとまず脇におくとして)、「国際的な教養人」と「高度職業人」の養成を、「国際政策学部」と「世界文化学部」の2つの異なった学部に分離しようとの発想がある。つまり「国際政策学部」が国際公務員などの高度職業人養成を担い、それに対して「世界文化学部」では「国際的な教養人」を育成していくことが考えられている。恐らくは、外大に「国際的な教養人」と「高度職業人」の2つの出口があることを、2つの学部に分離することで対社会的に(とりわけ受験生に対して)明確化しようとしたのであろう。
しかし問題はこの「国際政策学部」の中身とスタッフである。 亀山案においては、社会科学の共通理論系の教官と地域研究系列の教官がそれぞれ「国際関係」と「地域政策」の2つの学科[課程]に分かれつつ「国際政策学部」を構成するものとされている。そして、本学の地域研究スタッフが「その広域性において他の追随を許さぬもの」であるがゆえにこの「地域研究」こそが外大の独自性の中核をなし、この地域部門をさらに一層充実することによって、慶応大学総合政策学部をはじめとする他の「大学とは異なる独自のビジョンを描くことができる」とされている。「本学の国際政策学部の最大の特色は、地域研究と国際関係論の強力かつ綿密な連携に見るべき」というのが亀山案の議論である。 だが、いったい他大学とは異なるこの「独自のビジョン」とは何なのか。地域研究と国際関係論をいったいどのようにして「連携」させようというのか。実際、亀山案の最大の難点はまさしくこの肝心な点が不明確なままに終わっている点にある。
結局のところ、「世界文化学部」を独立して立てることによって各地域の言語・文化と密接な連関にあるべき地域研究を文化研究から切り離し、英語中心のグローバルな国際関係論と「連携」させて「高度職業人」養成に従事させようという構想そのものがそもそも無理なのである。 われわれ地域研究者は「高度職業人」養成のお手伝いはする。そうした意味での「連携」を拒否はしない。しかし、少なくとも本案の提案者が、そして恐らくは現在の地域研究スタッフの大半がまず第一に優先したいと考えているのは、今後とも本学の最大数を占めると思われる学生に対する「国際的な教養教育」なのではなかろうか。もしそうでないというのなら話は別で、亀山構想通りの「国際政策学部」に進むことに何の問題もないのだが。
「世界文化学部」とは別個に、英語バリバリの「国際政策学部」を設けたいというのならそれはそれで結構である。その場合には、現在の総合文化講座と地域・国際講座の大半の教官とから構成される「地域文化学部」と、英語中心の文字通りの「国際政策学部」の並立ということになるだろう。だが、地域研究スタッフの多くが抜けた「国際政策学部」に本学独自のどのような魅力があるというのか。
これに対して本案では、研究者と並んで「国際的な教養人」と高度職業人の両者の養成を「地域文化学部」が担うこととなる。これによって出口が不明確となりそれゆえに受験生に対するイメージも不鮮明となる、との予想される批判に対しては、履修コースを明確化することで対処できると答えたい。
その際、「高度職業人」養成コースにあっては、同時通訳者、翻訳家などの場合を別として、英語教育に大きく比重がかけられることになるだろう。だがそれだけでは、競合するかもしれぬ他大学との差別化が図られない。本学出身の「高度職業人」は、たとえ将来的に英語を中心的な武器として国際舞台で活躍することになろうとも、ある一定期間(それが1セメスターか、それ以上になるのかはともかく)は英語以外の言語と文化領域の科目を履修しなければならない。そうした条件が何故に課せられるのかは、すでにホセ・マルティを例に述べたことであり、ここではくり返さない。ただ一言、高度職業人として国際協力の分野で働く人間が対象国の言語と文化に無知な場合にどんな結果が予想されることになるかは想像に難くない、とだけは言っておこう。
次に「国際的な教養人」だが、卒業後、企業や官庁に就職していくことになる彼らは、本学が送り出す人材の中でおそらく最大多数を占めることとなるはずである。彼らにどのような教育を授けるかはカリキュラム編成と密接に関係している問題だが、基本的な考えは以前文章化したことがあるのでそちらを参照していただければと思う(文末の参考資料)。
以上の述べてきたことはあくまでも基本的な考え方のレベルでのことである。この点で基本的な合意に至ることができたとしても、さらに以下のような問題についてより詰めた具体的な検討が必要である。
(1) 学部内部の課程をどう立てるか(地域別?)
(2) 入試をどの枠で行うのか(学部一括? 地域別?)
(3) 定員をどうするか
(4) 言語教育をどうするか
ただちに開始すべきこと
たとえ概算要求の結果がどうなろうとも、現制度の中で可能な限り改革を図るべきである。そのために、一人一人の教官が教育上どのような問題に直面しているのか、その改善のためにはどのような方向性が考えられるのかを各講座において早急に調査し、それをもとに改善計画を立てる必要がある。
地域・国際講座でのアンケート集計結果による限り、当面、以下のような検討課題が考えられるのではないか。
(1) 専攻語履修制度の再検討(セメスター制導入の可能性、単位認定方式の見直しなど)
(2) 履修コースの明確化と柔軟化(地域・国際コースの学生でも文化人類学で卒論執筆が可能になるようにするなど)
(3) カリキュラム編成の合理化(特に地域科目の再検討)
(4) 定員枠の再検討(各課程の学生定員数)
またカリキュラム改善のために、それぞれの講座でカリキュラム委員会を設置すること、さらに学部全体においても、この講座カリキュラム委員会を統合した全学カリキュラム委員会を設置することを提案したい。