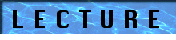
2002年度試験講評
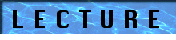
科学思想史(講義)
100点:宮崎里紗(F3);岩崎正太(Cz3);荒井尚彦(T3);
90点以上:宮崎彩子 (S4);大山美樹(R4);袴田祐介(93,Cz4);高木振一郎(93,L4)
加藤厚(92,E3);櫻田祐子(F2);鎌田瑞穂(93;I2);
栗田紅(93,R3);高橋敬明(92,C3);栗山恩(A3);三原飛雄馬(92,Pr3)
85点以上:田代陽子(D3);會田志歩(86,Po2);平林紘明(R3);小峰香織(86,Ph2)
逆井かほり(Ph2);石山倫子(87,U3);関章江(Tr3)
佐々木芙美子(88,D4);志田恭子(88,S4);黒木直人(C4)
宮崎里紗(F3):なんと言っても、「万年筆の歴史」というタイトルのレポートが優秀。ワープロで11枚、恐らく400字詰め原稿用紙換算40枚〜50枚の力作です。とてもよく調べていますし、文章もしっかりしています。自由レポートとして文句なし、です。試験解答の「映像の方向性」という文章も、非常に教えられることの多かった優秀な内容です。
岩崎正太(Cz3):自由科目として、ゼミに参加してくれている学生。答案は、シベルブシュ『鉄道旅行の歴史』(法政大学出版局、1982)に基づき、鉄道の出現がもたらした変容について述べています。研究の場合、いかにすぐれた先行研究に出会うかというのが大きなポイントになります。『鉄道旅行の歴史』を選び、しっかり内容を把握した時点で優は約束された、と言えます。自由レポートの「SF的クローン人間について」もよく書けています。
荒井尚彦(T3):答案は、DTM ( Desk Top Music )すなわち、パソコン上での音楽製作について。これはしっかり調べて、きちんと書かれた答案です。自由レポートは、「インターネットの歴史と将来」。今、焦点の問題となっているセキュリテイの問題についてインターネットをフルに活用して、しっかり書かれています。
袴田祐介(Cz4):答案は、映画と写真という映像についての、しっかりとした批評文。我々がとくに写真を考えるときに重要なのは、いかに我々の頭にしみついている「写真がリアルである」という思いこみから抜け出すことができるか、ということですが、このもっとも重要なポイントにおいて、高い批評性に基づくよい文章を書いてくれています。
高木振一郎(L4):答案は、「自動車の発展とその貢献」。その出発点から、現在のハイブリッドカーまでの歴史をしっかりと押さえています。自由レポートは、「ITS技術の発展とプローブカー」。新しい技術を駆使したプローブカー構想について、しっかりと技術的内容をまとめています。
栗山恩(A3):答案は、「イブン・スィーナー」について。イスラム医学の双璧のひとり、イブン・スィーナーの医学について、非常よく調べてきっちりとまとめています。せっかく外語ですから、この種の人物を取り上げたもらえるのがうれしい。心身医学に関する紹介は、とても勉強になりました。
櫻田祐子(F2):答案は、アップルコンピュータとビル・アメリオ。自由レポートは、「映画はいかにして芸術へと変化したのか」。映画興行のはじまりの時期に、どういう映画がどういうふうに放映されたかについて、面白い材料を紹介しています。このレポートの発展性を評価しました。
三原飛雄馬(Pr3):「日本におけるサイバーパンクとは何を意味するか?」というタイトルのもと、1)日本におけるサイバーパンクの影響、2)サイバーパンク運動とサイバーパンクスタイル、3)サイバーパンクスタイルの特徴という3節構成で、びっしり4頁を埋める力作です。日本の状況が、本場アメリカと比べてよくわかります。
加藤厚(E3):近代の視覚文化という設問を選び、1昨年の「9.11事件」を扱っています。映像メディアを通してのみ、戦争や大事件といった事柄を知る、現在のあり方(知のメディア的あり方と呼べよう)について、優れた批判的思考を展開しています。
高橋敬明(C3):中国を2ヶ月にわたり旅行した体験に基づき、中国のさまざまな土地のサウンドスケープについて、述べています。特に、少数民族との交流の部分は印象的でした。
栗田紅(R3):「職人」という立場、そして現代日本での(「職人」と切り離された)「芸術」の必要性について、述べています。栗田氏は、「職人」を「芸術家」と「職工」の中間に位置づけ、これを東洋に特徴的な存在と考えています。この見通しにたって、古くからの問題、art の二重性、つまり技術と芸術の重なりと相克の問題を、よく考えています。
石山倫子(U3):「環境問題と情報技術のかかわりについて」論述しています。たとえば、シリコン半導体の生産が実は非常にエネルギーと水を要するものである点など、情報化がさらなる大きな環境負荷をもたらしていることを拠点にして、環境問題と情報技術の関連について現実の企業の取り組みを含め、考察している。
関章江(Tr3):製茶法について、その出発点からはじめ、その文化史的意義をサーベイしています。よくまとまっています。
會田志歩(Po2):燃料電池について、述べています。アポロ11号が月で使用した電源が燃料電池であったこと、現在のスペースシャトルが使っているのも燃料電池であることをイントロにして、燃料電池の歴史・現状・展望をまとめています。自由レポートは、「バイオテクノロジーと同一化」の問題を扱っています。
志田恭子(S4):今回の試験で、4番目の設問「英語またはその他の外国語による学術書を1冊読み、その書物についてエッセイ・レビューを書き上げなさい。」を選択した学生は2名でした。予想しやすいことですが、この課題にしっかり取り組めば、まず、優は約束されたようなものです。私としては、学部の段階で、こういう作業がみんなできるようになればいいなと思っています。志田さんの取り上げたのは、「アメリカ合衆国におけるプエルトリコ移民のアイデンティテイとその音楽」について書かれた英語の書物です。
佐々木芙美子(D4):設問3「今世紀に活躍した、あるいは今活躍している思想史の研究者のうちから、特に関心を持った人物を1名取り上げ、その人の研究業績を可能な限りリストアップした上で、その人の研究のもつ意味を自由に述べよ。」を選び、丸山真男を取り上げています。この設問もできるだけ多くの学生に選択してもらいたい問題です。こういう作業を一度やってもらえると、大学での学習に見通しパースペクティブが持てるようになります。
黒木直人(C4):「近代の音声文化」の一例として、「ラジオ体操」を取り上げ、考察してます。ラジオ体操は、日本独自のものと思われていますが、その起源を、アメリカ・メトロポリタン社の「ラジオ体操」にもつものであること、日本でラジオ体操がスタートした1920年代は公衆衛生運動の時代であったこと、日本における時間概念の変容にかんけいすること、がしっかりと書かれています。
宮崎彩子 (S4):「電話の成り立ちと、それが人間の思想の与えた影響」というテーマで、電話の起源の問題を扱っています。電話が、1880年代以降、有線ラジオ的に娯楽メディアとして利用されていたこと、またITにおけるグローバリゼーションのはしりと位置づけられること等、電話という技術における、起源の忘却をうまくまとめています。
小峰香織(Ph2):ウォルト・ディズニーを技術者としてとらえ、とくに1964年に開催されたニューヨーク万国博を転回点として、記述しています。
逆井かほり(Ph2):「20世紀に活躍した思想家、マーシャル・マクルーハンについて記述し、彼の研究業績をリストアップし、その意義を述べて」います。
田代陽子(D3):問い4を選択し、村上陽一郎を取り上げています。村上氏の直区をジャンルごとに分類し、その特徴を押さえた上で、とくに聖俗革命論について述べています。ゼミの学生です。このテーマで卒論を執筆予定ということです。
伊藤あい(I3):ジェットコースターの進化について、の楽しい文章です。私のあまり知らない分野ですが、楽しく読みました。
木下祐子(R3):コンスタンチン・メーリンコフというロシアの今ではあまり知られていない建築家を取り上げています。ロシア・アバンギャルドの時代に、いわば一匹狼として活躍した建築家の仕事を紹介しています。
平林紘明(R3):武器の一つとしての「日本刀」の特徴について、歴史を辿り、考察しています。
今年の試験結果の講評の続き
総合科目III「科学技術と社会」
90点以上:西方麻衣子、東内岳裕、鈴木崇之、一橋直樹、山谷直詩、金谷梓、佐々木幹人、塚田真裕、
「科学思想史」自由レポートコメント
10月3日受理。徳田宗一郎「人間の老化と科学技術一般について」
科学思想史(講義)1番目の提出は、評価できます。また、参考文献から判断すると、本はよく読んでいると思います。
しかし、そのことが内容に反映されていません。しっかりとして科学の考え方では、「老化促進物質」や「若返り物質」というものに対して、慎重にならなければなりません。何か顕著な現象があると、その原因を1つの物質に求めるのは、わかりやすい考え方ですが、(もちろん、一定割合でにそういう事柄もありますが)はっきりとした部分の故障ということでなければ、多くは様々な要因がいろんな仕方で絡み合うのが普通です。
もっと粘り強く、参考文献の内容に取り組んでほしかった。
「科学技術と社会」自由レポートコメント
1番。2002年8月15日受理。田代麻美「食品添加物について」
2002年度の第1号の自由レポートをお盆の真っ最中に受け取りました。お盆という一番暑さがこたえる時期にレポートを送ってくれる学生がいるとは思っていなかったので、それが少し驚きでした。最初に「今回のレポートを書いたことで自分の食品添加物に対する認識を考え直し、自分の食生活を振り返る良い機会となったと思います。
また、外語大では文系領域の科目が多く、自分もそのような授業ばかり取っていたのですが、今回初めて理系領域である科学技術についての授業を取り、授業でも20世紀における科学技術について学んだり、今回のレポートを書いたりしたことで、新たな領域へ視野を広げることができて本当に良かったと思います。」という自己コメントを書いてくれていますが、まったくその通りだと思います。今ちょうどメディアを騒がしている日ハムの問題なんかよりも、毎日口にする(日本人の一人の一日あたりの平均摂取量で11グラムにもなる―彼女のレポートによる)食品添加物の問題の方が、ずっとずっと深刻です。どうもマスメディアは、重要で深刻な問題は深刻ゆえに大きく取り上げず、時事的で軽い問題の方を大きく取り上げる傾向があります。
現在社会で、健康に生きていこうと思えば、知ったうえでしっかりと対応しなければいけない事柄が多くあります。
3番目。2002年12月4日受理。吉岡祐紀米本昌平『地球環境問題とは何か』を読んで(本人はタイトルをつけていませんでしたが、内容により、私が命名)
本のまとめとしては、まずまずです。大筋は押さえられていると思います。ですが、自分がおかしいと思う点、引っかかった点にもう少し粘り強く取り組んでもらえればと思います。アメリカの対応が問題があると考えるのなら、それを追求してもらえるとよいレポートになるのですが。
2003年度授業関係情報
2002年度授業関係情報
2001年度授業関係情報
Back to
HomePage = Entrance