
「どのような芸術形式の歴史にもいくつかの危機的な時代というものがある。そのとき形式は、技術の水準が変化したのちに、つまりある新しい芸術形式においてはじめて無理なく生じる効果を目指して進むことになる。このようにして生じる、つまり、特にいわゆる衰退期において生じる、奇矯な芸術表現や粗野な芸術表現は、実際には、そのもっとも豊穣な、歴史の力の中心から現れるものなのである。」1 ベンヤミンは『複製技術時代における芸術作品』の比較的末尾に近い部分でこのように述べ、そのような「衰退期」の特徴を帯びた現象としてここでダダイズムを取り上げている。つまりベンヤミンの言い方によれば、ダダイズムは、いかにアヴァンギャルドとしての位置づけが顕著であるにせよ、新たな芸術形式(ここではもちろん「映画」が念頭に置かれている)が本来的に志向する芸術のあり方を、それ以前の芸術形式によって2 得ようと奮闘していたということになるだろう。そのように、目指すものとは本来異なる芸術形式に基づくがゆえに、ダダイズムにおいては「奇矯な芸術表現や粗野な芸術表現」といった現象が特徴的に現れるとされる。しかし、ベンヤミンはこのことをある種の無理な試みの帰結として否定的に位置づけるのではなく、むしろそういった不自然さに起因する奇矯さが、この変転のなかで動いていることがらの本質、「もっとも豊穣な、歴史の力の中心から現れるもの」をまさにあらわすものとなっていることにアクセントを置いている。
ここで問題となっている過渡期の「形式」に対しては、一九世紀的な芸術の観念をともすれば連想させる「芸術」という言葉よりも、まさに複製技術論が、そしてベンヤミンの思考そのものが、さまざまなかたちをとりつつそのことをテーマとしているように、むしろ「メディア」という言葉を冠するほうがふさわしい。というのも、ここでいわれている「芸術」とはいうまでもなく、ベンヤミンが克服の対象としている「創造性や天才性、永遠の価値や神秘といった一連の伝統的概念」3 に関わるものではなく、そういった伝統的な芸術観をも展開の過程の一段階として包摂するような、より高次の概念であるからだ。『複製時代における芸術作品』はそれ自体、メディアの形式の転換期において――つまり旧来のメディア形式が、新しく出現したメディア形式の技術的特性の要請する新たな知覚・認識のパラダイムによって危機にさらされた時代において――生まれたまさにメディア形式の転換を主題とするドキュメントである。ベンヤミンのメディア理論的な思考においては〈画像メディア〉と〈言語メディア〉という二つのメディア系列がパラレルに展開していることを確認できるが、4 複製技術論では、「芸術作品」という位置づけを得ることによって(少なくとも映画以前は)美の領域における強力な支配権を得ていた〈画像メディア〉の系列にほぼ焦点が絞られて論じられている。しかし、高い「技術的複製可能性」をもった新たなメディアによって存在の基盤を揺るがされていたのは、伝統的な美の領域だけではなく、同じように〈言語メディア〉の系列において知の領域を席巻していた「書物/文字」でもあったということ、そして「伝統的な形態における書物が終焉に向かいつつある」ことを、ベンヤミンは複製技術論の一〇年あまり前に『一方通行路』のなかですでに述べていた。5 それとほぼ同じ一九二四年に出版されたベラ・バラージュの『視覚的人間』において浮き彫りにされているのもやはり、映画という新たな技術メディアの出現によってはじめて明らかになった文字メディアの特異性であり、そういった特異性が――確かにオプティミスティックな定式化であることは否めないが――映画によっていわば乗り越えられることになるという認識である。6 彼らが提示しているそれぞれのメディアの特性やメディアの展開の見取り図は、基本的にマクルーハンを継承している今日のメディア論のテーゼとほとんど心地よいまでに符合する。そのマクルーハンが二冊の主著を発表した一九六〇年代半ばは、例えばテレビや自家用車の普及によって特徴づけられる時代といえるだろうが、その意味でマクルーハンの著書もやはり新しい技術メディアによって惹き起こされた「危機的な時代」の産物である。
ベンヤミンの区分にそのまま従うならば、写真・映画以降はすべて「技術的複製可能性の時代」のメディアとしてまとめられてしまうことになるのだが、無論われわれはその後のメディアがたどってきた技術的展開を知っている。それらの技術的メディアの中で、例えばテレビは(あるいはビデオ、「ウォークマン」、携帯電話なども)メディアの技術的・物質的特質によって、そのメディアに接続する人間の社会的・文化的環境を劇的に変化させたという意味で、確かにメディア史において特別な意味をもつものということができるだろう。しかし、技術のバックエンドにおいて対象が0と1のインフォーメーションに還元されることにより、ほとんど究極の複製可能性を達成し、かつ否が応でもマクルーハンの「グローバル・ビレッジ」という表現を連想してしまうようなインフォーメーションの高度な交通ネットワークを獲得したハイパーテクストのウェブ環境ほど、映画以降のメディアの展開においてラディカルな転換点となっているものはないだろう。確かにハイパーテクストは、いわゆるインターネットというかたちで実際の技術的具現物を得たときには、まだその技術的特性を遺憾なく発揮したものではなかったかもしれない。ハイパーテクストの生みの親であるヴァネヴァー・ブッシュやテッド・ネルソンの理念的コンセプト自体が、テクストを「超えた」ものを構想しながらも、テクスト的特質を色濃く残したものであったのだが、7 一九九〇年代半ばにインターネットが広く使われ始めた当初も、その言語であるHTMLは、基本的に文字テクストの論理的構造を記述するものであり、画像的要素にはそれほどの重点がおかれていなかった。メディア理論においてメディアの展開を提示する場合、(それは思考モデルとして当然のことなのではあるが)ある新たなメディア段階は、その技術的特質に基づいた認識・思考を、そしてそれにともなう新たな文化段階をもたらすものとして描き出される。しかし実際には、新たなメディアが出現したとき、そのメディアには(あるいはもっと正確に言うならば、新たなメディアを用いる人間の思考のあり方には)往々にして前のメディアの特質がまだ強い支配力を保っている。それは単に新たなメディアが志向するものを実現するために必要な技術がその段階においてはまだ十分にないためというよりも、むしろそのメディアに接続する人間の知覚・認識・思考のあり方がまだ十分な変容を遂げていないためである。後に取り上げるように、新しいメディアはそのうちに古いメディアを包摂するので、このように新しいメディアにおいても古いメディアのパラダイムが部分的に許容されることも大いにありうる。このようなメディア――新しいパラダイムを目指しながらも古い技術段階のうちにある「危機的な時代」のメディアの裏返しの対応物として、黎明期のメディアと呼んでよいかもしれない――は、新しい技術段階にありながらいまだ古い技術段階のパラダイムを残しており、その意味で未熟なメディアであるのだが、次第にその新しいメディア段階の特質をますます強烈に志向し、そのメディアの本質的な特性をますます明確に体現していくことになる。
「危機的な時代」という言葉には(ベンヤミンはこの言葉を決してそのような意味で使ったわけではないのだが)、失われゆくものに対する保守的な危機感が往々にして伴われる。「文学」は、そういった危機感をさまざまなかたちで表明してきた。「ニューメディア」(およびその周辺のさまざまな対象、価値)に対する批判や、本を読まなくなることに対する慨嘆といった直接的な現れはここで改めて指摘するまでもないが、例えば「文学と技術」というテーマのもとに企画された論集、シンポジウムなども、「文学」という制度が安んじて存続することを妨げる異質な闖入者、それによって文学の変容が迫られることになる要素との関係に対する認識批判的な考察を目指しているはずである。「文学」と同じように、「演劇」、「舞踏」といったとりわけ身体的な領域に関わる芸術領域、あるいは「音楽」、「美術」なども、それぞれの領域の特質に応じて、技術との関係が問い直されることになる。このことはテレビ、映画、電話、音響機器などが、より新しい技術段階によってその存在を脅かされるのではなく、むしろそれらのメディアの本来的なあり方へとより近づいているように感じられることとはっきりとした対照を成している。「文学」、あるいはその他の「芸術」として制度化されてきた諸領域が「技術」との関係に対して反省的なまなざしを向けることは、もちろん今に始まったことではない。バラージュやベンヤミンにせよ、マクルーハンにせよ、危機の兆候としての自己省察は、新たなメディアによってこれまでのパラダイムが揺り動かされることにより生まれた。八十年代後半からのパーソナルコンピュータの浸透、そしてとりわけ九十年代後半以降、加速度的な展開を見せるハイパーテクストは、おそらくメディアの展開の歴史において「映画」が与えたと同じ程度、いやそれ以上の「衝撃(ショック)」(ベンヤミン)をメディアの担い手に与え、現在、危機の兆候としての「メディア論」を次々と生み出している。
こういったメディアの転換において何が起こっているのか。(主に人文系の)メディア理論においては、メディアの段階的な展開とそれに伴う認識・思考・文化のあり方の展開が、指標となるいくつかのキーワードとともに描き出される。その基本的なモデルは、現在のメディア論者においても、マクルーハンやW.J.オングの枠組みを継承しているといってよい。吉見俊哉は、(1)(「文字」以前の)「一次的な声の(oral)文化」における口承性、(2) 筆記、(3) 活字、(4) 「二次的な声の文化」をもたらす電子性、という四つのメディアの局面を、(a) 複製性/非複製性、(b) 文字性/身体性という二つの座標軸によって次のように整理している(図1)。8 この図をとりあえずの足がかりとして、メディアの展開において問題となるいくつかの主要な概念について再検討を加えてみたい。

これは非常に魅力的な図式である。マクルーハンにせよ、オングにせよ、メディアの展開のテーゼを空間的に視覚化するとすれば、上にあげた四つの段階を単なる直線的な矢印の流れによって示すしかないのだろうが、この図では、電子メディアにおける「声の文化」の回帰(縦軸)と技術的な進展(横軸)とが見事に示されているからだ。ただし、この図で十分に見て取れないのは、この四つのメディア段階の展開が同じ平面状で起こっているものではなく、吉見自身指摘しているように「螺旋的発展」だという点である。
そういったことはともかくとして、この非常に説得力のある図式化にもさらに考察を要する点があるように思われる。それは、縦軸、横軸それぞれの指標となる概念に関してである。
まず、縦軸の「身体性」―「文字性」という対置は、メディア理論における基本的な論議に照らして考えるならば、おそらくそれほど抵抗なく受け入れられるものである。マクルーハンにおいてもオングにおいても、口承文化から文字文化への転換は、「聴覚」中心の全感覚的な文化から、意味を負わされた「文字」を読み解く「視覚」中心の文化への移行という言葉で説明されている。文字文化においては「視覚」が強調されているが、その視覚は世界を直接的に目にする視覚とは全く異なり、文字という(ここではマクルーハン、オング、さらにはベンヤミンの論議にしたがって、表音文字のみを問題とする)それ自体としては世界となんの類似性も持たないメディアのエンコード/デコードに仕える機能のみが問題となる。そのようにして「文字」においては、世界との「身体的」な関係は背後に退くことになる。それに対して電子メディアの文化は、マクルーハン、オングにとって声の文化/口承文化の回帰、新たな口承性の段階の獲得という意味合いをもっている。バラージュは、文字における非身体性と新たな視覚メディアとしての映画における身体性を、まさにDer sichtbare Menschという言葉によって集約的に表した。「印刷術の発明は、時代がたつにつれ、人間の顔つきを読めないものにしてしまった。人間は非常に多くのことを紙から読むことができるようになったが、それとともに他の伝達形式を省みないということも起こった。(…)今や映画は、文化に再びラディカルな転換をもたらそうとしている。(…)全人類は今日すでに、顔つきや身振りといった、もうはるかかなたに忘れ去ってしまった言語を再び習得しようとしているところなのだ。それは、口が聞けない人が使う代替的な言葉ではなく、直接的に具現化された魂の視覚的対応物なのである。人間は再び目に見えるもの(sichtbar)となったのだ。」9 いずれの論議においても、文字とは世界の直接的な体験から人間を遠ざけてしまうもの、その意味で身体的ではないものということになるのだろう。しかし、素朴な疑問であるが、純度の高い概念であるはずの座標軸上の指標として、「文字性」―「身体性」という対概念はそもそもありうるのだろうか。例えば、「身体性」に対して「技術性」を対置させるという論議もありうる。その場合、技術の進展に伴って身体性は後退することになるだろうが、右の図では電子メディアの段階で身体性は回復されることになる。それぞれの相矛盾する位置づけにおいて「身体性」とは何を意味するのだろうか。
横軸の「複製性」―「非複製性」という対概念は、それ自体としては対称性を保っている。しかし、なぜ「複製性」という概念が座標として据えられるほどの突出した重要性をもちうるのか。「複製性」はいずれにせよ「技術性」との相関性をもつ概念であるが、より包括的な概念である「技術性」を横軸にもってくることは、この場合相応しくないように見える。というのも、そのようにすると例えば「活字」から「電子」への展開には技術性の変化はないことになってしまうからだ(各メディア段階における技術性の上昇は、この図を「螺旋的発展」と見るならば、読み取ることも一応可能であるかもしれないが。)しかし、同じことは「複製性」についても言える。四つのメディア段階における複製性は、おそらくそれぞれ質的な違いによって区別されるだろう。
さらに議論を交錯させていくならば、ベンヤミンにおいても右にあげたようなメディアの展開の枠組みを確認することができるのだが、彼のメディア論的な思考において根本的な座標を形成している「魔術」と「技術」という概念は、これまであげてきたような基本概念とどのように関わってくるのだろうか。「身体性」と「技術性」という対概念を参照項とするならば、魔術性と身体性は親近的な概念であるように見える。そうであるとすれば、これらの概念はどのように関わるのだろうか。メディア理論において「魔術」という概念を持ち出すのは、一見唐突な印象を与えるかもしれない。しかし、それはベンヤミンの秘教性として片付けられるものではなく、これから考察していくように、メディアの問題における最も中心的な概念の一つとして位置づけられるべきものだろう。10
メディアにおいて技術と身体はいずれにせよ中心的な概念であることは間違いないが、以下においては、先にあげたいくつかの疑問(それらは吉見氏の図式に対して向けられたものというよりも、メディア論で一般に用いられる概念に関わるものだが)を手がかりにしながら、メディアの展開における技術性、身体性のうちに、より細かな概念の層を組み込んでいくことを試みたい。また、それらの概念連関のうちに「魔術性」がどのように関わっているかを示すこともここでの中心的な論点の一つとなる。
そもそもメディアはなぜ展開していくのか――話を最初に戻すならば、メディアの展開は、あるメディア段階が危機を迎えるときに生じる。その危機とは、単に既存のメディアに慣れ親しんだ者がもつ感情というよりも、むしろそのメディアの文化段階においてメディアそのものが迎える危機である。こういった認識に立つという意味でも、ヴィレム・フルッサーが提示している、〈画像〉から〈テクスト〉を経て〈テクノ画像〉へと進んでいくメディア展開のテーゼは、以下の議論において非常に有効な拠点となる。まず、この展開全体を見渡すために、フルッサーの示す図を掲げておこう(図2)。11

この図は、とりあえず歴史的な展開の過程を表すものと読むとすれば、フルッサーのいう「テクノ画像」までメディアが展開を遂げた状態を描いている。(「テクノ画像」についてはここでは詳しくふれないが、文字メディアとしての「テクスト」の次の段階のメディアとして、メディア理論一般において了解されているように、例えば「写真」、「映画」がこの位置を占めることになる。)順を追って展開の過程を示すとすれば、まず最初に描かれることになるのは「画像」というメディアが生まれる以前の段階である。そこでは人間(●)はまだ世界を対象化することなく、いわば世界のうちに合一化した状態にある(図3)。この状態においては、まだ何ら特定の技術を伴った「メディア」によって世界との関係を持っているわけではないが、世界と(あるいはその次の段階以降においてはメディアと)つながっていく人間のインターフェースとしての感覚器官に対して、「光・音・匂い・味・触覚/温度」といった物理的・物質的メディアが働きかけている(図4)。
 この最初の段階は、いわゆるメディアの展開の段階には本来含まれないものなのかもしれないが、それ以降の図式の原点となる。「光・音・匂い・味・触覚」はそれ自体確かに物理的・物質的なメディアではあるが、ここには技術性は全く介在しない。その意味で、主体としての人間と世界との間に「直接的な=無媒介な」関係が存在する。この直接的な関係は、世界から人間の感覚器官への刺激でもあり、また反対に世界に対する人間の働きかけでもある。この段階においては、現前性(いま・ここ)も感覚性も最大であり、その意味で「身体性」は最も高いといえるだろう。それに対して、「技術性」はゼロである。
この最初の段階は、いわゆるメディアの展開の段階には本来含まれないものなのかもしれないが、それ以降の図式の原点となる。「光・音・匂い・味・触覚」はそれ自体確かに物理的・物質的なメディアではあるが、ここには技術性は全く介在しない。その意味で、主体としての人間と世界との間に「直接的な=無媒介な」関係が存在する。この直接的な関係は、世界から人間の感覚器官への刺激でもあり、また反対に世界に対する人間の働きかけでもある。この段階においては、現前性(いま・ここ)も感覚性も最大であり、その意味で「身体性」は最も高いといえるだろう。それに対して、「技術性」はゼロである。

しかし、(初期観念論・ロマン派において、あるいはユダヤ神秘主義においてそうであるように)人間はこういった世界とのいわばユートピア的な関係のうちにいつまでもとどまることはできず、世界を認識の対象とすることによって世界の外に立つことになる(異境化[Verfremdung] 1)。世界から切り離されてしまった人間は、ここではじめて(「画像」という)メディアを通じて、世界とのつながりを回復しようとする(図5)。
「画像」というメディアを用いる、ここでの世界に対する人間の関係のあり方は、フルッサーによれば「呪術・魔術(Magie)」ということになる。ここではこの最初のメディアとして「画像」のみがあげられているが、この段階はマクルーハンやオングのいう「口承文化/(一次的な)声の文化」にそのまま重なるものと見てよいだろう。ベンヤミンは複製技術論の中で、「芸術作品」につながっていく画像的メディアの展開を概観しているが、そこであげられる洞窟に描かれた呪術的な絵はここでの「画像」にそのまま当てはまる。

このもっとも単純な技術性をもつメディアが世界と人間との間に介在することによって、ここで初めて世界は「メディア」の背後に退くことになり、人間は音声や画像を通して世界に到達する。ここでは、図4においてとりあえず最初の物理的・物質的なメディアとしてあげた光や音などは、原始的な技術である画像や音声のうちに取り込まれたものとなる(図6)。このようにして、メディアの機能はつねに世界と主体としての人間の間に存在するものとして問題となる。その機能はおそらく〈世界〉の表象/再現前と〈世界〉の伝達の二つに集約されるだろう。この表象/再現前と伝達の二つの機能がそれぞれに身体性と技術性にかかわっている。人間は音声や画像を通じて、世界を再び現前的なものとして現出させようとする。もちろんそれはかつてあった、あるいは空間的に離れたところにあった世界そのものの再現前ではなく、いわば模倣による世界の再生産/複製である。このとき、世界をその姿のまま模倣しようとする類似性への志向は、一般的に言って身体性の高さを生み出すことになる。さらにその模倣は、子供の遊びでの真似事や舞踏、演じることのうちにその姿をとどめているように(ベンヤミン)、 まさに身体と結びついたものでもある。このことを技術性との関連で言い換えるならば、音声や身体表現は、〈世界〉との関係を架橋するためのメディアにおける技術上のインターフェースに他ならないということである。それらはあまりにも身体と深く結びついたものであるがゆえに、メディアの技術的特質そのものであることが見えにくくなっているのだが、逆に言えば、このことはそれらの技術上のインターフェースがいかに高い身体性をもつものであるかということの現われでもある。

最初の段階のメディアはこのように高い身体性を示す一方で、複製にかかわる情報の質と量の貧しさ(これは技術性の低さと相関している)のために、身体性の相関概念である再現前性・表象可能性は逆に低いものとならざるを得ない。こういった問題についてはまた後に立ち戻ることにしよう。
このメディア段階において世界に対する人間の関係が最も端的に現れた姿は、ベンヤミンが二つのヴァージョンの短いエッセイ(「類似的なものの理論」、「模倣(ミメーシス)の能力について」)のなかで描き出しているように、「模倣する」こと、そしてそれが集約された「演じること」・「踊り」にあるのかもしれない。世界を模倣するということは、究極的には「メディア」によって世界を創造することでもある。メディアの表象/再現前の機能は、(少しばかりベンヤミン的な言い方をしてよければ)今ではほとんど退化してしまった創造の機能の控えめな表れでもあるだろう。そのように「メディア」としての言葉や画像によって世界を創造すること、いやほんの一部でさえ世界に働きかけることは、いうまでもなく「魔術」そのものの行為である。世界と人間とを媒介するメディアは、このようにして必然的に「魔術」の領域と関わる。もちろん、メディアがいわゆる魔術となって実際に世界に力を及ぼすことはないだろう。12 しかし、そういった状態をいわば理念的な姿としながら、実際のメディアはその発展の段階に応じて、いくぶんかの魔術性を自らのうちに保っている。ベンヤミンが彼の模倣論や複製技術論で示そうとしているのは、まさにこういった技術の展開と魔術性の関係である。
このメディア段階において世界に対する人間の関係が最も端的に現れた姿は、ベンヤミンが二つのヴァージョンの短いエッセイ(「類似的なものの理論」、「模倣(ミメーシス)の能力について」)のなかで描き出しているように、「模倣する」こと、そしてそれが集約された「演じること」・「踊り」にあるのかもしれない。世界を模倣するということは、究極的には「メディア」によって世界を創造することでもある。メディアの表象/再現前の機能は、(少しばかりベンヤミン的な言い方をしてよければ)今ではほとんど退化してしまった創造の機能の控えめな表れでもあるだろう。そのように「メディア」としての言葉や画像によって世界を創造すること、いやほんの一部でさえ世界に働きかけることは、いうまでもなく「魔術」そのものの行為である。世界と人間とを媒介するメディアは、このようにして必然的に「魔術」の領域と関わる。もちろん、メディアがいわゆる魔術となって実際に世界に力を及ぼすことはないだろう。12 しかし、そういった状態をいわば理念的な姿としながら、実際のメディアはその発展の段階に応じて、いくぶんかの魔術性を自らのうちに保っている。ベンヤミンが彼の模倣論や複製技術論で示そうとしているのは、まさにこういった技術の展開と魔術性の関係である。
ベンヤミンが複製技術論で提示している基本的な枠組みによれば、メディアはそのもっとも原初的な段階においては魔術的・儀式的な力を強くとどめていたが、その技術的展開に伴って魔術性は(少なくとも表面的には)遠ざけられていく。複製技術論で述べられている「アウラ」は、現前性、一回性、真正性そして「遠さ」として言い表されるようなある種の権威によって特徴づけられるが、これらの特質はベンヤミンが強調しているように儀式的なもの、魔術的なものと結びついている。複製技術論では、「知覚のメディア」における「技術的複製可能性」の展開が、魔術的なもの、宗教的なものの「世俗化」の過程とパラレルに提示されている。アウラの衰退はその兆候である。例えば、芸術作品に対する関係がベンヤミンのいう「礼拝価値」から「展示価値」へと重心を移していったこと、あるいは同じ画像メディアである「絵画」と「映画」の根本的相違が、「魔術師」と「外科医」という対概念によって説明されていることも、そういった「世俗化」の文脈において語られている。ベンヤミンはこの論文の中で、「芸術作品の技術的複製可能性の時代において萎縮していくものは、芸術作品のアウラである」13 とあまりにも明確に宣言しているため、技術の展開に伴う「世俗化」によってメディアから魔術性が払拭されていく側面ばかりが強調されてしまうことになった。しかし、『写真小史』では技術と魔術との関係に対して、もう一つ別の側面が指摘されていることを見逃してはならないだろう。「(…)この場合も両極端は相通ずることがわかってくる。すなわち精密きわまる技術は、その産物に魔術的な価値を与えうるのだ。」14 複製技術論のなかでは、「展示価値が礼拝価値を全面的に追いやり始めている」15 写真においてさえ「礼拝価値」として言い表される魔術性が残存していることが、いわば補論的に言及されている。しかし、『写真小史』のなかで述べられているのは、そのように未熟な段階にあった時期には写真が「礼拝価値」から完全に脱却していなかったということではなく、むしろ技術の展開がいわば別の魔術性を生み出す可能性をもつということなのである。このことを考察していくために、ここではさらにメディアの展開の図式を追っていくことにしよう。
〈世界〉の外に立たされた人間は「画像」によって世界との関係を回復することになるが(図5)、ただしその状態も永続的に保たれるわけではない。世界を意識によって対象化した人間が、世界とは疎遠な(fremd)なものとして世界の外に追いやられたと同じことが、ここでも起こることになる。つまり、「画像」が単純に世界を媒介するものとして機能するのでなく、それがまさに「メディア」であることが意識され、対象化されるまでに肥大化するとき、「画像」は人間と世界とを結びつけていたその透明性を失い、逆に「媒介することをやめて世界のまえに立ちふさがり、世界を覆い隠す」。16
このとき人間は画像とは疎遠なものとして画像の外に立ち(「異境化2」)、もはや世界との媒介をやめた画像のかわりに別のコードをもつメディア、すなわち「テクスト」を求めることになる(図7)。 フルッサーによれば、「テクスト」は〈世界〉を記述するメディアなのではなく、あくまでも「画像」を説明するコードをもつメディアである。17 マクルーハンがいうように、新しいメディアはそれまでのメディアを包摂する。「テクスト」は前の段階のメディアである画像や(話される)言葉をうちに含みつつ、新たなインターフェースとして「文字」を用いることになる(図8)。世界を身体の感覚器官によって直接的に体験していた段階(図3)が最も身体性の高い状態であるとするならば、メディアが重層化されることによって世界との距離が増すことは、一般的に身体性がそれだけ少なくなることを意味することになるだろう。しかし、文字メディアの場合に感じられる圧倒的な身体性の後退の要因となっているのは、むしろインターフェースにおいて根本的なパラダイムの転換が生じたことである。画像や音声としての言葉、身振りといった最初のメディア段階のインターフェースが、感覚器官によってとらえられる世界の像との類似性を根本的な特質としつつ人間の感覚器官と接続しているとするならば、「テクスト」というメディアにおけるインターフェースとしての「文字」は、確かに視覚という人間の身体的インターフェースに接続しているものの(ここでは単純化のために紙の上に書かれた表音文字を目で読むという行為に即して話を進めていこう)、それ自体としては単に紙の上にインクが付着したものでしかない。そのインクがなす線の形態そのものが世界との類似性によって世界の像を生み出すのではなく、その線の形態のなす「文字」(その複合体としての語)に与えられた記号的コードを経ることによってはじめて世界の像が与えられる。フルッサーが「コンセプション」と名づけるこの「テクスト」―「画像」間のエンコード/デコードの能力が、「画像」と〈世界〉の間のエンコード/デコード能力である「イマジネーション」とは、インターフェースのレベルにおいて質的にまったく異なったものであることがフルッサーの図式では見えてこない。
フルッサーによれば、「テクスト」は〈世界〉を記述するメディアなのではなく、あくまでも「画像」を説明するコードをもつメディアである。17 マクルーハンがいうように、新しいメディアはそれまでのメディアを包摂する。「テクスト」は前の段階のメディアである画像や(話される)言葉をうちに含みつつ、新たなインターフェースとして「文字」を用いることになる(図8)。世界を身体の感覚器官によって直接的に体験していた段階(図3)が最も身体性の高い状態であるとするならば、メディアが重層化されることによって世界との距離が増すことは、一般的に身体性がそれだけ少なくなることを意味することになるだろう。しかし、文字メディアの場合に感じられる圧倒的な身体性の後退の要因となっているのは、むしろインターフェースにおいて根本的なパラダイムの転換が生じたことである。画像や音声としての言葉、身振りといった最初のメディア段階のインターフェースが、感覚器官によってとらえられる世界の像との類似性を根本的な特質としつつ人間の感覚器官と接続しているとするならば、「テクスト」というメディアにおけるインターフェースとしての「文字」は、確かに視覚という人間の身体的インターフェースに接続しているものの(ここでは単純化のために紙の上に書かれた表音文字を目で読むという行為に即して話を進めていこう)、それ自体としては単に紙の上にインクが付着したものでしかない。そのインクがなす線の形態そのものが世界との類似性によって世界の像を生み出すのではなく、その線の形態のなす「文字」(その複合体としての語)に与えられた記号的コードを経ることによってはじめて世界の像が与えられる。フルッサーが「コンセプション」と名づけるこの「テクスト」―「画像」間のエンコード/デコードの能力が、「画像」と〈世界〉の間のエンコード/デコード能力である「イマジネーション」とは、インターフェースのレベルにおいて質的にまったく異なったものであることがフルッサーの図式では見えてこない。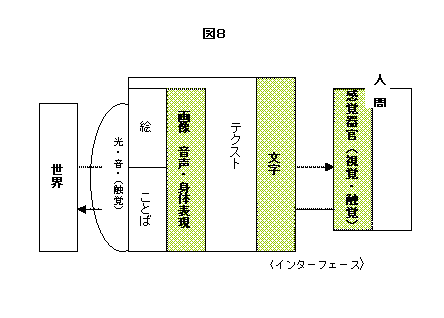 技術側のインターフェースは、メディアの技術性と人間の身体性の界面をなすものとして、人間の身体的インターフェースである感覚器官に接続する要件を備えている。その意味で技術側のインターフェースはいずれにせよ最低限の身体性を保持しているわけだが、メディアに接続する人間がそのメディアをどの程度「身体的」であると感じるかは、身体性に関わる複合的な要因のうち、メディア側のインターフェースが世界との類似性に基づいて人間と接続しているかどうか、ということにかなりの部分依拠しているように思われる。そのように考えるならば、吉見俊哉のメディア変容の図式(図1)における縦軸は、むしろ類似的コードに基づく「像的なもの」と記号的コードに基づく「文字的なもの」を両極とする座標として読み替えることができるのではないだろうか。ここでの「像的なもの」は、視覚によって得られた画像に限らず、感覚器官を通じてとらえられた世界の像一般に関わるものを指している。この「像的なもの」は、身体性を構成する複合的な要件のうち特に高い比重をもつものと思われるので、吉見氏がこれを「身体性」としていることもさほど抵抗なく受け入れられるのである。
技術側のインターフェースは、メディアの技術性と人間の身体性の界面をなすものとして、人間の身体的インターフェースである感覚器官に接続する要件を備えている。その意味で技術側のインターフェースはいずれにせよ最低限の身体性を保持しているわけだが、メディアに接続する人間がそのメディアをどの程度「身体的」であると感じるかは、身体性に関わる複合的な要因のうち、メディア側のインターフェースが世界との類似性に基づいて人間と接続しているかどうか、ということにかなりの部分依拠しているように思われる。そのように考えるならば、吉見俊哉のメディア変容の図式(図1)における縦軸は、むしろ類似的コードに基づく「像的なもの」と記号的コードに基づく「文字的なもの」を両極とする座標として読み替えることができるのではないだろうか。ここでの「像的なもの」は、視覚によって得られた画像に限らず、感覚器官を通じてとらえられた世界の像一般に関わるものを指している。この「像的なもの」は、身体性を構成する複合的な要件のうち特に高い比重をもつものと思われるので、吉見氏がこれを「身体性」としていることもさほど抵抗なく受け入れられるのである。
では、記号的コードを特質とする「テクスト」へとメディアが展開するとき、そのインターフェースである文字からは、かつてのメディアの特質である類似性は完全に失われてしまうのだろうか。ベンヤミンの二つの模倣(ミメーシス)論、「類似的なものの理論」および「模倣(ミメーシス)の能力について」は、まさにこの「文字(Schrift)」における類似性をテーマとしている。ベンヤミンによれば、現代のわれわれの「知覚世界(Merkwelt)」18は太古の人間のうちにまだ保たれていたような「魔術的万物照応(コレスポンデンツ)」を圧倒的に失い、世界との結びつきを魔術的に生み出そうとする「模倣の能力」はますます弱々しいものとなっている。しかしそれは模倣の能力がなくなっていくことを意味するのではなく、単にある種の「変容」を遂げて見えにくいものとなっているに過ぎない。変容した模倣の能力が「非感性的な類似」となって保たれている領域としてベンヤミンはとりあえず占星術をあげているが、彼がそのような領域として最終的に強調しようとしているのは、「非感性的な類似、非感性的な万物照応の文書庫(アルヒーフ)」である「言葉(Sprache)」、とりわけ「文字(Schrift)」である。われわれが文字を読むとき、われわれの注意の大部分はほとんどの場合それが担っている意味にしか向けられていないかもしれないが、文字にはそういった「記号的なもの(das
Semiotische)」と並んでもうひとつ、その視覚的インターフェースがどのように書かれ、どのように配置されるかという画像的な側面が存在する。ベンヤミンは文字におけるこの画像的側面を、「記号的なもの」に対して、「模倣的なもの(das
Mimetische)」と呼んでいるが、この両極は、さきほど「像的なもの」と「文字的なもの」ととりあえず読み替えた吉見氏の図の縦軸の座標にそのまま当てはめてもよいだろう。それに従えば、メディアの展開は次のように読めることになる(図9)。 まず、最初のメディア段階(話される言葉、語ること、絵、そしてベンヤミンが「非感性的類似」の保たれていた場として強調している「舞踏」あるいは「演じること」等)における技術側のインターフェースは「模倣的なもの」を基本的な特質としており、それによって高い身体性をもつことになる。それに対して、次のメディア段階にある書かれた「文字」は、なによりも記号的なコードによって意味を担うという機能によって特徴づけられる。その意味で文字は「記号的」なメディアである。しかし、そのように記号的特質が圧倒的な比重を占めつつも、視覚的インターフェースとしての文字は、その画像性のうちに前のメディアの「模倣的」特質を「非感性的類似」として残している。そして、まさにその特質のうちに、より世俗化されたメディアである「文字」に残存する魔術性が保たれることになるのである。文字はその「記号的」特質によって身体性を大きく失うことになるが、しかし、そこにもまだ身体性が残されているとすれば、それはまさに視覚的メディアであるがゆえに文字がもつ画像的側面に由来する。あるいは、これも「読む」というわれわれの行為からすれば、多くの場合あまり意識されないままとなっている、文字が印刷された(書かれた)紙の品質やそれに伴う触感、本そのものの物質性、つまり「文字/書物」というメディアのインターフェースがもつ(本来あまり意図されていないかもしれない)触感的特質もまた、本に残された比較的目立たない身体性に関わっているといえるだろう。「文字/書物」というメディアにおける身体性の問題は、同じ「記号的」メディアでありながら、複製可能性の段階が異なる「筆記」と「活字」とを比べるとき、さらにはっきりと見えてくる。筆記は(ベンヤミンがまさに「筆跡学」について言及しているように)「非感性的類似」をそのうちに保つ画像的特質を豊かに含み、それによって活字と比べてより高い身体性をもっているといえる。つまり、筆記から活字への展開において文字における模倣的特質は減少し、記号的特質がより高い比重を占めることになる。それはまた、メディアの展開において魔術性がいっそう駆逐される過程でもある。それでもなお活字のうちに保たれた画像的特質に対して、ベンヤミンは「文字像/字体(Schriftbild)」という言葉によって光を当てている。『一方通行路』の中で書物の終焉について語るコンテクストにおいて、ベンヤミンはメディアがますます画像的表現へと転換を遂げつつあることを指摘するが、彼にとって「文字像/字体」における画像的・デザイン的特質こそが、伝統的な形態における書物のうちに保たれた、次のメディアへのパラダイム転換の契機なのである。
まず、最初のメディア段階(話される言葉、語ること、絵、そしてベンヤミンが「非感性的類似」の保たれていた場として強調している「舞踏」あるいは「演じること」等)における技術側のインターフェースは「模倣的なもの」を基本的な特質としており、それによって高い身体性をもつことになる。それに対して、次のメディア段階にある書かれた「文字」は、なによりも記号的なコードによって意味を担うという機能によって特徴づけられる。その意味で文字は「記号的」なメディアである。しかし、そのように記号的特質が圧倒的な比重を占めつつも、視覚的インターフェースとしての文字は、その画像性のうちに前のメディアの「模倣的」特質を「非感性的類似」として残している。そして、まさにその特質のうちに、より世俗化されたメディアである「文字」に残存する魔術性が保たれることになるのである。文字はその「記号的」特質によって身体性を大きく失うことになるが、しかし、そこにもまだ身体性が残されているとすれば、それはまさに視覚的メディアであるがゆえに文字がもつ画像的側面に由来する。あるいは、これも「読む」というわれわれの行為からすれば、多くの場合あまり意識されないままとなっている、文字が印刷された(書かれた)紙の品質やそれに伴う触感、本そのものの物質性、つまり「文字/書物」というメディアのインターフェースがもつ(本来あまり意図されていないかもしれない)触感的特質もまた、本に残された比較的目立たない身体性に関わっているといえるだろう。「文字/書物」というメディアにおける身体性の問題は、同じ「記号的」メディアでありながら、複製可能性の段階が異なる「筆記」と「活字」とを比べるとき、さらにはっきりと見えてくる。筆記は(ベンヤミンがまさに「筆跡学」について言及しているように)「非感性的類似」をそのうちに保つ画像的特質を豊かに含み、それによって活字と比べてより高い身体性をもっているといえる。つまり、筆記から活字への展開において文字における模倣的特質は減少し、記号的特質がより高い比重を占めることになる。それはまた、メディアの展開において魔術性がいっそう駆逐される過程でもある。それでもなお活字のうちに保たれた画像的特質に対して、ベンヤミンは「文字像/字体(Schriftbild)」という言葉によって光を当てている。『一方通行路』の中で書物の終焉について語るコンテクストにおいて、ベンヤミンはメディアがますます画像的表現へと転換を遂げつつあることを指摘するが、彼にとって「文字像/字体」における画像的・デザイン的特質こそが、伝統的な形態における書物のうちに保たれた、次のメディアへのパラダイム転換の契機なのである。
そういった書物世界の終焉、つまり「グーテンベルク銀河系の終焉」(ボルツ)もまた、フルッサーが「異境化」と呼ぶメディアの(あるいはメディアを通じて世界へと至ろうとする人間の)危機的状態によって引き起こされたものである。「画像」を通じての「イマジネーション」が肥大化し、奇矯なものとなることによって、「画像」がもはや世界を表象するための透明なメディアでありえなくなったように、「テクスト」もまた、たとえば概念化の肥大によって、「画像」(またそれを通じて「世界」)を表象する透明性を失うことになる。ホフマンスタールの「チャンドス書簡」は、まさに書くことを仕事とする作家が感じ取ったそのような言語の危機が最もありありと描き出された例の一つである。チャンドス卿は世界そのものを感じ取ることができなくなってしまったのではない。むしろ反対に、常人とは比べ物にならないほどの細やかな感受性を持って世界の存在そのものを感じ取っているのだが、そこへ至ろうとするときに、それまでは仲立ちとなったはずの言語が逆に世界とのあいだを阻む障壁として立ちふさがることになる。早熟の天才作家という設定のうちに描かれるチャンドス卿が断念したのは、世界に至ることそれ自体ではなく、言語によって世界へと至ろうとする行為である。
「文字/書物」というメディア段階の次にくる「電子メディア」(マクルーハン)、「テクノ画像」(フルッサー)は、メディア論者にとって、こういった言語の飽和状態を経ることによって生まれたものということになるだろう。もちろんチャンドス卿にとってそういった技術メディアは問題となりえないが、しかし、ある意味で同じ方向を目指すことになっているのかもしれない。飽和してしまった言語に代わってチャンドス卿が世界の存在そのものへと至るために求めるのは、記号的コードによらない、いわば「像的」な体験である。書物の次のメディア段階をなんと呼ぶにせよ、それを特徴づけているのはまず画像的特質である。あるいは図9に即して言えば、記号的特質から模倣的特質への回帰である。ベンヤミンは「映画」に代表されるような「技術的複製可能性」をもつメディアを、画像メディアの系列でのみ論じているのではなく、それとパラレルに展開する言語メディアの系列と接合する過程のうちに捉えている。19 映画を特徴づけているのは確かに、まず画像から成り立っているということである。しかし、映画が伝統的な画像メディアと決定的に袂を分かつのは――ベンヤミンがしきりに強調する「モンタージュ」によって指し示されるように――その画像が断片的特質をもつという点においてであろう。ベンヤミンにとって映画とは、こういった断片的な画像によって構成される像(モザイク像)を現実にもたらすための、彼の時代としては最も有効な技術的手段だった。しかし、このコンセプトを複製技術論以上にラディカルに推し進めているのはむしろ、素材的には一七世紀のドイツ・バロックにおける悲劇(Trauerspiel)を扱う『ドイツ悲劇の根源』である。ベンヤミンはこの著作で、一九世紀の精神科学的思考(それはとりもなおさず「書物/文字」というメディアの技術的・物質的特質に依拠するとともに、それに基づいて形成された価値観をともなう思考なのだが)の限界を指摘し、それに対して、アレゴリー的な画像的断片にある構成的な配置を与えることによってモザイク像を獲得する新たな認識・思考のパラダイムを提起している。20 こういったコンセプトを体現する実際の技術メディアは「映画」であるよりも、むしろ「ハイパーテクスト」である。(あるいは、ゴダールの『映画史』のように、まさにハイパーテクストを体現したかのような映画であるかもしれない。)映画は確かにメディアの展開の中でひとつの決定的な転換点をなすメディアとして位置づけることができるだろうが、また同時にそれ自体、ある完成されたメディアがもつ本質的な特性を志向しつつも、いまだその途上にある未完成なメディアでもある。ここではその意味で、「テクスト」の次のメディア段階として、「ハイパーテクスト」に即したモデルを考えてみることにしよう(図10)。

すでに述べたように、このメディア段階は再び「模倣的」特質のコードをもつ技術側のインターフェースに人間の感覚器官が接続することによって、その意味での身体性の高さを取り戻している。マクルーハンらのメディア論者が、電子メディアのうちに口承文化における全感覚的な身体性が回復されているのを見て取るのは、まさにこのこととかかわっている。しかし逆に、メディアがまさに高い技術性を持つものであるがゆえに、電子的な技術メディアを用いるものは、それがいかに模倣的コードを持つものであるにせよ、身体からの疎外感をもつのではないだろうか。このことはたとえば、ある実際に描かれた絵とその写真、あるいはさらにコンピュータのモニター上に映し出された写真とを比べて考えてみれば明らかである。写真においては、そしてコンピュータの画面においてはなお一層のこと、ベンヤミンのいう「アウラ」が失われている。あるいはまた、紙のうえにペンで書いていくこととワードプロセッサで文章を書いていくこと、伝統的な書物を手にし、そのページを繰っていくことと、コンピュータのモニター上でEテクストを読んでいくこととを比べてもよいかもしれない。ここでは身体性を構成する要件として、インターフェースの模倣的特質・記号的特質とは別の要因が強力に働いていることになる。
こういった身体性の減少と相関関係にあるメディアの技術性の高さは、ひとつはメディアの重層性にかかわっている。新しいメディア段階は前のメディアとそのインターフェースを包摂する。メディアのインターフェースは、前のメディアのインターフェースを包摂しつつ人間側のインターフェースに接続されることによってとりあえずの身体性を確保するのだが、メディアにおける技術上のフロントエンドとしてのインターフェースに対して、技術のバックエンドは技術の進展に伴ってフロントエンドからますます遠ざかっていく。コンピュータにおけるハイパーテクスト環境のバックエンドは、人間の身体性から最も離れた電子回路内の0と1の世界である。技術性が増大するにつれてバックエンドはフロントエンドであるインターフェースから遠ざかり、それによってメディアは、感覚性によってそれに接続する人間にとっていわばブラックボックス化していく。このようにメディアが重層化されることにより、最初のメディア段階が豊かに含んでいた魔術性はますます間接化されていくことになる。アウラの衰退は、ひとつにはそのようなメディアの重層化によって引き起こされている。
このことと並んで、技術性の進展と身体性の減少にかかわってくるもうひとつの要因は、フルッサーが「抽象ゲーム」と呼んでいる、メディアの基づく次元(ディメンジョン)の減少である。「あらゆる〈現実的なもの〉――われわれに対して外部から働きかけてくるものという意味において――は、時空世界 [三次元性をもつ〈空間〉に〈時間〉の次元が加えられた空間] の四つの次元を持っている。すなわち、そこには運動する物体が存在する。われわれは、しかし、そこから捨象することができる。たとえば、現実から時間の次元を除外し、ついで一方では〈時間〉を、他方では〈空間〉を表象や概念のうちに捉えようとすることができる。そのように表象され、概念化された空間から、〈深さ〉を除外し、ついで一方では平面を、他方では容器を表象や概念のうちに捉えようとすることができる。そのように表象され、概念化された平面から〈表面〉を除外し、ついで一方では線を、他方では線の体系(〈織物〉)を表象や概念のうちに捉えようとすることができる。そしてそのように表象され、概念化された線から、〈放射する線〉を除外し、ついで一方では点を、他方では点の体系(〈モザイク〉)を表象や概念のうちに捉えようとすることができる。こういった抽象ゲームにおいては、それにしたがってさまざまな〈非現実的な〉宇宙が生み出されることになろう。すなわち、彫刻――時間のない物体――の宇宙、画像――深さのない表面――の宇宙、テクスト――平面のない線――の宇宙、そしてコンピュテーション――線のない点――の宇宙である。そして、この抽象ゲームは一歩ずつ進展していき、何千年もそれにかかることになる。最初に、時空世界から彫刻の宇宙、たとえば〈ヴィーナス〉の宇宙が取り出されることになり、そこから画像の宇宙、たとえば洞窟画の宇宙が、さらにそこからテクストの宇宙、たとえばメソポタミアの叙事詩の宇宙が、そして最後にそこからコンピュテーションの宇宙、たとえば卓上計算機の宇宙が取り出されるのだ。」21 四次元的な時空世界が〈現実的なもの〉として人間の身体が直接的に体験するものであるのに対して、そこから次元が捨象されていくにつれてメディアは抽象性を増していく。次元の減少は同時に、メディアの伝達機能(そしてそれとともに保存の機能)にとって決定的な重要性をもつ複製可能性の増大を意味するものでもある。最も抽象化が進んだコンピュータ内部の0と1の世界は、とりあえず技術的には完全な複製可能性を達成している。ベンヤミンにとってアウラの衰退は、メディアの展開における複製可能性の増大とパラレルに進行していくものと捉えられていたが、このことはまたメディアの展開に伴う抽象性の増大によって、〈現実的なもの〉としての世界と結びつく魔術性がますます追いやられていく過程として説明することもできる。
しかしながら、こういった魔術性の駆逐や身体性の後退の一方で、同じ複製可能性の増大が逆に身体性の高さを生み出すものともなっているのである。それは、先ほどと同じ例になってしまうのだが、世界の模倣(ミメーシス)として描かれた絵(写実的でない絵を思い浮かべるほうがわかりよいだろう)に対して、同じ世界を例えば精細なカラー写真でとった画像がもつ身体性の高さである。技術の重層性(それに伴うフロントエンドとバックエンドの距離)からいえば、すでに述べたように前者のほうが高い身体性をもつことになるのだが、その画像がどれだけ仮想現実として体験されるかということに身体性の高さを求めるとすれば、反対に技術性の高い画像のほうがより高い身体性を持つことになる。技術性の増大とともにますます精密に複製される世界の模倣像は、まさに仮想現実という新たな世界を創造する。この新たな魔術性こそが――ここで『写真小史』で掲げられているテーゼに立ち戻るならば――技術性の増大とともに与えられる魔術性ということになるのかもしれない。
しかし、この新たな魔術性によって与えられる身体性は、確かに技術のインターフェースに接続しているときの身体そのものは同じであるが、その「現実」の身体によって与えられるものとは別のものである。メディアを用いることによって引き起こされる身体性の変容と述べられているものは、22 メディアと接続することによって生まれた新たな身体感覚の経験に関わるものである。メディアと接続する人間は、本来は例えば「コンピュータ」という〈世界〉の中の一事物を「直接的」に経験しているに過ぎないのだが(図4参照)、技術のインターフェースといわばシームレスに接続したとき、つまりインターフェースがその機能を十全に発揮したとき、コンピュータに接続している身体という「現実」は消滅し、もともとは「模倣像」であった世界が新たな現実として立ち現れ、その世界の中での身体感覚が経験されることになる。そのようにして経験される世界は、「仮想現実」という言葉がすぐさま結びつけられる、電子メディアによって実現されたシミュレーションの世界に限られるわけではない。線状的に配置される記号コードをもち、その物理的特性に従って世界を線状的に分節化する「文字」という、ある意味でかなり特殊なインターフェースに接続することの障害が〈読む〉ことの習熟によって消え去ったとき、人間は例えば世界の模倣像として立ち現れる物語世界の内に埋没し、その中での身体感覚を体験する。このことはさらに低いメディア段階についてもあてはまるだろう。しかし、そういった仮想的な身体性は、複製可能性の高さによってもたらされた再現前/表象の程度が高いほど大きなものとなる。このようにして、技術の展開に伴って「現実的」な身体性が後退していくのに対し、「仮想的」な身体性は高まっていく。そしてそれとパラレルに進行しているのが、技術の展開に伴う魔術性の衰退と、新たな魔術性の増大である。
こういった「現実的」な身体性と「仮想的」な身体性、本来的な「魔術」と新たな「魔術性」の違いは、例えばメディアに接続したときの「トリップ」から我に返ったときに「ずれ」として経験されるものであるが、これら二つの領域は互いにふれることのない世界というわけではない。確かに新たな魔術性は、「ほんものの」現実に対して「仮想」というレッテルを貼られた(それによって安全な圏内に括り入れられたかのように扱われる)世界にかかわるものでしかない。また、電子メディアの段階における全感覚的な身体性の回復と見なされているものも、あくまで擬似的な身体性であり、世界を直接的に経験する最初の身体性そのものではあり得ない。しかしだからといって、最初の段階の身体性が手つかずのまま保持されるということではない。「仮想」の世界――例えばウェブ上の世界はまさにそのような世界である――は、モノとしてのメディアが現実の世界をますます埋め尽くしていくことによって、また、メディアに接続した仮想的な身体経験が、そこから復帰した現実の身体のうちに余韻を残しつつその身体性のパラダイムを変えていくことによって、ますます「ほんものの」現実を侵食していく。
このことは新しいメディアによる旧来のメディアの変容という現象にそのまま関わっている。いや、メディアそのものが変容するのではない。新たなメディア段階のうちにある人間は、同じ「文字」あるいは「音声」というメディアを用いるときも、それらのメディアに対してそれまでとは違ったパラダイムにおいて接することになる(「二次的な声の文化」)。新たなメディア段階によって旧来のメディアが消滅することはない。電子メディアによって本は消滅するのではなく、電子メディアのうちに重層的に吸収されつつ、本によって成立していた思考のパラダイムや価値を変容させていく。書物というとりあえずは伝統的なメディアに基づきつつ、原理的にハイパーテクスト的な思考をすでに目指していたのが『フィネガンズ・ウェイク』や『ドイツ悲劇の根源』であるとするならば、「ハイパーテクスト小説」は、ハイパーテクストというメディアによってその特質を意識しながらも、「文学」といういわば文字メディアの頂点に座すものに関わり、そのパラダイムに正面から刺激を与えている。しかしこういった直接的な例をあえて挙げるまでもない。ハイパーテクストというメディア段階に移行するとき、そのうちに包摂される「文字」や「音声」は、それらが経ていくメディアの特質によって、メディアに接続する人間に対して重層的な変容を与えていく。同じことは「演劇」などのまさに身体表現の領域においても当てはまる。新たなメディアを経験することによって、本来的な身体性がまさにそのメディアのパラダイムのうちに組み込まれていくことになるのである。23
メディアの展開にともなう身体性の変容は、つまり三重のプロセスのうちに生じている。第一のものは、メディアの技術的展開そのものと相関する変容である。そこでは、模倣性―記号性という特質の程度と、技術性の展開にともなう重層化によって生じる〈世界〉との距離、という二つの相異なる(そして場合によっては相反する)要因が複合的に身体性を規定している。第二のものは、メディアに接続する人間が仮想的に経験する身体性に関わる。そしてさらに第三のものは、そのようにして獲得された「仮想的」な身体性が、「現実」の身体性、あるいは「現実」のうちに埋め込まれた旧来のメディアのパラダイムを浸食することによって生じた変容といえるだろう。それはいわば、仮想的な夢の世界の産物が現実の世界の事物と交錯する過程である。その意味では、メディアによる「仮想的」な経験は、もはや仮想的なものではない。
そして基本的には同じことが魔術性と技術との関係においても当てはまる。仮想現実の魔術性を高めるもっとも普通の方法は、現在まさにそのようになされているように、技術側のインターフェースが人間の身体的インターフェースとしての感覚器官に対してもはや世界の模倣像とは感じられないほどの感覚性をもって接続するように、技術的な洗練を追求することであろう。理論的には「抽象ゲーム」の極限まで進んだかのように見えるメディアの展開に、そういった程度的な進展ではなく、まだこれ以上の質的展開があるとすれば、それはメディアが人間側のインターフェースである感覚器官にではなく、その背後の回路に接続することによってもたらされるものであるかもしれない。そのようにして生み出される世界、『トータル・リコール』や『マトリックス』、あるいは『ニューロマンサー』や『攻殻機動隊』において描き出される世界は、メディアが世界の創造に対して支配権を握る新たな魔術性の世界でもある。こういった世界を極点としながら、人間がメディアと接続することによって生まれた新たな魔術性の感覚は、「現実」の世界に対する人間の関係の中へと入り込んでいるのである。