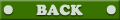1998年度 インターネット講座
メディア・情報・身体 ―― メディア論の射程
第7回講義 註
- 註1
- 西洋近代哲学の文脈において「身体」が問題となるのは、特に、デカルト以降の、精神と物体という二元論におけるいわゆる「心身問題」と、とりわけ現象学(フッサール、メルロ=ポンティなど)における身体性の問題、という二つの流れにおおきく分けることができると思います。そしてさらに、比較的新しい、身体と文化との関係の問題(ここでは社会学・民族学・生命倫理学など多元的な領域が交差します)もこれに加わります。デカルトは、「思惟」を属性とする<精神>と「延長」(物体が空間の中でしめる広がり)を属性とする<物体>という二つのまったく異なる実体から世界が成り立つと考えましたが、人間は一方では考える存在として<精神>を有しながらも、他方では身体的存在として<物体>(ヨーロッパの言語では身体と物体は同じ語ですが)でもあります。つまり、人間においては精神と物体という本来まったく相容れない二つの実体が共存していることになるのですが、実際には、人間の心と体は確かに相関して動いているわけですから、これをどう説明するかということが心身問題として論議されてきました。この問題は、きわめて現代的なテーマ設定としては、たとえばAIの問題――機械とその意識――のうちに引き継がれています。二番目に挙げた身体性の論議は、このデカルト的な心身二元論を前提としながらも、こういった二分法的な枠組みを乗り越える立場を示そうとしています。つまり、身体とは、知覚の対象となるという意味で、確かに対象としての<物>の世界のうちに含まれるものではあるけれども、そこでの知覚・経験は身体を媒介として初めて可能となるものです。身体は、そこにおいて対象世界が立ち現れてくる媒体であり、精神と物体、主体(意識)と客体(対象)のどちらかに還元できないような両義的な存在であるということが、ここでの出発点となっています。
身体論に関する文献としては、たとえば以下のものを参考に挙げておきます。
- 『哲学・思想事典』岩波書店、「身体」の項
- デカルト『哲学原理』岩波文庫、中央公論社「世界の名著」など
- 廣松渉『心身問題』青土社1994
- メルロ=ポンティ『知覚の現象学』みすず書房(2巻)1974/法政大学出版局
- 市川浩『精神としての身体』講談社学術文庫 1992
- 市川浩『<身>の構造 身体論を超えて』講談社学術文庫 1993
- 大澤真幸『身体の比較社会学 I, II』勁草書房
メディア論において身体論が問題となるのは、とりわけ二番目に挙げた身体性の論議と、三番目に挙げた身体と文化との関係においてですが、文字文化における思考の枠組みは、精神と物体の二元論に深く関わっているので、第一番目の心身問題についてものちにその文脈で取り上げることになると思います。
メディア論の文脈で身体の問題があつかわれているものとして特に次のものを挙げておきます。これらについては、これからふれることになると思います。
- 石光泰夫『身体 光と闇』未来社1995
- 大澤真幸『電子メディア論 身体のメディア的変容』新曜社1995
- 註2
- 大澤真幸『電子メディア論』、50頁。この引用自体、吉見俊哉「個室のネットワーク――電話コミュニケーションと生活空間の変容」『東京大学新聞研究所紀要』43号、99頁からの引用。吉見氏は他にも、
- 『メディアとしての電話』(共著)弘文堂 1992
- 『「声」の資本主義 電話・ラジオ・蓄音機の社会史』講談社 1995
など、電話に関する考察を精力的に行っています。